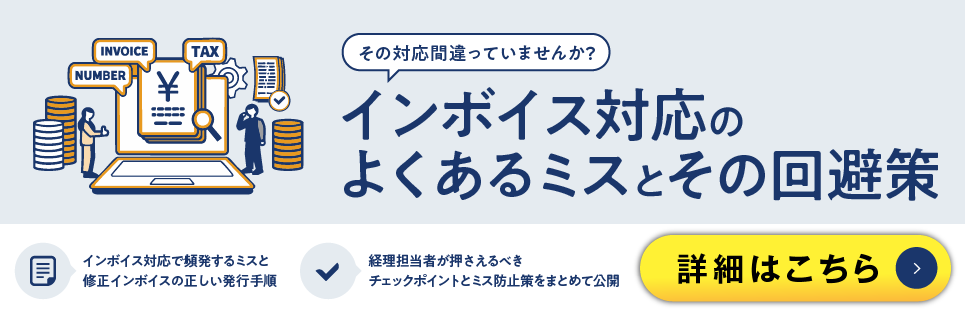副業でインボイス制度の登録は必要?基本的なルールや影響、バレない対策も解説
更新日:2026.01.29
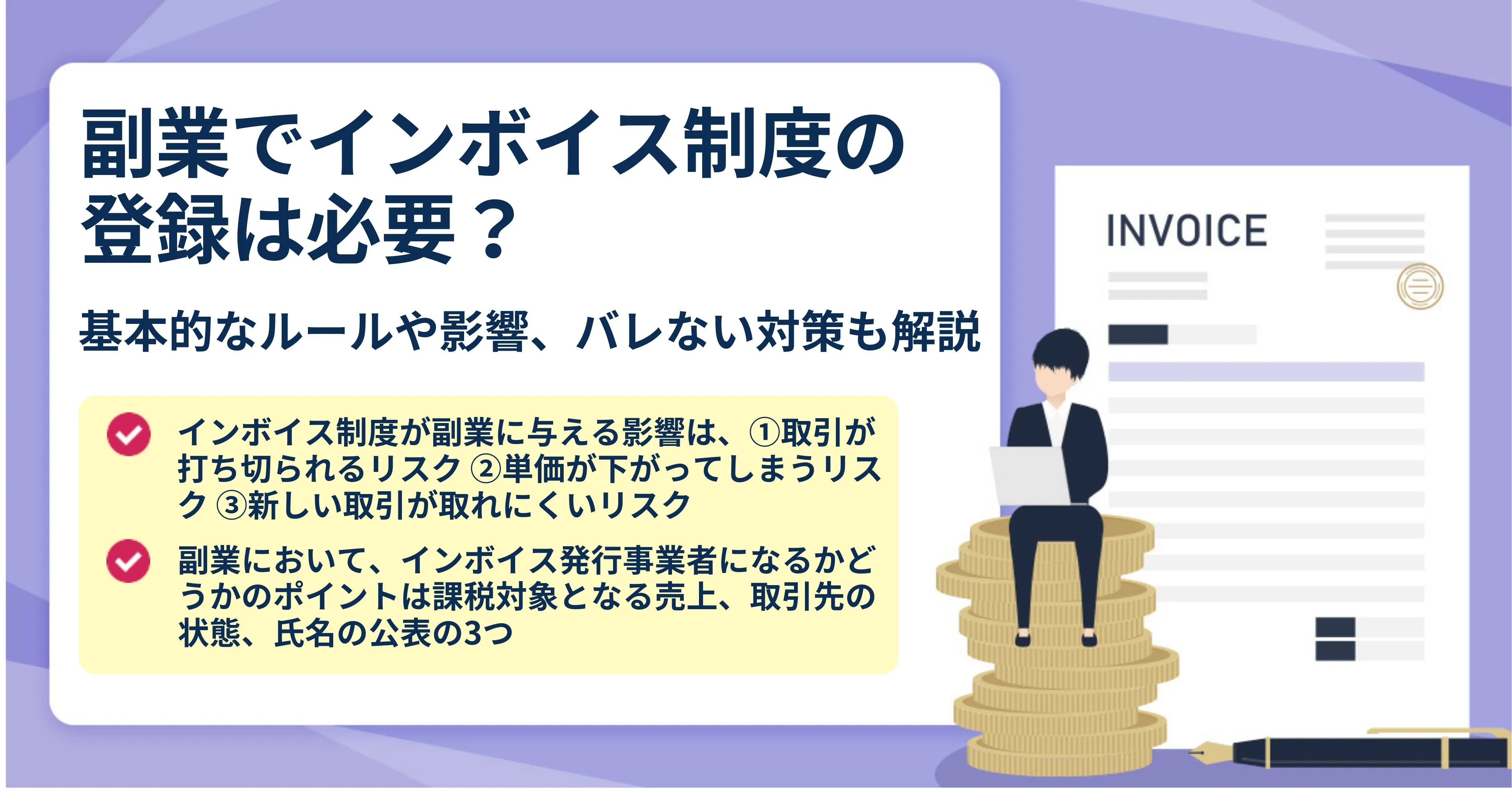
ー 目次 ー
2023年のインボイス制度の施行にともなって、消費税にまつわる対応が大きく変更となりました。この制度はすべての事業者を対象にしており、副業の事業者も例外ではありません。
インボイス制度による副業への影響は、登録をしているか確認されたり、取引先に登録を求められたりする場合も考えられるでしょう。また、インボイス制度に登録していないと、急に取引が打ち切られたり、減額交渉を持ち掛けられたりするような悪影響を受けるおそれもあります。
このようなことからインボイス制度に関する基本的なルールや副業への影響を把握し、適切な対策を講じなければなりません。
本記事では、副業でインボイス制度の登録は必要なのかについて、基本的なルールや影響などを解説します。
【基本】インボイス制度とは?3つの特徴を解説
インボイス制度は、消費税にまつわる請求書の作成や計算方法などを定めたルールです。2019年に軽減税率が導入され、消費税の納付が正確に把握できないことや、税率を誤ってトラブルになるリスクがあることなどの問題点がありました。このような背景を踏まえて、2023年にインボイス制度が施行されました。
インボイス制度では書類の記載事項や消費税の計算方法などの細かなルールが定められ、副業においても与える影響が大きいことから、基本的なルールを把握しておく必要があります。
ここでは、インボイス制度の特徴について、以下の3点を解説します。
- インボイス(適格請求書)の発行・保存が必要である
- インボイス発行事業者への登録が必要である
- 要件を満たすと、仕入税額控除が受けられる
関連記事:【消費税の新ルール】インボイス制度とは?2割特例や経過措置も紹介
①インボイス(適格請求書)の発行・保存が必要である
インボイス制度が施行されたことによってこれまでの記載方式から「適格請求書等保存方式」に変更となりました。この方式にしたがって発行された書類を「インボイス(適格請求書)」と呼び、インボイス制度を利用する際には発行・保存が義務付けられています。
なお、インボイスには以下の記載が求められます。
- 発行者の氏名や名称
- インボイス発行事業者の登録番号
- 取引年月日
- 支払期日
- 取引内容(軽減税率の対象となる品目があればその旨も)
- 取引金額(税率ごとの消費税額も含む)
- 受領者の氏名や名称
関連記事:【テンプレートあり】インボイス(適格請求書)の書き方とは?記載例をもとに要件も解説
②インボイス発行事業者への登録が必要である
インボイス制度では、インボイス(適格請求書)の発行・保存に「インボイス発行事業者」への登録が必要です。インボイス発行事業者の登録は取引当事者の双方がおこなっている必要があるため、自身がインボイスを受領する際には注意しましょう。
なお、インボイス発行事業者の登録は、税務署や登録センターに申請手続きをおこないます。詳しい手続き方法については別記事で解説しているため、あわせて参考にしてください。
関連記事:インボイス制度の登録方法とは?申請のやり方や注意点を解説
③要件を満たすと、仕入税額控除が受けられる
インボイス制度の要件を満たせば、「仕入税額控除」が受けられます。この「仕入税額控除」とは、売上にかかる消費税から仕入れに支払った消費税を差し引ける仕組みです。
仕入税額控除を利用すれば、従来の方式で生じていた消費税の二重課税を防げ、納付する事業者の税負担が軽減される可能性があります。
インボイス制度が副業に与える影響とは?
インボイス制度はすべての事業者を対象とした制度であり、副業に与える影響も十分にあります。
もし、副業に対する影響を知らなかった場合、インボイス制度への対応が遅れてしまい、既存の取引がいきなり打ち切られたり、新しい仕事が取りにくかったりと、今後の事業展開の支障になりかねません。
このようなことから、インボイス制度の内容だけでなく、実際に与える副業への影響を理解しておきましょう。
ここでは、インボイス制度が副業に与える影響について、解説します。
①取引が打ち切られるリスク
インボイス制度では、仕入税額控除を受けるためにインボイス(適格請求書)発行事業者への登録が要件となっています。これは取引当事者双方に求められる要件であり、自身が登録していない場合には取引先が仕入税額控除を受けられません。
仕入税額控除が受けられないと、取引先にとって税負担が増えてしまうため、インボイス制度に登録した事業者との取引を優先する可能性があります。もし、インボイス制度に登録していなければ、自身の取引が打ち切られるリスクもあるかもしれません。
②単価が下がってしまうリスク
インボイス制度で仕入税額控除を受けられない場合、消費税分の負担をしなければなりません。自身がインボイス制度に登録していない場合には、取引先に負担を強いることになります。
取引先にとっては税負担を抑えたいと考えるため、登録していない事業者との取引では消費税分の単価を下げる交渉を持ち掛けてくる可能性があります。単価交渉を断ってしまうと、契約が打ち切られることも十分に考えられるため、半ば強引に単価交渉に応じなければならない状況に追い込まれかねません。
③新しい取引が取れにくいリスク
インボイス制度は既存の取引だけでなく、新しい取引にも影響を与えかねません。具体的には、新しい取引が取れにくくなる可能性があります。
これはインボイス制度で仕入税額控除を受けたいと考える事業者が多くなることが要因です。依頼する事業者はインボイス発行事業者との取引を積極的におこなう可能性が高まるため、登録していない事業者が新しい取引を取りにくくなります。
【必要?バレる?】インボイス制度の登録で、副業の事業者が考えるべきポイントとは?
副業において、インボイス発行事業者への登録を判断するポイントは以下の3点です。
- 課税対象となる売上
- 取引先の状況
- 氏名の公表
どのポイントも事業運営に影響する大切なポイントであることから、上記のポイントを整理できれば、インボイス制度で悪影響を受けるリスクを抑えられます。
最後に、インボイス制度の登録で、副業の事業者が考えるべきポイントについて、解説します。
①課税対象となる売上
消費税の申告・納付は、基準期間や特定期間の課税売上が1,000万円未満の場合には免除されるルールがあります。このような事業者を「免税事業者」と呼び、多くの副業事業者はこれにあてはまります。
しかし、インボイス制度では、課税売上と関係なく消費税の申告・納付が必要です。
上記を踏まえると、課税売上が1,000万円未満の場合には登録をしなくても良いということになります。一方、すでに課税売上が1,000万円超の事業者は、インボイス制度に登録しても事務的な負担は大きく変わりません。
②取引先の状況
インボイス制度の登録を検討する場合、自身の状況だけでなく、取引先の状況を確認する必要があります。具体的には、インボイス制度への登録状況が挙げられるでしょう。
インボイス制度に登録している事業者が多い場合、仕入税額控除を取引先が受けられるようにするために自身の登録が必要です。一方で、登録している事業者が少ない場合には、積極的に登録しなくても良い可能性が高いでしょう。
ただし、自身が買い手となって仕入税額控除を受けたい場合には、インボイス制度の登録が必要であるため、このような場合と混合しないように注意してください。
③氏名の公表
インボイス制度に登録すると、国税庁のホームページ「適格請求書発行事業者公表サイト」で事業者の氏名が公表されます。
そのため、副業を禁止・制限している会社で勤めている場合には、公表サイトによって身バレしてしまうリスクが高まります。これはインボイス制度における弊害であるため注意が必要です。
身バレを避けたい場合には、インボイス制度への登録は避けたほうが無難でしょう。
関連記事:インボイス登録で公表される情報とは?サイトの使い方や個人事業主の立ち回りも
まとめ|事業や取引相手の状況を的確に捉え、インボイス制度への対応を!
本記事では、副業でインボイス制度の登録は必要なのかについて、基本的なルールや影響などを解説しました。
インボイス制度は、副業をおこなう事業者に対して大きな選択を迫る制度です。これからインボイス制度の登録を検討する際には、必ず基本的なルールや、自身への影響を理解し、自身や取引相手の状況を整理しておくことが大切です。
インボイス制度によって事業を停滞させないために、適切な対応・対策を講じるようにしましょう。