インボイスの請求書に8%の記載がない場合どうする?記載不要なケースと不備になる境界線
更新日:2025.12.06
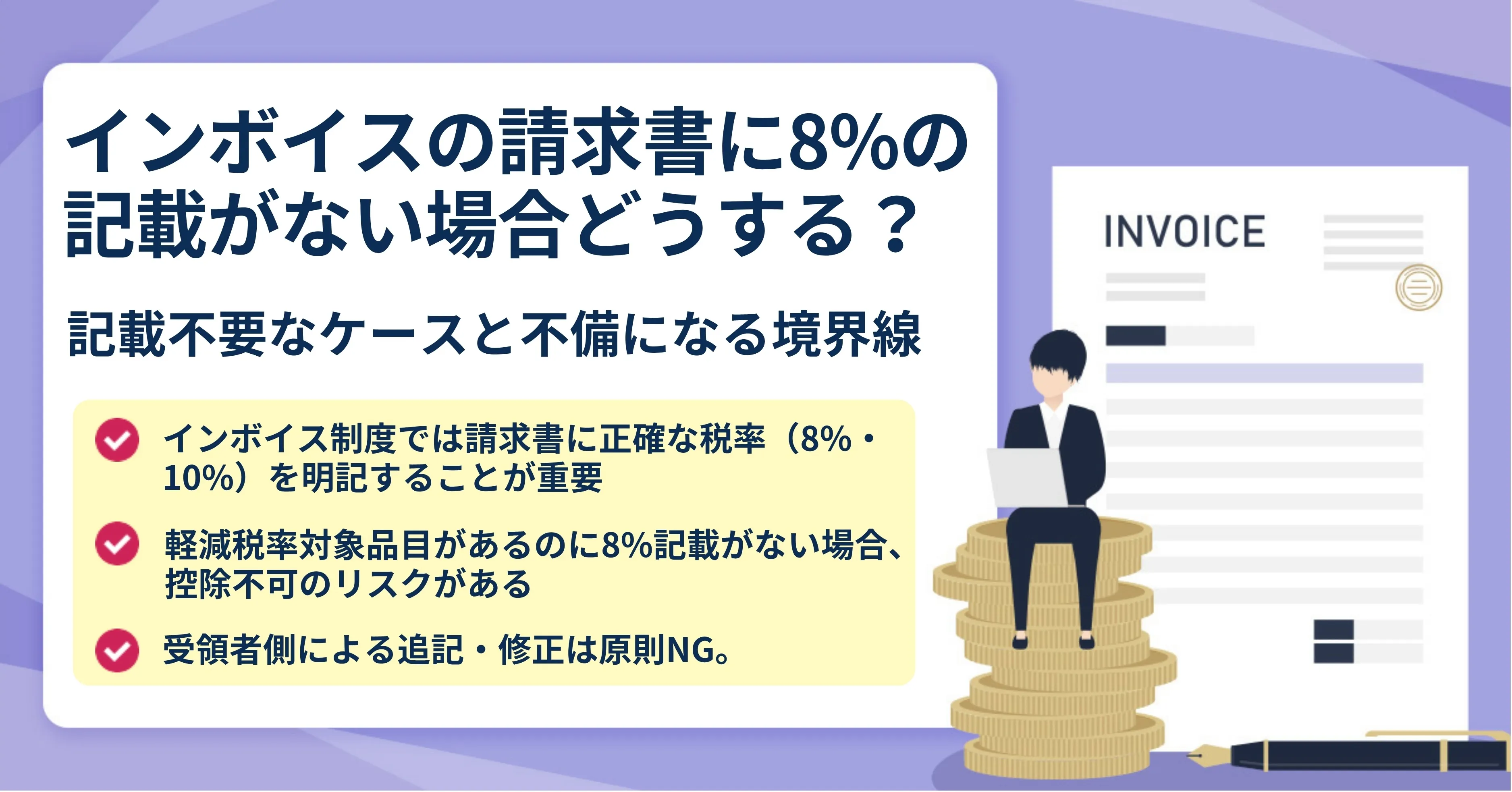
ー 目次 ー
インボイスに8%の記載がない場合、どう対応すべきか迷いますよね。
この記事では、記載がない場合に仕入税額控除が受けられなくなるケースや、実は記載が不要なケース、その判断基準についてわかりやすく解説いたします。正しく処理するための知識として、ぜひご活用ください。
インボイス制度と請求書の税率記載の基本をおさえよう!
2023年10月1日から開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、消費税の仕入税額控除の適用を受けるための新しい仕組みです。この制度において、請求書や領収書などの書類に正確な税率を記載することが極めて重要になります。
まずは、インボイス制度における請求書の基本的な記載ルールについて確認しましょう。
適格請求書(インボイス)に必要な記載事項とは?
適格請求書(インボイス)として認められるためには、以下の事項を記載する必要があります。これらの記載事項が一つでも欠けていると、原則として仕入税額控除の適用を受けることができません。
|
項目 |
記載内容 |
|
1. 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号 |
インボイス発行事業者の氏名(個人の場合)または名称(法人の場合)と、税務署から通知された「T」で始まる13桁の登録番号を記載します。 |
|
2. 取引年月日 |
課税資産の譲渡等を行った年月日を記載します。 |
|
3. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨) |
販売した商品や提供したサービスの内容を具体的に記載します。軽減税率(8%)の対象品目については、その旨がわかるように(例:「※軽減税率対象」など)明記する必要があります。 |
|
4. 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率 |
適用される税率(10%または8%)ごとに、合計した取引金額(税抜または税込)と、適用した税率そのものを記載します。例えば、「10%対象 XXXX円」「8%対象 YYYY円」のように記載します。 |
|
5. 税率ごとに区分した消費税額等 |
適用税率ごとに区分した消費税額または地方消費税額を記載します。消費税額の端数処理は、一つの適格請求書につき、税率ごとに1回ずつ行います。 |
|
6. 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称 |
請求書を受け取る相手方の事業者名を正確に記載します。 |
税率記載はなぜ必要?10%と8%が分けて書かれる理由
現在の日本の消費税制度では、標準税率10%と軽減税率8%の複数税率が採用されています。インボイス制度において、請求書にこれらの税率を明確に区分して記載することが求められる主な理由は、以下の2点です。
第一に、正確な消費税額の計算と把握のためです。事業者は、売上げにかかる消費税額から仕入れにかかった消費税額を差し引いて(これを仕入税額控除といいます)、納付する消費税額を計算します。軽減税率8%の対象となる品目(例:飲食料品(酒類・外食を除く)、新聞など)と、標準税率10%の対象となる品目が混在する取引の場合、それぞれの税率で消費税額を正しく計算し、区分して記載しなければ、正確な納税額を算出できません。
第二に、仕入税額控除の適用要件を満たすためです。インボイス制度では、買い手側が仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として売り手側から交付された適格請求書の保存が必要です。そして、その適格請求書には、税率ごとに区分された消費税額等が記載されていることが必須条件となります。もし8%対象の取引があるにもかかわらず、その旨や税率ごとの消費税額が明記されていなければ、買い手側はその部分について仕入税額控除を受けられないリスクが生じます。
請求書に8%の記載がない場合の考えられるケースと対処法
8%対象の取引があるのにインボイスに記載がない場合どうする?
飲食料品(酒類・外食を除く)や新聞(定期購読契約に基づくもの)など、軽減税率8%が適用される取引が含まれているにもかかわらず、受領した適格請求書(インボイス)にその旨の記載がない場合があります。このような場合、原則としてそのままでは仕入税額控除の適用を受けることができません。速やかな対応が必要です。
考えられる主な原因は以下の通りです。
- 発行側の単純な記載ミスやシステム設定の誤り
- 発行側がインボイスの記載要件を十分に理解していない
- 取引内容について、発行側と受領側で適用税率の認識に齟齬がある
いずれの場合も、まずは請求書の発行元に事実確認を行い、正しいインボイスの再発行を依頼することが基本的な対処法となります。
発行元への確認とインボイス再発行依頼のスムーズな進め方
発行元へ確認し、インボイスの再発行を依頼する際は、以下の点を押さえてスムーズに進めましょう。
|
ステップ |
内容 |
ポイント |
|
1. 状況の確認 |
受け取ったインボイスのどの部分に問題があるか(8%の記載がない、税率ごとの合計額がない等)を具体的に把握します。 |
請求書番号、取引年月日、具体的な商品名やサービス名を控えておくとスムーズです。 |
|
2. 発行元への連絡 |
電話やメールで発行元の経理担当者などに連絡を取ります。 |
丁寧な言葉遣いを心がけ、高圧的な態度は避けましょう。相手方も意図せず誤っている可能性があります。 |
|
3. 問題点の伝達 |
「〇月〇日付の請求書(No.XXXX)について、軽減税率8%対象の取引(例:商品A)が含まれておりますが、税率8%の記載および税率ごとの合計額の記載がございません。インボイスの要件を満たしていないため、仕入税額控除の処理ができません。」など具体的に伝えます。 |
インボイス制度の記載要件(税率ごとの消費税額等および適用税率)に触れると理解を得やすくなります。 |
|
4. 再発行の依頼 |
正しい記載がされたインボイスの再発行を明確に依頼します。 |
いつまでに再発行が必要か(自社の月次処理の締め日など)を伝えられると、相手方も対応しやすくなります。 |
|
5. 再発行インボイスの確認 |
再発行されたインボイスを受け取ったら、記載内容が正しく修正されているか(8%の税率、税額、対象品目が明記されているかなど)を必ず確認します。 |
問題が解消されていれば、仕入税額控除の処理を進めます。 |
取引先との良好な関係を維持するためにも、冷静かつ丁寧なコミュニケーションを心がけることが重要です。
受領したインボイスへの追記や修正は認められる?
受け取ったインボイスに8%の記載がないなどの不備があった場合、「自分で追記や修正をしてしまえば良いのでは?」と考えるかもしれません。しかし、原則として、受領側がインボイスに追記したり修正したりすることは認められていません。
適格請求書(インボイス)は、その発行事業者が記載内容に責任を負うものです。そのため、記載内容に誤りや不足がある場合は、必ず発行事業者に連絡し、修正された適格請求書の再発行を求める必要があります。
もし受領側で勝手に追記や修正を行った場合、そのインボイスは適格請求書としての要件を満たさないものとみなされ、仕入税額控除が否認されるリスクがあります。税務調査などで指摘される可能性もあるため、安易な追記・修正は絶対に避けましょう。
例外的に、仕入明細書等(買手側が作成し、相手方の確認を受けたもの)をインボイスとして保存する方法もありますが、これはあくまで買手側が発行するものであり、受領したインボイスへの追記・修正とは異なります。8%の記載がないインボイスを受け取った場合の基本は、発行元への再発行依頼であることを覚えておきましょう。
インボイスで8%の記載が不要となるケースを解説!
インボイスで10%のみ(標準税率)の取引なら8%の税率記載なしでOK
最も基本的なケースとして、行った取引のすべてが標準税率10%の対象である場合、インボイス(適格請求書)に軽減税率8%に関する記載は不要です。この場合、請求書には10%の税率とそれに対応する消費税額のみを記載すれば、インボイスの記載要件を満たします。
例えば、コンサルティング料や事務用品の販売など、軽減税率の対象となる品目(飲食料品や新聞など)を一切含まない取引のみを行った事業者が発行するインボイスがこれに該当します。この際、「8%対象品目なし」や「8% 消費税額 0円」といった記載を無理に行う必要はありません。インボイスの記載事項である「税率ごとに区分した消費税額等」および「適用税率」については、10%に関する情報のみで十分です。
簡易インボイス(適格簡易請求書)では8%記載は必要?
小売業、飲食店業、タクシー業、駐車場業など、不特定多数の者に対して商品やサービスを提供する特定の事業者は、通常の適格請求書に代えて、記載事項を簡略化した適格簡易請求書(簡易インボイス)を交付することが認められています。レシートなどがこれに該当することが多いです。
結論、簡易インボイスにおいても取引のすべてが標準税率10%対象であれば、8%に関する記載は不要です。
簡易インボイスの場合、税率の記載については、「税率ごとに区分した消費税額等」または「適用税率」のいずれか一方の記載でよいとされています。例えば、10%対象の商品しか取り扱っていない小売店のレシートであれば、「10%対象 合計額 XXXX円(うち消費税額等 XXX円)」または単に「適用税率10%」といった記載があれば問題ありません。
ただし、軽減税率8%対象の商品と標準税率10%対象の商品が混在する取引を行った場合は、簡易インボイスであっても、それぞれの税率に対応する消費税額等を記載するか、適用税率(8%と10%の両方)を明記する必要があります。具体的には、「8%対象 XXX円」「10%対象 YYY円」といった形で区別して表示します。
|
インボイスの種類 |
税率記載のルール(原則) |
10%のみの取引の場合の8%記載 |
|
適格請求書(インボイス) |
税率ごとに区分した消費税額等及び適用税率 |
不要(10%の税率と消費税額のみ記載) |
|
適格簡易請求書(簡易インボイス) |
税率ごとに区分した消費税額等または適用税率 |
不要(10%の税率と消費税額、または適用税率10%のみ記載) |
その他、インボイスで8%の記載が省略できる条件はある?
基本的に、軽減税率8%の対象となる取引が実際に行われたにもかかわらず、インボイスへの8%に関する記載を「省略」できる特別な条件は設けられていません。8%対象の取引が存在する場合には、その旨をインボイスに正確に記載することが原則です。
したがって、「8%の記載が不要となる」のは、具体的には以下のような状況が考えられます。
- 提供する全ての商品・サービスが標準税率10%の対象である場合。
- 売上値引きや返品、割戻しなど(売上にかかる対価の返還等)が発生し、適格返還請求書を発行する際に、その対象となった元の取引がすべて標準税率10%のみであった場合。この場合、適格返還請求書にも8%の記載は不要です。
これらのケースは、「省略」というよりは、「該当する税率の取引が存在しないため、記載する必要がない」と理解するのが適切です。インボイスの記載要件は、仕入税額控除を受けるための重要な根拠となりますので、取引の実態に即して正確に記載することが求められます。もし判断に迷う場合は、税理士や所轄の税務署に確認することをお勧めします。
つまり境界線はどこ?インボイスで記載不備になる場合のチェックポイント
明らかにインボイスの記載要件を満たさないパターン
まず、インボイスとして認められるための基本的な記載要件を満たしていないケースは、明確な記載不備となります。これには、8%の税率記載の有無以前の問題も含まれます。
- 発行事業者の登録番号の記載がない、または誤っている場合: 適格請求書発行事業者の登録番号はインボイスの必須事項です。この記載がなければ、インボイスとして認められません。
- 取引年月日が記載されていない場合: いつ行われた取引なのかを特定できない請求書は不備となります。
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)が記載されていない場合: 軽減税率の対象となる品目が含まれているにもかかわらず、その旨が明記されていない(例:「※」印などによる注記がない)場合は、税率の判定ができず不備となります。
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称の記載がない場合: 原則として、買い手の氏名または名称の記載が必要です。ただし、小売業、飲食店業、タクシー業などが交付する適格簡易請求書(簡易インボイス)の場合は省略可能です。
これらの基本的な項目が欠けていると、たとえ税率の記載が正しくてもインボイスとしての効力が認められない可能性があります。
8%と10%の区別が不明瞭なインボイスのリスク
複数の税率が適用される取引において、それぞれの税率対象品目や金額が明確に区別されていないインボイスは、記載不備と判断されるリスクが高まります。具体的には、以下のようなケースが考えられます。
- どの品目が8%で、どの品目が10%なのか判別できない: 商品名だけでは税率が判断できず、かつ軽減税率対象である旨の表示(例:「※」など)もない場合、税務調査などで指摘を受ける可能性があります。
- 税率ごとの合計額がまとめられていない: 8%対象の合計額と10%対象の合計額がそれぞれ記載されておらず、全体の合計額しか書かれていない場合、仕入税額控除の計算が困難になります。
このようなインボイスを受け取った場合、仕入税額控除の適用が認められない、あるいは税務署からの問い合わせや指導が入る可能性があり、経理処理の遅延や追加の事務負担が発生するリスクがあります。
税率ごとの合計額や適用税率の記載漏れと8%未記載
インボイスにおいて、特に8%の軽減税率対象取引があるにもかかわらず、その記載が不十分な場合は記載不備となります。具体的にどのような記載漏れが問題となるのか、チェックポイントをまとめました。
|
チェック項目 |
記載不備となるケース(8%対象取引がある場合) |
備考 |
|
軽減税率の対象品目である旨の記載 |
軽減税率対象の商品やサービスが含まれているにも関わらず、「※」印や「(軽)」などのように、軽減税率の対象品目であることが明記されていない。 |
どの品目が8%適用なのかを明確にする必要があります。 |
|
税率ごとに区分した合計対価の額(税抜または税込) |
8%対象の取引額と10%対象の取引額がそれぞれ集計されておらず、個別の金額が記載されていない。または、総額のみが記載されている。 |
「8%対象合計 ●●円」「10%対象合計 ▲▲円」のように、税率ごとの合計額を記載します。 |
|
適用税率 |
「8%」「10%」といった適用税率の記載がない、または税率ごとの合計額に対応して記載されていない。 |
それぞれの合計額に対して、どの税率が適用されているかを示す必要があります。 |
|
税率ごとに区分した消費税額等 |
8%対象の消費税額と10%対象の消費税額がそれぞれ記載されていない。または、合計消費税額のみが記載されている。 |
「8%対象消費税額等 ●●円」「10%対象消費税額等 ▲▲円」のように、税率ごとの消費税額等を記載します。 |
これらの項目は、適格請求書の必須記載事項です。8%対象の取引があるにもかかわらず、これらのいずれかが欠けている場合、その請求書はインボイスの要件を満たしていないと判断され、原則として仕入税額控除の適用を受けることができません。取引内容が10%のみの場合は、「8%」に関する記載は不要ですが、8%対象の取引が一つでもあれば、上記の記載が求められます。
まとめ
インボイスに8%の記載がない場合には、まず本当に軽減税率対象の取引が含まれているかをしっかり確認しましょう。対象取引があるにも関わらず記載が漏れている場合は、発行元に丁寧に連絡し、正しいインボイスの再発行を依頼することが大切です。逆に、10%の取引のみであれば8%の記載は必要ありません。経理処理や税務調査で不利益を被らないためにも、インボイス受領時には記載内容をしっかりチェックしておくと安心です。










