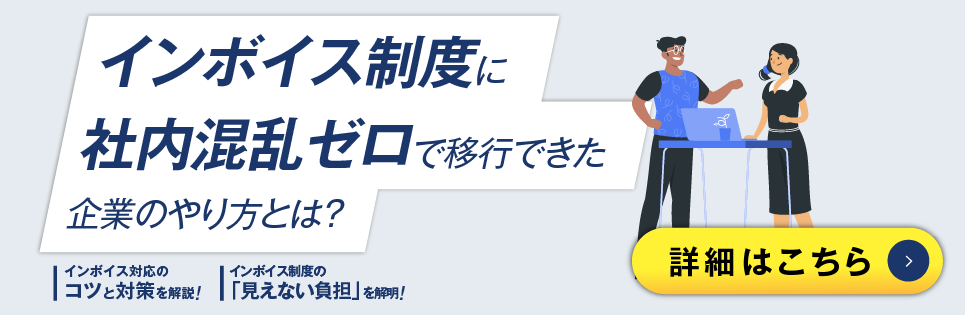インボイスの減免制度とは?経過措置の対象者・条件をわかりやすく解説
更新日:2026.01.29
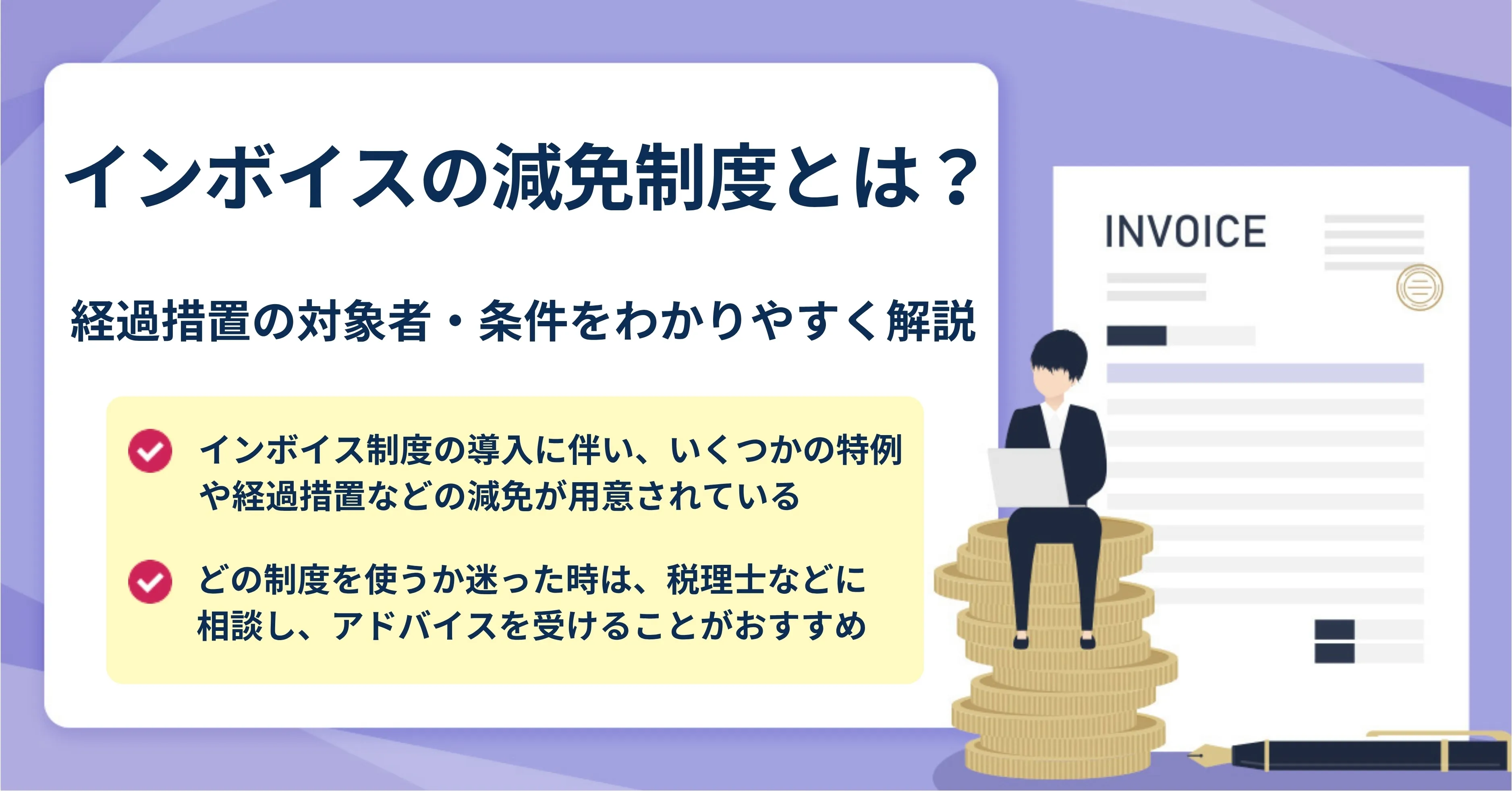
ー 目次 ー
インボイス制度の導入により、これまで以上に消費税の負担が重くなるのではと不安に感じていらっしゃいませんか?
この記事では、そうしたご負担を軽減するための「2割特例」や「少額特例」といった経過措置に加え、「簡易課税制度」についても分かりやすくご紹介します。事業者の皆さまにとって最も適した制度の選び方が見えてくる内容となっていますので、ぜひ参考になさってください。
インボイス制度における減免とは?基本的な考え方
2023年10月1日から始まったインボイス制度導入に伴う負担増を懸念し、「減免」措置について情報を求める方が増えています。この章では、インボイス制度における「減免」の基本的な考え方について解説します。
インボイス制度とは?
インボイス制度とは、正式には「適格請求書等保存方式」といい、消費税の仕入税額控除の適用を受けるための新しい仕組みです。この制度の下では、買い手側が仕入税額控除を受けるためには、原則として売り手側から交付された適格請求書(インボイス)の保存が必要となります。
適格請求書を発行できるのは「適格請求書発行事業者」として登録を受けた課税事業者のみです。この制度導入により、特に免税事業者や、免税事業者と取引のある課税事業者は、対応を迫られることになりました。
インボイス制度における減免とは?
インボイス制度では、「減免」という名前の決まった制度が法律で定められているわけではありません。けれども、制度の導入によって特に小規模な事業者に大きな負担がかかることを考慮し、いくつかの「特例」や「経過措置」が用意されています。
これらの措置は、実際には納税額や経理の手間を軽くする効果があるため、広く「減免」と呼ばれることがあります。たとえば、免税事業者がインボイス発行事業者として登録した場合の負担を軽くする「2割特例」や、少額取引の経理処理を簡単にできる「少額特例」などがその一例です。
つまり、「インボイス制度の減免」とは、税金が直接免除される特定の制度を指すのではなく、事業者の負担を軽減するために設けられた特例や経過措置の総称です。
インボイスの簡易課税とは?減免に関係あるのかわかりやすく解説
インボイス制度の開始に伴い、「簡易課税制度」が注目されています。その一つが「簡易課税制度」です。この制度は、直接的な「減免」措置とは異なりますが、事業者の納税事務負担を軽減することがあるため、関連知識として理解しておくことが重要です。
簡易課税の仕組みを解説
簡易課税制度とは、中小事業者の納税事務負担を軽減するために設けられた制度です。通常、消費税の納税額は「預かった消費税額(売上にかかる消費税額)」から「支払った消費税額(仕入れにかかる消費税額)」を差し引いて計算します(これを「本則課税」または「一般課税」といいます)。
しかし、簡易課税制度を選択すると、売上にかかる消費税額に、事業の種類ごとに定められた「みなし仕入率」を掛けて仕入控除税額を計算します。つまり、実際の仕入れにかかった消費税額を個別に集計・計算する必要がありません。
納税額の計算式は以下の通りです。
納税額 = 売上にかかる消費税額 - (売上にかかる消費税額 × みなし仕入率)
みなし仕入率は、事業の業種によって区分されており、以下のようになっています。
|
事業区分 |
みなし仕入率 |
該当する事業(例) |
|
第一種事業 |
90% |
卸売業 |
|
第二種事業 |
80% |
小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業) |
|
第三種事業 |
70% |
農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業 |
|
第四種事業 |
60% |
第一種事業、第二種事業、第三種事業、第五種事業、第六種事業以外の事業(例:飲食店業) |
|
第五種事業 |
50% |
運輸通信業、金融・保険業、サービス業(飲食店業に該当するものを除く) |
|
第六種事業 |
40% |
不動産業 |
このように、簡易課税制度は結果的に納税額が少なくなるケースや事務負担が軽減されるという点で、事業者にとって有利な選択肢となり得ます。
簡易課税の対象者と注意点
簡易課税制度を利用するには、いくつかの条件があり、また注意すべき点も存在します。
簡易課税の対象者
簡易課税制度を選択できる事業者は、以下の要件を満たす必要があります。
- 基準期間(個人事業者の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度)の課税売上高が5,000万円以下であること。
- 原則として、適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地を管轄する税務署長に提出していること。ただし、新規開業や設立の場合は、その開業・設立した課税期間中に届出書を提出すれば、その課税期間から適用を受けることができます。
簡易課税の注意点
簡易課税制度を選択する際には、以下の点に注意が必要です。
- 一度選択すると原則2年間は継続適用: 簡易課税制度を選択した場合、原則として2年間は本則課税に変更することはできません。事業の状況が大きく変わる可能性がある場合は、慎重な判断が求められます。
- 実際の仕入税額が多い場合は不利になる可能性: みなし仕入率を用いて計算するため、多額の設備投資を行った場合や、仕入れが多い業態で、実際に支払った消費税額がみなし仕入率で計算した仕入控除税額よりも大きい場合には、本則課税を選択した方が納税額が少なくなることがあります。
- インボイスの保存は原則不要だが発行義務はある: 簡易課税制度の適用を受ける事業者は、仕入税額控除の計算にあたってインボイスの保存は必要ありません。ただし、売手としてインボイス発行事業者の登録を受けている場合は、買手から求められた際にインボイスを交付する義務があります。
- 複数の事業を行っている場合: 複数の種類の事業を行っている場合、原則としてそれぞれの事業の売上を区分し、該当するみなし仕入率を適用して計算します。もし事業ごとの売上を区分していない場合は、その区分していない売上全体に対して、最も低いみなし仕入率が適用されるため注意が必要です。
- 免税事業者から課税事業者になる際の検討: インボイス制度の開始を機に免税事業者からインボイス発行事業者(課税事業者)になった場合、消費税の申告義務が生じます。その際、本則課税と簡易課税のどちらを選択するか検討が必要となり、簡易課税を選択する場合は事前の届出が不可欠です。
簡易課税制度は事務負担の軽減に優れていますが、本則課税との比較も忘れず、慎重に判断する必要があります。
2割特例とは?減免のメリット・デメリットと対象者
インボイス制度の導入により、免税事業者が新たに課税事業者となるケースが増えています。そうした事業者の税負担を抑えるために設けられたのが「2割特例」です。本記事では、その概要やメリット・デメリット、対象条件について分かりやすくご紹介します。
2割特例を利用するメリット
2割特例を活用することで、インボイス制度に対応する事業者は以下のようなメリットを享受できます。
- 納税額の大幅な軽減: 最大のメリットは、売上にかかる消費税額の2割を納付すれば済む点です。例えば、売上税額が100万円だった場合、納税額は20万円となり、80万円分の負担が軽減されます。特に、仕入れが少ないサービス業や、経費に占める人件費の割合が高い業種にとっては、大きな節税効果が期待できます。
- 経理事務の簡素化: 消費税の申告において、原則課税の場合は仕入れにかかった消費税額を正確に把握し、インボイス(適格請求書)を保存・管理する必要があります。しかし、2割特例を適用すれば、売上税額さえ把握していれば納税額を計算できるため、仕入税額控除のための複雑な計算やインボイスの集計作業が不要となり、経理事務の負担が大幅に軽減されます。
- 事前の届出が不要: 簡易課税制度を利用する場合は、原則として適用を受けたい課税期間の開始日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出する必要があります。一方、2割特例は事前の届出が不要で、消費税の確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記するだけで適用を受けられます。この手軽さも大きなメリットと言えるでしょう。
2割特例を利用するデメリット
メリットの多い2割特例ですが、以下のようなデメリットや注意点も存在します。これらを理解した上で、制度の利用を検討することが重要です。
- 期間限定の措置であること: 2割特例は恒久的な制度ではなく、適用期間が限定されています。具体的には、2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する各課税期間のみ適用可能です。この期間が終了した後は、原則課税または簡易課税(要件を満たせば)のいずれかの方法で消費税を申告・納付する必要があるため、将来的な対応も視野に入れておく必要があります。
- 仕入税額が多い場合は不利になる可能性: 2割特例では、売上税額の8割をみなし仕入率として控除しますが、実際の仕入れや経費にかかる消費税額が売上税額の8割を超えるような業種や、高額な設備投資を行った課税期間などでは、原則課税で申告した方が納税額が少なくなる可能性があります。どちらが有利になるか、事前にシミュレーションを行うことが望ましいでしょう。
- 簡易課税制度との併用は不可: すでに簡易課税制度を選択している事業者は、2割特例を適用できません。2割特例の適用を希望する場合は、簡易課税制度の選択を取りやめる必要がありますが、その手続きやタイミングには注意が必要です。
2割特例の対象者と適用条件
2割特例の適用を受けることができるのは、インボイス制度の開始をきっかけに免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった方です。具体的には、以下の全ての条件を満たす個人事業主または法人が対象となります。
- インボイス発行事業者の登録を受けたことによって、新たに課税事業者となった者であること。
- 基準期間(個人事業主の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下であること。または、特定期間(個人事業主の場合は前年の1月1日から6月30日まで、法人の場合は前事業年度開始の日以後6ヶ月間)の課税売上高または給与等支払額が1,000万円以下であること。
- 課税期間を1ヶ月または3ヶ月に短縮する特例の適用を受けていないこと。
なお、2023年9月30日以前から課税事業者であった場合や、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者、資本金1,000万円以上の新設法人などは、原則として2割特例の対象外となりますので注意が必要です。
2割特例の適用期間と具体的な計算方法
2割特例をいつからいつまで利用できるのか、そして具体的にどのように納税額を計算するのかを見ていきましょう。
適用期間:
2割特例の適用対象となる期間は、2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する各課税期間です。
- 個人事業主の場合:2023年10月1日から2023年12月31日までの申告(2023年分)から、2026年1月1日から2026年12月31日までの申告(2026年分)までが対象となります。ただし、2026年分の申告については、2026年10月1日以降の取引は対象外です。
- 法人の場合:事業年度によって異なりますが、上記の期間が含まれる課税期間が対象です。例えば3月決算法人の場合、2023年10月1日を含む事業年度から、2026年9月30日を含む事業年度までが対象となります。
具体的な計算方法:
2割特例を適用した場合の消費税の納税額は、非常にシンプルな計算式で算出できます。
納税額(国税) = 売上にかかる消費税額 × 20%
例えば、ある課税期間の課税売上高が550万円(うち消費税額50万円)だった場合、納税額は以下のように計算されます。
50万円(売上税額) × 20% = 10万円(納税額)
この計算により、本来50万円納めるはずだった消費税が10万円に軽減されます。この計算には、仕入れにかかった消費税額を考慮する必要はありません。なお、実際に納付する税額は、この国税としての消費税額に加えて、地方消費税額(国税である消費税額の22/78)も含まれます。地方消費税も同様に軽減されるため、トータルの納税額も売上税額の2割相当となります。
以下に、2割特例の概要をまとめます。
|
項目 |
内容 |
|
制度名 |
2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置) |
|
適用対象期間 |
2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する各課税期間 |
|
主な対象者 |
インボイス発行事業者の登録を機に免税事業者から課税事業者になった個人事業主・法人(基準期間の課税売上高1,000万円以下等) |
|
納税額の計算方法 |
売上税額 × 20% (国税分。地方消費税も同様に計算) |
|
事前の届出 |
不要(確定申告書に付記して申告) |
|
主なメリット |
納税額の大幅な軽減、経理事務の簡素化 |
|
主なデメリット |
期間限定の措置、仕入税額が多い場合は不利になる可能性 |
ご自身の事業が対象となるか、また、他の制度と比較してメリットがあるかを慎重に検討し、賢く活用しましょう。
少額特例とは?減免のメリット・デメリットと適用条件
インボイス制度では、事業者の負担を軽減するために「少額特例(少額な返還インボイスの交付義務免除)」が設けられています。少額の経費が多い事業者にとって、事務負担を減らす有効な手段となります。
少額特例を利用するメリット
少額特例を利用することには、以下のようなメリットがあります。
- 事務負担の軽減: 1万円未満の取引について、インボイスの受領・確認・保存といった一連の作業が不要となるため、経理処理にかかる手間や時間を大幅に削減できます。特に、消耗品の購入や交通費の精算など、少額の取引が頻繁に発生する事業者にとっては大きなメリットです。
- 仕入税額控除の適用容易化: インボイスの入手が困難な場合や、受け取ったインボイスに不備があった場合でも、帳簿への適切な記載と保存があれば仕入税額控除を受けることができます。これにより、控除漏れのリスクを低減できます。
- キャッシュレス決済等での利便性向上: クレジットカード明細や交通系ICカードの利用履歴など、インボイスの要件を満たさない書類でも、帳簿への記載があれば仕入税額控除の対象とできるため、経費精算の柔軟性が増します。
少額特例を利用するデメリット
一方で、少額特例の利用にはいくつかの注意点やデメリットも存在します。
- 対象取引金額の上限: この特例が適用されるのは、1回の取引の税込価額が1万円未満のものに限られます。1万円以上の取引については、原則通りインボイスの保存が必要です。
- 対象事業者の制限: 少額特例を利用できるのは、基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者、または特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者に限られます。これを超える規模の事業者は対象外となります。
- 期間限定の措置: この特例は、2023年10月1日から2029年9月30日までの間の課税仕入れに適用される期間限定の措置です。将来的に制度が変更される可能性も考慮しておく必要があります。
- 帳簿記載の義務: インボイスの保存は不要になりますが、代わりに帳簿へ記載すべき事項が増えます。具体的には、仕入れの相手方の氏名または名称、取引年月日、取引内容、支払対価の額に加え、「少額特例の対象である旨」を明記する必要があります。この帳簿作成と保存を怠ると、仕入税額控除が認められない可能性があります。
少額特例の対象者と適用条件
少額特例の対象となる事業者と、適用を受けるための具体的な条件は以下の通りです。これらの条件を正確に理解し、適切に対応することが重要です。
|
項目 |
内容 |
|
対象者 |
基準期間(前々事業年度または前々年)における課税売上高が1億円以下の事業者、または特定期間(前事業年度の開始の日以後6か月の期間または前年の1月1日から6月30日までの期間)における課税売上高が5千万円以下の事業者(個人事業主・法人を問いません)。 |
|
対象となる取引 |
国内で行われる課税仕入れのうち、その支払対価の額(税込)が1万円未満のもの。 |
|
必要な帳簿記載事項 |
以下の事項を記載した帳簿の保存が必要です。
|
|
適用期間 |
2023年10月1日から2029年9月30日までの間に行われる課税仕入れ。 |
インボイスの減免は何を使えばいい?自分に合う制度の選び方!
インボイス制度の開始に伴い、事業者の負担を軽減するための様々な経過措置が用意されていますが、どの制度を利用すれば自社にとって最もメリットが大きいのか、判断に迷う方も多いのではないでしょうか。
この章では、これまでにご紹介した「簡易課税制度」「2割特例」「少額特例」について、それぞれの特徴を踏まえ、ご自身の状況に合った制度を選ぶためのポイントを解説します。
タイプ別に見る!紹介した3つの制度のおすすめの選び方
どの制度が適しているかは、事業者の売上規模、業種、取引の状況などによって異なります。ここでは、代表的なケース別に、おすすめの制度とその理由について見ていきましょう。
各制度の概要比較
まずは、それぞれの制度の主な特徴を比較してみましょう。ご自身の状況と照らし合わせながらご確認ください。
|
制度名 |
主な対象者 |
メリット |
デメリット・注意点 |
事前の届出 |
適用期間の目安 |
|
簡易課税制度 |
基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者 |
仕入税額の計算が簡便、みなし仕入率によっては納税額が有利になる場合がある |
実際の仕入が多くてもみなし仕入率で計算、有利不利の判断が必要、一度選択すると原則2年間継続 |
必要(「消費税簡易課税制度選択届出書」を適用を受けたい課税期間の開始の日の前日までに提出) |
恒久的(要件を満たす限り) |
|
2割特例 |
インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった事業者(適格請求書発行事業者) |
売上税額の2割を納付すればよく、計算が非常に簡便、税負担が大幅に軽減される可能性 |
対象期間が限定的、簡易課税制度を選択している場合は適用不可(有利な方を選択可能) |
原則不要(確定申告書に適用を受ける旨を付記) |
2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する各課税期間 |
|
少額特例(少額な返還インボイスの交付義務免除) |
全ての事業者(売手側) |
税込1万円未満の値引きや返品等について、返還インボイスの交付が不要となり事務負担軽減 |
適用対象が限定的(値引き・返品等であり、直接的な納税額の減免ではない) |
不要 |
恒久的 |
|
少額特例(一定規模以下の事業者の少額な仕入れに係る帳簿のみの保存による仕入税額控除) |
基準期間の課税売上高が1億円以下、または特定期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者(買手側) |
税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくても帳簿のみで仕入税額控除が可能となり事務負担軽減 |
対象期間が限定的、対象となる取引金額に上限あり |
不要 |
2023年10月1日から2029年9月30日までの仕入れ |
※少額特例には、売手側の「少額な返還インボイスの交付義務免除」と、買手側の「一定規模以下の事業者の少額な仕入れに係る帳簿のみの保存による仕入税額控除」の2種類があります。インボイスの減免という観点では、2割特例や簡易課税制度が直接的な納税額の軽減につながる可能性があります。少額特例は主に事務負担の軽減や、買手側における仕入税額控除の適用要件緩和に関するものです。
ケース1:インボイス発行のために免税事業者から課税事業者になった方
これまで免税事業者だった方が、インボイス制度への対応のために適格請求書発行事業者の登録を受け、課税事業者になった場合には、まず「2割特例」の適用を検討しましょう。
事前の届出も原則不要で、確定申告時に適用を受ける旨を記載するだけで済みます。
ただし、2割特例の適用期間は2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する各課税期間と限定的です。その後の対応も視野に入れつつ、まずはこの特例を活用するのがおすすめです。業種や取引内容によっては「簡易課税制度」の方が有利になるケースもあるため、比較検討することも重要です。
ケース2:基準期間の課税売上高が5,000万円以下で、経理事務を簡素化しつつ納税額も抑えたい事業者の方
基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が5,000万円以下で、消費税の計算事務を簡略化したい事業者の方には、「簡易課税制度」が適している場合があります。
簡易課税制度は、売上にかかる消費税額に業種ごとに定められた「みなし仕入率」を掛けて仕入税額控除額を計算するため、実際の仕入れや経費に関するインボイスを一枚一枚集計・保存する手間が軽減されます。みなし仕入率が高い業種で、かつ実際の仕入率(課税売上に対する課税仕入の割合)が低い場合には、本則課税(原則課税)よりも納税額が少なくなることがあります。
ただし、簡易課税制度を選択するには、原則として適用を受けたい課税期間の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出する必要があります。また、一度選択すると原則として2年間は継続適用しなければならない点にも注意が必要です。
ケース3:少額な経費の支払いが多い事業者の方(買手側)
税込1万円未満の経費の支払いが多い事業者の方で、基準期間の課税売上高が1億円以下または特定期間(個人事業者は前年1月~6月、法人は前事業年度開始の日以後6ヶ月)の課税売上高が5,000万円以下の場合、「少額特例(一定規模以下の事業者の少額な仕入れに係る帳簿のみの保存による仕入税額控除)」の利用を検討できます。これは買手側の特例です。
この特例を利用すると、2023年10月1日から2029年9月30日までの間に行う税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくても、一定の事項を記載した帳簿を保存していれば仕入税額控除が認められます。これにより、少額取引に関するインボイスの管理負担が軽減されます。
なお、売手側としては、全ての事業者を対象に、税込1万円未満の値引きや返品等を行った場合に返還インボイスの交付義務が免除される「少額な返還インボイスの交付義務免除」という別の少額特例もあります。こちらは事務負担軽減に繋がります。
複数の制度の対象となる場合の考え方
事業者の状況によっては、複数の制度の適用対象となる場合があります。例えば、インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になり、かつ基準期間の課税売上高が5,000万円以下である場合などです。この場合、「2割特例」と「簡易課税制度」のどちらを選択するかがポイントになります。
一般的には、免税事業者から課税事業者になった当初は「2割特例」が有利になるケースが多いと考えられます。しかし、業種や実際の仕入れ状況によっては「簡易課税制度」のみなし仕入率を適用した方が納税額が少なくなる可能性もあります。どちらが有利になるかは、ご自身の事業の売上や仕入れの状況を具体的にシミュレーションして比較検討することが最も重要です。「2割特例」と「簡易課税制度」は、有利な方を選択適用できますが、簡易課税制度の適用には事前の届出が必要な点に留意しましょう。
どの制度を選択すべきか迷った場合は、税理士などの専門家に相談し、アドバイスを受けることをおすすめします。自社にとって最適な制度を選択し、インボイス制度への対応をスムーズに進めましょう。
まとめ
インボイス制度に対応する中で、事業者の方々にとって重要となるのが「2割特例」や「少額特例」、さらに「簡易課税制度」といった各種の経過措置です。それぞれの制度には適用条件やメリット・注意点がありますが、ご自身の売上規模や取引の状況などに応じて適切に選択することで、税負担や事務作業を大きく軽減できる可能性があります。不明点がある場合には、専門家へのご相談も視野に入れながら、無理なくスムーズに制度へ対応できるようご準備を進めてみてください。