インボイス登録で公表される情報とは?サイトの使い方や個人事業主の立ち回りも
更新日:2026.01.29
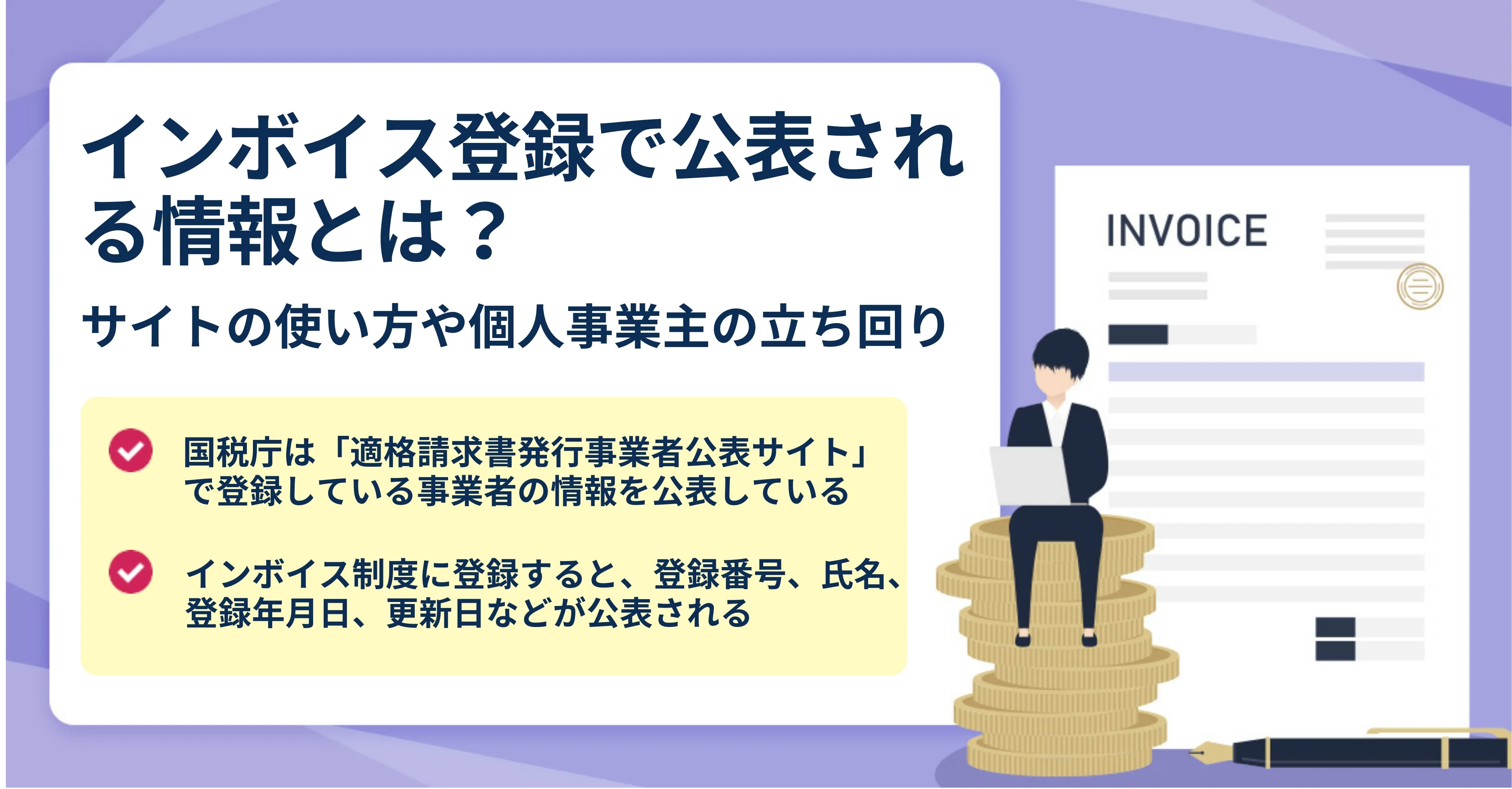
ー 目次 ー
インボイス制度では登録してしまうと、公表される情報があるため注意が必要です。とくに、副業やフリーランスとして活動する方の場合、身バレによるトラブルに巻き込まれる可能性があります。
インボイス制度は消費税に関する大切なルールであることから、どのような情報が公開されて、どのような影響があるのか、また登録をしない場合の影響はどのようなものなのかを知っておく必要があるでしょう。
本記事では、インボイス制度の登録で公表される情報について、公表サイトの使い方や個人事業主の立ち回りも交えて解説します。
【おさらい】インボイス制度とは?ポイントを簡単に解説!
インボイス制度とは消費税の計算や請求書類の記載に関するルールを定めたものです。その目的は事業者が納める税金を正確に把握することにあります。
従来のルールと比べても請求書の作成や保存、また消費税の申告や納税での対応をしっかりとおこなう必要があり、どのような制度なのかを知っておかないと、取引先も巻き込むトラブルに発展しかねません。
ここでは、インボイス制度のポイントについて、解説します。
①「仕入税額控除」が利用できる
事業は通常、商品やサービスを提供するための仕入れをおこなっており、この仕入れに対しても消費税が発生しています。
インボイス制度では、売上に対して発生する消費税から、仕入れに支払った消費税を差し引け、納付すべき消費税の負担を和らげられます。これを「仕入税額控除」と呼び、結果的に消費税の納税額を抑えられる可能性があることから、インボイス制度を活用するメリットの1つとして挙げられるでしょう。
②「適格請求書発行事業者」に登録する必要がある
インボイス制度では「適格請求書(インボイス)」による請求対応が求められます。加えて、この適格請求書を発行するためには「適格請求書発行事業者」への登録も必要です。
この適格請求書発行事業者は課税事業者と同様に扱われ、仮に課税売上が免税事業者に該当する事業者であっても消費税の申告や納付が必要になります。そのため、もし免税事業者がインボイス制度の登録を検討していれば、その点に注意が必要です。
【注意】インボイスに登録すると、氏名や登録した日付などが公表される!公表される情報も紹介!
国税庁では「インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイト」を運営しており、このサイト内で登録された氏名や登録した日付などの情報を公表しています。個人事業主と法人で公表される情報は異なり、具体的には以下のとおりです。
- 個人:登録番号、氏名または名称、登録年月日、更新日
- 法人:登録番号、氏名または名称、登録年月日、本店または事業所の住所、更新日
なお、個人事業主では住所の公表を任意で決められます。ただ、公表した際のリスクが十分にあることから、住所の公表は慎重に考えてからおこなうようにしましょう。
インボイス制度の公表サイトとは?実際のイメージや使い方を確認
インボイス制度では登録した事業者の一部情報を「インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイト」で公表しています。この公表サイトは国税庁が運営しており、簡単な操作で登録されている情報の開示が可能です。
ここでは、インボイス制度の公表サイトについて、実際のイメージや使い方を紹介します。
公表サイトで公表される際のイメージ
公表サイトでは、基本的に登録番号や氏名・名称、登録年月日、更新日の情報を公表しています。公表されている様子は、国税庁のサイトでもイメージを掲載しており、簡単に確認できます。
<個人事業主の場合>

出典:国税庁「インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイト」
<法人の場合>

出典:国税庁「インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイト」
公表サイトは、調べたい事業所の登録番号を入れて使用する
基本的な操作方法として、調べたい事業所の登録番号(「T」を除く13桁の半角数字)を入力して検索して使用します。複数の事業所を調べたい場合には、最大10件まで同時に検索可能です。
また、公表情報ダウンロード画面より、全件データをダウンロードして事業者を調べる方法もあります。該当のページからデータをダウンロード、ファイルを開くだけの操作であるため、こちらの方法でも簡単です。
インボイス制度を登録したことによるリスクとは?公表でのデメリットを紹介
インボイス制度では登録したことによって、氏名や登録年月日などの情報が公表されてしまいます。公表されたことによってアクシデントが発生するリスクもあるため、どのような問題があるのかを知っておく必要があるでしょう。
ここでは、インボイス制度を登録したことによるリスクについて、解説します。
- ストーカー被害
- 営利目的による情報収集
- 副業の身バレ
①ストーカー被害
公表サイトでは住所を公表する可能性があり、公表したことによって自宅や事業所の場所がバレてしまうリスクがあります。とくに、個人事業主で自宅を事業所としていた場合に、ストーカー被害に遭う可能性も否定できません。
法人では住所の公表は必須となっているものの、個人事業主では公表は任意であることから、公表しない方向で検討しておきましょう。
②営利目的による情報収集
公表サイトは利用規約に「サイトのコンテンツにおける商用利用」を可能としています(※)。このことから営利目的で利用する業者もおり、執拗な営業行為を受けるリスクをはらんでいます。
氏名や名称のみであれば大胆な営業活動はしづらいため、住所の公表は避けておいたほうが無難でしょう。
(※)参考:国税庁「利用規約」
③副業の身バレ
公表サイトでは氏名・名称を公表しており、誰でも利用できることから、全件データから簡単に個人事業主として登録されているかどうかの確認が可能です。もし副業が推奨されていない会社に勤めていれば、人事担当者に検索されてしまうリスクがあります。
インボイス制度に登録してしまうと公表されてしまうため、副業の身バレが不安な場合には登録しないことも方法の1つでしょう。
【大切】公表によるリスクを回避するために必要な個人事業主の立ち回りとは?対策を紹介
個人事業主として事業を運営しているなかで、情報が公表されたことによるリスクが大きいと感じる場合には対策を講じる必要があります。方法は限られているものの、上手に立ち回れば、公表せずにインボイス制度を活用できます。
ただ、根本的な問題の解消にはなっていないため、その点を踏まえて検討しましょう。
ここでは、公表によるリスクを回避するために必要な個人事業主の立ち回りについて、2つ紹介します。
①インボイス制度への登録をしない
もしインボイス制度を登録しなくても問題ないことがわかっている場合には、登録をしない選択肢もあります。
これは、取引先との関係も問題なく、また仕入税額控除を受けるメリットがあまりない事業者が該当します。このような場合には従来の対応で特段問題ないことから、インボイス制度の登録をする必要がありません。
もし自身の事業内容や事業規模、取引先との関係性などを整理できていない場合は、一度整理してみてください。
②媒介者交付特例を活用する
媒介者交付特例は顧客との取引間で「媒介業者」を立て、適格請求書(インボイス)の代理交付をおこなってもらえる制度です。この制度を利用するためには要件がいくつかあるため、活用する場合には事前に確認しておきましょう。
インボイス制度での公表は避けられないものの、取引によって身バレするリスクを避けられます。
参考:国税庁「適格請求書等保存方式(インボイス)の手引き」25ページ
まとめ:インボイス制度の登録は、公表される情報やリスクを天秤にかけて検討しよう!
本記事では、インボイス制度の登録で公表される情報について、公表サイトの使い方や個人事業主の立ち回りも交えて解説しました。
インボイス制度の登録がまだの事業者は、事業運営や発生する税金、また公表されたことによるリスクなどを総合的に勘案し、登録を検討するべきでしょう。インボイス制度はあくまでも税金にまつわる大切なルールであるため、事業を運営していればいずれ生じる問題となります。
本記事の内容や本メディアで取り挙げている情報を参考に、インボイス制度のルールを最低限おさえてから行動するようにしましょう。










