【テンプレートあり】インボイス(適格請求書)の書き方とは?記載例をもとに要件も解説
更新日:2026.01.29
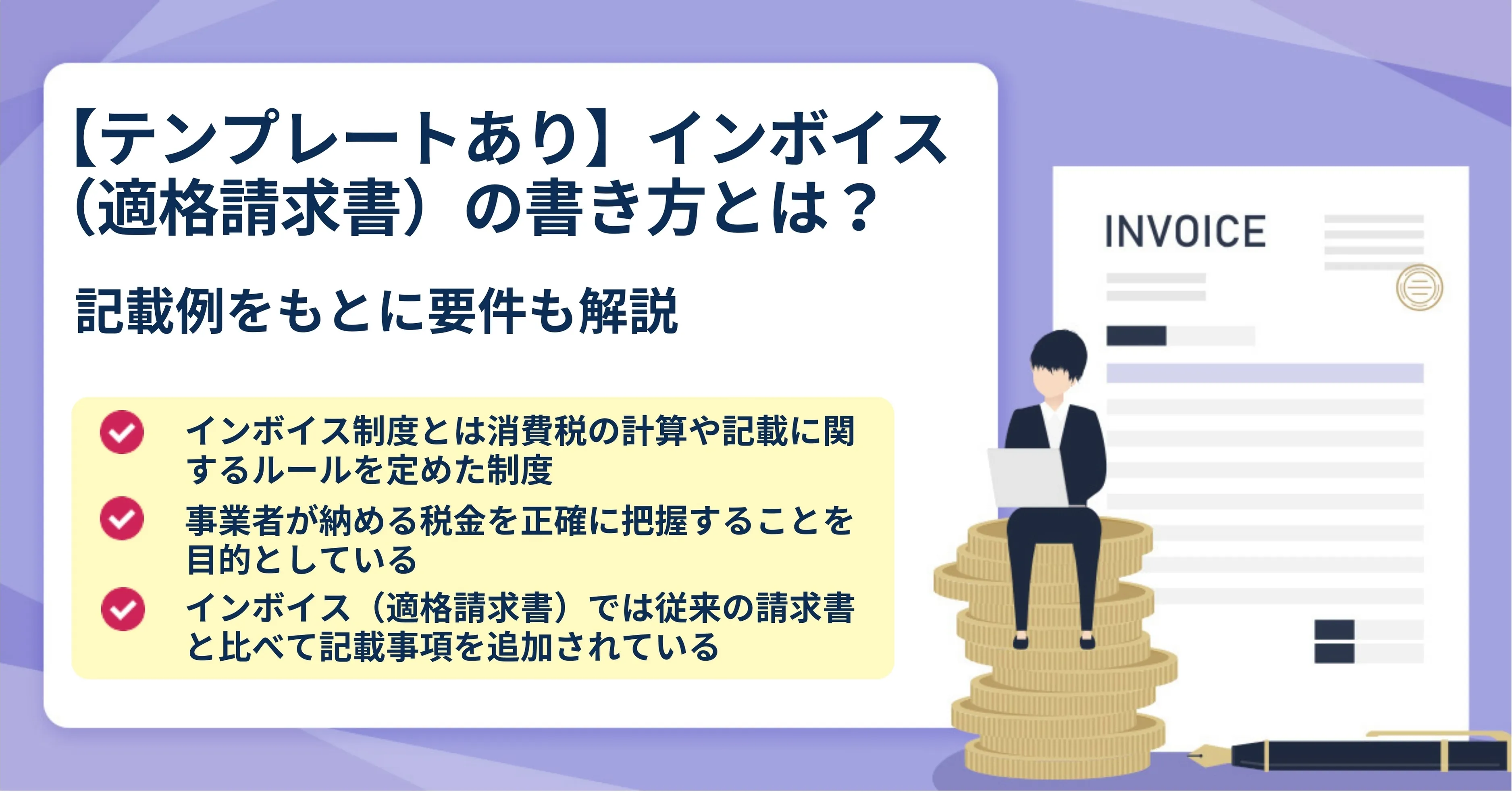
ー 目次 ー
2023年10月、消費税の計算や請求書の書き方のルールを定めた「インボイス制度」がスタートしました。この制度では、従来の請求書の記載方式から「適格請求書発行方式」に変更となり、「インボイス(適格請求書)」の発行・保存が必須となっています。
インボイス制度は消費税に関するルールであることから、誤った対応をしてしまえば自社だけでなく、取引先も税金のトラブルに巻き込んでしまうリスクがあります。
このようなリスクを避けるためにも、インボイスの書き方や消費税の計算方法などの細かなルールを把握しておくことが大切です。
本記事では、インボイス(適格請求書)の書き方について、記載例をもとに要件も解説します。
【基本】インボイス制度とは、消費税の計算や請求書の書き方を定めたルール
2023年10月にスタートした「インボイス制度」とは、消費税の計算や記載に関するルールを定めた制度です。この制度では、事業者が納める税金を正確に把握することを目的としています。
インボイス制度では「インボイス(適格請求書)」の発行・保存が必要です。また、この制度を活用するためには「インボイス発行事業者」の登録が求められます。
これらの要件を満たした場合には、売上の消費税額から仕入で支払った消費税額を控除できる「仕入税額控除」が利用でき、税負担が和らぐ可能性があります。
このようにインボイス制度が施行され、これまで以上に消費税に関係する請求書や領収書などでしっかりとした対応が求められるようになりました。
インボイス(適格請求書)の書き方とは?記載例・テンプレートも紹介
インボイス(適格請求書)では、従来のルールと比べて記載事項が追加されています。もし定められたルールを守らなかった場合、インボイスとして扱われず、仕入税額控除の活用もできなくなるため注意が必要です。
このようなことから本記事の記載例を参考に、自社のテンプレートを作成しておくと良いでしょう。
ここでは、インボイス(適格請求書)の書き方について、記載例を交えながら記載事項ごとのポイントを解説します。
- 発行者の氏名や名称
- インボイスの登録番号
- 取引年月日
- 支払期日
- 取引内容
- 取引金額
- 請求書を受け取る事業者の氏名や名称
発行日:20XX年XX月XX日 請求書 〇〇株式会社 御中 自社名 件名:〇〇のご請求について
※軽減税率(8%)の対象商品
|
①発行者の氏名や名称
請求書の発行元を明確にするために、自身の氏名・会社名や住所などを記載します。
インボイス(適格請求書)では、インボイス発行事業者として申請した正式名称を記載する必要があるため注意が必要です。
②インボイスの登録番号
インボイス(適格請求書)を発行する場合には、インボイス発行事業者として申請した際に発行された登録番号の記載が必要です。
この登録番号は「T」からはじまる13桁の数字で構成されています。法人の場合には法人番号が、個人事業主の場合には法人番号と重複しない数字が発行されます。
③取引年月日
発行するインボイス(適格請求書)には取引をおこなった日を明記しなければなりません。もし、複数取引をまとめて請求する場合には、取引ごとの取引年月日を記載しましょう。
④支払期日
インボイス(適格請求書)には支払期日を記載しましょう。
一般的には支払期日は、「60日以内」とされているため、取引先と相談して日程を決めることが大切です。ただ、もし取引先との関係が「下請代金支払遅延防止法」にあてはまる場合には、「60日以内かつ限りなく早くの期間」が定められています(※)。
(※)参考:公正取引委員会・中小企業庁「ポイント解説 下請法」
⑤取引内容
インボイス(適格請求書)には必ず、取引先に提供した商品・サービスの取引内容を記載します。記載する際には取引ごとに種類や単価、数量を記載してください。
なお、もし取引内容に軽減税率対象の品目があればその旨の記載が必要です。
⑥取引金額
取引先に提供した商品やサービスの対価として受け取る金額を記載します。これは商品金額だけでなく、税率ごとに合計した取引金額と消費税額の記載も必要です。
⑦請求書を受け取る事業者の氏名や名称
インボイス(適格請求書)を受け取る側の事業者の氏名・会社名を記載します。
記載する名称は会社によっては指定されているケースもあるため、請求書の作成前に確認しておくとスムーズに進められるでしょう。
インボイス(適格請求書)の発行・保存する際の注意点とは?
インボイス制度では請求書の記載事項をはじめとして、さまざまな細かなルールが設けられています。とくに、発行や保存にあたっては従来のものと異なるポイントも多くあるため、注意点を知っておかないと、トラブルになるおそれがあるでしょう。
ここでは、インボイス(適格請求書)の発行・保存する際の注意点について、解説します。
①お互いにインボイス制度の登録が必要である
インボイス制度の利用には「インボイス(適格請求書)発行事業者」の登録が必要です。ただ、これは自社だけでなく、取引当事者双方が対象となっています。勘違いされている事業者も多く存在するため、取引をおこなう際にはあらかじめ確認しておきましょう。
なお、2024年2月現在、2割特例や簡易課税制度などの特例・制度の利用も可能です。これらのルールを利用する場合には、インボイスが必要ではない可能性もあるため、事前にルールの確認が必要です。
②不備があると、インボイス制度が利用できない
インボイス(適格請求書)に必要な記載事項に不備があった場合、インボイスとして認められず、仕入税額控除の適用も受けられません。
そのため、必ずインボイスを作成する際には、記載事項に不備がないことを確認してください。もし不備があった場合には、すぐに取引先に連絡し、インボイスの修正をおこないます。
なお、これは取引先からインボイスを受領した際も同様です。インボイスに記載された内容に問題がないかを確認したうえで、保存するようにしましょう。
③請求書以外をインボイス(適格請求書)とする場合に要件がある
取引によっては請求書と納品書などの複数の書類で、1つの契約内容を示しているケースもあります。これはインボイス制度も同様であり、1つの書類にすべて記載している必要はなく、複数の書類で必要事項すべてが揃っていればインボイス(適格請求書)として認められます。
このようなケースは稀ではあるものの、知っておかないと取引先から求められた時にトラブルになりかねません。
関連記事:【記載例あり】インボイスは複数書類でも発行可能?請求書の要件や注意点を解説
【おすすめ】インボイス(適格請求書)を簡単に作成できるサービスの導入を!
インボイス制度はすでに請求書作成サービスや会計ソフトなどで対応しています。
ただ、サービス・システムによって特徴が異なるため、導入を検討する際には注意が必要です。自社の事業規模や内容、タイミングや導入すべき内容などを整理し、サービス・システムごとの特徴を理解したうえで検討することが大切です。
とくに、帳票の発行や送付などを代行するサービスが人気であり、以下のようなものがおすすめです。
- OneVoice明細
- @トバス
など
関連記事:インボイス制度で導入すべきシステム4選!導入するべき理由も紹介
まとめ|インボイス(適格請求書)の正しいルールを理解し、トラブルをなくそう
本記事では、インボイス(適格請求書)の書き方について、記載例をもとに要件も解説しました。
インボイス制度のルールのなかでも、インボイス(適格請求書)の書き方に関するものは直接的にトラブルになりやすい内容となっています。
ただ、一度ルールを理解し、テンプレートやマニュアルなどで対応してしまえば、適切な対応をスムーズに進めることが可能です。まずは、インボイス制度の正しいルールの理解を深め、自社でどのような対応が必要なのかを整理することが大切です。










