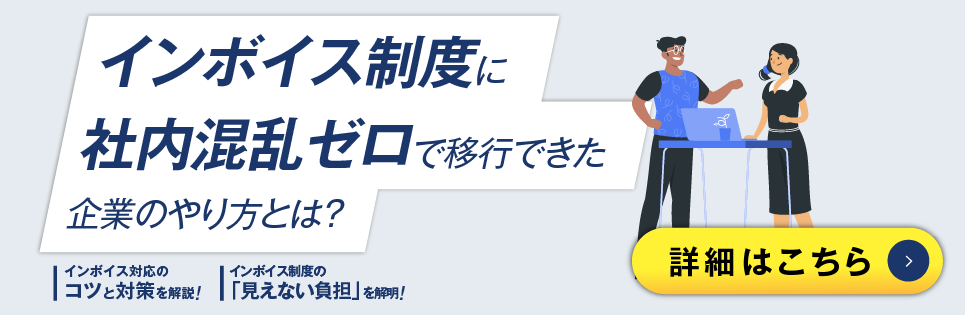インボイス制度が反対されているのはなぜ?制度廃止の可能性や支援措置も紹介
更新日:2025.12.23
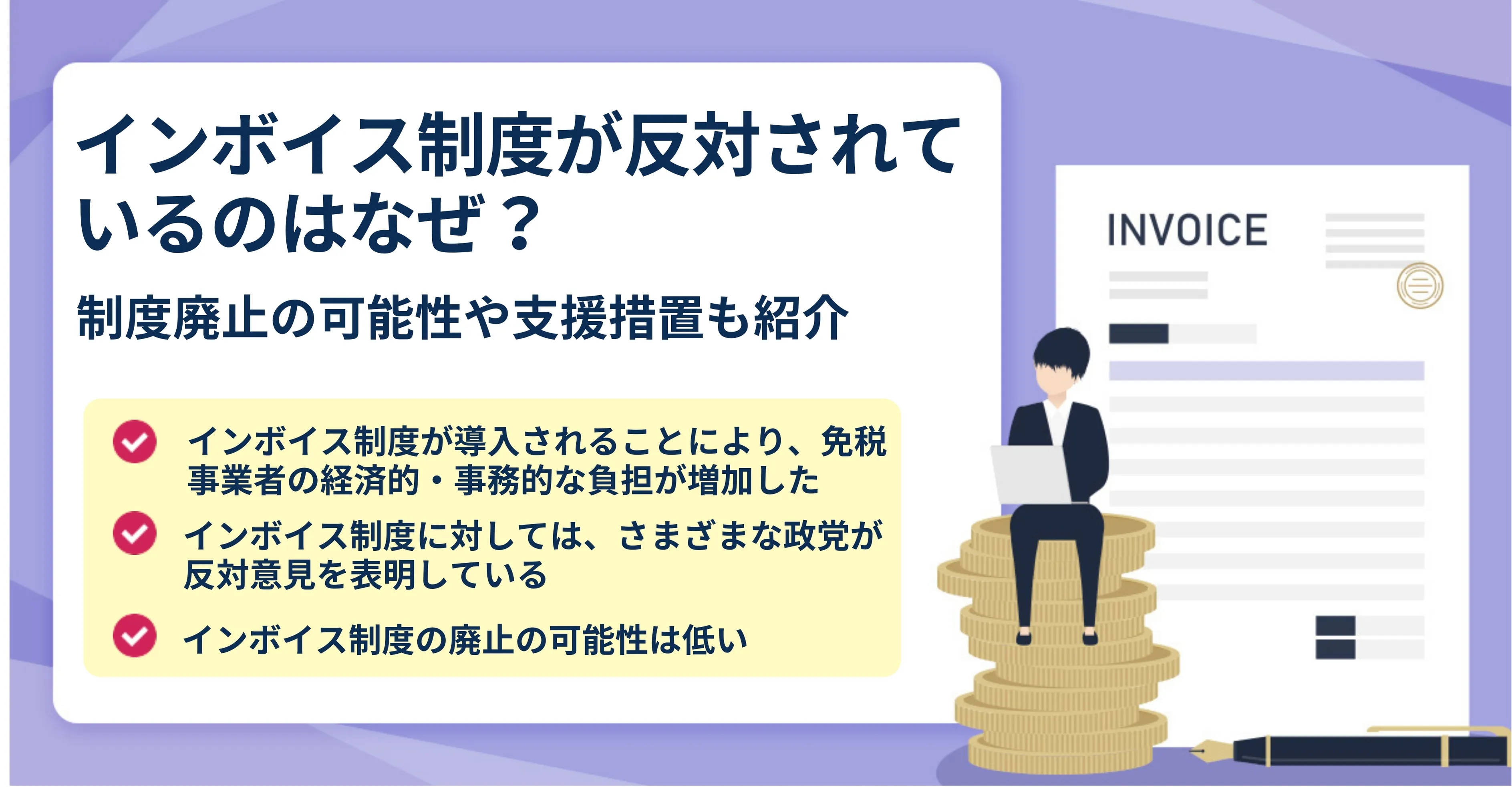
ー 目次 ー
インボイス制度は、消費税を正確に納めるための仕組みとして導入されました。一方で、事業者にとっては手続きが複雑になるなどの負担が大きくなる側面もあります。そのため、イラストレーターや声優、農家などの個人事業主として活動する著名人のなかには、制度への反対意見を述べる人も少なくありません。
インボイス制度への理解を深めつつ、適切な対応をおこなうためには、インボイス制度がなぜ反対されているのかを理解することが重要です。
本記事では、インボイス制度がなぜ反対されているのかを、制度廃止の可能性、支援措置もあわせて紹介します。
▼関連記事
インボイス制度はいつから始まる?適格請求書発行事業者の登録申請前に準備しておくべきこと | 請求ABC
インボイス制度はなぜ反対されているのか|理由を解説
インボイス制度が導入されることで、多くの事業者の事務的な負担が増加しました。制度に反対する声が上がっている要因には、このような背景があります。
ここでは、インボイス制度はなぜ反対されているのか、その理由を具体的に解説します。
①仕入税額控除の要件が増える
仕入税額控除とは、売上時に預かった消費税から仕入時に支払った消費税を差し引いて納税額を計算できる制度です。これまでは請求書があれば仕入税額控除を受けられましたが、インボイス制度導入後は、「適格請求書(インボイス)」がなければ仕入税額控除を受けられません。
適格請求書とは、インボイス制度に対応した請求書のことで、発行するには適格請求書発行事業者として登録する必要があります。
したがって、これまでどおり仕入税額控除を受けるには、取引先に適格請求書を発行してもらわなければいけません。これによって発生するコストや手間が事業者の懸念材料となっています。
②免税事業者の取引相手が減る可能性がある
インボイス制度の導入後、事業者は仕入税額控除を受ける際、取引先を適格請求書発行事業者に限定する必要があります。
その結果、インボイス制度に登録していない免税事業者との取引を避ける動きが広がり、取引相手が減少する可能性が高まるでしょう。また、既存の取引先から消費税分の値下げ要求を受けるケースも増えるかもしれません。
このような状況は免税事業者の収益を直接的に圧迫し、経済的な打撃となるおそれがあります。
③消費税の負担が増える
適格請求書を発行するためには、適格請求書発行事業者に登録しなければいけません。適格請求書発行事業者に登録すると、課税事業者として消費税の申告・納税が必要になるため、利益率の低い事業者ほど厳しい状況に直面することが予想されます。
また、申告や納税のための経理事務が増えるため、事務作業の負担やコストの増加も避けられないでしょう。
インボイス制度に反対している政党一覧
インボイス制度に対しては、さまざまな政党が反対意見を表明しており、とくに免税事業者や小規模事業者への影響を懸念する声が多く挙がっています。
ここでは、インボイス制度に反対している政党を紹介します。
①立憲民主党
立憲民主党は、インボイス制度の廃止を掲げ、税制改革に積極的に取り組んでいます。同党は2022年3月にインボイス制度廃止法案を衆議院に提出し、「適切な課税は別の方法でも実現可能である」と訴えました。
また、新型コロナウイルス感染拡大や物価高騰への対策として、一時的に消費税を5%に引き下げる政策も提案しています。
参考:立憲民主党「【提出法案】インボイス制度廃止法案を提出」
②社会民主党
社会民主党は、インボイス制度の廃止と同時に消費税の一時ゼロ化を提案しています。同党は、生活困窮者や労働者への支援を重視し、雇用格差の改善や給付金制度の強化も主張しています。
2022年10月には党首がインボイス反対集会に参加し、制度導入による不利益を訴えました。また、同党の自治体議員は、制度中止を求める請願書を作成し、地方自治体レベルでも問題を取り上げています。
(※)参考:社会民主党「インボイス制度は弱い者いじめ! 福島党首がインボイスを止めようと訴え」
③国民民主党
国民民主党は、インボイス制度が中小事業者やフリーランスに過度な負担をもたらすとし、消費税の時限的な引き下げや、インボイス制度廃止が盛り込まれた要望案を提出しました(※)。
同党は経済政策全般において減税を推進しており、消費税率の引き下げや幅広い減税措置を掲げ、持続可能な経済成長を目指しています。
(※)参考:読売新聞「国民民主党、中小企業の賃上げに向け減税措置要望へ...消費税5%への引き下げやインボイス廃止も」
④日本共産党
日本共産党は、2022年11月7日に「STOP!インボイス対策チーム」を設立(※1)し、この制度がもたらす影響を問題視してきました。
また、2022年5月30日には、消費税の減税とインボイス制度の廃止を盛り込んだ法案を参議院に提出しました(※2)。この法案を通じて、同党は世論の支持を得るため、啓発活動を進めています。とくに、個人事業主やフリーランスなど、制度の影響を直接受ける立場の人々の声を代弁し、現場の実態を国会に届けることを重視している点が特徴です。
(※1)参考:日本共産党「インボイス対策チーム党国会議員団立ち上げ」
(※2)参考:日本共産党「消費税減税・インボイス中止」
⑤れいわ新選組
れいわ新選組は、消費税そのものの廃止を掲げる政策を打ち出し、インボイス制度にも明確に反対の立場を取っています(※1)。また、同党は消費税が国民生活を圧迫していると主張し、消費税を廃止すればインボイス制度も不要になるという一貫した考えを示しています。
さらに、「STOP!インボイス街宣!」と題した街頭活動を実施(※2)し、インボイス制度の問題点を広く周知する取り組みをおこなうといった、現場の意見を重視した独自のスタイルが特徴です。
(※1)参考:れいわ新選組「消費税廃止インボイスも廃止」
(※2)参考:れいわ新選組「【STOP!インボイス街宣!】 2023年4月7日(金)18時スタート! 新宿駅西口地下」
インボイス制度の廃止の可能性は低い
インボイス制度は消費税における益税問題を解消し、税収の安定化を図ることを目的として導入されました。
一方で、この制度は事業者にとって新たな負担をともなうため、一部の野党や事業者団体からは廃止を求める声が挙がっています。しかし、政府や国税庁はインボイス制度の必要性を主張しており、現時点で廃止に関する発表はありません。
インボイス制度の負担を軽減させるための支援措置
現時点で、インボイス制度が廃止される可能性は低いです。しばらくはインボイス制度下で事業を続けることになるため、負担を減らす支援措置について理解しておくことが重要です。
ここでは、インボイス制度の負担を軽減させるための支援措置を紹介します。
①【2026年9月まで】売上消費税の8割が免除される「2割特例」
「2割特例」とは、消費税納入額を計算する際、控除できる金額を「特別控除金額」にできる特例です。特別控除金額とは、売上時の消費税の8割であるため、2割特例を適用した際の消費税納入額は、売上時の消費税の2割になります。
なお、この特例の対象はインボイス制度の導入を機に、免税事業者から適格請求書発行事業者として課税事業者になった事業者です。
関連記事:2割特例とは|対象事業者や計算方法と申請方法について徹底解説。
②【2026年9月まで】1万円以下の取引では適格請求書が不要になる「少額特例」
「少額特例」とは、税込1万円未満の仕入れについて、適格請求書の保存を省略できる制度です。必要事項(※1)が記載された帳簿を保存するだけで、仕入税額控除を受けられます。
この特例の対象者は、基準期間(※2)における売上高が1億円以下、または特定期間(※2)における売上高が5,000万円以下の事業者です。
(※1)参考:国税庁「帳簿の保存」
(※2)参考:国税庁「少額特例の概要」
関連記事:1万円未満の取引では少額特例が適用される要件をわかりやすく解説|インボイス保存が不要になる?
③「少額な返還インボイスの交付義務免除」
インボイス制度では、商品の値引きや返品をおこなった際、返還インボイスを発行する必要があります。
ただし、税込1万円未満の値引きや返品が発生した場合は、「少額な返還インボイスの交付義務免除」が適用されるため、その分の返還インボイスの発行が不要とされています。
なお、「少額な返還インボイスの交付義務免除」には期限は設けられていません。
まとめ|インボイス制度は収入が減る事業者が反対している
本記事では、インボイス制度がなぜ反対されているのかを、制度廃止の可能性、支援措置もあわせて紹介しました。
一部の政党や事業者団体がインボイス制度廃止を求めて活動を続けています。政府や国税庁は制度の必要性を強調しているため、現時点で廃止される可能性は低いでしょう。
インボイス制度に適応し、事業を円滑に進めるためには、支援措置を正しく理解して活用することが重要です。また、今後も政府や関係機関の発表に注目し、制度変更や新たな支援策に対応する準備を進めていきましょう。