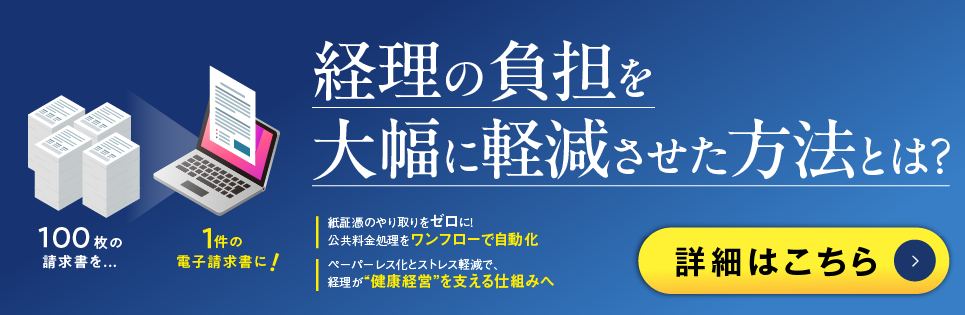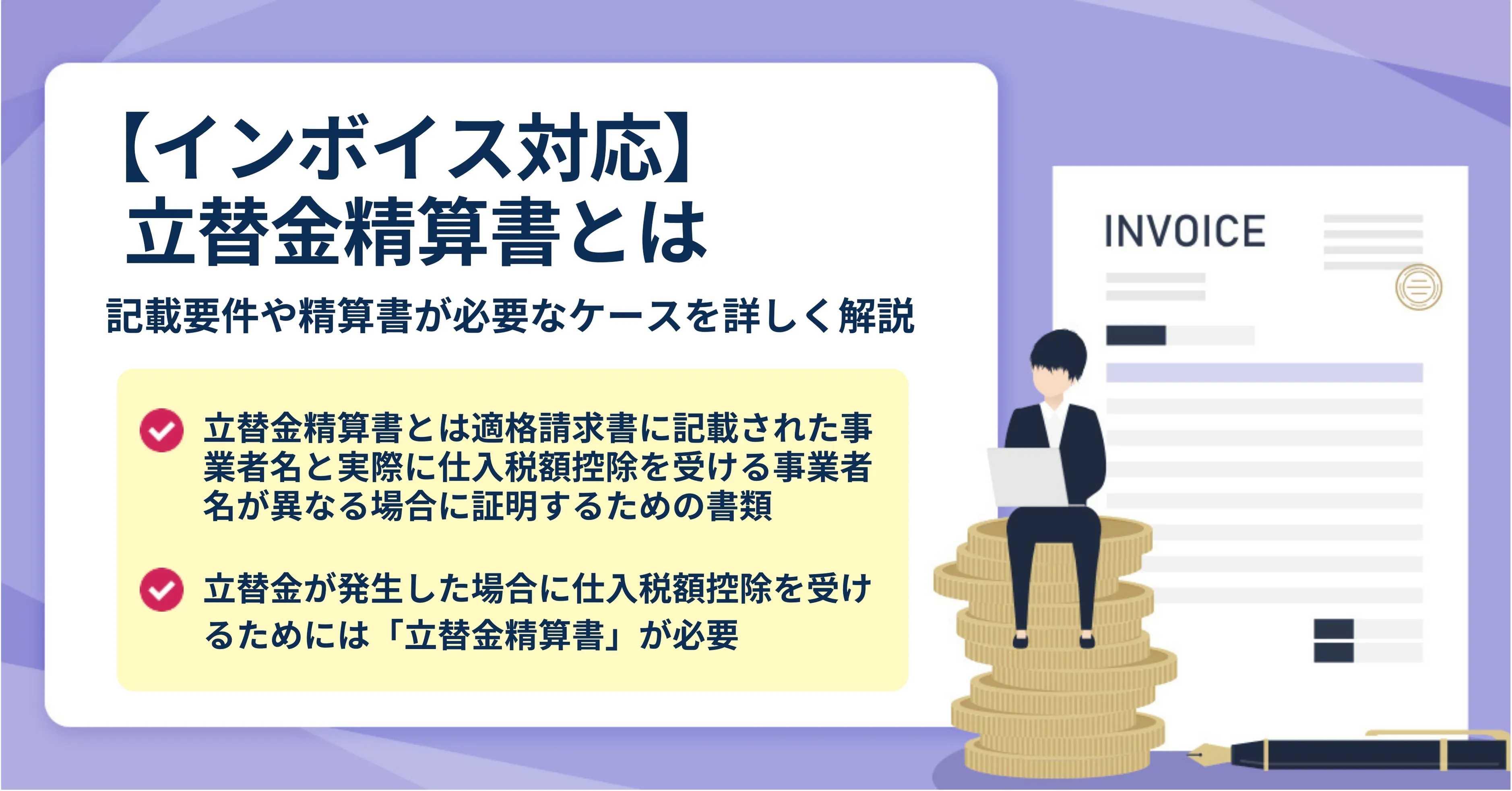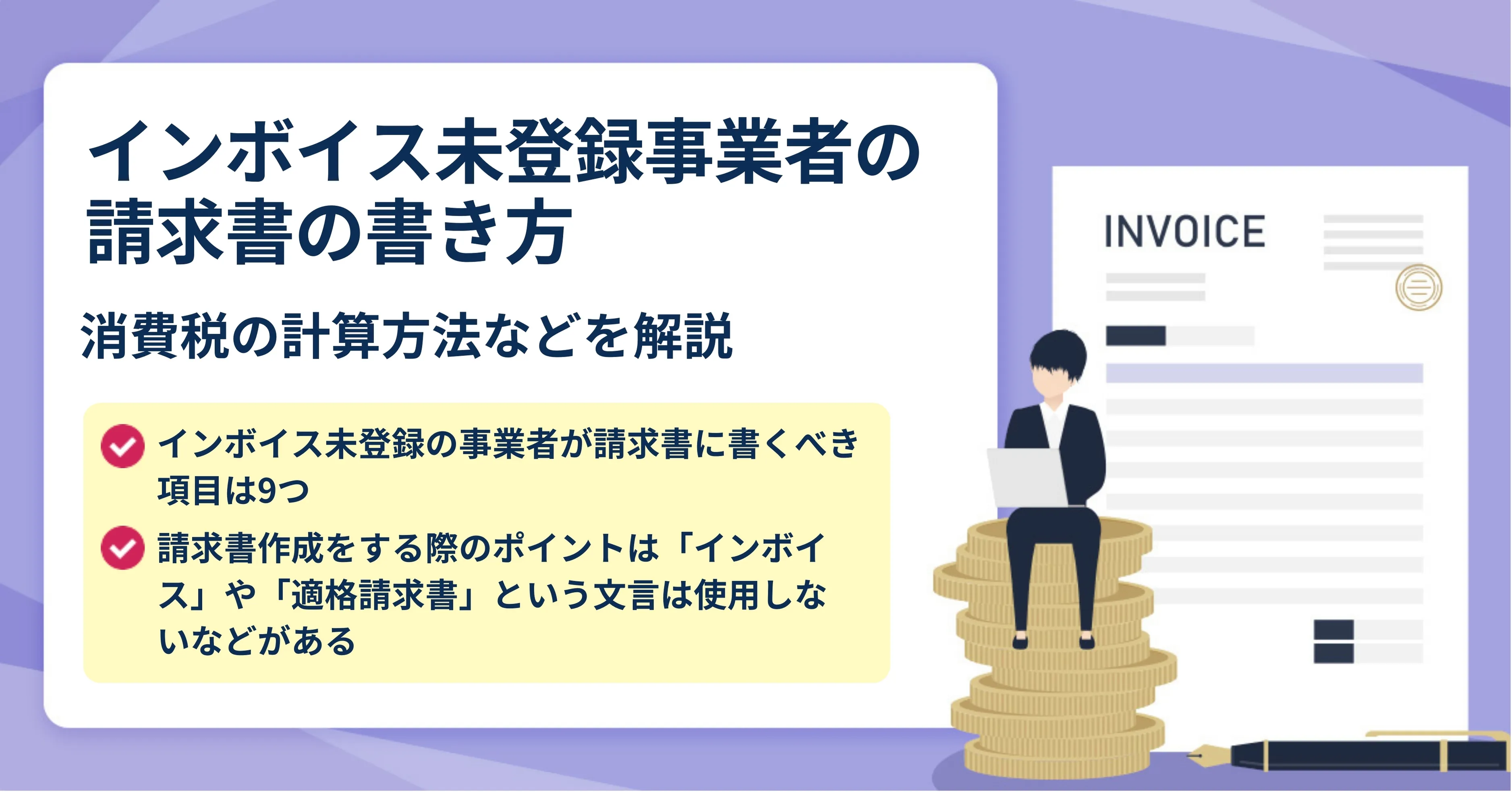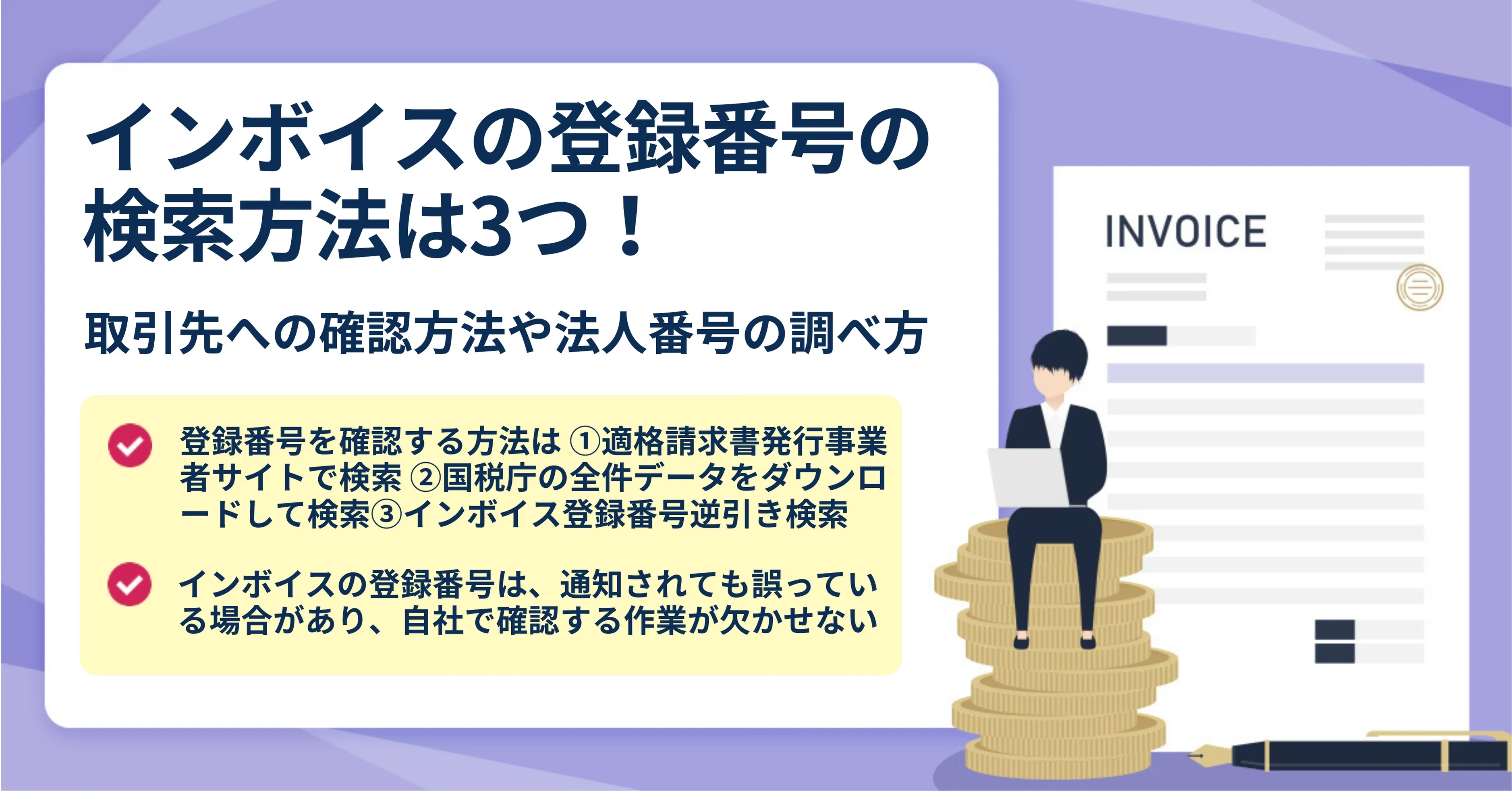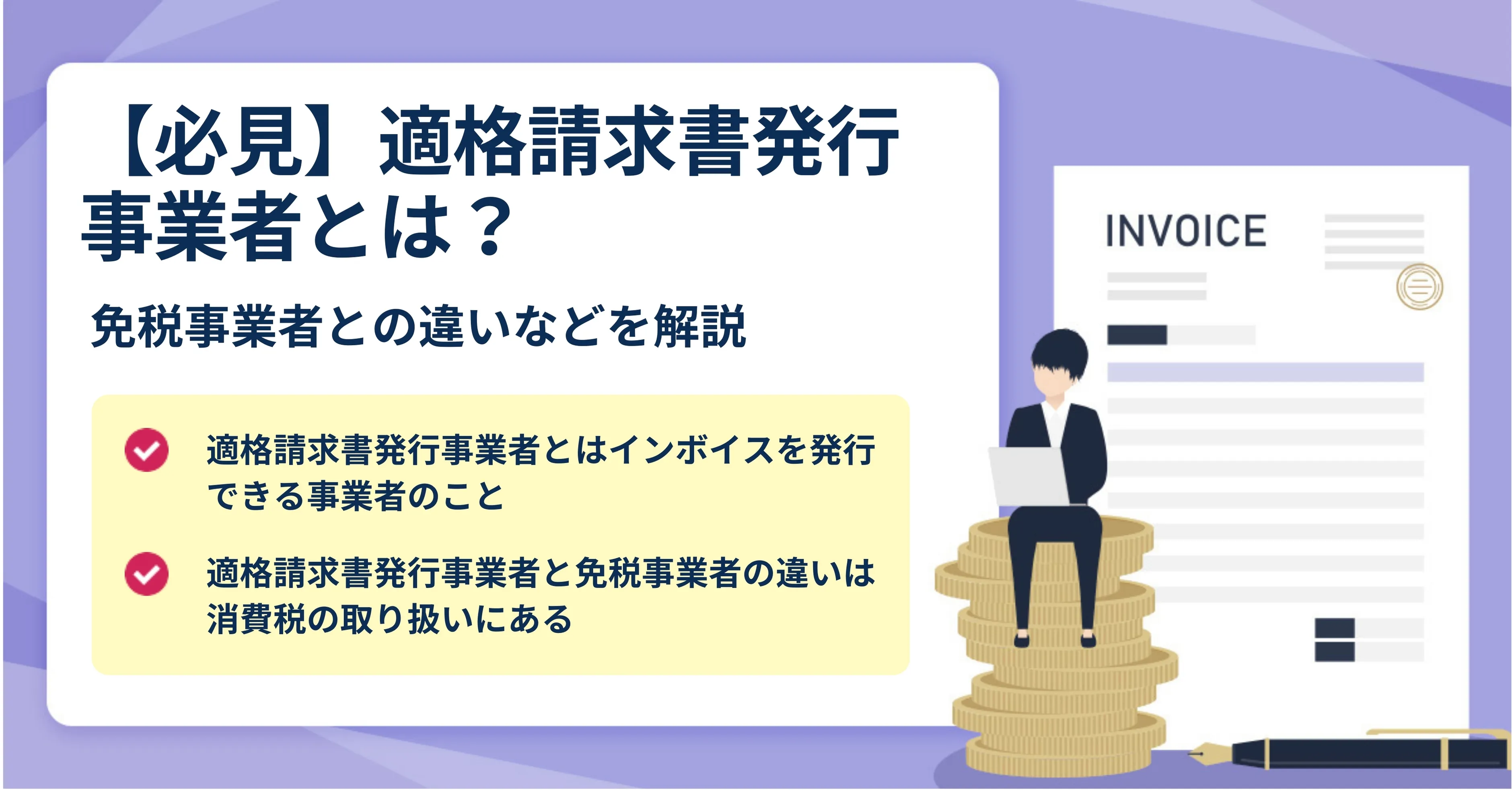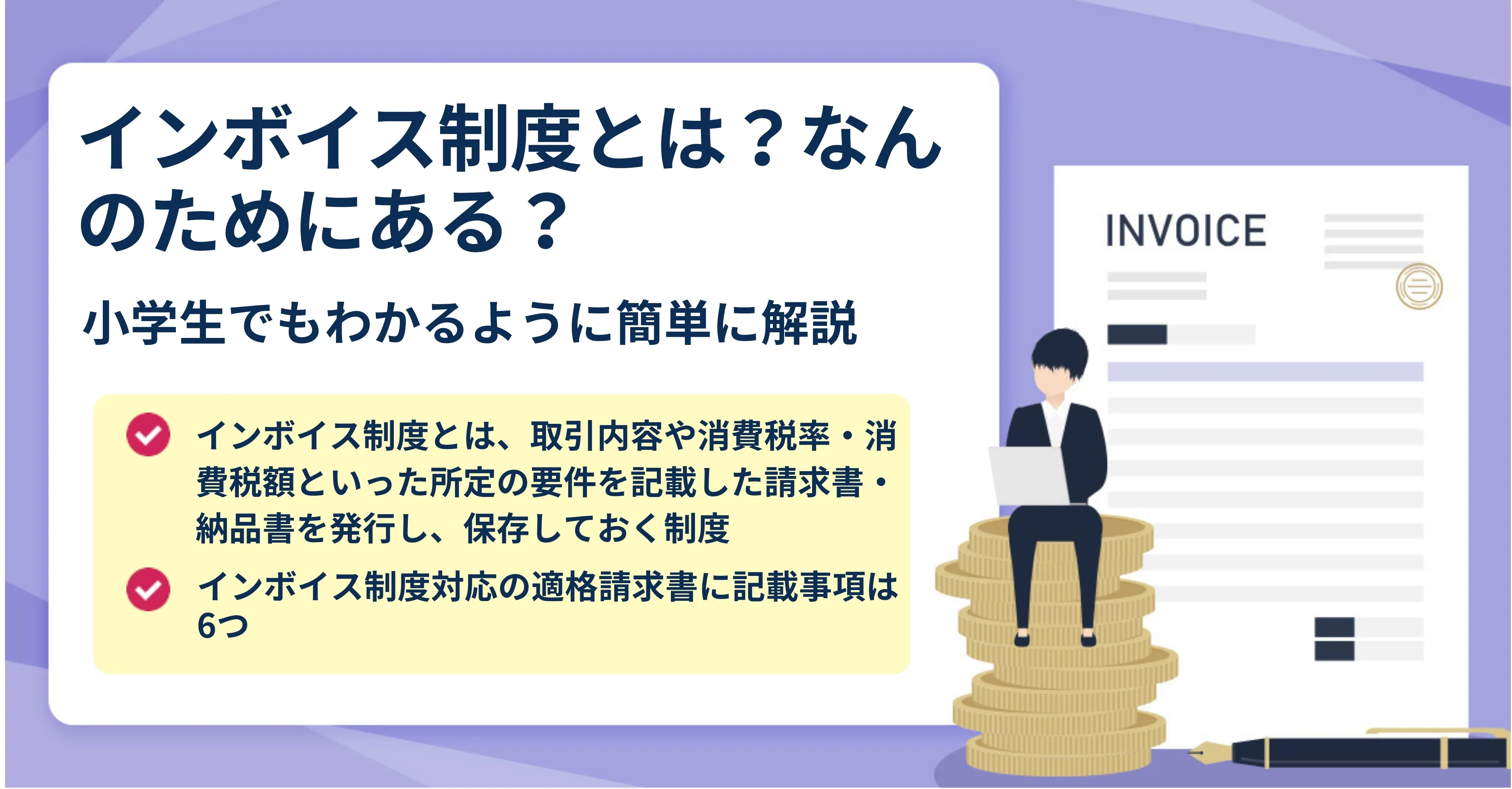【2025最新版】インボイス制度のPeppolとは?仕組みと導入の注意点をわかりやすく解説
更新日:2026.01.15
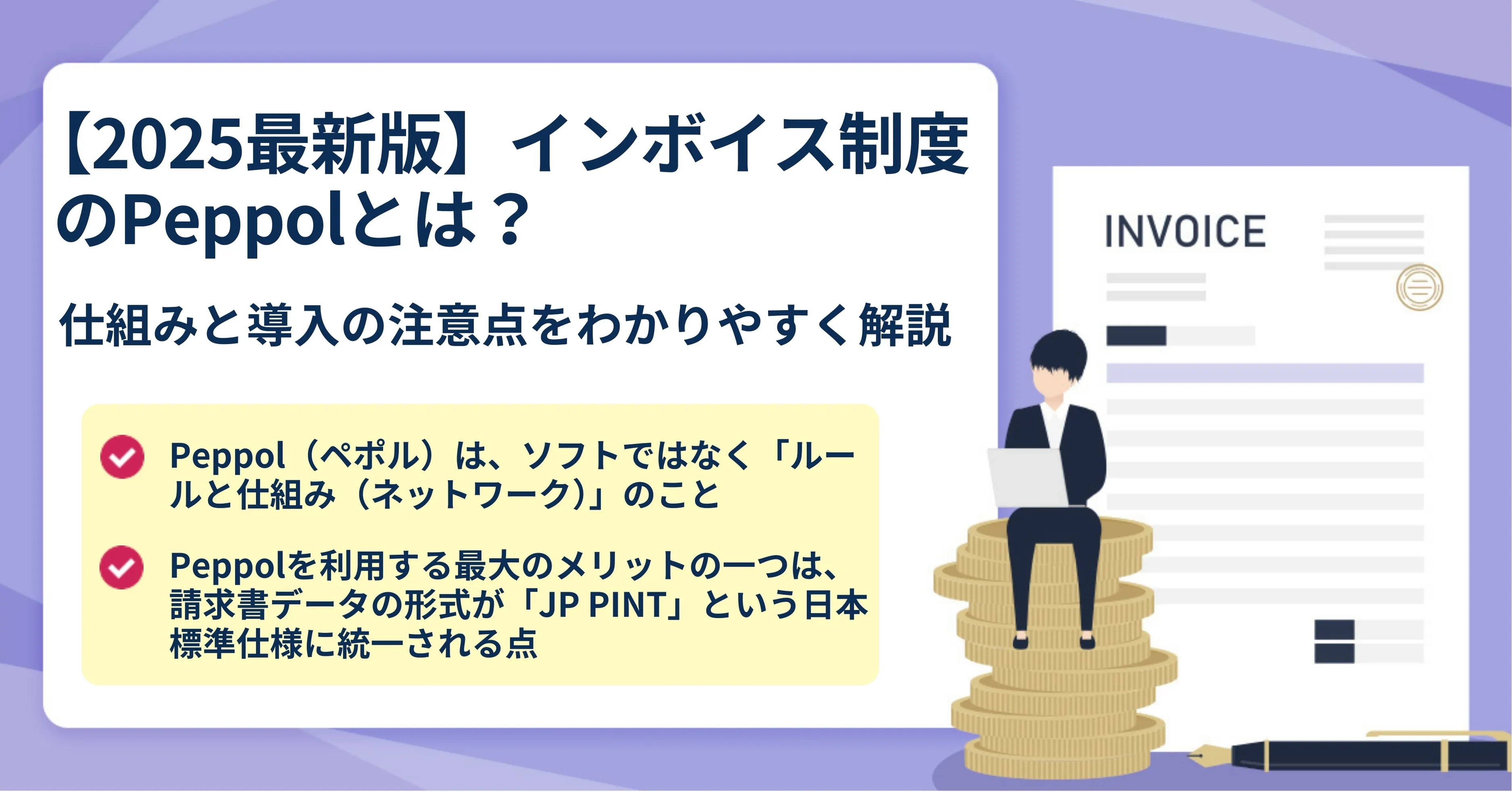
ー 目次 ー
インボイス制度への対応で、請求書業務のデジタル化にお困りではありませんか。
この記事では、デジタル庁が推進する電子インボイスの国際標準規格「Peppol(ペポル)」について、その仕組みから導入のメリット・デメリット、注意点までをわかりやすくお伝えします。実務目線で丁寧に解説しますので、導入を検討されている方はぜひ最後までご覧ください。
Peppol(ペポル)とは?インボイス制度との関係
この章では、まずPeppolの基礎知識と、インボイス制度においてどのような役割を担うのかを解説します。
まず確認!デジタルインボイスとは?
Peppol(ペポル)を理解するために欠かせないのが「デジタルインボイス」です。これは、単に請求書をPDFにしてメールで送るやり方とは大きく違います。
デジタルインボイスとは、請求書の内容を項目ごとに整理して構造化したデータ(XML形式など)で作られた、電子的な請求書のことです。
紙やPDFの請求書は、人が目で見て確認する画像や文章のデータですが、デジタルインボイス(Peppol準拠)はシステムが直接読み取れる構造化データ(XMLなど)です。
この形式なら、受け取った側は請求書データをそのまま会計システムに取り込み、自動で対応・処理することができます。
インボイス制度におけるPeppolの位置づけと普及率は?
Peppol(ペポル)は、ソフトではなく「ルールと仕組み(ネットワーク)」のことです。
Peppolは請求書などの電子文書をネットワーク上でやり取りするための国際的な標準規格で、2023年10月に始まったインボイス制度をきっかけに、日本でも注目が高まっています。
インボイス制度への対応と、請求書業務のデジタル化(DX)を同時に進められる重要な仕組みとして、政府も活用を推奨しています。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)では、消費税の仕入税額控除を受けるために、定められた条件を満たす「適格請求書」を保存する必要があります。
Peppolは、この適格請求書の条件を満たしたデジタルインボイスを、安全かつ確実にやり取りするための仕組みです。
ただし、Peppolの利用は義務ではなく、事業者の任意です。インボイス制度への対応方法の一つに過ぎません。
日本での普及はまだこれからですが、対応する会計ソフトやITサービスはどんどん増えており、今後は企業規模を問わず導入が進んでいくと見込まれています。
Peppolの仕組みをわかりやすく解説!デジタル庁が勧めるインボイス対応
ここでは、請求書データが相手に届くまでの具体的な流れや、安全性を担保する仕組みについて、わかりやすく解説します。
Peppolってどう動くの?請求書が届くまでの流れ
Peppolのネットワークは、電話網に似た仕組みで動きます。売り手と買い手がそれぞれ「アクセスポイント」と呼ばれるサービス提供事業者と契約することで、異なる会計ソフトやシステム間でもスムーズに請求書のやり取りが可能になります。請求書が送信されてから相手に届くまでの流れは、以下の4つのステップで構成されます。
Step1:売り手が請求書データを作成・送信
売り手は、利用している会計ソフトなどでPeppol形式の請求書データを作成し、契約している自社のアクセスポイント(C1)へ送信します。
Step2:買い手のアクセスポイントを検索
売り手側のアクセスポイント(C1)は、Peppolネットワーク上で買い手のPeppol IDを基に、相手が利用しているアクセスポイント(C4)を自動で検索・特定します。
Step3:アクセスポイント間でデータを送信
売り手側のアクセスポイント(C1)から、特定された買い手側のアクセスポイント(C4)へ、暗号化された請求書データが送信されます。
Step4:買い手が請求書データを受信
買い手は、自社のアクセスポイント(C4)に届いた請求書データを、利用している会計ソフトなどで受信・確認します。これにより、手入力や確認作業の手間が大幅に削減されます。
日本向けの仕様「JP PINT」ってなに?国際仕様の違い
Peppolは国際標準規格ですが、そのままでは日本の複雑な税制度や商習慣に対応しきれない部分があります。そこで、デジタル庁は日本の要件に合わせて策定した標準仕様「JP PINT」を定めています。これにより、事業者は日本のインボイス制度(適格請求書等保存方式)に準拠したデジタルインボイスを安心して発行・受領できます。
国際標準仕様である「Peppol BIS Billing 3.0」と、日本仕様「JP PINT」の主な違いは以下の通りです。
|
項目 |
国際仕様(Peppol BIS Billing 3.0) |
日本仕様(JP PINT) |
|
消費税の扱い |
単一税率を基本とする。 |
軽減税率(8%)と標準税率(10%)の複数税率に対応し、税率ごとの合計金額や消費税額の記載が可能。 |
|
支払先の口座情報 |
必須項目ではない。 |
日本の商習慣に合わせ、支払先の銀行口座情報を記載する項目が任意で追加されている。 |
|
適格請求書発行事業者登録番号 |
対応する項目がない。 |
インボイス制度で必須となる「T」から始まる登録番号を記載する項目が設けられている。 |
デジタル庁が定める運用ルールと安全基準
事業者が安心してPeppolを利用できるよう、デジタル庁は日本におけるPeppolの管理局(Peppol Authority)として、厳格な運用ルールとセキュリティ基準を定めています。これにより、ネットワーク全体の信頼性と安全性が担保されています。
主なルールとして、Peppolネットワークへの接続口となる「アクセスポイント」のプロバイダーは、誰でもなれるわけではありません。デジタル庁が定める技術仕様やセキュリティ要件を満たし、厳正な審査に合格した事業者のみが認定されます。この認定制度により、データの送受信における安全性や安定したサービス品質が保証されています。また、通信はすべて暗号化されており、データの盗聴や改ざんといったリスクから保護されています。これらの取り組みにより、事業者は紙の請求書よりも安全かつ確実に取引を行うことが可能です。
インボイス対応がスムーズに!Peppol導入のメリット
ここでは、Peppolがもたらす具体的な3つのメリットを詳しく解説します。
人為的ミスや記載漏れを防ぐ統一フォーマット
Peppolを利用する最大のメリットの一つは、請求書データの形式が「JP PINT」という日本標準仕様に統一される点です。これにより、手作業による入力ミスや、インボイス制度で定められた記載要件(登録番号、適用税率、消費税額など)の漏れをシステム的に防ぐことができます。
データは送信者と受信者のシステム間で直接やり取りされるため、請求書の再発行や内容確認といったコミュニケーションコストが大幅に削減され、月次決算の早期化にも繋がります。データの正確性が担保されることで、安心して経理業務を進めることが可能です。
請求書業務の自動化・印刷・郵送・保管コストの削減
Peppolは、請求書業務のプロセス全体をデジタル化し、自動化を促進します。これまで手作業で行っていた請求書の発行・送付・受領・システム入力といった一連の作業が、ネットワークを介して自動で完結します。
このデジタル化により、紙の請求書にかかっていた印刷代、封筒代、郵送料といった物理的なコストが不要になります。さらに、電子帳簿保存法の要件を満たした形でデータを保管できるため、ファイリングの手間や保管スペースの確保といった管理コストも削減できます。以下の表は、Peppol導入による業務の変化をまとめたものです。
|
業務フロー |
従来の方法(紙・メール) |
Peppol導入後 |
|
請求書発行 |
Excelなどで作成し、手動で内容を確認 |
会計システムからデータを自動で生成 |
|
送付 |
印刷、封入、郵送またはPDFをメールに添付 |
アクセスポイントを介して自動で送信 |
|
受領・入力 |
郵送物やメールを開封し、会計システムへ手入力 |
システムが自動で受領し、仕訳データを自動で生成 |
|
保管 |
紙でファイリングし、保管庫で管理 |
電子データとしてシステム上で自動保管 |
国内外の取引にも対応できる!国際標準のネットワーク
Peppolは、もともとヨーロッパで普及した電子文書交換の国際標準規格です。そのため、日本国内の取引はもちろん、海外のPeppolネットワーク参加企業との取引においても、同じ仕組みを利用して請求書(インボイス)をやり取りできます。
これにより、海外企業との取引で発生しがちな、請求書のフォーマットの違い、言語の壁、商習慣の違いといった課題を乗り越えやすくなります。グローバルに事業を展開する企業にとって、Peppolは国内外の請求書業務を標準化し、一元管理するための強力なツールとなるでしょう。
Peppol導入のデメリットは?失敗しないための注意点を解説
Peppolの導入は業務効率化に大きく貢献する一方、事前に把握しておくべきデメリットや注意点も存在します。ここでは、Peppol導入における主なデメリットと、失敗しないためのポイントを解説します。
取引先のPeppol対応が必要になる
Peppolは、請求書などをやり取りする双方の事業者がPeppolネットワークに参加していて初めて機能します。つまり、自社だけがPeppolを導入しても、取引先が対応していなければ、その取引先との間ではデジタルインボイスの送受信はできません。
取引先が未対応の場合、その相手とは従来通り紙やPDFファイルでのやり取りを継続する必要があります。そのため、Peppol導入による業務効率化の効果が限定的になってしまう可能性があります。
導入を検討する段階で、主要な取引先のPeppol対応状況や導入予定を確認することが大切です。また、自社が導入するタイミングで、取引先にもPeppol導入のメリットを伝え、対応を働きかけるといったコミュニケーションも成功の鍵となります。
既存システムとの連携性を確認する必要がある
多くの企業では、すでに会計システムや販売管理システム、受発注システムなどを利用しています。Peppolを導入する際は、これらの既存システムとスムーズにデータ連携できるかどうかが極めて重要です。
もし連携がうまくいかない場合、Peppolで受け取った請求書データを既存の会計システムに手入力したり、二重で管理したりする必要が生じ、かえって業務が煩雑になる恐れがあります。これでは、業務効率化という本来の目的を達成できません。
Peppol対応のサービスやソフトウェアを選定する際には、自社で利用中のシステムとのAPI連携が可能か、あるいはCSVファイルなどでのデータ連携に対応しているかを必ず確認しましょう。サービスプロバイダーが公開している連携実績や導入事例を参考にすることも有効です。
導入には初期費用と運用コストがかかる
日本では、Peppolそのものに費用はかかりませんが、それを使うためのソフトウェアやサービス、アクセスポイント利用料などには費用が発生する場合があります
またPeppolを導入する際、今までのシステムの切り替えや新規導入に伴う初期費用、そして継続的な運用コストが発生します。全くコストをかけずに導入することは難しく、自社の状況に合わせた予算計画が必要です。
具体的なコストは、企業の規模や既存システムの状況、選択するサービスプロバイダーによって大きく異なります。主な費用には以下のようなものがあります。
|
費用の種類 |
内容の例 |
|
初期費用 |
Peppolに対応した会計ソフトや販売管理システムの導入費用、既存システムとの連携開発費用、導入コンサルティング費用など |
|
運用コスト |
システムの月額・年額利用料、Peppolアクセスポイント利用料、送受信するインボイスの件数に応じた従量課金など |
Q&A|インボイスとPeppolに関するよくある質問
インボイス制度への対応やPeppolの導入を検討する際に、多くの方が抱く疑問についてQ&A形式でわかりやすく解説します。
Peppolの導入でIT導入補助金は活用できますか?
はい、活用できる可能性があります。中小企業・小規模事業者がインボイス制度に対応するためのITツール導入を支援する「IT導入補助金」には、「インボイス枠(インボイス対応類型)」が設けられています。
この枠は、インボイス制度に対応した会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフトなどの導入費用の一部を補助するものです。Peppolに対応したサービスも多くがこの補助金の対象となっています。補助対象となる経費や補助率、申請要件などの詳細は、IT導入補助金の公式サイトで最新情報をご確認ください。
Peppolの具体的な導入方法は?
Peppolを導入する一般的な方法は、デジタル庁に認定された「Peppolサービスプロバイダー」が提供するサービスを利用することです。具体的な導入手順は以下の通りです。
- Peppol対応サービスの選定:自社の業務内容や予算に合った会計ソフトや請求書発行システムを選びます。現在利用中のシステムがPeppolに対応するオプションを提供している場合もあります。
- 利用申し込みと設定:選んだサービスの利用を申し込み、必要な初期設定を行います。サービスによっては、Peppolネットワークで自社を識別するための「Peppol ID」の取得手続きも代行してくれます。
- 取引先への通知:Peppolでのデジタルインボイス送受信が可能になったことを取引先に連絡し、必要に応じてPeppol IDを交換します。
多くのサービス事業者が導入サポートを提供しているため、専門知識がなくてもスムーズに導入を進めることが可能です。
Peppolのサービスプロバイダーの失敗しない選び方は?
自社に最適なPeppolサービスプロバイダーを選ぶことは、導入後の業務効率を大きく左右します。選定の際は、以下のポイントを確認しましょう。
|
確認ポイント |
詳細 |
|
機能の網羅性 |
請求書の発行だけでなく、受領やデータ化、会計ソフトとの連携など、自社が必要とする業務をカバーできるかを確認します。 |
|
料金体系の妥当性 |
初期費用や月額費用、追加オプションの料金などを比較し、自社の予算規模に合っているか検討します。送受信する請求書の枚数に応じた従量課金制のプランもあります。 |
|
既存システムとの連携性 |
現在利用している会計ソフトや販売管理システムとAPI連携などが可能かを確認します。スムーズな連携は、データ入力の手間を削減し、業務効率化に直結します。 |
|
サポート体制の充実度 |
導入時の設定サポートや、運用開始後のトラブルシューティングなど、問い合わせに対するサポート体制が整っているかを確認します。 |
|
信頼性と実績 |
デジタル庁から認定を受けている正規のプロバイダーであることは必須条件です。同業種での導入実績が豊富かどうかも、信頼性を判断する材料になります。 |
まとめ
Peppolは、請求書業務を自動化し、入力ミスや記載漏れを防ぐことで業務負担を軽減できます。一方で、取引先の対応状況や既存システムとの連携、導入コストといった課題もあります。導入は義務ではありませんが、政府も推奨しており、対応サービスも年々増えています。IT導入補助金を活用すれば、費用負担を軽減できる場合もあります。
まずは、自社と取引先の状況を整理し、信頼できるサービスプロバイダーを選ぶことが成功の第一歩です。インボイス制度への対応をきっかけに、請求業務全体のデジタル化と効率化を進めていきましょう。