インボイスの振込手数料は売り手負担にできない?可能なケースと仕訳の方法を解説
更新日:2025.12.24
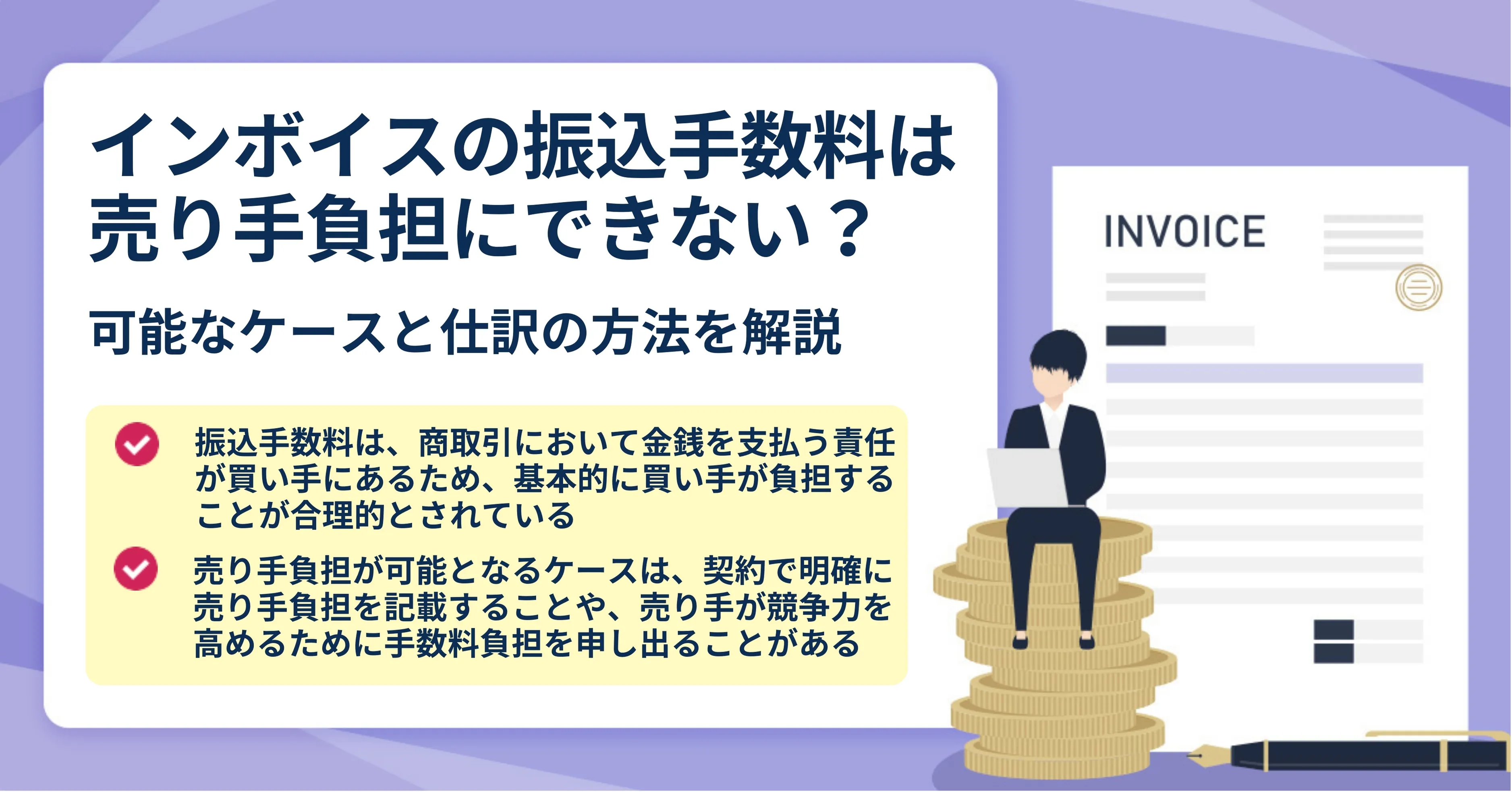
ー 目次 ー
インボイス制度の導入に伴い、取引における振込手数料の負担と処理方法についてお悩みの方も多いのではないでしょうか。
本記事では、振込手数料を売り手負担にすることができるのか、またそれが可能となる特殊なケースや仕訳の具体例を詳しく解説しています。さらに、インボイス制度との関係性や課税対象となるかどうかといった重要なポイントも網羅しており、振込手数料を巡るトラブルを未然に防ぐための実務的な対応策も紹介しています。
また、最後には仕訳方法について具体例を提示し、ミスを防ぐコツにも触れています。本記事を読むことで、インボイス制度における振込手数料の取り扱い方を的確に理解し、安心して業務に活かせる知識を得られるはずです。
振込手数料とは何か 基本的な知識をおさらい
振込手数料の定義と目的
振込手数料とは、銀行や金融機関を通じて資金の振込を行う際に発生する手数料を指します。この手数料は、振込を依頼する側が負担することが一般的です。振込手数料の目的は、金融機関が提供する振込サービスの運営費用を賄うことであり、システムの維持や運用コスト、そして利便性の提供に対する対価として徴収されます。
振込手数料は、主に2つの要因によって変動します。一つ目は送金額で、一定の金額を超える送金には高額な手数料が適用されることがあります。二つ目は送金先の金融機関で、同一銀行内での送金よりも別の金融機関への送金が高い手数料となる場合があります。
例えば、国内送金の場合、大手銀行には「みずほ銀行」「三菱UFJ銀行」などがあり、これらの銀行が設定する振込手数料の金額は、それぞれの規定によって細かく異なります。また振込手段として、インターネットバンキングを選んだ場合、窓口での送金よりも手数料が安くなるケースが多いです。このように、振込手数料は取引の形態や条件により変動するため、しっかりと確認することが大切です。
取引における振込手数料の一般的な負担方法
事業取引において、振込手数料は通常、どちらが負担するかを取引当事者間で明確に取り決めることが求められます。一般的には、振込依頼人、つまり買い手が負担するケースが多いです。これは、振込手数料があくまでも依頼者側のサービス利用料として扱われるためです。
多くの契約書においても、「振込手数料は買い手側にて負担」といった文言が明記されることで、後々のトラブルを回避できます。ただし、事例によっては売り手側が好意的にこれを負担するケースも見受けられます。この場合には、商品の価格にあらかじめ振込手数料が反映されている可能性が高いです。
例えば、フリーランスや小規模事業者が得意先と取引を行う際、取引先の規模や関係性に応じて手数料を売り手側が負担するといった柔軟な対応が選択されることもあります。また、業界によっては、慣例的に売り手が負担することが求められる場合もあり、この点は十分な事前確認が必要です。
インボイス制度と振込手数料が関係するポイント
2023年10月から施行されたインボイス制度においても、振込手数料は事業者間取引で注意が必要な要素の一つです。インボイスは、正式には「適格請求書」と呼ばれ、消費税の仕入税額控除を適用するために買い手が請求書の情報を正確に記録することを求められます。この際、振込手数料がどちらの負担になるかは取引全体の清算プロセスに影響するため、事前の取り決めや記帳方法が重要です。
具体的には、振込手数料が売り手負担となる場合、その費用をどの勘定科目で処理するかが会計実務上の課題となります。また、振込手数料が消費税の課税対象に該当しない点にも注意が必要です。金融取引に関連する手数料は不課税となるため、仕訳処理やインボイス作成時の項目分けには十分な理解が求められます。
さらに、振込手数料に関するトラブルを防ぐため、インボイスには手数料負担がどちらであるかを明記することが推奨されます。これにより、買い手と売り手の双方が負担割合や費用の処理方法についての誤解を防ぎ円滑な取引を進めることが可能となります。
関連記事:インボイスの振込手数料負担はどっち?売り手負担の対応や記載例も | 請求ABC
振込手数料は売り手負担にできない理由と可能なケース
売り手負担にできない理由 法的な背景
振込手数料は、一般的に買い手側が負担することが基本とされています。これは、商取引においてお金を支払う側が支払方法を選択し、それに伴うコスト(ここでは振込手数料)を支払うのが合理的とされるためです。また、振込手数料の負担は民法や商法などの法律によって直接規定されているわけではありませんが、取引における一般的な商慣習として確立されています。
さらに、インボイス制度の導入により、正確な取引金額が記録される必要があります。この制度では納税処理の整合性が求められるため、振込手数料を売り手が負担する場合にはその金額の取り扱いについて慎重に対応しなければなりません。売り手負担にすることで税務処理を誤るリスクがあることも理由の一つです。
買い手負担が基本となる根拠
買い手負担が基本となる理由は、取引の対価として金銭を支払う責任が買い手にあるためです。振込手数料は、対価を振り込むために必要な諸費用の一部とみなされます。そのため、通常は買い手が「代金」と「その代金を送金するためのコスト」を負担するという形が自然とされています。
加えて、契約書や請求書に振込手数料についての記載がない場合、一般的な商慣習に従い買い手が負担すると解釈されます。これにより、取引上のトラブルを回避することが期待されます。
売り手負担が可能となる特殊なケース
契約段階での特別な取り決め
売り手負担が可能となる最も一般的なケースは、契約段階で買い手と売り手の間で特別な取り決めが行われた場合です。これは、契約書や注文書に明示的に「振込手数料は売り手が負担する」と記載することで実現できます。契約の内容が明確であれば、トラブルを防ぐことができます。
売り手が一定の条件を提示した場合
売り手自身が競争力を高めるためや取引をスムーズに進めるために、「振込手数料を当社が負担します」といった条件を提示するケースもあります。このような条件は、特に取引先が多い業界や競争が激しい業界で見られることがあります。例えば、特定の金額以上の取引に振込手数料を負担するキャンペーンなどがその例です。
番外:業界の慣習で売り手が負担することも
一部の業界では慣習として振込手数料を売り手が負担する場合があります。例えば、IT業界や一部のサービス業では、売り手の負担が一般的なルールとして共有されることがあります。このような場合には、契約書や請求書に特別な記載がなくとも、暗黙的に売り手が負担する前提で取引が進む場合もあります。
ただし、業界慣習のみに基づいて処理を進めることは、トラブルの原因となる可能性もあるため、事前に買い手と売り手の間で負担者を明確にしておくことが重要です。
関連記事:インボイス制度における振込手数料は誰が負担する?仕訳のポイントも解説
振込手数料が売り手負担となるときの実務的な注意点
売り手負担を契約に明記する重要性
振込手数料を売り手負担にする場合、契約書や取引条件にその旨を明記することが最も重要です。これは、後々のトラブルを防ぐだけでなく、税務上の証拠としても重要な役割を果たします。
たとえば、見積書や契約書に「振込手数料はすべて売り手負担とする」と具体的に記載しておくことで、取引の透明性が高まります。また、お互いの認識に齟齬が生じにくくなり、振込後に振込手数料を巡る補償問題が発生しません。
売り手負担を契約に明記する際には次のポイントを押さえましょう。
- 振込手数料の負担者を特定して明確化する。
- 負担の条件や対象とする範囲を具体的に提示する。
- 合意内容を正式な契約書や請求書、見積書に記載する。
また、場合によっては弁護士や税理士など専門家の意見を取り入れることで、より適切な内容にすることができます。
消費税の課税対象となるかどうか
インボイス制度のもとで振込手数料を売り手負担にした場合、その金額が消費税の課税対象となるのかどうかを確認する必要があります。
基本的に、振込手数料自体は金融取引であり非課税取引に該当するため、消費税は発生しません。しかし、振込手数料を売り手が「負担する」という形で商品やサービスの代金に含めて請求する場合、その金額は課税取引として扱われる可能性があります。
そのため、仕訳を行う際や請求書を作成する際には、以下の点に注意してください:
|
ケース |
振込手数料の扱い |
消費税課税の有無 |
|
金融機関の手数料 |
非課税 |
なし |
|
代金に振込手数料を含む請求 |
課税対象 |
あり |
売り手負担で実務処理を行う際には、課税の有無をきちんと把握し、帳簿への記載内容を正確にすることが求められます。
インボイス発行者が気を付けるべき制度上の制約
インボイス発行者として振込手数料を売り手負担とする場合、制度上の制約を踏まえた運用が必要です。
特に、買い手側が適格請求書(インボイス)を活用して仕入税額控除を行う場合、請求書の記載内容に不備があってはいけません。振込手数料を売り手が負担する場合でも、インボイスに以下の点を記載しておくことが推奨されます:
- 商品やサービスごとの価格(税込価格または税抜価格)。
- 振込手数料を含む場合、その金額と課税の有無を区別して記載。
- 取引総額が振込手数料を含む場合、その旨の注意書き。
また、振込手数料が契約条件として取り決められている場合には、適格請求書にその旨を記載し、契約書との整合性を図る必要があります。
これが適切に行われていない場合、税務署から指摘を受ける可能性があり、買い手に不利益が生じることも考えられるため、インボイス運用上の注意が必要です。
インボイス関連の振込手数料の仕訳方法
仕訳を行う際の基本ルール
インボイス制度が導入されることで、企業は取引において適格請求書(通称:インボイス)を発行または受領することが求められるようになります。これに伴い、振込手数料に関連する会計処理も正確に行う必要があります。仕訳を行う際の基本ルールとして、取引の日付、金額、仕訳の目的(収益・費用など)を正確に記録することが重要です。
また、買い手が負担する振込手数料の場合と、売り手負担の振込手数料については、それぞれ異なる勘定科目を用いる必要がありますので注意が必要です。特に、インボイス発行者である場合には、これが消費税の課税対象になる可能性があるため、より厳密な仕訳を行う必要があります。
買い手負担の場合の仕訳例
買い手が振込手数料を負担する場合は、売上金額そのものには影響がありません。このケースでは、買い手が負担した振込手数料を「預金」または「普通預金」などの勘定科目で記録します。以下に具体例を示します。
|
科目 |
借方(取引日ごとに集計) |
貸方 |
|
未収金 |
100,000円 |
---- |
|
普通預金 |
---- |
95,000円 |
|
振込手数料 |
---- |
5,000円 |
売り手負担の場合の仕訳例
売り手が振込手数料を負担する場合は、売上高から振込手数料を差し引いた金額が手元に残ります。この場合、一般的に「振込手数料」を費用として計上することになります。以下に仕訳例を挙げます。
|
科目 |
借方 |
貸方 |
|
売上高 |
---- |
100,000円 |
|
振込手数料 |
5,000円 |
---- |
|
普通預金 |
95,000円 |
---- |
売上計上の仕訳方法と注意点
売上計上において注意すべき点は、売上の金額を振込手数料が控除される前の額で正確に計上することです。その上で、振込手数料として控除された金額を別途費用科目として計上します。このようにすることで、振込手数料が売上にどのように影響しているかが明確になります。税務申告や帳簿管理の際にも役立ちます。
振込手数料を経費計上する際の仕訳例
振込手数料を経費計上する際は、損益計算書上では「販売費および一般管理費」に分類されることが一般的です。以下に具体的な仕訳例を示します。
|
科目 |
借方 |
貸方 |
|
販売費および一般管理費 |
5,000円 |
---- |
|
普通預金 |
---- |
5,000円 |
仕訳のミスを防ぐポイント
仕訳のミスを防ぐためには、定期的に帳簿を確認し、未記録の取引がないかをチェックする習慣をつけることが重要です。また、振込手数料の負担が発生するたびに、その負担が買い手か売り手か、契約内容によるものかを明確に記録しておくことで、仕訳時の混乱を防ぐことができます。
さらに、インボイス対応の会計ソフトを活用することも有効です。これにより、インボイス制度に基づいた正確な仕訳が行えるだけでなく、消費税の課税対象取引の管理もスムーズになります。
関連記事:インボイス制度における振込手数料の対応は?正しい仕訳方法と実務のポイント | 請求ABC
インボイス制度と振込手数料への対応策
振込手数料を巡るトラブルを回避する方法
インボイス制度の導入により、振込手数料を巡るトラブルが発生するリスクが高まる可能性があります。特に、買い手と売り手双方の立場で振込手数料の負担について認識にズレがある場合には注意が必要です。これを防ぐためには、双方が手数料負担に関する取り決めを明確にし、契約書などの文書化を行うことが重要です。また、業界の一般的な慣習や法的背景をよく理解し、関係者全員でその内容を共有するよう努めましょう。
さらに、振込手数料に関するトラブルが発生した際には、事前に合意した契約内容や法律に基づいて冷静に対応することが求められます。誤解や争いを未然に防ぐためにも、契約や合意事項をしっかりと記録に残しておきましょう。
事前に取り決めを行う重要性とその具体策
インボイス制度下では、振込手数料について事前に明確な取り決めを行うことが取引の円滑化に大きく寄与します。買い手と売り手の双方で負担ルールを明示的に定めておくことで、後々のトラブルを避けることができます。例えば、契約書の「支払条件」欄に振込手数料の負担者を明記する、または請求書にあらかじめ手数料負担について一文を追記するといった形が考えられます。
また、定期的に取引を行う相手に対しては、取引開始前に双方で負担ルールに合意しておくといいでしょう。たとえば、以下のような文言を契約書や注文書に記載することが考えられます:
|
項目 |
サンプル文言 |
|
振込手数料負担 |
「振込手数料は、原則として買い手の負担とします。」 |
|
特別な取り決め |
「売り手が受け取る金額には振込手数料を含むものとし、手数料分を相殺した金額を送金します。」 |
このような取り決めを事前に行うことで、後々の誤解を防ぐことができます。また、書面のみならずメールやチャットのやり取りであっても、正式な記録として保存しておくことで、必要に応じて証拠として使用することが可能です。
売り手に振込手数料の負担をお願いする場合の例文
取引先に対して振込手数料の取り扱いについて協議する必要がある場合、適切なコミュニケーションをもって相手に意図を伝えることが重要です。以下は、売り手に振込手数料負担をお願いする例文です:
|
ケース |
例文 |
|
新規取引の場合 |
「弊社では取引慣行として、振込手数料を全額売り手様のご負担とさせていただいております。こちらの条件でご了承いただける場合のみ、正式な取引をお願いしたく存じます。」 |
|
既存取引で変更をお願いする場合 |
「インボイス制度の導入に伴い、振込手数料の取り扱いについて見直しを検討しております。つきましては、今後貴社の方で振込手数料を負担していただけないか、ご検討お願い申し上げます。」 |
上記のような文言を使用することで、相手に失礼のない形で負担を依頼できる可能性が高まります。ただし、相手の立場も尊重し、無理のない範囲で合意を得ることが重要です。
まとめ
インボイス制度下における振込手数料は、基本的に買い手負担が原則となりますが、契約に基づいて売り手負担とすることも可能です。その場合は、契約内容を明記し、双方で合意する必要があります。
また、振込手数料が売り手負担となる際の仕訳では、手数料を経費計上する方法や消費税の課税対象となるかを明確にすることが重要です。仕訳ミスを防ぐためには基本ルールや具体例を理解し、実務に則した対応を行いましょう。
さらに、トラブル回避には事前の取り決めが不可欠であり、明確なガイドラインを設けることで運用をスムーズに進められます。インボイス制度を適切に活用し、円滑な取引を継続することがポイントです。










