経費精算で電子帳簿保存法の対象となる書類は2種類!電子化期限や注意点も解説
更新日:2025.03.27
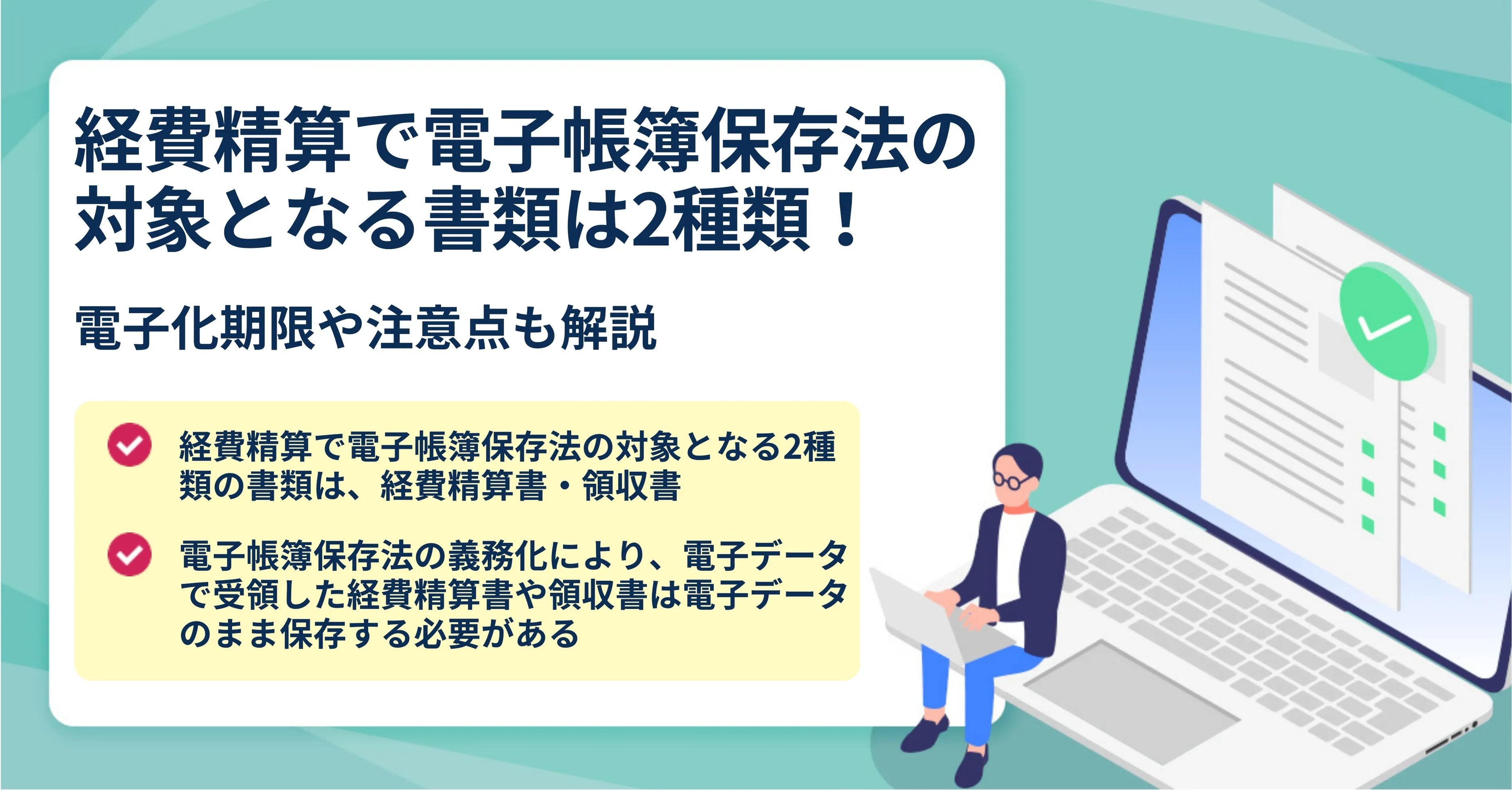
ー 目次 ー
経費精算に必要な書類は、2024年1月1日に義務化された電子帳簿保存法の対象です。
受け取った書類の形式によってそれぞれ保存方法が異なっており、正しく対応しなければなりません。とくに、紙で受領した書類には電子化期限が設けられているため、期限内の対応が必要となります。
電子帳簿保存法の要件や注意点を押さえたうえで、経費精算に必要な書類を適切に保管することが重要です。
本記事では、経費精算で電子帳簿保存法の対象となる書類について、概要や保存方法、電子化期限、注意点も交えて解説します。
【重要】経費精算で電子帳簿保存法の対象となる2種類の書類とは?
2022年1月1日に電子帳簿保存法が改正されたことで、経費精算に関する書類も電子保存が可能となりました。また、2024年1月1日以降に電子データの領収書を受領した場合は、電子データとしての保存が義務化されています。
経費精算で電子帳簿保存法に対応するには、対象となる書類をあらかじめ把握することが重要です。
ここでは、経費精算で電子帳簿保存法の対象となる2種類の書類について解説します。
①経費精算書
経費精算書は、従業員が立て替えた経費を精算する際に必要な書類です。また、経費精算書には経費の内訳を正確に把握し、不正な経費申請を防ぐ役割があります。経費精算書は、おもに会社で購入すべき事務用品を従業員が購入した場合や、交通費や交際費を従業員が支払った場合に用いられます。
なお、企業で利用される経費精算書の種類は以下のとおりです。
- 仮払経費精算書
- 出張旅費精算書
- 交通費精算書・旅費精算書
- 立替経費精算書
書類ごとに役割が異なるため、適切に使い分けましょう。
②領収書
領収書は、本来企業が負担すべき経費を従業員が立て替えたことを証明する際に必要な書類です。従業員による不正行為や代金の二重払い・過払いを防止するために提出が求められます。
提出する領収書には以下の項目が記載されていなければなりません。
- 支払日
- 支払先
- 支払内容
- 支払金額
領収書がない場合は、発行元の事業者に再発行を依頼する必要があります。また、レシートでも代用できますが、領収書と同じ項目の記載が必須です。
経費精算に必要な書類を電子化するには?2種類の方法を解説
電子帳簿保存法では、電子データで受領した経費精算書や領収書は電子データのまま保存する必要があります。
一方、紙の経費精算書や領収書については従来通りの保存方法で問題ありませんが、スキャナで読み取ることで電子データとしての保存も可能です。ただし、電子データ化を選択する場合には、定められた要件を満たさなければなりません。
経費精算に必要な書類を適切に取り扱うために、要件や保存方法を把握しましょう。
ここでは、経費精算に必要な書類を電子化する際の要件と保存方法を解説します。
①電子データのまま保存する
メールやクラウドサービスなどで経費精算書や領収書を受領した場合、電子帳簿保存法に基づいて電子データのままで保存しなければなりません。電子データとして保存する際には、以下の要件を満たす必要があります。
- ディスプレイ・プリンタを備え付けている
- 「取引年月日」「取引金額」「取引先」の3項目で検索できる
また、「取引年月日」「取引金額」について範囲を指定した検索ができること、2つ以上の項目を組み合わせて検索できることも必要です。
関連記事:電子取引はこれを読めば完璧!電子帳簿保存法の電子データの保存方法
②紙の書類をスキャナ保存する
紙で受領した経費精算書や領収書についても、要件を満たすことでスキャナ保存が可能です。紙の書類を電子化する際はスキャナで読み取って保存する方法、またはスマートフォンやデジタルカメラで撮影した画像を電子データとして保存する方法の2種類があります。
スキャナ保存の要件は以下のとおりです。
- 入力期間の制限
- 一定水準以上の解像度
- カラー画像による読み取り
- タイムスタンプの付与
- ヴァージョン管理
- 帳簿との相互関連性の確保
- 見読可能装置等の備え付け
- 速やかに出力すること
- 検索機能の確保
また、紙の書類をスキャナ保存すれば、読み取ったあとの書類は破棄できます。
関連記事:電子帳簿保存法のスキャナー保存完全ガイド【一問一答】よくある質問・解説付き
電子帳簿保存法で経費精算書や領収書を電子化できるのは最長「2か月7営業日」まで
2022年1月1日の電子帳簿保存法の改正によって電子化期限が緩和されたことで、経費精算書や領収書を電子化できるのは最長で2か月7営業日までとなりました。
2019年に改正された際には電子化期限が3営業日以内でしたが、2022年以降は余裕をもって対応しやすくなっています。書類の受領から2か月7営業日以内に電子化し、タイムスタンプの付与によって、電子帳簿保存法の要件を満たすことが可能です。
しかし、電子帳簿保存法のスキャナ保存の要件には「速やかに出力すること」と記載されています。あくまでも最長期間であり、経費精算書や領収書の受領後は迅速な対応が必要です。
関連記事:電子帳簿保存法で入力期間の2ヶ月を過ぎたらどうすべき?要件や対応のコツを紹介
電子帳簿保存法に基づいて経費精算書や領収書を取り扱う際の3つの注意点
電子帳簿保存法に基づいて経費精算書や領収書を取り扱う際には3つの注意が必要です。注意点を事前に把握していない場合、書類の改ざんや不正を疑われるおそれがあります。
ここでは、電子帳簿保存法に基づいて経費精算書や領収書を取り扱う際の3つの注意点を解説します。
- 紙で受領した経費精算書や領収書も一定期間保存する
- データ管理を徹底する
- 電子化した経費精算書や領収書の保存期間を把握しておく
①紙で受領した経費精算書や領収書も一定期間保存する
紙で受領した経費精算書や領収書を電子データとして保存したあとに、データの不備が発覚する場合があります。
たとえば、データがうまく読み取れていない、必要な項目の文字が切れていて読めないなどのトラブルが考えられます。そのため、紙で受領した経費精算書や領収書をスキャナ保存したあとも、一定期間は原本を保存するのがおすすめです。
経費精算書や領収書が正確に電子データ化できていることを確認してから、原本を破棄するようにしましょう。
②データの管理を徹底する
電子帳簿保存法は2022年1月1日の法改正により、要件が大幅に緩和されました。
しかし、取り扱いに不備があった場合の罰則規定は強化されています。税務関連の書類を適切に管理するためには、社内で仕組みを構築することが重要です。とくに、保存する場所が1か所に集約されていない場合や、書類の管理が属人化している場合は注意しなければなりません。
書類の申請漏れを防ぐためには、データ管理に関して社内でマニュアルを整備するのが良いでしょう。
③電子化した経費精算書や領収書の保存期間を把握しておく
電子帳簿保存法に基づいて電子化したデータには保存期間が定められています。
経費精算書や領収書は重要書類に該当するため、原則として法人では7年、個人事業主では5年(※)の保管が義務付けられています。保存形式が電子データと紙のどちらであるかにかかわらず、保存期間を遵守しなければなりません。
また、青色申告をおこなう事業者で年度内に欠損金がある場合は、10年間の保管が求められます。
保存期間内は税務署からの問い合わせがあった場合に、必要な書類をいつでも提出できるようにしておきましょう。
(※)前々年分の事業所得および不動産所得の金額が300万円を超える場合は7年となります。
関連記事:電子帳簿保存法の保存期間をかんたん解説|対象書類と注意点まとめ【永久保存版】
電子帳簿保存法に基づく経費精算に関してよくある質問
最後に、電子帳簿保存法に基づく経費精算に関してよくある質問を紹介します。
①経費精算書を電子化するには請求書と領収書のどっちが必要?
経費精算書を電子化する際には、領収書もあわせて電子化する必要があります。
領収書が必要な理由は以下のとおりです。
- 精算が完了していることを証明する
- 経費の内容を正確に把握する
- 従業員の不正な申請を防ぐ
このように、経費精算をおこなう際は取引の事実を確認し、不正行為や代金の二重払い・過払いを防止するために領収書の提出と保管が求められます。
②電子帳簿保存法で紙の領収書を保存したい場合はどうする?
紙で受領した領収書を保存する場合、そのまま保存するかスキャナ保存するかの2種類から選択できます。スキャナ保存する場合は、電子化する際に定められた要件を満たすことが必要です。
また、紙の領収書を電子化する際は、受領してから最長2か月7営業日以内におこなわなければなりません。
③旅費の経費精算でも領収書の保存は必要?
旅費の経費精算をおこなう際は、基本的に領収書の提出が必要です。とくに、ホテル代やタクシー代の領収書は、現地で発行してもらわなければなりません。
ただし、電車移動した場合の交通費は経路から金額を割り出せるため、領収書の提出を求められないケースもあります。
まとめ|電子帳簿保存法に基づく経費精算書や領収書の保存方法を把握して、適切に保存しよう
本記事では、経費精算で電子帳簿保存法の対象となる書類について、概要や保存方法、電子化期限、注意点も交えて解説しました。
経費精算をおこなう際には、経費精算書と領収書の2種類が電子帳簿保存法の対象となります。原則として、紙で受領した経費精算書や領収書を電子化する際は、最長2か月7営業日までに対応しなければなりません。
また、経費精算書や領収書の保存期限の把握やデータ管理の徹底など、注意点を理解して適切に保管することが重要です。
電子帳簿保存法への対応を検討している方は、本記事で解説した要件やルールに基づいて、適切に保存しましょう。










