交通系ICカード履歴はスクショでOK?電子帳簿保存法の対応法まとめ
更新日:2025.07.28
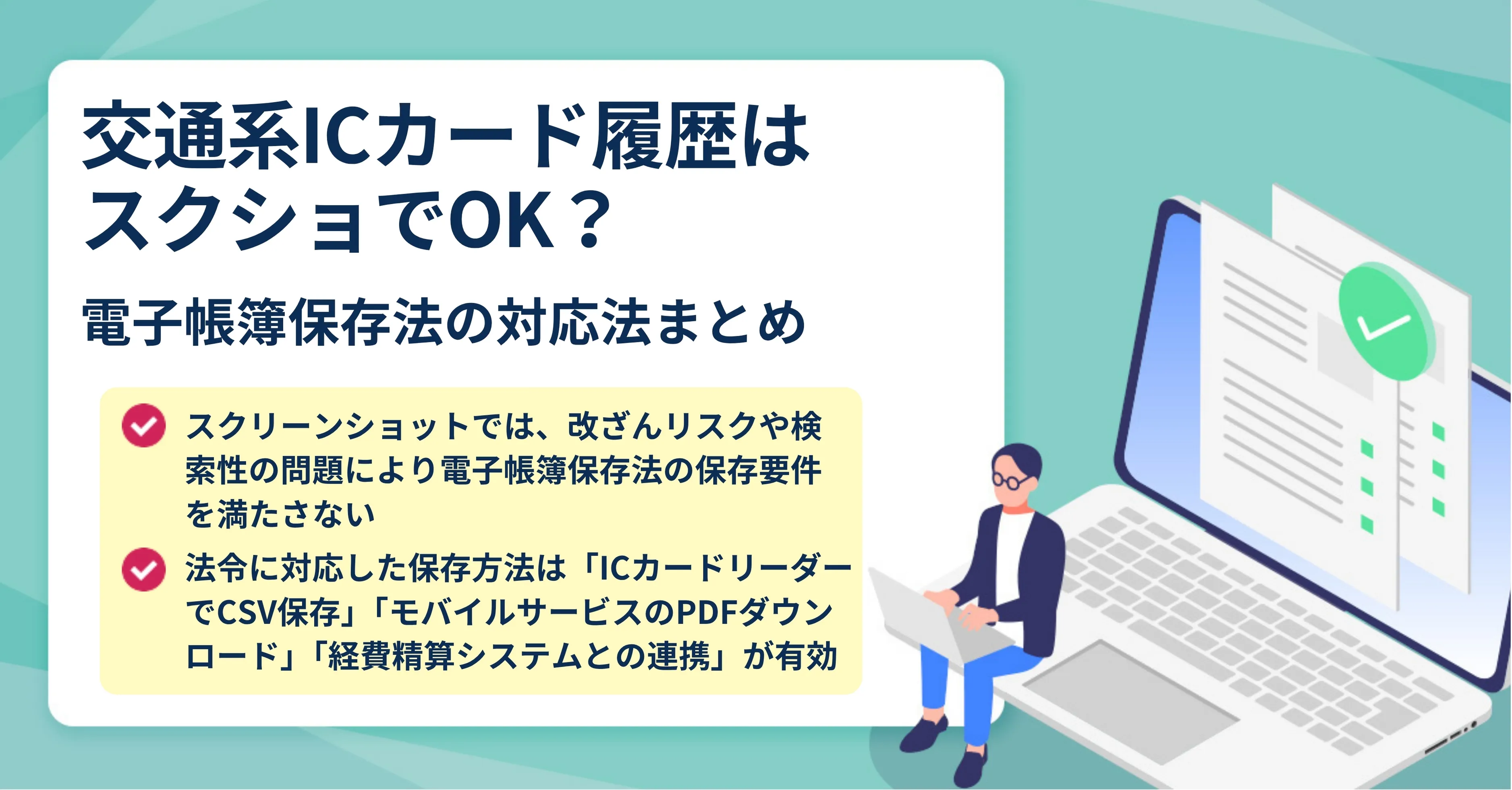
ー 目次 ー
交通系ICカードの利用履歴、電子帳簿保存法にどう対応すればいいかお悩みではありませんか。結論から言うと、SuicaやPASMOなどの利用履歴をスクリーンショットで保存する方法は、原則として法令の要件を満たしません。この記事では、スクショが認められない理由と、ICカードリーダーや経費精算システムなどを使った電子帳簿保存法に準拠した正しいデータ保存方法を具体的に解説します。この記事を読めば、交通費精算における悩みが解決します。
そもそも電子帳簿保存法とは?基本ルールを確認!
交通費の経費精算でSuicaやPASMOなどの交通系ICカードを利用する個人事業主や企業担当者にとって、電子帳簿保存法(電帳法)への対応は避けて通れない課題です。2024年1月から電子取引データの電子保存が完全義務化され、正しい知識がなければ追徴課税などのリスクも生じます。まずは、法律の基本をしっかり押さえることから始めましょう。
電子帳簿保存法とは?わかりやすく要件を解説
電子帳簿保存法とは、国税関係の帳簿や書類(請求書・領収書など)を、紙ではなく電子データ(ファイル)のまま保存することを認めた法律です。ペーパーレス化を促進し、経理業務の効率化やコスト削減を目的としています。保存方法は、データの種類に応じて次の3つに区分されています。
|
保存区分 |
概要 |
具体例 |
|
電子帳簿等保存 |
会計ソフトなどで最初から一貫して電子的に作成した帳簿・書類を、データのまま保存すること。 |
会計ソフトで作成した仕訳帳、総勘定元帳、決算関係書類など |
|
スキャナ保存 |
紙で受け取った、または作成した書類をスキャナーやスマートフォンで読み取り、画像データとして保存すること。 |
紙で受け取った請求書や領収書のスキャンデータ |
|
電子取引データ保存 |
電子メールやクラウドサービスなど、電子的にやり取りした取引情報をデータのまま保存すること。(※2024年1月より完全義務化) |
PDFで受け取った請求書、ECサイトの領収書データ、交通系ICカードの利用履歴データなど |
特に重要なのが「電子取引データ保存」です。交通系ICカードの利用履歴をウェブサイトからダウンロードした場合などは、この電子取引に該当するため、定められた要件に従って電子データのまま保存しなければなりません。
対象になる書類・データは?電子取引とは何を指すのか
電子帳簿保存法の対象となるのは、法人税や所得税など国税に関する法律で保存が義務付けられている「国税関係帳簿」と「国税関係書類」です。
- 国税関係帳簿:仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛金元帳など
- 国税関係書類:貸借対照表、損益計算書などの決算関係書類、および契約書、見積書、請求書、領収書などの取引関係書類
交通系ICカードの利用履歴は、経費の支払いを証明する「領収書」に準ずるものとして、国税関係書類に含まれます。
そして、これらの取引情報をデータでやり取りした場合、それは「電子取引」と定義されます。具体的には、以下のような取引が該当します。
- 電子メールに添付された請求書や領収書のPDF
- ウェブサイト上からダウンロードした領収書や利用明細のデータ
- クラウドサービスを利用した経費精算や請求書発行
- ECサイトでの購入履歴データ
- EDI(電子データ交換)取引
つまり、モバイルSuicaやモバイルPASMOのアプリ、または会員専用サイトから利用履歴データをダウンロードして経費精算を行う場合、そのデータは「電子取引」に該当し、紙に印刷して保存するだけでは法令の要件を満たせないということになります。
【結論】電子帳簿保存法において交通系ICカード履歴のスクショ保存は原則NG
結論から言うと、交通系ICカードの利用履歴をスクリーンショットで撮影し、画像ファイルとして保存する方法は、電子帳簿保存法の要件を満たさないため原則として認められません。手軽に保存できるため多くの人が検討する方法ですが、税務調査などで指摘されるリスクがあるため避けるべきです。
スクリーンショットが認められない理由
スクリーンショットによる保存が電子帳簿保存法の要件を満たさない主な理由は、「真実性の確保」と「可視性の確保」ができない点にあります。具体的にどの要件を満たせないのか、以下の表で確認してみましょう。
|
保存要件 |
具体的な内容 |
スクリーンショットの問題点 |
|
真実性の確保 |
保存されたデータが改ざんされていないことを証明するための要件。タイムスタンプの付与や、訂正・削除の履歴が残るシステムでの保存などが求められる。 |
画像編集ソフトで簡単に日付や金額を改ざんできるため、データの真実性を担保できません。また、誰がいつ保存したかの証明も困難です。 |
|
可視性の確保 |
税務調査などの際に、誰もが内容を確認できるようにするための要件。「取引年月日」「取引金額」「取引先」の3項目で検索できる機能の確保が必要。 |
画像データであるため、ファイル内の文字情報(駅名や金額)を対象とした検索ができません。ファイル名を手動で変更する方法もありますが、手間がかかり、検索要件を完全に満たしているとは言えません。 |
このように、スクリーンショットは手軽な一方、データの改ざんが容易であり、検索性も著しく低いという問題があります。電子帳簿保存法に対応するためには、単にデータを画像として残すだけでなく、定められたルールに則った方法で保存・管理することが不可欠です。
【実践】電子帳簿保存法に対応する交通系ICカードの保存方法3選
交通系ICカードの利用履歴をスクリーンショットで保存するのは、電子帳簿保存法の要件を満たさないため原則として認められません。では、どのように保存すればよいのでしょうか。ここでは、電子帳簿保存法の「電子取引」の要件を満たす、具体的な保存方法を3つご紹介します。
方法① ICカードリーダーで利用履歴をCSV出力して保存する
物理的な交通系ICカード(プラスチックカード)を利用している場合に有効な方法です。ICカードリーダーを使ってパソコンに利用履歴を読み込み、CSVデータとして保存します。このCSVデータが、電子帳簿保存法における「電子取引データ」に該当します。
準備するもの
この方法を実践するには、以下のものが必要です。特にICカードリーダーは、お使いのICカードに対応しているか事前に確認しましょう。
|
項目 |
具体例・補足 |
|
交通系ICカード |
Suica、PASMO、ICOCAなど、普段利用しているカード |
|
ICカードリーダーライター |
ソニー社の「PaSoRi(パソリ)」などが有名です。 |
|
パソコン |
WindowsまたはMac |
|
利用履歴閲覧ソフト |
「SFCard Viewer 2」などのフリーソフトを利用します。 |
具体的な手順
準備が整ったら、以下の手順で利用履歴をCSVファイルとして保存します。
- パソコンにICカードリーダーライターを接続し、利用履歴閲覧ソフトをインストールします。
- ソフトを起動し、ICカードリーダーの上に交通系ICカードを置きます。
- カード情報が自動で読み込まれ、乗車履歴やチャージ履歴が画面に表示されます。
- 表示された履歴の中から、経費精算に必要な期間や項目を選択します。
- メニューから「エクスポート」や「CSV形式で保存」などを選択し、パソコンにデータを保存します。
- 保存したCSVファイルは、電子帳簿保存法の検索要件を満たすように「20241026_交通費_山田太郎」のような規則性のあるファイル名に変更して、所定のフォルダに保管します。
この方法では、データの訂正・削除の履歴が残らないため、訂正削除を原則禁止とするなどの事務処理規程を別途備え付けておく必要があります。
方法② モバイルSuicaやモバイルPASMOの利用明細書をPDFで保存する
スマートフォンでモバイルSuicaやモバイルPASMOを利用している場合に、最も手軽で確実な方法です。各サービスの会員サイトから、公式な利用明細書(領収書)をPDF形式でダウンロードして保存します。
モバイルSuicaの場合
モバイルSuicaの会員メニューサイトから、領収書機能を持つ利用明細書をPDFで発行できます。アプリからは発行できないため、ブラウザでサイトにアクセスする必要があります。
- パソコンやスマートフォンのブラウザで「モバイルSuica会員メニュー」サイトにアクセスし、ログインします。
- メニューの中から「ご利用明細書(領収書)/払戻計算書」を選択します。
- 利用日や期間を指定して、表示させたい履歴を検索します。
- 画面に表示された内容を確認し、「ご利用明細書(PDF)」ボタンをクリックしてPDFファイルをダウンロード・保存します。
- 保存したPDFファイルは、方法①と同様に、検索しやすいファイル名に変更して保管します。
モバイルPASMOの場合
モバイルPASMOも同様に、会員メニューサイトからPDF形式の利用明細書を発行・保存することが可能です。
- 「モバイルPASMO会員メニュー」サイトにブラウザでアクセスし、ログインします。
- 「ご利用明細書(領収書・払戻計算書)発行」のメニューを選択します。
- 対象期間(月単位)を選択し、明細を表示させます。
- 「PDFダウンロード」ボタンをクリックし、ファイルを保存します。
- 保存したファイルは、電子帳簿保存法の要件に従ってファイル名を変更し、管理・保管してください。
方法③ 電子帳簿保存法対応の経費精算システムと連携する
経費精算の頻度が高い法人や個人事業主の方には、電子帳簿保存法に対応した経費精算システムの導入が最もおすすめです。手作業によるミスや手間を大幅に削減し、法改正にも自動で対応できるメリットがあります。
多くの経費精算システムには、交通系ICカードやモバイルSuica/PASMOと連携する機能が備わっています。
- 経費精算システムに、利用している交通系ICカードの情報を登録します。
- システムが定期的に利用履歴を自動で取得します。
- 従業員は、システムに取り込まれた履歴データの中から経費として申請したいものを選択するだけで、簡単に経費申請が完了します。
- 申請されたデータは、電子帳簿保存法の要件(真実性の確保・可視性の確保)を満たした状態でシステム内に保存されます。
この方法であれば、ファイル名の変更やタイムスタンプの付与、検索要件の確保といった煩雑な作業をシステムが自動で行ってくれるため、担当者の負担を大きく軽減できます。
Q&A|交通系ICカードと電子帳簿保存法に関するよくある質問
ここでは、交通系ICカードの経費精算と電子帳簿保存法に関して、多くの方が疑問に思う点をQ&A形式で解説します。具体的なケースを想定して、対応方法をわかりやすく説明します。
私用と仕事用が混ざってるICカードでも大丈夫?どう処理すればいい?
はい、プライベートの支払いと業務上の経費が混在している交通系ICカードでも、電子帳簿保存法の要件を満たす形で経費精算が可能です。
重要なのは、業務で利用した経費を客観的に区別できるように処理することです。具体的には、ICカードリーダーやモバイルSuicaのアプリなどから利用履歴データ(CSVやPDF)を出力した後、経費精算システムやExcel上で業務利用分にチェックを入れる、あるいは備考欄に「A社訪問のため」といった利用目的を記載します。このように、私的利用と業務利用を明確に仕分けした上でデータを保存すれば、税務調査の際にも適切な証拠として認められます。
領収書をまとめてスキャンしたらダメ?1枚ずつ保存は必要?
複数枚の領収書を1つのPDFファイルなどにまとめてスキャン保存すること(いわゆる「複数枚スキャン」)は、一定の要件を満たせば認められています。
ただし、スキャナ保存の要件である解像度(200dpi以上)や階調(カラー画像)を満たし、かつ、スキャンした画像上でそれぞれの領収書が重なることなく、記載内容を明確に読み取れる状態でなければなりません。1枚ずつスキャンして保存する方が、後の管理や検索がしやすいというメリットもあります。利用している経費精算システムが1取引につき1ファイルのアップロードを推奨している場合も多いため、自社の運用ルールに合わせて最適な方法を選択しましょう。
電子帳簿保存法では、領収書なしでも交通費として認められる?
はい、特に3万円未満の公共交通機関を利用した交通費については、領収書がなくても経費として認められるケースが一般的です。その際、支払いの事実を証明する代替書類が必要となります。
交通系ICカードの利用履歴データは、この「支払いの事実を証明する代替書類」として非常に有効です。「いつ」「どの区間を」「いくらで」利用したかが記録されているため、客観的な証拠能力が高いと判断されます。この利用履歴データを電子取引データとして正しく保存しておくことで、領収書がなくても交通費として経費計上することが可能です。
履歴を印字してスキャンした場合は、電子取引ではなくスキャナ保存になる?
その通りです。取引データの保存方法は、そのデータがどのように生成・受領されたかによって決まります。
モバイルSuicaなどのPDF明細は「電子取引保存」、駅で印刷した紙の履歴をスキャンしたものは「スキャナ保存」に該当します。どの方法で受領したかによって保存区分が異なるため注意が必要です。一般的に、電子取引データをそのまま保存する方が手間が少なく、効率的です。
まとめ
電子帳簿保存法が本格的に義務化されたことで、交通系ICカードの履歴保存にも、より正確な対応が求められるようになりました。この記事で解説した通り、改ざんのリスクがあるためスクリーンショットでの保存は原則として認められません。
本記事でご紹介した方法の中から、自社の運用に合った対応策を選び、安心して経費処理ができる体制を整えていただければと思います。










