電子帳簿保存法と交通費の最新ルール!領収書・IC履歴の対応まとめ
更新日:2025.07.28
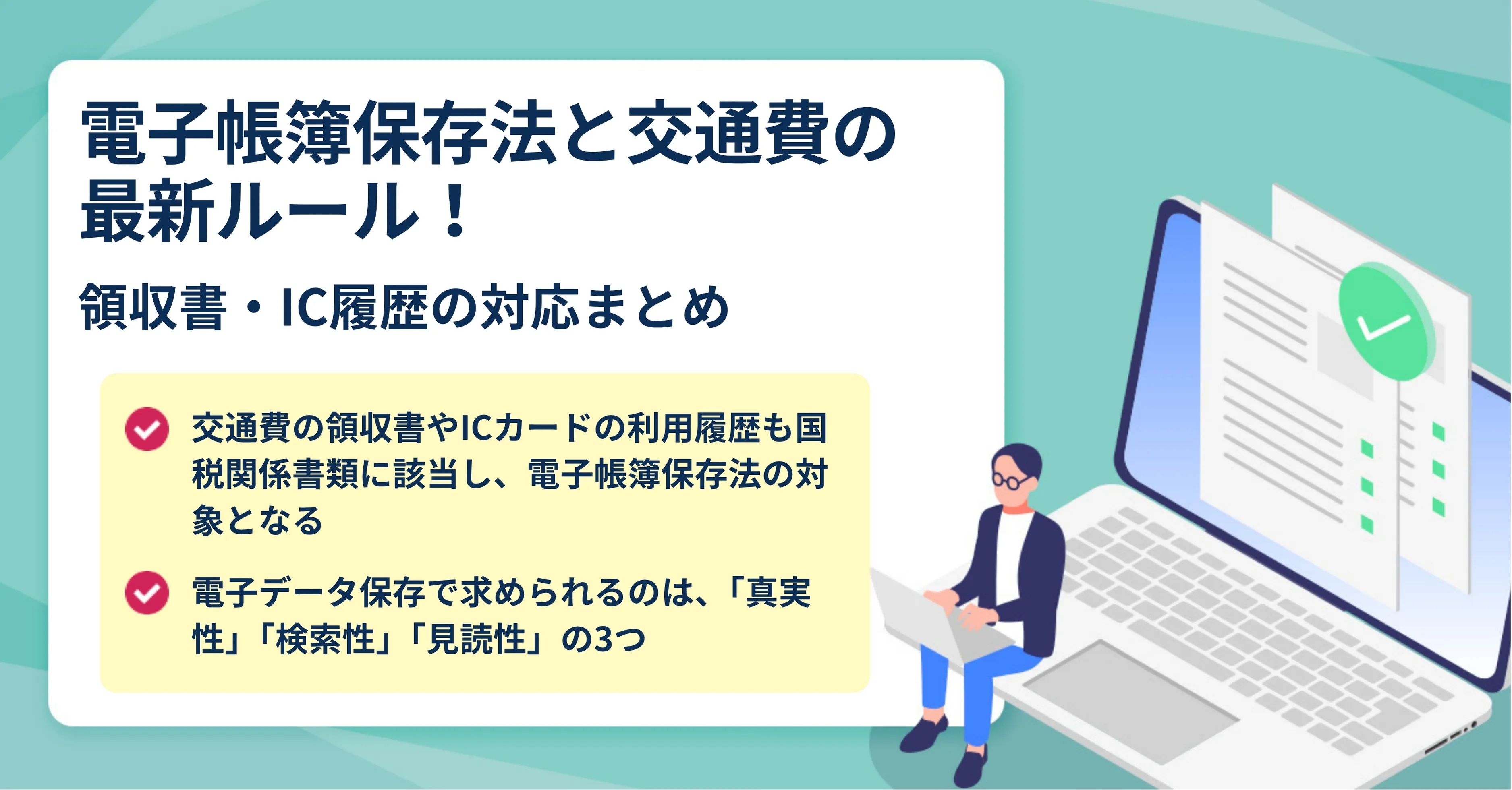
ー 目次 ー
電子帳簿保存法の改正により、「交通費の領収書やICカードの履歴ってどうすればいいの?」とお困りの方も多いのではないでしょうか。
実は、交通費も電子帳簿保存法の対象に含まれており、SuicaなどのIC履歴や、領収書が出ないケースでも、ルールに沿った電子保存が求められています。本記事では、電子帳簿保存法の基本から、紙の領収書やIC履歴といった交通費ごとの具体的な保存方法まで、実務に役立つポイントをわかりやすく解説いたします。
電子帳簿保存法では交通費も対象?基本ルールをやさしく解説
2022年1月の法改正により、多くの事業者にとって対応が必須となった電子帳簿保存法(電帳法)。日々の業務で扱う交通費の領収書やICカードの利用履歴が、どのように関わってくるのか、まずは基本的なルールから確認していきましょう。
そもそも電子帳簿保存法とは?
電子帳簿保存法とは、法人税や所得税などの国税に関する帳簿や書類について、紙ではなく電子データ(電磁的記録)で保存することを認めた法律です。これまで原則として紙での保存が義務付けられていた会計帳簿や領収書、請求書などを、一定のルールを満たすことでパソコンやサーバー上にデータとして保存できます。
この法律は、ペーパーレス化によるコスト削減や業務効率化を目的としていますが、特に重要なのが2022年1月の改正です。この改正により、メールやWebサイト経由で受け取った請求書や領収書などの「電子取引データ」は、紙に印刷して保存することが認められなくなり、すべての事業者(法人・個人事業主)でデータそのものの電子保存が義務化されました。
電子帳簿保存法で交通費は対象?
結論から言うと、交通費の精算に関わる書類やデータも電子帳簿保存法の対象となります。
具体的には、次のようなケースが考えられます。
- 交通系ICカード(SuicaやPASMOなど)の利用履歴データ:Webサイトからダウンロードした場合、「電子取引データ保存」の対象となり、データのまま保存する義務があります。
- 紙で受け取ったタクシーの領収書や切符:従来通り紙のまま保存できますが、スキャンして電子データとして保存する場合は「スキャナ保存」の要件を満たす必要があります。
- 経費精算システムで申請された交通費データ:システム上で完結する取引は「電子取引」に該当する可能性があります。
このように、交通費の精算方法によって、どの保存区分に該当するかが変わってきます。特に、多くのビジネスパーソンが利用する交通系ICカードの履歴は電子保存が義務付けられているため、正しい対応が不可欠です。
難しくない!電子帳簿保存法で求められる3つのルール
電子帳簿保存法と聞くと複雑なイメージがあるかもしれませんが、交通費の経費精算データなどを電子保存する際に求められる要件は、大きく分けて3つだけです。それは「真実性の確保」「検索性の確保」「見読性の確保」です。一つひとつのポイントを押さえれば、決して難しいものではありません。
改ざんされていないことを証明!「真実性の確保」の対応方法
「真実性の確保」とは、保存された電子データが本物であり、作成されてから誰も改ざんしていないことを証明するためのルールです。スキャナで読み取って保存する場合(スキャナ保存)や、電子データを受け取る場合(電子取引)には、「真実性の確保」が特に重要となります。※スキャナ保存方法については、後述の「紙の領収書の保存方法」の章で詳しく解説します。
以下のいずれかの措置を講じることで、この要件を満たすことができます。
・タイムスタンプが付与されたデータを受領する
取引先から受け取る請求書PDFなどに、最初からタイムスタンプが付いているケース。
・データ受領後、速やかにタイムスタンプを付与する
自社で契約しているタイムスタンプ付与システムを利用し、受領したデータに時刻認証を記録。
・訂正や削除の履歴が残る(またはできない)システムを利用する
クラウド型の経費精算システムなど、データの変更履歴がすべて記録される仕組みを導入。
・訂正削除の防止に関する事務処理規程を定めて守る
データ訂正や削除の手順・責任者を定めた社内ルールを作成し、それに沿って運用。
国税庁が公表するサンプルを参考に作成可能。システム導入不要で低コスト対応。
後からすぐ探せる?「検索性の確保」はファイル名の工夫がカギ
「検索性の確保」とは、税務調査などで特定の取引記録を求められた際に、膨大なデータの中からすぐに見つけ出せるようにしておくためのルールです。原則として、以下の3つの条件でデータを検索できるようにしておく必要があります。
- 「取引年月日」「取引金額」「取引先名」を検索条件として設定できること。
- 日付または金額については、範囲を指定して検索できること。(例:「2024年4月1日から4月30日まで」)
- 2つ以上の任意の記録項目を組み合わせて検索できること。(例:「2024年4月1日」かつ「株式会社〇〇」)
これらの要件は専用の会計ソフトや文書管理システムを導入することで満たせますが、実は緩和措置も用意されています。税務職員からデータのダウンロードを求められた際に、それに応じられるようにしていれば、範囲指定や複数項目での検索機能は不要になります。
システムを導入しない場合は、ファイル名の付け方を工夫するのが最も手軽な方法です。「20240415_株式会社交通_5500.pdf」のように、「日付_取引先_金額」といったルールを統一することで、フォルダの検索機能で簡単に見つけ出すことができます。
データはすぐ確認できる?「見読性の確保」で求められること
「見読性の確保」とは、保存した電子データを、パソコンのモニターや書類などで、誰もがはっきりと読める状態で速やかに確認できるようにしておくためのルールです。具体的には、以下の環境を整えることが求められます。
- 電子データが保存されている場所に、パソコン、ディスプレイ、プリンタを設置すること。
- 上記機器の操作説明書を備え付けておくこと。
- データが整理された状態で保存されており、速やかに表示・印刷できること。
この要件は、特別なシステムを導入しなくても、一般的なオフィス環境が整っていれば問題なく満たすことができます。電子データがどのPCのどのフォルダに保存されているかを明確にしておくだけで十分です。
交通費の種類別!紙領収書・ICカード・定期代の電子帳簿保存法の対応
交通費の精算方法は、紙の領収書、交通系ICカード、定期券など多岐にわたります。ここでは、それぞれの種類に応じた電子帳簿保存法の正しい対応方法を具体的に解説します。
紙の領収書はそのまま保存してOK?注意点と保管ルール
電車やタクシーなどを利用した際に受け取る紙の領収書は、電子帳簿保存法において「スキャナ保存」の対象となります。スキャナ保存は義務ではないため、従来通り紙のまま7年間ファイリングして保存することも認められています。しかし、ペーパーレス化や業務効率化の観点からスキャナ保存を選択する企業が増えています。
紙の領収書をスキャナ保存する場合、以下の要件を満たす必要があります。
|
保存方法 |
主なルールと注意点 |
|
紙のまま保存 |
|
|
スキャナ保存(電子化) |
|
スキャナ保存を行うことで、物理的な保管場所が不要になり、後からの検索も容易になるというメリットがあります。
ICカード(Suica・PASMO)の履歴はどう保存すればいい?
SuicaやPASMOなどの交通系ICカードの利用履歴データを使って交通費を精算する場合、そのデータは「電子取引」に該当します。電子取引データは、紙に出力して保存するのではなく、データのまま電子保存することが義務付けられています。
具体的な保存方法は、利用しているICカードの種類によって異なります。
モバイルSuicaやモバイルPASMOの場合
スマートフォンのアプリや会員用ウェブサイトから、利用履歴をCSVファイルやPDFファイルとしてダウンロードできます。このダウンロードした電子データを、検索要件を満たす形でサーバーやクラウドストレージに保存します。
カード型のSuicaやPASMOの場合
カード型のICカードの場合、いくつかの対応方法が考えられます。
- 券売機で履歴を印字しスキャンする: 駅の券売機などで利用履歴を印字し、その紙をスキャナ保存の要件に沿って電子化します。この場合、扱いは「スキャナ保存」となります。
- 経費精算システムと連携する: ICカードリーダーと連携する経費精算システムを導入している場合、システムが自動で利用履歴データを取得・保存してくれます。これが最も効率的な方法です。
いずれの場合も、保存するデータには「利用日」「利用区間」「鉄道会社名」「金額」といった情報が含まれている必要があります。
定期券代・回数券の精算は対象?対応が必要なケースと免除されるケース
業務で利用する定期券や回数券の購入費用も、もちろん経費として計上できます。その際の領収書の扱いは、受け取り方によって変わります。
|
購入・精算のケース |
証憑(領収書)の形式 |
電子帳簿保存法上の扱い |
|
窓口で現金購入 |
紙の領収書 |
「スキャナ保存」の対象。紙のままの保存も可。 |
|
Webサイトやアプリで購入 |
PDFやWeb画面の領収書データ |
「電子取引」の対象。電子データのまま保存が必須。 |
|
通勤手当として給与で支給 |
(個別の領収書は不要) |
給与計算の範囲となり、交通費精算としての電子保存は通常不要。 |
注意点として、通勤手当として支給される定期代は、従業員の給与の一部と見なされるため、交通費精算とは別の扱いです。この場合、会社は従業員からの領収書を個別に回収・保存する必要はありません。あくまで、業務上の必要経費として会社が直接購入したり、従業員が立て替えて精算したりする場合に、電子帳簿保存法の対象となります。
電車やバスなどの領収書がない交通費の場合
近距離の電車やバスの利用など、領収書の発行が難しい、または慣例として受け取らないケースは少なくありません。特に3万円未満の公共交通機関の利用については、領収書がなくても経費精算が認められています。
ただし、その場合は領収書の代わりとなる「交通費精算書」や「出金伝票」を作成する必要があります。この精算書が、税法上の証憑書類となります。
交通費精算書には、以下の項目を正確に記載することが求められます。
- 従業員の氏名
- 利用日
- 利用した交通機関(例:JR、東京メトロ)
- 利用区間(例:新宿駅~東京駅)
- 目的(例:〇〇社との打ち合わせのため)
- 金額
この交通費精算書をExcelなどの電子データで作成し、社内システムで申請・承認している場合、その電子データ自体が「電子取引」もしくは「電子的に作成した国税関係書類」に該当します。そのため、電子帳簿保存法の要件に従って、データのまま保存する必要があります。
Q&A|電子帳簿保存法と交通費に関するよくある質問
ここでは、電子帳簿保存法と交通費の取り扱いに関して、特にお問い合わせの多い疑問点についてQ&A形式で解説します。
ICカードのチャージ代は経費にできる?
原則として、SuicaやPASMOなどの交通系ICカードにチャージ(入金)した時点では、経費として計上することはできません。チャージした金額は「前払金」や「仮払金」といった資産として扱われます。
経費として認められるのは、実際に電車やバスなどの交通機関を利用し、運賃が支払われた時点です。そのため、経費精算や帳簿付けのためには、チャージ時の領収書ではなく、実際に利用した日付、区間、金額が記載された「利用履歴」が必要となります。
モバイルSuicaやモバイルPASMOのアプリからCSV形式でダウンロードした利用履歴データや、券売機で印字した利用履歴をスキャンしたデータは、電子帳簿保存法の要件に従って保存する必要があります。
個人事業主も交通費を電子保存しないとダメ?
はい、個人事業主やフリーランスの方も電子帳簿保存法の対象となります。所得税の申告(青色申告・白色申告)を行うすべての事業者は、法律の適用対象です。
したがって、交通費に関して以下のような電子取引データを受け取った場合、原則として電子データのまま保存する義務があります。
- 交通系ICカードの利用履歴データ(CSVファイルなど)
- インターネットで予約・購入した航空券や新幹線の領収書データ(PDFファイルなど)
- タクシー配車アプリから発行された電子領収書
一方で、紙で受け取った領収書やレシートは、引き続き紙のまま保存することが認められています。スキャナ保存制度を利用して電子化することも可能ですが、これは任意です。重要なのは「電子データで受け取ったものは電子データで保存する」というルールです。
出張旅費特例とは?領収書なしでもOKになるって本当?
「出張旅費特例」とは、電子帳簿保存法のスキャナ保存制度における特例の一つです。この特例を適用すると、従業員が立て替えた出張旅費等について、領収書の提出を不要にできます。
ただし、無条件で領収書が不要になるわけではありません。適用には、社内で「出張旅費規程」を整備し、その規程に基づいて経費精算を行うことが前提となります。この場合、規程で定められた範囲内の金額であれば、領収書の代わりに「出張旅費精算書」を作成・保存することで、経費として認められます。
この特例のポイントを以下にまとめます。
|
項目 |
内容 |
|
適用条件 |
社内で「出張旅費規程」が整備されており、その規程に基づいて精算が行われること。 |
|
対象となる経費 |
従業員が立て替えた出張旅費(交通費、日当、宿泊費など)のうち、規程で定める通常必要と認められる範囲内の金額。 |
|
保存する書類 |
領収書の代わりに、定められた様式の「出張旅費精算書」をスキャナ保存する。 |
|
注意点 |
あくまでスキャナ保存における特例です。電子取引で受領した領収書データ(PDFなど)は、この特例の対象外となり、電子データのまま保存する必要があります。 |
この特例を活用することで、従業員の領収書の糊付けや提出の手間、経理担当者の確認・保管作業を大幅に削減できるメリットがあります。
まとめ
電子帳簿保存法では、交通費のデータも例外ではなく、適切に保存することが求められます。
一見むずかしそうに感じるかもしれませんが、ファイル名のルールを決めたり、領収書の扱いを整理したりするだけでも、実は要件をクリアできます。
本記事の内容を参考に、ご自身や会社の運用スタイルに合った方法から、できる範囲で対応を始めてみましょう。










