【令和5年度税制改正大綱】電子帳簿保存法への影響は?変更点をわかりやすく解説
更新日:2025.07.28
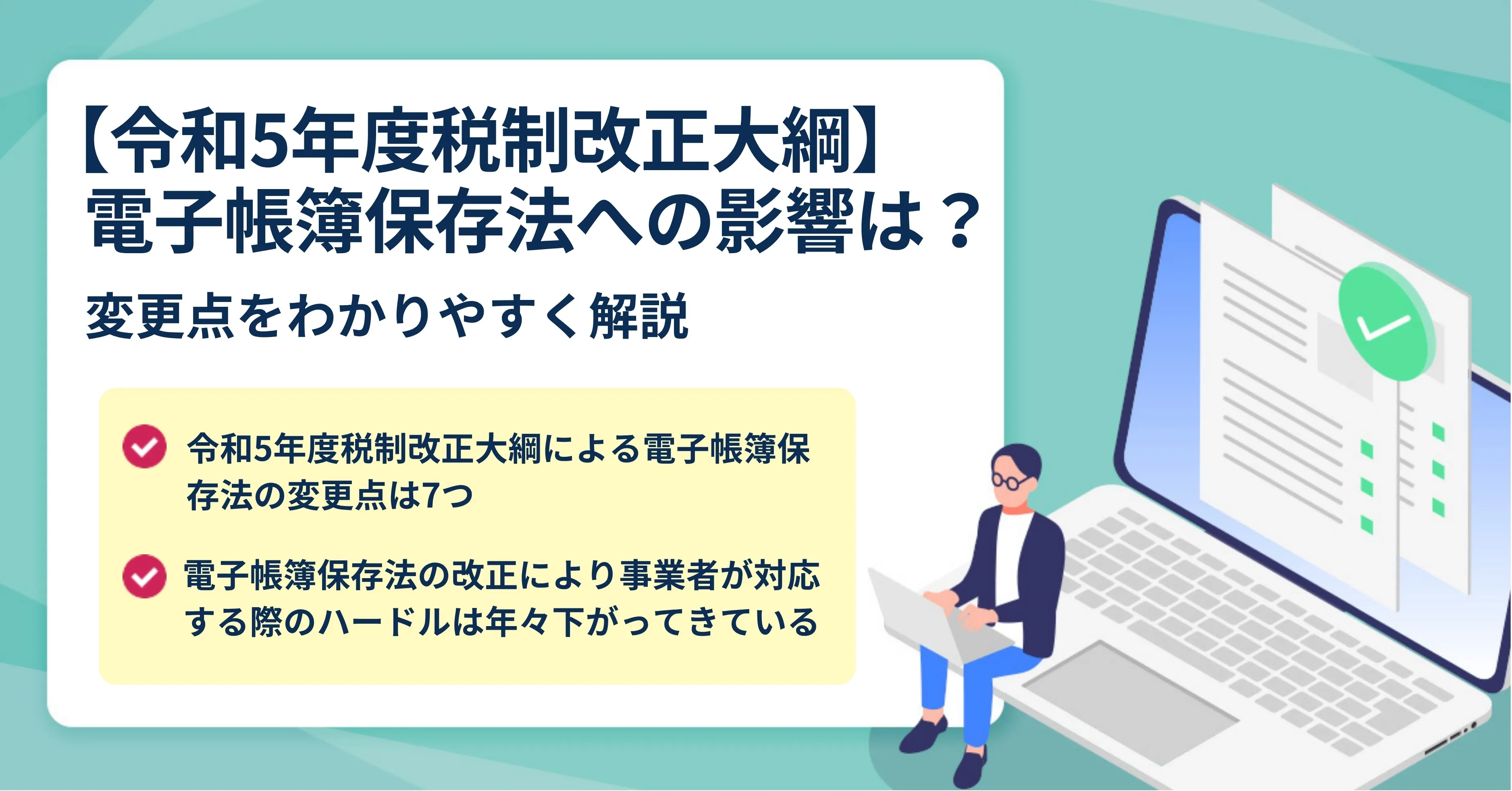
ー 目次 ー
2023(令和5)年の税制改正大綱には電子帳簿保存法に関する項目が取りまとめられており、事業者の対応に影響を与えます。
電子帳簿保存法は法改正の度に内容に変更が加えられるため、対応に悩む事業者は少なくありません。
法改正にあわせて適切な対応をおこなうためには、税制改正大綱の内容を把握し、事前に準備を進めることが重要です。税制改正大綱を参照して具体的な変更点を知ることで、法改正後にスムーズに対応できます。
本記事では、令和5年度税制改正大綱について、電子帳簿保存法に与える影響や具体的な変更点、法改正に対応するためのポイントを解説します。
【前提】税制改正大綱とは、税制のあり方や具体的な改正事項をまとめた方針
税制改正がおこなわれる際には、税制調査委員会が中心となり、各省庁から提出された要望がまとめられます。このプロセスは、税制における仕組みの見直しや租税特別措置の検討に必要です。
そして、毎年度の具体的な税制改正事項を審議し、その内容を取りまとめたものが「税制改正大綱」として公表されています。税制改正大綱は毎年12月中旬頃に公表され、審議される項目は以下のとおりです。
- 個人所得課税
- 資産課税
- 法人課税
- 消費課税
- 国際課税
- 納税環境整備
- 関税
上記に関して取りまとめた税制改正大綱をもとに財務省が国税の改正法案を、総務省が地方税の改正法案を作成し、国会に提出されます。
令和5年度税制改正大綱による電子帳簿保存法の7つの変更点
2023(令和5)年の税制改正大綱では、電子帳簿保存法における7つの変更点が盛り込まれました。
税制改正大綱には保存要件の緩和から猶予措置の整備まで、さまざまな変更が取りまとめられています。法律を遵守して国税関連書類を適切に保存するためには、変更点を把握することが重要です。
ここでは、令和5年度税制改正大綱による電子帳簿保存法の7つの変更点を解説します。
- 電子帳簿等保存における「優良な電子帳簿」の範囲が変更
- 解像度・階調・大きさに関する情報の保存を廃止
- 入力者等情報の確認要件を廃止
- 帳簿との相互関連性の確保が必要な書類を重要書類に限定
- 検索機能のすべてを不要とする対象者の要件を変更
- 宥恕(ゆうじょ)措置の廃止と猶予措置の整備
- 電磁的記録の保存をおこなう者等に関する情報の確認要件を廃止
①電子帳簿等保存における「優良な電子帳簿」の範囲が変更
電子帳簿保存法の電子帳簿等保存では、「優良な電子帳簿」の要件を満たしていると、過少申告が判明した際に過少申告加算税の5%軽減を受けられます。
2023(令和5)年の税制改正大綱によって、軽減措置の対象となる帳簿の範囲が以下のように変更されました。
- 仕訳帳
- 総勘定元帳
- その他必要な帳簿
なお、その他必要な帳簿の項目は以下のとおりです。
- 売上帳
- 仕入帳、経費帳、賃金台帳(所得税のみ)
- 売掛帳
- 買掛帳
- 受取手形記入帳、支払手形記入帳
- 貸付帳、借入帳、未決済項目にかかる帳簿
- 有価証券受払い帳(法人税のみ)
- 固定資産台帳
- 繰延資産台帳
また、「優良な電子帳簿」の範囲変更は、2024年1月1日から適用されています。
②解像度・階調・大きさに関する情報の保存を廃止
スキャナ保存をおこなう際、これまでは解像度・階調・大きさに関する情報を保存しなければなりませんでした。
しかし、2023(令和5)年の税制改正大綱には、これらの要件を廃止する案が盛り込まれています。ただし、国税関連書類をスキャナ保存する場合は、これまでと同様に200dpi以上の解像度や原則としてカラー画像での保存を守らなければなりません。
③入力者等情報の確認要件を廃止
電子帳簿保存法が改正される前は、タイムスタンプを付与する際に記録事項の入力をおこなう者とその者を直接監視する者に関する情報の確認が必要でした。
しかし、2023(令和5)年の税制改正大綱で入力者等情報に対する情報の保存要件廃止が検討され、2024年1月1日以降は情報の保存が不要となっています。
これにより、企業がスキャナ保存をおこなう際の負担が軽減されました。
④帳簿との相互関連性の確保が必要な書類を重要書類に限定
電子帳簿保存法の改正前は、スキャナ保存をおこなう際に取引において受領した注文書や見積書などの書類と帳簿の関連性を確認できる状態にしなければなりませんでした。
しかし、2023(令和5)年の税制改正大綱により要件が見直されたことで、相互関連性の確認が必要な処理は以下のようなものに限定されています。
- 契約書
- 領収書
- 送り状
- 納品書
そのため、2024年1月1日以降は、見積書や注文書など資金や物の流れに直結しない書類は相互関連性の確保が不要となりました。
⑤検索機能のすべてを不要とする対象者の要件を変更
電子帳簿保存法の電子取引では、電子データを必要なときに探し出すために「検索性の確保」が求められています。
しかし、経理担当者にとって、電子データに検索項目を付与する業務は負担となります。そこで、2023(令和5)年の税制改正大綱では、検索機能のすべてを不要とする対象者の要件変更を提案しました。
変更後の対象者は以下のとおりです。
- 基準期間(2課税年度前)の売上高が5,000万円以下の者
- 書面を取引年月日や取引先ごとに整理した状態で提示・提出できること
対象者の要件を満たす事業者が、税務調査で電子データのダウンロードを求められた際に対応できる場合に限り、検索機能の付与が不要となります。
⑥宥恕(ゆうじょ)措置の廃止と猶予措置の整備
2022年1月1日に電子帳簿保存法が改正された際、電子取引の電子保存の義務化にともない、宥恕(ゆうじょ)措置が整備されました。
しかし、2023(令和5)年の税制改正大綱により、この宥恕措置は2023年12月31日をもって廃止となります。
また、宥恕措置の廃止により、2024年1月1日以降は、以下の要件を満たすことで猶予措置の適用が可能です。
- 電子取引データの保存ができないことについて、所轄税務署長が相当の理由であると認めている
- 税務調査で電子取引データのダウンロードを求められた際に、書面を提示・提出できる
猶予措置の期間は定められていませんが、将来的に廃止される可能性があるため、国税庁の対応には注視しておきましょう。
⑦電磁的記録の保存をおこなう者等に関する情報の確認要件を廃止
電子取引において電子データ保存をおこなう場合、真実性と可視性の確保が必要です。真実性と可視性は、電子データにタイムスタンプを付与することで確保できます。
電子帳簿保存法が改正される前は、タイムスタンプ付与において記録事項の入力をおこなう者とその者を直接監視する者に関する情報を記録できる状態で保存しなければなりませんでした。
しかし、2023(令和5)年の税制改正大綱で確認要件の廃止が盛り込まれたため、電子データ保存への対応負荷が低減されています。
電子帳簿保存法の改正に対応するための3つのポイント
電子帳簿保存法の改正により、事業者が対応するハードルは年々下がってきました。
しかし、すべての書類を一度に電子化することは困難なため、優先順位をつけて取り組むのがおすすめです。優先順位をつけていれば、必要なところに焦点を当てて効率良く電子化を進められます。
ここでは、電子帳簿保存法の改正に対応するための3つのポイントを解説します。
- 現状を確認して対応すべき書類に優先順位をつける
- 保存方法と業務フローを事前に決めておく
- 自社にあったシステムを導入する
①現状を確認して対応すべき書類に優先順位をつける
社内で取り扱うすべての書類を電子化することは、決して簡単ではありません。まずは書類の取扱状況を把握して、どの書類から電子化を進めるべきかをリストアップすることが重要です。
電子化する書類の選定で悩んでいる場合は、業務効率化やコスト削減につながるものから進めるのがおすすめです。たとえば、請求書や領収書を紙で発行している事業者であれば、電子取引に変更することからはじめてみましょう。
②保存方法と業務フローを事前に決めておく
電子帳簿保存法の改正に対応する場合、自社の状況によって適切な保存方法や運用方法が異なります。
たとえば、紙の書類を多く扱う事業者であれば、スキャナ保存の要件緩和を活用し、紙の運用から電子化への移行を進めるのがおすすめです。電子化を進める場合は不正防止のために社内規定を整備する必要があり、運用ルールを定めなければなりません。
自社の状況を把握したうえで、業務フローを事前に決定しておきましょう。
③自社にあったシステムを導入する
電子帳簿保存法の改正に効率良く対応するためには、システムの導入がおすすめです。
システムを導入する場合は、必要な機能が備わったものを選ぶ必要があります。必要な機能は事業者によって異なるため、まずはどのような機能が求められるかをリストアップしてください。
たとえば、すでに書類の電子化を進めている事業者であれば、作成・発行を自動化できるシステムがおすすめです。
また、必要な機能とあわせてランニングコストや将来的な拡張性についても検討しておきましょう。
関連記事:電子帳簿保存法対応のシステムとは?導入するメリットや選ぶ際のポイントも解説
まとめ|令和5年度税制改正大綱の内容を理解したうえで電子帳簿保存法に対応しよう
本記事では、令和5年度税制改正大綱について、電子帳簿保存法に与える影響や具体的な変更点、法改正に対応するためのポイントを解説しました。
税制改正大綱には毎年度の具体的な税制改正事項を審議した内容が取りまとめられています。
2023(令和5)年の税制改正大綱では、電子帳簿等保存・スキャナ保存・電子取引の3項目に関する変更点が盛り込まれました。そのなかでも、とくに電子帳簿保存法の要件緩和がおもな変更点となっています。
税制改正大綱には、今後も電子帳簿保存法に関する検討事項が記される可能性があります。そのため、税制改正大綱の内容を理解し、電子帳簿保存法の改正に向けて準備を進めましょう。










