電子帳簿保存法における検索機能の確保とは?要件を満たす方法や不要となるケースを解説
更新日:2025.07.28
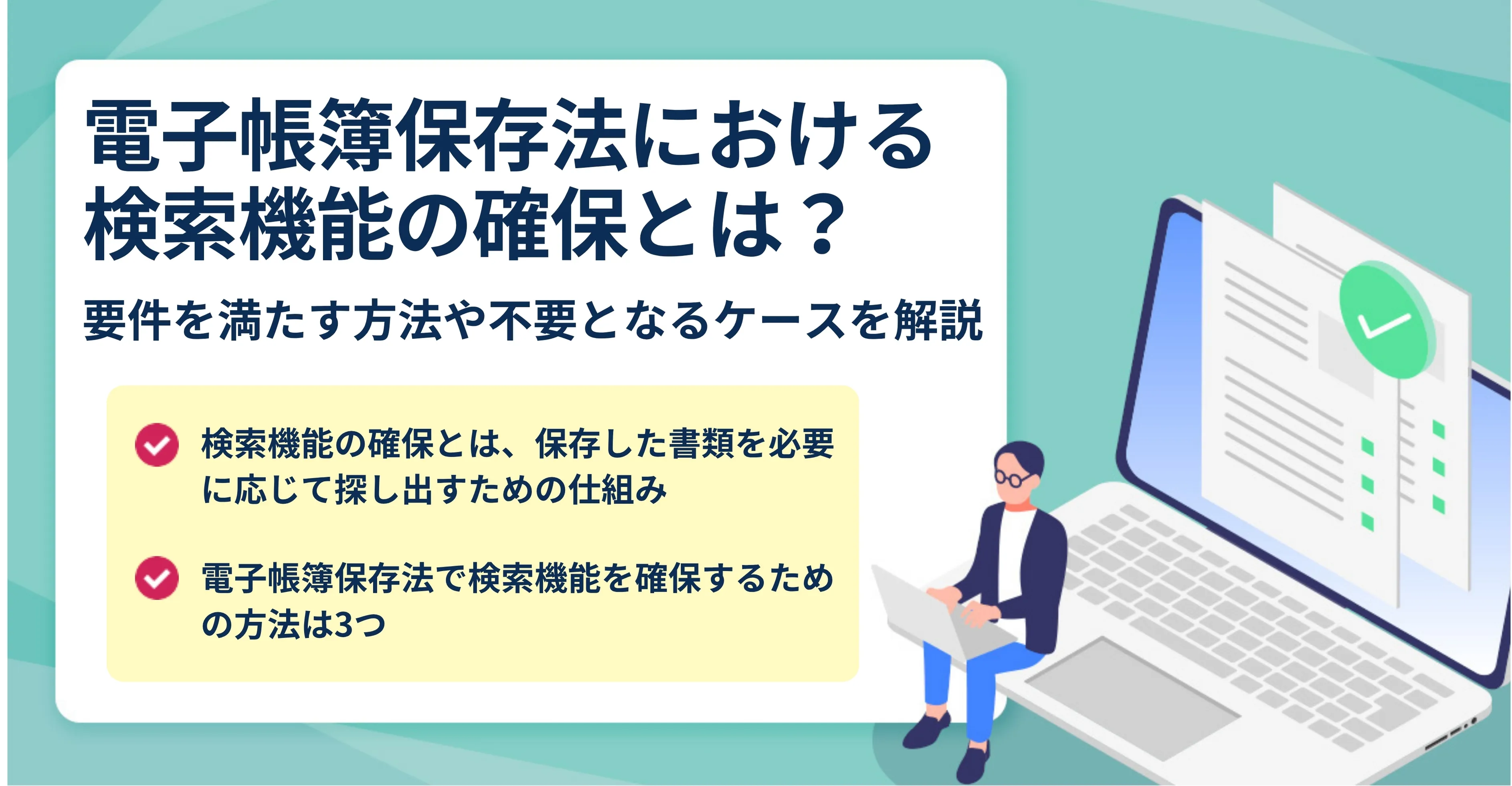
ー 目次 ー
電子帳簿保存法に対応する際は、定められた要件を満たすことが求められます。そのなかでも検索要件は可視性を確保するために設けられており、保存された電子データを速やかに探し出す際に必要です。
電子データを保存する際、検索要件を満たしていない場合は法律違反に該当し、罰則を科せられる可能性があります。そのため、検索機能を確保したうえで、適切に電子データを保存することが重要です。
本記事では、電子帳簿保存法における検索機能の確保について、要件を満たす方法や要件が不要となるケースを解説します。
【基本】検索機能の確保とは、保存した書類を必要に応じて探し出すための仕組み
電子帳簿保存法に対応する際は、真実性や可視性を確保するための要件を満たさなければなりません。
要件のなかでも、検索要件は電子データの可視性を確保するために設けられています。可視性の確保とは、保存された電子データを必要に応じて検索・提示できるようにすることです。
電子帳簿保存法において、検索機能の確保は電子帳簿等保存・スキャナ保存・電子取引の3区分ごとに項目が決められています。そのため、保存区分ごとに検索要件の内容をおさえ、電子データを適切に保存することが重要です。
検索機能の確保が必要な電子帳簿保存法3つの区分と要件は?
電子帳簿保存法に対応する際は、保存された電子データを必要に応じて探し出せる状態にすることが求められます。
たとえば、税務調査で電子データのダウンロードを求められる場合に備えて、速やかに応じるために検索機能の確保が必要です。
また、法律で定められた検索要件を満たしていないと、罰則を科せられる可能性があるため、保存区分ごとに検索要件の内容を正しく理解しておきましょう。
ここでは、検索機能の確保が必要な電子帳簿保存法における3つの区分と要件を解説します。
- 電子帳簿等保存における検索要件
- スキャナ保存における検索要件
- 電子取引における検索要件
①電子帳簿等保存における検索要件
電子帳簿等保存では「優良な電子帳簿」の要件を満たすことで、過少申告加算税の軽減措置を適用できます。そして、「優良な電子帳簿」の要件を満たすためには、検索機能を確保しなければなりません。
電子帳簿等保存における検索要件の項目は以下の3つです。
- 「取引年月日」「取引金額」「取引先」の記録項目で検索できること
- 日付または金額の範囲指定により検索できること
- 2つ以上の任意の項目を組み合わせた条件により検索できること
なお、税務職員による電子データのダウンロードの求めに応じる場合は、2と3の検索要件が不要となります。
②スキャナ保存における検索要件
紙で受領した国税関連書類をスキャナ保存する場合は、以下3つの検索要件をすべて満たす必要があります。
- 「取引年月日」「取引金額」「取引先」の記録項目で検索できること
- 日付または金額の範囲指定により検索できること
- 2つ以上の任意の項目を組み合わせた条件により検索できること
ただし、電子帳簿等保存と同様に、税務調査での求めに応じて電子データのダウンロードに対応できる場合は、2と3の要件が不要となり検索要件が緩和されます。
参考:国税庁「スキャナ保存!」
③電子取引における検索要件
電子取引における電子データ保存の義務化により、電子取引で受領した国税関連書類は電子データのままで保存が必要です。電子データを保存する際には、以下3つの要件を満たさなければなりません。
- 「取引年月日」「取引金額」「取引先」の記録項目で検索できること
- 日付または金額の範囲指定により検索できること
- 2つ以上の任意の項目を組み合わせた条件により検索できること
なお、税務調査の際にダウンロードの求めに応じる場合は、範囲指定・組み合わせ検索の要件が緩和されます。
電子帳簿保存法で検索機能を確保するための3つの方法
電子帳簿保存法で検索機能を確保する際には、3種類の方法を選択できます。選択する方法によって必要なソフトやシステムが異なるため、事業者の状況にあわせた方法で対応することが重要です。
効率的に検索機能を確保するために、各方法の特徴を把握しておきましょう。
ここでは、電子帳簿保存法で検索機能を確保するための3つの方法を解説します。
- 表計算ソフトを活用して索引簿を作成する
- 規則性のあるファイル名をつける
- 電子帳簿保存法に対応した会計システムを導入する
①表計算ソフトを活用して索引簿を作成する
電子データを手動で管理する場合は、視認性の高い索引簿が必要となります。電子データの索引簿を作成する際は、MicrosoftのExcelやGoogleのスプレッドシートなど、表計算ソフトの活用がおすすめです。
索引簿には以下の項目を記載してください。
- 連番
- 取引年月日
- 取引金額
- 取引先
- 備考
ただし、表計算ソフトを活用して索引簿を作成する場合、件数が増えるとファイルのデータ容量が重くなります。必要なときにすぐ参照するために、適宜ファイルをわけることが重要です。
②規則性のあるファイル名をつける
電子帳簿保存法の検索要件を満たすためには、「取引年月日」「取引金額」「取引先」の3項目で検索できる必要があります。業務フローの工夫で検索要件を満たすなら、規則性のあるファイル名をつけることがおすすめです。
たとえば、2025年7月20日に取引先のA株式会社から100,000円の請求書を受領した場合、ファイル名を「20250720_100000_A株式会社」とします。
この際に、取引年月日は和暦と西暦のどちらでも問題はありません。また、取引金額は帳簿に記載した金額とあわせるようにしましょう。
③電子帳簿保存法に対応した会計システムを導入する
電子帳簿保存法への対応を効率化するためには、会計システムの導入がおすすめです。検索要件を含めた保存要件を自動で満たせるため、経理業務の負担低減につながります。
会計システムを選ぶ際には、以下のポイントに注目してください。
- JIIMA認証を得ているか
- 導入・ランニングコストが予算にあうか
- 自社で扱う書類に対応しているか
- 将来的な拡張が可能か
- セキュリティ対策に問題がないか
電子帳簿保存法への対応とあわせて業務効率化を図るなら、会計システムの導入を検討しましょう。
検索機能の確保が不要な2つのケース
電子帳簿保存法では、可視性を確保するために検索要件を満たすことが必要です。
ただし、事業者の負担を考慮して、検索機能の確保が不要となるケースがあります。例外となるケースを把握していれば、電子帳簿保存法に対応する際の負担低減が可能です。
ここでは、検索機能の確保が不要な2つのケースについて解説します。
- 税務調査の際に電子データのダウンロードに応じる場合
- 電子帳簿保存法の猶予措置を適用する場合
①税務調査の際に電子データのダウンロードに応じる場合
2024年1月1日の法改正によって、検索機能のすべてを不要とする措置の対象者が拡大されました。そのため、税務調査の際に電子データのダウンロードの求めに応じれる場合に限り、検索機能の確保が不要となります。
この措置の対象者は以下のとおりです。
- 基準期間(2課税年度前)の売上高が5,000万円以下の者
- 書面を取引年月日や取引金額ごとに整理した状態で提示・提出できること
上記のいずれか一方に該当していれば、検索機能を確保する必要はありません。
②電子帳簿保存法の猶予措置を適用する場合
電子帳簿保存法への対応が間に合わない場合、以下の要件を満たしていれば、電子取引データを単に保存するだけで問題ありません。
- 電子取引データの保存ができないことについて、所轄税務署長が相当の理由であると認めている
- 税務調査で電子取引データのダウンロードを求められた際に、書面を提示・提出できる
なお、相当の理由にはシステムの整備が間に合わないケースや、資金繰りや人手不足で対応できない場合などが該当します。
電子帳簿保存法における検索機能の確保に関するよくある質問
最後に、電子帳簿保存法における検索機能の確保に関するよくある質問を紹介します。
①検索要件の取引金額は税込と税抜のどちらにするべき?
国税庁のホームページでは、帳簿の処理方法が税込経理と税抜経理のどちらであるかにあわせるべきとしています。
また、受領した書類に記載された取引金額を検索要件の記録項目としても問題ありません。
②検索要件を満たすための索引簿のサンプルはある?
索引簿のサンプルは、国税庁のホームページでダウンロードできます。表計算ソフトを活用して索引簿を作成する際は、以下のサンプルも参考にしてください。
|
連番 |
日付 |
金額 |
取引先 |
備考 |
|
① |
20250618 |
100000 |
A株式会社 |
請求書 |
|
② |
20250710 |
250000 |
B株式会社 |
領収書 |
|
③ |
20250729 |
220000 |
C株式会社 |
注文書 |
③電子帳簿保存法の検索要件は何が緩和された?
2024年1月1日の法改正により、電子取引における検索機能のすべてを不要とする措置の対象者が見直されました。
法改正前は基準期間(2課税年度前)の売上高が1,000万円以下の保存義務者が対象でしたが、法改正後は5,000万円以下に範囲が拡大されています。
まとめ|自社の状況に応じて、検索機能を確保するための方法を検討しよう
本記事では、電子帳簿保存法における検索機能の確保について、要件を満たす方法や要件が不要となるケースを解説しました。
電子帳簿保存法に対応する際は、検索機能の確保が必要です。検索機能を確保することで必要なときに保存したデータを参照でき、データ管理の効率性を高められます。
検索機能を確保する方法としては、表計算ソフトを活用した索引簿の作成や規則性のあるファイル名の設定、会計システムの導入などが考えられます。
事業者の状況や取り扱う書類によって適切な方法が異なるため、対応方法をしっかり検討しましょう。










