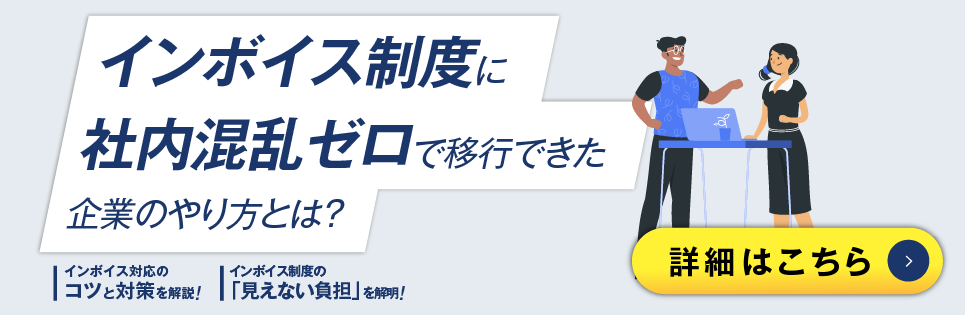フリーランス・個人事業主がインボイス制度に登録しないとどうなるの?デメリットや登録する場合の手順も解説
更新日:2026.01.29
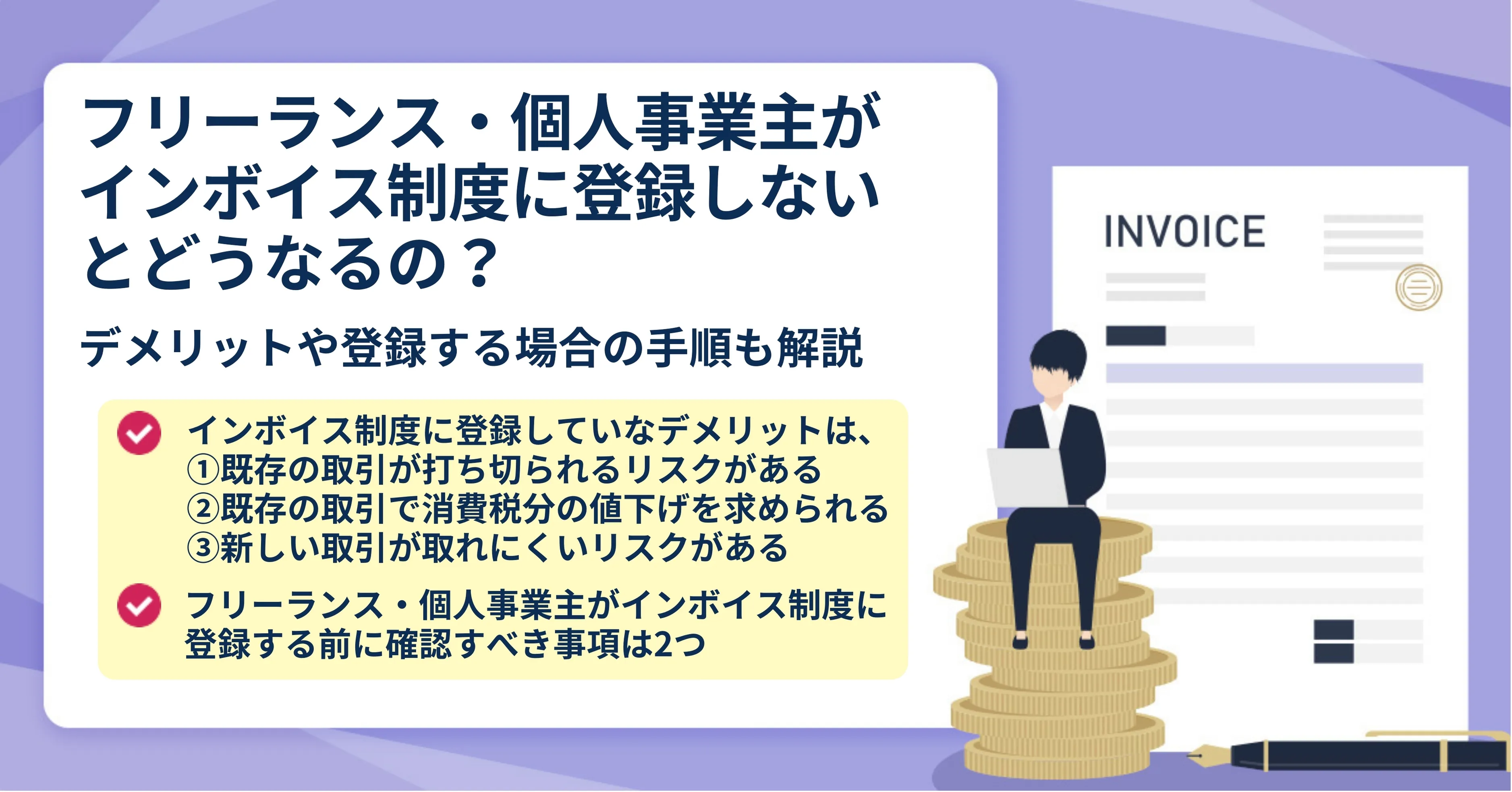
ー 目次 ー
2023年10月に施行されたインボイス制度は、消費税にまつわる書類の作成や税金の計算などを定めた新しいルールです。すべての事業者を対象としているため、フリーランスや個人事業主も例外ではありません。
そんなインボイス制度は、事業規模や内容、取引先の状況などによって既存の取引にも大きな影響を与えるおそれがあります。たとえば、既存の取引を失ったり、新規取引ができなかったりと、事業運営に支障を来たすケースも想定されるでしょう。
このような事態に陥らないためにも、インボイス制度の基本やフリーランス・個人事業主への影響を理解しておき、適切なアクションを起こすことが大切です。
本記事では、フリーランス・個人事業主がインボイス制度に登録しないとどうなるのかについて、デメリットや登録する場合の手順もあわせて解説します。
【そもそも】インボイス制度とは、消費税に関する対応を定めたルール
インボイス制度とは、消費税に関する書類の記載や消費税の計算などの対応方法を定めたルールです。この制度は軽減税率の導入による複数税率に対応し、事業者の適正な申告・納付を促すために定められました。
インボイス制度では、新しい記載方式に対応した「インボイス(適格請求書)」の発行・保存が必須です。ただ、インボイスを発行するためには「適格請求書発行事業者」の登録をしなければなりません。
このような要件を満たせば、売上にかかる消費税から仕入れに支払った消費税を差し引ける「仕入税額控除」が利用できます。事業者によってはインボイス制度施行以前と比べて、税負担が軽減できる可能性があります。
フリーランス・個人事業主がインボイス制度に登録しないとどうなるの?3つの影響やデメリット
インボイス制度はすべての事業者を対象にした制度であり、フリーランス・個人事業主にも大きな影響を与えます。制度への登録有無によって、フリーランス・個人事業主が受ける影響が異なります。
そのため、もしインボイス制度に未登録である場合には、どのような影響があるのかを知っておく必要があるでしょう。
ここでは、フリーランス・個人事業主に与えるインボイス制度の影響について、解説します。
①既存の取引が打ち切られるリスクがある
インボイス制度では、取引当事者のどちらも適格請求書発行事業者に登録していないと仕入税額控除が受けられません。
たとえば、自身が未登録の場合に、取引先は仕入税額控除を受けられません。取引先としては税負担を軽減するため、インボイス制度に登録した事業者との取引を優先するようになります。
このようなことから、仕入税額控除が受けられない事業者との取引が打ち切られるリスクがあるといえるでしょう。
②既存の取引で消費税分の値下げを求められる
インボイス制度では、売上にかかる消費税から仕入れに支払った消費税が差し引ける仕入税額控除が適用できます。この控除を活用すれば、税負担を和らげることが可能です。
一方で、要件を満たしていない事業者の場合、取引先は仕入税額控除が受けられません。そのため、消費税による負担が重くなるおそれがあります。
取引先としては負担を抑えたいと考えるため、インボイス制度の未登録事業者との取引に対して消費税分の値下げを求めるかもしれません。
③新しい取引が取れにくいリスクがある
インボイス制度に登録しないと、取引先は仕入税額控除が受けられません。取引先は相手を選べる立場であることから、仕入税額控除が受けられる相手と取引がしたいと考える可能性があるでしょう。
このように考えた場合に既存の取引だけでなく、新規の取引にも影響を与えるおそれがあります。具体的には、取引先はインボイス制度に登録している事業者を優先して契約を締結するようになり、未登録事業者は新規の取引が取りにくくなります。
フリーランス・個人事業主がインボイス制度に登録する前に確認すべき2つの事項とは?
インボイス制度は強制的なルールではないため、フリーランス・個人事業主が登録をしなければならないわけではありません。
しかし、事業の売上や取引先の状況によって、登録したほうが良いケースもあるため、必ず自身や取引先の状況を整理したうえで慎重に判断すべきでしょう。
ここでは、フリーランス・個人事業主がインボイス制度に登録する前に確認すべき事項について、解説します。
①課税売上がどのくらいあるか?
インボイス制度の適格請求書発行業者に登録すると、課税事業者と同じように消費税の申告・納付が必要です。そのため、これまで免税事業者であった場合には、インボイス制度の登録によって税務面と事務面での負担が増えます。
このような点を踏まえて、まず課税売上が課税事業者の要件を満たしているかどうかの確認をすることが大切です。具体的には、基準となる期間において、課税売上が1,000万円を超えているかを確認すべきでしょう。
もし、課税売上が1,000万円を超えていた場合には課税事業者となるため、インボイス制度の登録によって税負担が増加するリスクは少ないといえるでしょう。
②取引先にインボイス制度の登録事業者はいるか?
インボイス制度で仕入税額控除を受けるためには、取引当事者の双方が適格請求書発行事業者に登録しておく必要があります。
そのため、もし取引先でインボイス制度に登録している事業者が少ない場合には、インボイス制度を登録しなくともその影響は大きくありません。一方で、登録している事業者が多い場合には、自身への影響は大きくなるおそれがあります。
インボイス制度の登録は5つのステップで簡単にできる!
インボイス制度の登録申請は、簡単な対応で完了します。
申請方法は、電子申請(e-Tax)あるいは書面(郵送や窓口)から選択可能です。そのうち、電子申請(e-Tax)は自身のスマートフォンから手続きをおこなえるため、いつでもどこでもインボイス制度の登録申請が可能です。また、申請から登録完了までの期間が1か月ほどであり、これは書面の場合と比べて短いという利点があります。
このようなことから、もしこれからインボイス制度の登録申請をおこなう場合には、電子申請(e-Tax)での対応がおすすめです。本記事では電子申請(e-Tax)での登録申請方法について以下に簡単にまとめています。
- e-Taxソフトからログインする
- 利用者識別番号を取得する
- 必要事項を入力する
- 電子署名をする
- 通知を確認する
関連記事:インボイス制度の登録方法とは?申請のやり方や注意点を解説
インボイス制度に対応した請求書作成サービス・システムの活用がおすすめ!
近年では、インボイス制度に対応している請求書作成サービス・システムが数多く提供されています。このサービス・システムは法人向けのものだけでなく、フリーランスや個人事業主も活用できる内容であることから、積極的に利用することをおすすめします。
ただし、提供するサービス・システムによって、利用できる機能や受けられるサポートが異なるため、事業規模や内容、取引先の状況に応じたものを見つけることが大切です。サービスごとの特徴を理解したうえで、適したサービス・システムを利用しましょう。
以下の2つは、おすすめのサービス・システムとなります。
- OneVoice明細
- @トバス
それぞれの詳細については別記事でまとめているため、本記事とあわせて参考にしてください
関連記事:インボイス制度で導入すべきシステム4選!導入するべき理由も紹介
まとめ|インボイス制度に登録して、スムーズな事業運営を!
本記事では、フリーランス・個人事業主がインボイス制度に登録しないとどうなるのかについて、デメリットや登録する場合の手順もあわせて解説しました。
インボイス制度はフリーランスや個人事業主に大きな影響を与えるルールとなっています。基本的なルールを理解することはもちろんのこと、適切な対応がおこなえるように環境を整えておくことが大切です。
インボイス制度の登録を検討する場合には、必ず自身の事業規模や内容、取引先の状況を確認し、登録前と登録後の違いや影響を整理しておきましょう。