インボイス申請の代行費用はいくら?相場・依頼先の選び方を解説
更新日:2026.01.13
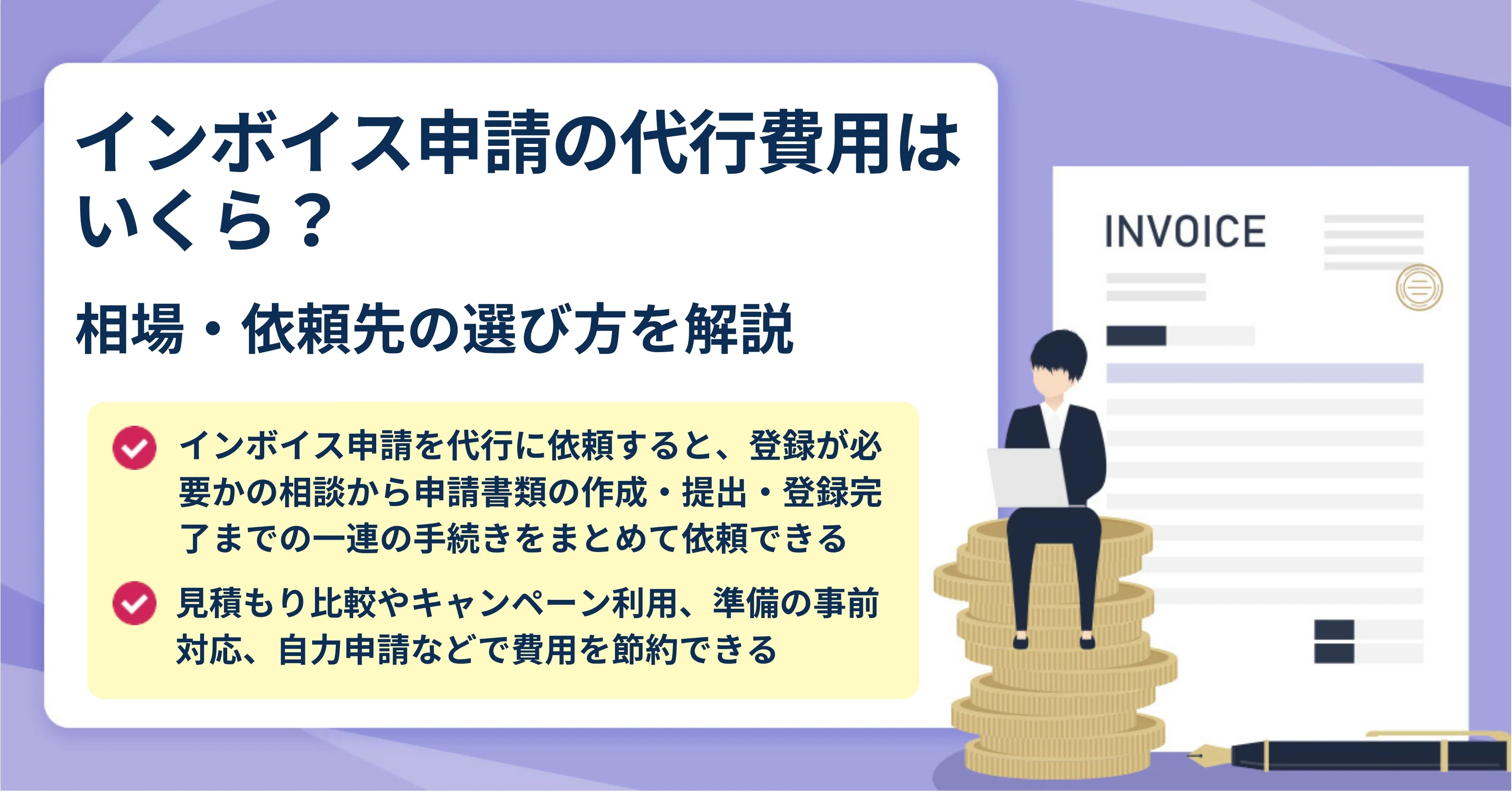
ー 目次 ー
「インボイス申請の手続き、時間もかかりそうだし不安...」「専門家に頼むといくらぐらいかかるんだろう?」そんなお悩みをお持ちの方へ。本記事では、インボイス申請代行の費用相場を依頼先別に比較しながら、サービス内容や依頼先の選び方、費用を抑える工夫までわかりやすく解説いたします。
インボイス申請の代行のサービス内容とは?
2023年10月1日から始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)に対応するためには、「適格請求書発行事業者」としての登録申請が必要です。本業で忙しい個人事業主やフリーランス、または手続きに不安を感じる方にとって、代行サービスは心強い味方となります。では、具体的にどのようなサービスを受けられるのか簡単にご紹介します。
代行サービスで対応してもらえる主な手続き
インボイス申請の代行を専門家に依頼すると、制度や手続きに不慣れな方でもスムーズに登録まで進めることができます。依頼先によって多少の違いはありますが、一般的には以下のような流れで対応してもらえるケースが多いです。
まず最初に行われるのが「事前相談」です。ここでは、インボイス登録が本当に必要かどうかの判断や、制度の基本的な説明、手続きの流れなどについて案内してもらえます。
次に「必要情報のヒアリング」が行われます。申請書作成に必要な、事業者名・住所・法人番号やマイナンバー・事業内容などの情報をヒアリングして整理します。
その後、ヒアリング内容をもとに、専門家が「登録申請書の作成」を行います。具体的には、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を正確に作成してくれるため、自分で書類を用意する手間が省けます。
書類が整ったら、税務署への「代理申請」に進みます。これはe-Tax(電子申請)や郵送などを通じて、申請書を代理で提出してもらえる工程です。
最後に、「登録完了までのフォロー」も行われます。申請後の税務署とのやり取りや、登録通知書の受領、登録番号の通知までしっかりサポートしてくれるのが一般的です。
このように、相談から登録完了の通知まで、ワンストップで任せられるのがインボイス申請代行サービスの大きな特徴です。
インボイス申請の代行を専門家に依頼するメリット
費用を払ってまでインボイス申請の代行を専門家に依頼するのには、明確なメリットがあります。主なメリットは以下の通りです。
メリット1:本業に集中できる時間の確保
最大のメリットは、手続きにかかる時間と手間を大幅に削減できる点です。制度を理解し、申請書の書き方を調べ、e-Taxの操作に慣れるといった作業には、思いのほか時間がかかります。専門家に任せることで、その時間を本来の事業活動に集中させることができます。
メリット2:正確でスピーディーな申請
専門家は申請手続きに精通しているため、記載ミスや添付書類の漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。申請書に不備があると、差し戻しや再提出で余計な時間がかかってしまいます。確実な手続きにより、スムーズな登録が期待できます。
メリット3:精神的な負担の軽減
「申請内容が合っているか不安」「もし間違えたらどうしよう」といった、慣れない手続きに対する精神的なストレスから解放されます。特に、初めてこうした公的な手続きを行う方にとっては、安心して任せられる専門家の存在は大きな支えとなるでしょう。
インボイス登録申請を丸ごと代行してもらうことは可能?
結論から言えば、インボイス登録申請は丸ごと代行してもらうことが可能です。税理士や行政書士、代行専門業者などが、必要書類の準備から電子申請の代行まで、一括して対応してくれるサービスを提供しています。
特に、インボイス制度に不慣れな個人事業主や小規模法人にとっては、申請ミスや申請漏れを防げるため、大きなメリットがあります。また、業者によっては、登録後の帳簿保存・請求書フォーマットの見直し・経理対応のアドバイスまでトータルサポートを提供していることもあります。
ただし、申請自体は「納税者本人の責任」であるため、委任状の提出や本人確認など一定の手続きが必要です。依頼する際は、信頼できる代行業者を選定し、サービス内容や料金体系を事前に確認しておくことが重要です。
インボイス申請は誰に代行を依頼できる?依頼先ごとの特徴とは
インボイス制度の登録申請は、。依頼先にはそれぞれ特徴があり費用やサービス内容も異なります。自分に合った依頼先を選ぶために、まずはそれぞれの違いを理解しましょう。
税理士 登録後の税務相談も可能
税理士は税務に関する専門家です。インボイス申請の代行はもちろん、制度開始後の消費税申告や日々の記帳、節税対策まで一貫して相談できるのが最大の強みです。すでに顧問税理士がいる場合や、インボイス登録を機に今後の税務全般の不安を解消したい事業者にとって、最も頼りになる存在と言えるでしょう。
特に、これまで免税事業者だった方が課税事業者になる場合、消費税の納税義務が発生します。登録を機に税理士との顧問契約を検討することで、安心して事業に集中できます。ただし、申請代行のみの依頼は受け付けていない事務所もあるため、事前に確認が必要です。
行政書士 書類作成のプロフェッショナル
行政書士は、官公署へ提出する書類作成の専門家です。「適格請求書発行事業者の登録申請書」の作成とe-Taxによる代理申請を、正確かつ迅速に行ってくれます。税理士とは異なり、業務範囲は基本的に申請手続きそのものに限られ、登録後の税務相談や申告代行は行えません。
「顧問税理士はいないが、書類の不備なく確実に登録を済ませたい」「とにかく申請手続きだけを専門家に任せたい」という方に向いています。費用も、税務相談まで含む税理士に依頼するよりは比較的安価な傾向にあります。
商工会議所 会員向けのサポート
地域の事業者を支援する商工会議所や商工会でも、インボイス制度に関する相談窓口を設けている場合があります。会員であれば、無料または非常に安価な料金で、派遣された税理士などによる相談会や申請サポートを受けられることがあります。
ただし、専門家が手続きを全て代行するのではなく、あくまで「相談」や「申請書の書き方指導」がメインとなるケースが多い点に注意が必要です。まずはご自身が所属する地域の商工会議所に、どのようなサポートが受けられるかを問い合わせてみましょう。
オンライン代行サービス 手軽さと安さが魅力
近年、ウェブサイト上で手続きが完結するオンラインのインボイス申請代行サービスも増えています。税理士法人や行政書士法人、IT企業などが運営しており、最大の魅力は費用の安さと手軽さです。数千円程度から依頼でき、スマートフォンやパソコンから24時間いつでも申し込めます。
対面での詳細なヒアリングはないため、申請内容がシンプルで、特に複雑な相談事項がない方におすすめです。サービスを選ぶ際は、運営元が信頼できるか(税理士・行政書士が監修しているかなど)、セキュリティ対策は万全かなどをしっかり確認することが重要です。
【相場まとめ】インボイス申請の代行費用を解説
インボイス制度の登録申請を代行してもらう際の費用は、誰に依頼するかによって大きく異なります。ここでは、依頼先ごとの費用相場を具体的に解説します。
税理士に依頼する場合の費用相場
インボイス申請を税理士に依頼する最大のメリットは、登録申請だけでなく、その後の税務処理や節税対策まで一括で相談できる点にあります。 費用は「顧問契約を結んでいるかどうか」によって大きく異なります。
顧問契約がある場合
すでに税理士と顧問契約を結んでいる方は、その契約の範囲内で無料〜3万円程度で対応してもらえるケースが多く見られます。
日頃から事業内容を把握している税理士であれば、申請の手間も少なく、スムーズに進めてもらえるのが特徴です。
スポット(単発)で依頼する場合
顧問契約がない場合は、3万円〜10万円程度の費用がかかるのが一般的です。
特に法人の場合は個人事業主よりも費用が高くなる傾向があり、申請後の税務相談などは別途料金が発生することもあります。
このように、同じ「税理士への依頼」でも、契約状況によって費用感に大きな差が出るため、顧問契約の有無と、今後の相談ニーズをふまえて検討することがポイントです。
行政書士に依頼する場合の費用相場
行政書士は、官公庁に提出する書類作成を専門とする国家資格者で、インボイス登録申請のような事務的な書類の作成・提出を正確に代行してくれる点が特徴です。 基本的には、スポットでの単発依頼となることが一般的です。
依頼の対象は個人事業主・法人のいずれも可能で、費用相場はおおよそ2万円〜5万円程度です。
主な対応内容は、申請書類の作成と提出手続きの代行に限られており、税理士とは異なり、申請後の税務相談や確定申告の代行は含まれません。
そのため、「手続きだけお願いしたい」「費用をなるべく抑えたい」という方にとっては、行政書士への依頼が適している場合もあります。
商工会議所に依頼する場合の費用相場
地域の商工会議所や商工会でも、インボイス制度に関する相談や申請サポートを受けられる支援サービスが提供されています。ただし、税理士や行政書士のように代行業務を専門で行うわけではなく、あくまで会員向けのサポート窓口的な位置づけである点が特徴です。
商工会議所のサービスには主に以下の2つがあります。
相談・アドバイス
インボイス制度に関する不安や申請方法の疑問点などを無料で相談できます。
とくに会員であれば、制度の基本的な説明や今後の流れについて、親身にアドバイスを受けられるケースが多く安心です。
申請サポート
実際の申請についても、書き方の指導やe-Taxの操作サポートといったかたちで支援を受けることができます。
費用は無料〜1万円程度で、提供内容や料金は商工会議所によって異なります。
このように、商工会議所は「まずは相談してみたい方や、できるだけ費用を抑えたい方」にとって、手軽な選択肢のひとつです。
オンラインの代行サービスを利用する場合の費用相場
近年では、Webサイト上で手続きを完結できるオンライン型のインボイス申請代行サービスも増えてきました。 「とにかく費用を抑えたい」「簡単な手続きだけ代わりにやってほしい」といった方に向いている選択肢です。
個人事業主・法人を問わず利用可能で、費用相場は5,000円〜2万円程度と、他の依頼先と比べて非常にリーズナブルです。
手軽さと価格の安さが最大の魅力ですが、その分サービス内容やサポート範囲は限定的な場合があります。
特に、税務に関する個別相談には対応していないことが多いため、利用前にサービス内容をよく確認することが重要です。 「申請書の提出代行だけしてほしい」「e-Taxを使うのが不安だから補助してほしい」といった、ピンポイントなニーズには非常に適しています。
失敗しない!インボイス申請代行サービスの選び方 3つのポイント
インボイス申請の代行を依頼する際には、費用だけでなくサービス内容や実績もしっかりと比較検討することが重要です。ここでは、自分に合った代行サービスを選ぶための3つのポイントを解説します。
ポイント1 サービス内容と料金体系が明確か
代行サービスを選ぶうえで最も重要なのが、サービス内容と料金体系の明確さです。どこまでの業務を、いくらで代行してくれるのかを契約前に必ず確認しましょう。「基本料金」に含まれるサービス範囲は依頼先によって大きく異なります。
例えば、「書類作成と提出のみ」のシンプルなプランもあれば、「登録後の税務相談」までセットになっているプランもあります。後から「これは追加料金だった」と後悔しないために、以下の点をチェックリストとして活用してください。
|
チェック項目 |
確認すべき内容の例 |
|
基本料金に含まれるサービス範囲 |
申請書類の作成、e-Taxでの代理申請、申請状況の確認、登録番号の通知まで含まれるか。 |
|
追加料金が発生するケース |
書類の修正対応、申請に関する相談、登録後のアフターフォローなどは別途費用がかかるか。 |
|
オプションサービスの内容と料金 |
顧問契約への移行プラン、記帳代行、確定申告サポートなどの有無と、その料金。 |
|
支払い方法とタイミング |
クレジットカード払いや銀行振込に対応しているか。支払いは前払いか後払いか。 |
公式サイトやパンフレットに料金が明記されていない場合は、必ず事前に見積もりを依頼し、内訳を詳細に確認することが大切です。
ポイント2 実績や専門性は十分か
インボイス制度は、事業者の取引や経理に大きな影響を与える重要な制度です。そのため、代行を依頼する専門家やサービスが、インボイス制度に関する十分な知識と実績を持っているかを確認する必要があります。
特に、個人事業主やフリーランス、小規模法人など、自身の事業形態に合わせた申請実績が豊富かどうかは重要な判断基準となります。公式サイトの「導入事例」や「お客様の声」を参考にしたり、無料相談の場で具体的な実績について質問したりしてみましょう。
また、依頼先ごとの専門性を理解することも大切です。
- 税理士:インボイス登録後の税務処理や節税対策まで見据えたアドバイスが期待できます。
- 行政書士:許認可申請などの書類作成のプロであり、正確でスピーディーな申請手続きを得意とします。
- オンライン代行サービス:テクノロジーを活用し、効率的な申請プロセスを構築している場合があります。
自分の目的(「とにかく早く登録したい」「今後の税務相談もしたい」など)に合わせて、最適な専門性を持つ依頼先を選びましょう。
ポイント3 コミュニケーションがスムーズか
申請手続きを代行してもらうとはいえ、担当者とのやり取りは必ず発生します。疑問点を質問した際の回答の速さや丁寧さ、説明の分かりやすさなど、コミュニケーションが円滑に進むかどうかも見極めるべきポイントです。
相性の悪い担当者に当たってしまうと、簡単な質問もしづらくなり、不安を抱えたまま手続きを進めることになりかねません。多くの事務所やサービスでは無料相談を実施しているため、契約前に一度話してみて、担当者の人柄や対応の質を確認することをおすすめします。
また、連絡手段が自分に合っているかも確認しておきましょう。電話やメールだけでなく、ChatworkやSlackなどのビジネスチャットツールに対応していると、より手軽に進捗確認や相談ができて便利です。契約前に、コミュニケーションに関する以下の点を確認しておくと安心です。
- 問い合わせへの返信は迅速か
- 専門用語を多用せず、分かりやすく説明してくれるか
- 希望する連絡手段(電話、メール、チャットなど)に対応しているか
- 高圧的な態度や、話を急かすような様子はないか
信頼できるパートナーとして、安心して任せられる相手かどうかをしっかり見極めましょう。
インボイス申請の代行費用を安く抑える方法!
インボイス制度への対応は必須ですが、専門家への代行依頼には費用がかかります。少しでもコストを抑えたいと考えるのは当然のことです。ここでは、インボイス申請の代行費用を賢く節約するための4つの具体的な方法を解説します。
複数の事務所やサービスから見積もりを取る
インボイス申請の代行費用は、依頼先によって料金体系やサービス範囲が異なります。そのため、必ず複数の事務所やサービスから見積もり(相見積もり)を取り、比較検討することが重要です。最低でも2〜3社から見積もりを取得し、料金だけでなく、どこまでの業務を代行してくれるのか、追加料金は発生しないかといった点を詳細に確認しましょう。相見積もりを取ることで、ご自身の状況に合った適正価格の依頼先を見つけることができ、不要な出費を防げます。
キャンペーンや無料相談を活用する
多くの税理士事務所やオンライン代行サービスでは、新規顧客向けに期間限定の割引キャンペーンや、顧問契約とのセット割引などを実施していることがあります。これらのキャンペーンを積極的に活用することで、通常よりも安く依頼できる可能性があります。また、多くの専門家が提供している「無料相談」も有効な手段です。費用に関する質問はもちろん、手続きの流れや専門家との相性を確認する絶好の機会となります。相談したからといって契約を強制されることはありませんので、気軽に利用してみましょう。
自分でできる範囲の準備は済ませておく
専門家に依頼する前に、自分でできる準備を済ませておくと、専門家の作業工数が減り、結果的に費用が安くなる場合があります。特に、申請に必要な情報の整理や書類の準備は、ご自身で行うことが可能です。依頼する前に、以下のものを手元に揃えておくと、手続きがスムーズに進みます。
|
準備しておくもの |
備考 |
|
事業者情報(氏名・名称、住所、法人番号など) |
申請書作成に必須の情報です。正確な情報をまとめておきましょう。 |
|
本人確認書類の写し |
個人事業主の場合、マイナンバーカードや運転免許証などが必要です。 |
|
課税事業者選択届出書の提出状況 |
すでに提出済みか、これから提出するのかを伝えておきましょう。 |
これらの準備を事前に行うことで、専門家とのやり取りが円滑になり、時間と費用の両方を節約できる可能性があります。
意外と簡単?自分でインボイス申請をする方法!
最も費用を抑える方法は、代行を依頼せず、自分でインボイス(適格請求書発行事業者)の登録申請を行うことです。申請手続きは、国税庁のウェブサイトに詳しいマニュアルや記載例が用意されており、手順に沿って進めれば個人事業主の方でも完了できます。
主な申請方法は以下の2つです。
- e-Tax(電子申請):パソコンやスマートフォンから24時間いつでも申請可能です。手続きがスピーディーで、登録通知も早く受け取れるメリットがあります。
- 郵送申請:申請書を国税庁のサイトからダウンロード・印刷し、必要事項を記入して管轄のインボイス登録センターへ郵送する方法です。PC操作が苦手な方でも対応できます。
少しでもコストを削減したい方は、自分で申請に挑戦してみるのも一つの有効な選択肢です。
Q&A|インボイス申請の代行・費用に関するよくある質問
インボイス申請の代行費用は経費として計上できますか?
はい、インボイス申請の代行を専門家に依頼した際にかかる費用は、事業に必要な経費として計上できます。勘定科目は、一般的に「支払手数料」や「雑費」として処理します。これは法人、個人事業主を問わず同様です。
ただし、会計処理の具体的な方法については、顧問税理士がいる場合はそちらに確認するか、ご自身の経理方式に合わせて適切に処理してください。
個人事業主でもインボイス申請の代行を頼めますか?
はい、もちろん個人事業主(フリーランス)の方でもインボイス申請の代行を依頼できます。多くの税理士事務所、行政書士事務所、オンライン代行サービスが個人事業主からの依頼を積極的に受け付けています。
特に、本業が忙しく手続きに時間を割けない方や、書類作成に不安がある方にとって、専門家への代行依頼は大きなメリットがあります。顧問税理士がいない場合でも、単発で依頼できるサービスが多数存在するため、気軽に相談してみるとよいでしょう。
インボイス申請の代行は登録完了までどのくらいの期間がかかりますか?
インボイス申請の代行を依頼してから登録が完了するまでの期間は、「代行業者による申請準備期間」と「税務署での審査期間」の合計で決まります。全体の期間は、税務署の混雑状況によって大きく変動するため、あくまで目安としてお考えください。
依頼先への相談から申請書類の提出までは、必要書類がスムーズに揃えば数日~1週間程度が一般的です。その後の税務署での審査期間の目安は以下の通りです。
|
申請方法 |
審査期間の目安 |
|
e-Tax(電子申請) |
約1.5ヶ月~2ヶ月 |
|
書面申請 |
約2ヶ月~3ヶ月 |
上記はあくまで目安であり、申請が集中する時期にはさらに時間がかかる可能性があります。インボイス登録が必要な時期から逆算し、余裕をもって手続きを進めることが重要です。
インボイス代行は何をどこまでやってくれるの?
インボイス制度対応の代行サービスは、単なる「申請サポート」にとどまらず、事前準備からアフターフォローまで幅広く対応してくれるのが特徴です。たとえば、以下のような業務が代行範囲に含まれます。
- 適格請求書発行事業者の登録申請(紙・電子申請)
- 必要書類のチェック・作成代行
- 電子帳簿保存法への対応アドバイス
- 登録完了後の通知管理や番号確認
- 請求書フォーマットの整備・テンプレート提供
- 記帳代行・経理ツールへの対応支援(※オプションの場合あり)
また、フリーランスや個人事業主向けに特化した低価格プランを用意している事業者も多く、税理士・会計士と提携しているケースでは、確定申告や消費税申告までトータルで依頼可能です。
「どこまでやってくれるか」は業者によって異なるため、サービス内容・料金体系・対応範囲を事前に比較検討することが大切です。
まとめ
インボイス申請の代行は、依頼先によって費用や対応内容に大きな違いがあります。安さだけで選ぶのではなく、ご自身の状況に合ったサービス内容や実績、コミュニケーションのしやすさも含めて慎重に検討することが大切です。複数社からの見積もりや無料相談なども活用しながら、信頼できる専門家と出会い、スムーズにインボイス登録を進めていきましょう。










