非課税取引を扱う事業者はインボイス制度に登録すべき?影響や知っておくべきポイントを解説
更新日:2026.01.29
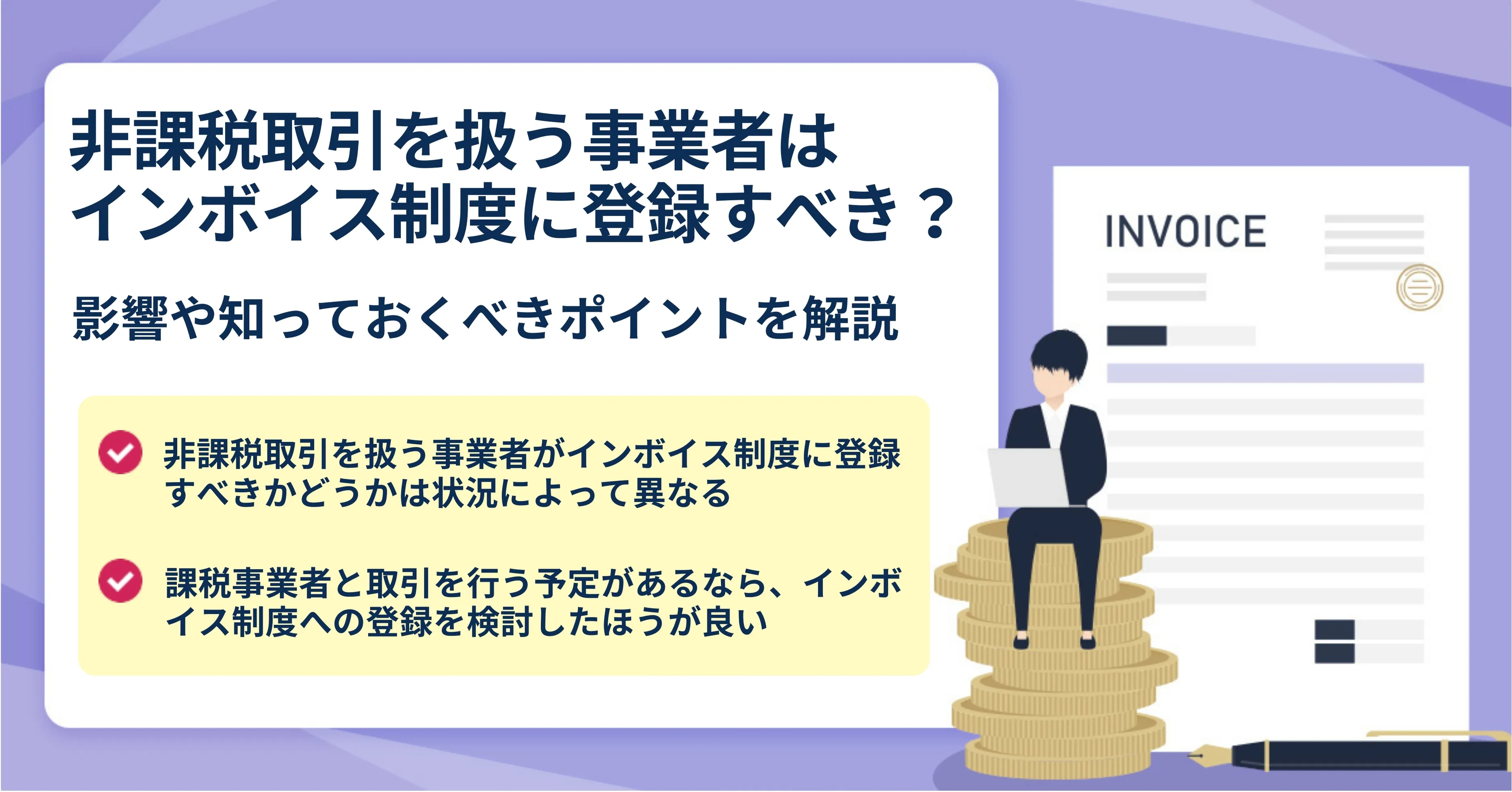
ー 目次 ー
インボイス制度は、2023年10月1日にはじまった消費税に関する制度です。課税事業者が仕入税額控除を適用するためには、インボイス(適格請求書)の発行・保存の対応が必要です。
そんなインボイス制度は、すべての事業者を対象としています。そのため、非課税取引を扱う事業者も例外ではなく、自社や取引先の状況によってはインボイス制度の対応が必要であるため、制度の概要を理解することが重要です。
事前に概要を理解していれば、インボイス制度への登録が必要となった場合にスムーズに対応できるでしょう。
本記事では、非課税取引を扱う事業者へのインボイス制度の影響や登録について、必要性や登録する前に知っておくべきポイントを交えて解説します。
インボイス制度とは、取引に適用される消費税にまつわるルール
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、2023年10月1日に開始した消費税に関する請求書の作成方法や計算方法、税額控除の適用要件などを定めたルールです。制度の開始にともなって従来の方式から変更となった点も多く、仕入税額控除を適用するためには、インボイス(適格請求書)の入手と保存が必要となりました。
また、インボイス制度を利用するためには、管轄の税務署にて事前に適格請求書発行事業者の登録をおこなわなければなりません。
そのため、課税売上高が1,000万円以下の免税事業者として取引をおこなう個人事業主やフリーランスは、インボイス制度に登録するかどうかを選択する必要があります。
インボイス制度が非課税取引を扱う事業者に与える影響
現在、非課税取引のみを扱う事業者であっても、将来的にインボイス制度の影響を受ける可能性があります。
そのため、免税事業者のままでいる場合と適格請求書発行事業者になる場合、それぞれの影響を把握することが重要です。影響の概要を理解していれば、どちらを選択すべきかを判断しやすくなります。
ここでは、インボイス制度が非課税取引を扱う事業者に与える影響について解説します。
- 免税事業者:非課税取引のみを扱うなら大きな影響はない
- 適格請求書発行事業者:消費税の納税義務が生じる
①免税事業者でいる場合、非課税取引のみを扱うなら大きな影響はない
免税事業者のままでいる場合、消費税の納税義務は発生しません。そのため、非課税取引のみを扱うなら、インボイス制度による大きな影響は受けずに済みます。
しかし、課税事業者にとって、免税事業者との取引では消費税の支払い負担が生じます。このようなことから、インボイス制度に登録せず課税事業者と取引をおこなう場合、以下のような影響が出るおそれがあるでしょう。
- 取引数が減少する
- 報酬の値下げ交渉がおこなわれる
- 新規の取引先を見つけにくくなる
関連記事:インボイス制度による免税事業者への影響は?経過措置や特例もあわせて解説
②適格請求書発行事業者になる場合、消費税の納税義務が生じる
インボイス制度に登録して適格請求書発行事業者になる場合、取引先に対してインボイスを交付できるようになります。
しかし、適格請求書発行事業者として登録した日の売上分から、消費税を納税しなければなりません。また、消費税額を計算して確定申告をおこなう手間も生じます。
ただし、インボイス制度に登録して免税事業者から課税事業者になった場合は、負担を軽減するための「2割特例」を2026年9月30日まで適用できます。
関連記事:【何パーセント?】インボイス制度の2割特例を解説!免税事業者の仕入に関する経過措置も
非課税取引を扱う事業者がインボイス制度に登録する場合の判断基準とは?
非課税取引を扱う事業者がインボイス制度に登録すべきかどうかは、状況によって異なります。状況を見誤ると、登録後の負担が大きくなる可能性があります。
そのため、自身の状況を把握して、インボイス制度への登録を慎重に判断することが重要です。
ここでは、非課税取引を扱う事業者がインボイス制度に登録する場合の判断基準について解説します。
- 非課税取引のみを扱う場合は、基本的に登録は不要
- 課税取引を扱う予定があるなら登録を検討すべき
①非課税取引のみを扱う場合は、基本的に登録は不要
基本的に、非課税取引のみを扱う事業者は、インボイス制度に登録する必要はありません。インボイス制度は仕入税額控除の適用に影響する制度であり、消費税が発生しない非課税取引には関係がないためです。
課税取引の場合はインボイスを保存することで、仕入税額控除を適用します。一方、非課税取引の場合は買手側が消費税を支払う必要がなく、インボイスの発行が不要です。
今後も非課税取引のみをおこなう予定であれば、インボイス制度に登録しなくても問題ありません。
②課税取引を扱う予定があるなら登録を検討すべき
非課税取引を扱う事業者であっても、将来的に課税取引をおこなう予定がある場合には、インボイス制度への登録を検討するべきです。
免税事業者のまま課税取引をおこなうと、買手側がインボイスを受け取れず、仕入税額控除を適用できません。そのため、インボイス制度に登録して適格請求書発行事業者にならなければ、新規取引先の開拓や既存取引先との契約に影響が出る可能性があります。
取引先と相談したうえで、インボイス制度に登録するかを慎重に判断しましょう。
非課税取引を扱う事業者が課税事業者になる前に知っておくべき3つのこと
非課税取引を扱う事業者がインボイス制度に登録して課税事業者になると、これまでとは状況が大きく変わります。
注意点を把握していなければ、事業に影響を与える可能性があるため、注意しなければなりません。インボイス制度への登録を判断するためにも、課税事業者になったあとに関して把握することが重要です。
ここでは、非課税取引を扱う事業者が課税事業者になる前に知っておくべきことについて解説します。
①課税事業者になると2年間は免税事業者に戻れない
インボイス制度に登録して課税事業者になると、その後2年間は免税事業者に戻れません。そのため、適格請求書発行事業者の取消し申請により登録が失効しても、2年間は課税事業者のままです。
また、適格請求書発行事業者の登録を取り消すには、翌課税期間の初日から起算して15日までに書類を作成して提出する必要があります。
②免税事業者と取引する場合は仕入税額控除を適用できない
インボイスを交付できるのは、インボイス制度に登録した適格請求書発行事業者のみです。免税事業者との取引で生じた消費税は、仕入税額控除の対象となりません。
ただし、簡易課税制度の対象となる事業者の場合は、課税事業者であっても仕入税額控除を適用する際にインボイスの保存が不要です。そのため、免税事業者との取引でも仕入税額控除を適用できます。
③インボイス制度では免税事業者に経過措置がある
インボイス制度では、免税事業者との取引がある課税事業者の負担を軽減するために経過措置を設けています。経過措置の期間は2029年9月30日までです。
また、以下の表のように期間によって、経過措置の適用割合は異なります。
|
期間 |
割合 |
|
2023年10月1日~2026年9月30日まで |
仕入税額相当額の80% |
|
2026年10月1日~2029年9月30日まで |
仕入税額相当額の50% |
関連記事:インボイス制度における経過措置とは?仕入税額を80%控除する計算方法を解説
非課税取引を扱う事業者が課税事業者になる方法
非課税取引を扱う事業者が適格請求書発行事業者になるためには、インボイス制度への登録が必要です。インボイス制度への登録はe-Taxまたは書類の郵送にておこなえます。
手軽に申請を済ませるなら、e-Taxを利用しましょう。また、e-Taxから申請する際には、マイナンバーカードと利用者識別番号が必要です。
ここでは、スマートフォンを使ったe-Tax申請の手順を解説します。
- マイナンバーカードを使ってe-Taxにログインする
- ログイン後は利用者識別番号を取得・登録する
- 画面に従って、登録申請データの作成に必要な情報を入力する
- 作成したデータに電子署名をおこなって送信する
e-Taxから登録申請をおこなったあとは、登録したメールアドレスに通知が届いているかを確認しましょう。
まとめ|非課税取引を扱う事業者はインボイス制度への登録を慎重に判断しよう
本記事では、非課税取引を扱う事業者へのインボイス制度の影響や登録について、必要性や登録する前に知っておくべきポイントを交えて解説しました。
基本的に、非課税取引のみを扱うのであれば、インボイス制度に登録する必要はありません。しかし、課税事業者と取引をおこなう予定があるなら、インボイスへの登録を検討すべきです。
適格請求書発行事業者になればインボイスを交付できるため、課税事業者である取引先の負担を軽減できます。ただし、インボイス制度に登録するためには、自身も課税事業者にならなければなりません。
インボイス制度への登録にはメリットとデメリットの両方があるため、本記事を参考にして慎重に検討しましょう。










