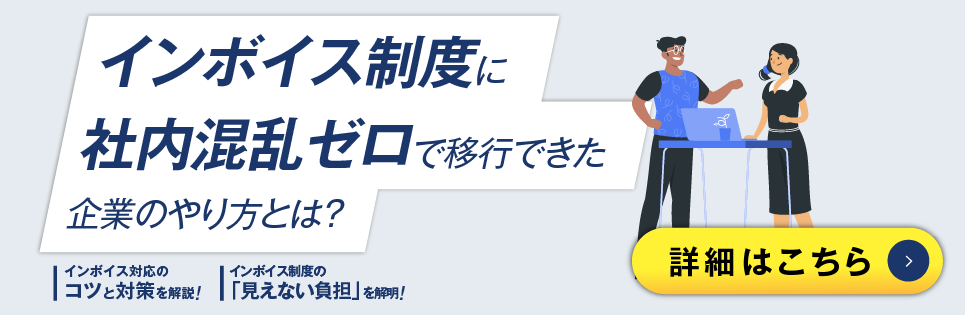インボイス制度における経過措置とは?仕入税額を80%控除する計算方法を解説
更新日:2025.12.06
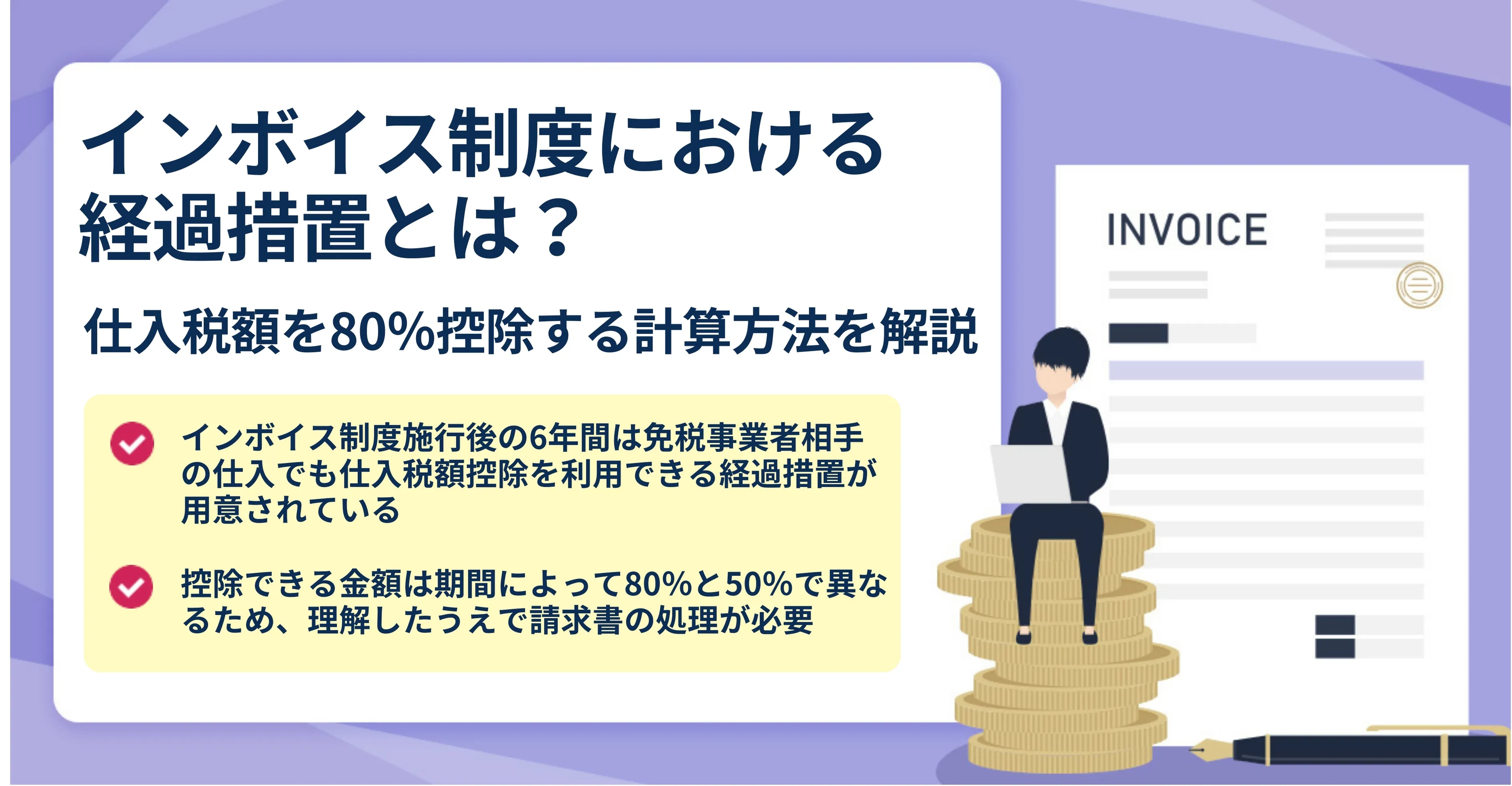
ー 目次 ー
2023年10月に施行された「インボイス制度」は、消費税にまつわる書類の記載や管理、計算方法などを定めた新しいルールです。この制度では従来の請求書の記載方式を変更し、新たに追加項目を備えた「インボイス(適格請求書)」の発行・保存が必要となりました。
インボイス制度では売上にかかる消費税から、仕入れに支払った消費税を控除できる「仕入税額控除」が利用できます。しかし、インボイスの発行・保存には、税務署に適格請求書発行事業者としての登録が必要であり、登録していない事業者との取引では消費税が控除できません。
ただ、政府はこのような状況に対して、「免税事業者の仕入れに関する経過措置」を実施しています。この経過措置を活用すれば、消費税の負担を軽減することが可能です。
本記事では、インボイス制度における経過措置について、計算や仕訳方法も交えて解説します。
インボイス制度では、適格請求書発行事業者同士でなければ仕入税額控除が利用できない
インボイス制度は2023年に施行された消費税にまつわる新しいルールであり、従来のルールと比べてさまざまな点が変更となりました。とくに、請求書の記載方式にいくつかの項目が追加され、仕入税額控除の適用要件が変わっています。
また、インボイス制度では「適格請求書発行事業者」に登録した事業に限り、インボイス(適格請求書)の発行・保存を認めています。このようなことから、インボイス制度が施行された現在において、仕入税額控除を受けるためには、取引当事者双方が適格請求書発行事業者でなければなりません。
なお、仕入税額控除とは売上にかかる消費税から、仕入れで支払った消費税を控除できる仕組みのことです。
【重要】インボイス制度では仕入税額控除に対して経過措置が設けられている
インボイス制度で仕入税額控除が適用されるためには、取引当事者双方が制度に登録している必要があります。このようなことから、インボイス(適格請求書)を発行できない免税事業者との取引には仕入税額控除が適用されません。
このような課題に対して政府は、一定期間の経過措置を設けています。具体的には「免税事業者の仕入に関する経過措置」と呼び、事業者との取引でインボイスが発行されない場合であっても仕入税額控除の利用が可能という内容です。
この経過措置によって、2026年9月30日までは免税事業者へ支払った消費税の80%が控除されます。また、2026年10月1日〜2029年9月30日の期間では控除割合が引き下げられ、免税事業者へ支払った消費税のうち50%が控除されます。
インボイス制度で消費税を計算する方法とは?
消費税の計算方法には「積上げ計算」と「割戻し計算」があり、一般的には積上げ計算が採用されています。ただし、売上を割戻し計算で算出している場合は、仕入税額を計算する際も割戻し計算の利用が可能です。
それぞれの計算方法を理解していないと、納税時のミスにつながるため注意しましょう。ここでは、インボイス制度で消費税を計算する方法について解説します。
①積上げ計算で消費税を80%控除する際の計算例
積上げ計算とは、請求書に記載された消費税を合計して、納税額を求める計算方法です。
積上げ計算では、インボイス(適格請求書)に記載されている消費税の合計額に110分の7.8を乗じましょう。そこから、100分の80を乗じることで、納税額を算出できます。
- 消費税額10%:仕入税額×7.8/110×80/100=納税消費税
- 消費税額8%:仕入税額×6.24/108×80/100=納税消費税
インボイスは発行段階で端数処理がおこなわれているため、課税事業者との取引がある場合は積上げ計算が基本になります。
②割戻し計算で消費税を80%控除する際の計算例
割戻し計算は「1年間の税込金額合計」から税抜金額を割り戻し、納税額を求める計算方法です。
割戻し計算では、課税期間中の課税仕入れを税率ごとに分けましょう。標準税率の場合は、算出できた課税仕入れに対して110分の7.8を乗じて仕入税額を計算します。軽減税率の際は、課税仕入れに対して108分の6.24を乗じることで仕入税額が明確になります。
どちらも、仕入税額に100分の80を乗じることで控除できる金額が算出できるでしょう。
- 消費税額10%:課税期間中の消費税×7.8/110×80/100=納税消費税
- 消費税額8%:課税期間中の消費税×6.24/108×80/100=納税消費税
インボイス制度の経過措置で控除できない消費税の仕訳方法
インボイス制度の経過措置の適用で生じた控除できない消費税を仕訳する際は、仕入れ費用に上乗せするか雑損失として扱います。仕訳方法を理解しておき、自社にあった方法を選びましょう。
ここからは、インボイス制度の経過措置で控除できない消費税の仕訳方法を解説します。
①費用に上乗せする
控除できない分の消費税は、帳簿に記載するときに「仮払消費税」で仕訳しておきましょう。仮払消費税は仕訳の時点で記載するため、取引があった段階で控除されない消費税分を計算しておく必要があります。
|
貸方 |
借方 |
||
|
仕入れ |
1,020 |
現金 |
1,100 |
|
仮払消費税 |
80 |
||
上記の例では、実際の消費税額は100円なものの、80円のみが控除の対象となるため、20円は仕入れの費用にくわえています。
②雑損失として扱う
控除できる消費税を決算時に計算する方法として、雑損失として扱う方法もあります。仕入れを記帳する際は控除を受けられたときと同じように処理しておき、決算時に控除が適用されない消費税を「雑損失」に仕訳するため、毎回の消費税を計算する手間がありません。
|
貸方 |
借方 |
||
|
仕入れ |
1,000 |
現金 |
1,100 |
|
仮払消費税 |
100 |
||
決算時の仕訳は下記でおこないましょう。
|
貸方 |
借方 |
||
|
雑損失 |
20 |
仮払消費税 |
20 |
インボイス制度における経過措置での3つの注意点
インボイス制度における経過措置では、消費税の扱いや控除される期間などの注意点があります。注意点を理解していなければ、決算時のトラブルにつながるおそれがあるため注意しましょう。
ここでは、インボイス制度における経過措置での3つの注意点を解説します。
①控除できない消費税の扱いを統一しておく
自社に免税事業者との取引がある際は、経理担当者のなかで控除できない消費税をどのように仕訳するかを統一しておきましょう。統一されていない場合、取引先ごとに仕訳の方法が異なり、決算時に混乱を招くおそれがあります。
確定申告時にすべてを修正するのは、経理業務が大幅に増えてしまいます。慣れるまではダブルチェックをおこない、確定申告時のミスを減らしましょう。
②控除される割合に注意する
インボイス制度における経過措置では、制度施行から一定期間しか控除が受けられない仕組みとなっています。また、段階的に控除割合も引き下げられています。この控除される期間と控除割合は以下のとおりです。
- 2023年10月1日〜2026年9月30日:80%
- 2026年10月1日〜2029年9月30日:50%
- 2029年10月1日〜:0%
上記のように2029年10月1日以降では経過措置による消費税の控除は期待できません。控除が受けられないと売上が大幅に減少するおそれもあるため、長期的な事業運営も踏まえた決断が求められます。
③取引額が税込1万円の場合は少額特例が適用される
2023年10月1日〜2029年9月30日の期間は、免税事業者相手の仕入れであっても、取引額が税込1万円未満であれば少額特例が適用されて仕入税額控除の利用は可能です。少額特例では仕入税額が満額控除されるため、経過措置を利用するよりも利益が多くなります。
なお、2029年10月1日以降は1万円以下の取引でも消費税を控除するためにはインボイス(適格請求書)が必要になります。
まとめ|インボイス制度後に仕入税額の経過措置を利用するなら計算方法を理解しよう
本記事では、インボイス制度における経過措置について、計算や仕訳方法も交えて解説しました。
インボイス制度の施行にともなって、消費税に関するさまざまなルールに大きな影響を与えています。
このようなことから、これからインボイス制度の登録を検討していれば、基本的なルールはもちろんのこと、特例や経過措置にも注目しておかなければなりません。国税庁の公式サイトや本メディアなどを活用し、インボイス制度に対応するための知識を蓄えましょう。