【何パーセント?】インボイス制度の2割特例を解説!免税事業者の仕入に関する経過措置も
更新日:2025.12.24
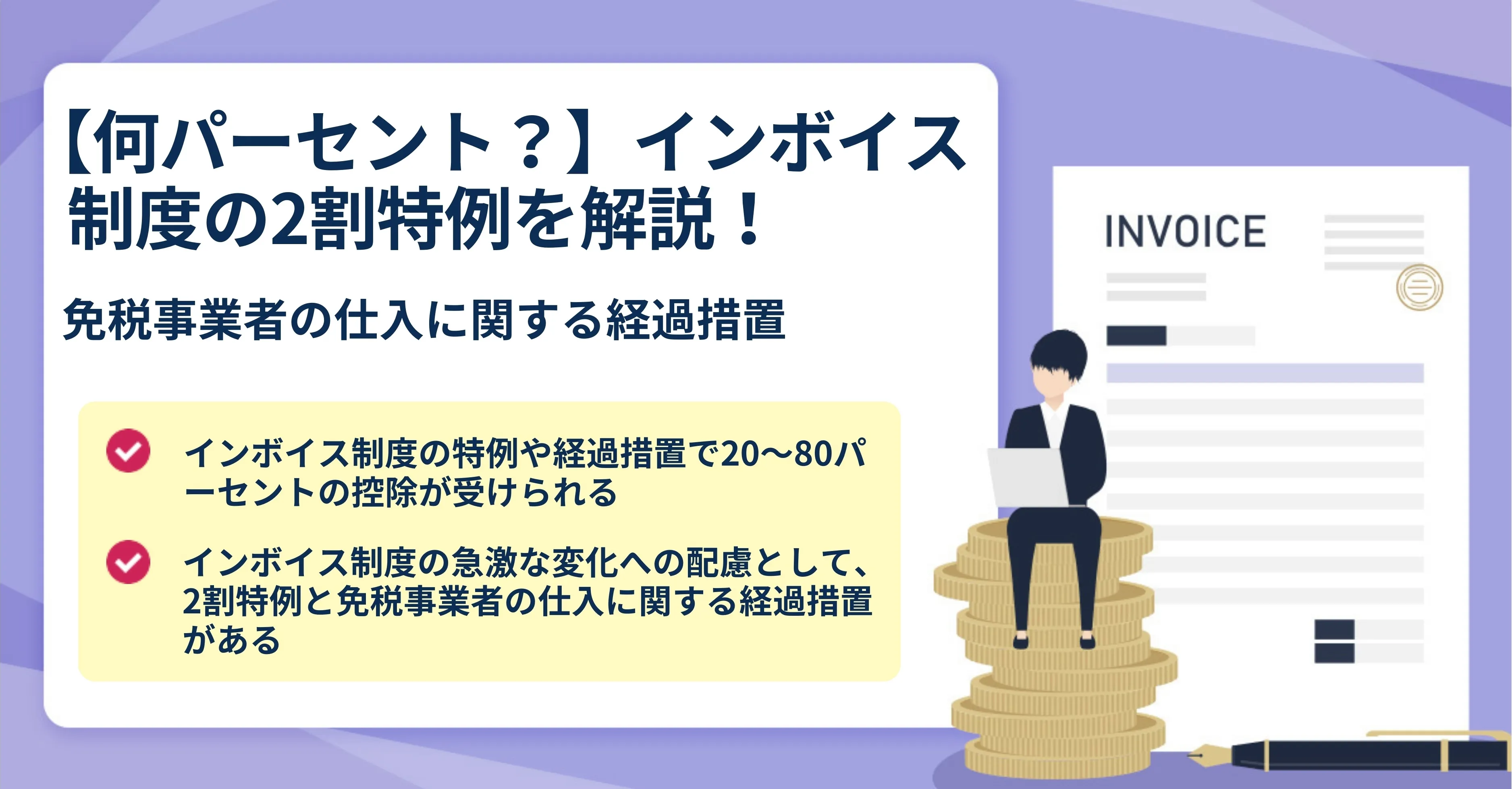
ー 目次 ー
インボイス制度では「適格請求書発行事業者」に登録することで、適格請求書(インボイス)の発行が可能になります。また、インボイスの発行・保存をおこなうことで、適格請求書発行事業者同士の取引であれば仕入税額控除が受けられます。
一方で、インボイス制度に登録すると、免税事業者であった事業者の場合でも消費税の申告・納付が必要です。
このような課題があるなか、導入のハードルを下げる目的で「2割特例」や「免税事業者の仕入に関する経過措置」が実施されました。もしこれから免税事業者がインボイス制度に登録する場合は、特例や措置の活用を検討しましょう。
本記事では、インボイス制度の2割特例と免税事業者の仕入に関する経過措置について、解説します。
【結論】インボイス制度の特例や経過措置で50〜80パーセントの控除が受けられる
インボイス制度では、免税事業者への影響を軽減するために「2割特例」と「免税事業者の仕入に関する経過措置」が設けられています。特例や措置を活用することで、50〜80パーセントの消費税の控除が可能です。
「2割特例」は、免税事業者が適格請求書発行事業者として登録する際、金銭的な負担を軽減する制度です。計算が簡略化され、事務処理の負担も軽減されます。
一方で、「免税事業者の仕入に関する経過措置」は、免税事業者から課税仕入をする事業者に対して一定の仕入税額控除を認めるものです。
どちらの制度も適用期間があるため、対象期間を把握し適切に活用しましょう。
インボイス制度とは?基本的なルールと特徴を紹介
インボイス制度は消費税にまつわる制度であり、複数税率でわかりにくくなった消費税の申告・納付の透明性を高めるために施行されました。この制度では、消費税の申告に必要な請求書や納品書などの書類に関する記載や取扱いのルールを定めています。
これからインボイス制度の活用を検討する事業者であれば、まずは基本的なルールについて理解しておきましょう。
ここでは、インボイス制度の基本的なルールと特徴を紹介します。
①仕入税額控除が受けられる
仕入税額控除は、売上の対象となる消費税から仕入で支払った消費税を差し引ける仕組みです。この仕入税額控除を活用すれば、これまでと比べて税負担が軽減する可能性があります。
ただし、インボイス制度は、適格請求書発行事業者同士の取引に対して利用できる制度であるため、仮に仕入先が免税事業者である場合には利用できません。このような課題に対して、免税事業者の仕入に関する経過措置が施行されています。
②適格請求書(インボイス)の発行が必要
インボイス制度は適格請求書(インボイス)をもとに計算するため、インボイスの発行と保存が必須です。インボイス制度では以下の記載事項を満たしたものをインボイスとして扱えるように定めています。
- 宛先の氏名または名称
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象項目である旨)
- 10%・8%それぞれの対象となる対価の総額および適用税率
- 10%・8%それぞれの消費税額など
上記の要件は請求書だけでなく、納品書や領収書も該当します。そのため、もし納品書や領収書をインボイスとして扱いたい場合には、上記の記載事項を備えた書類を発行しましょう。
③適格請求書発行事業者の登録が必要
インボイスを発行したい場合、適格請求書発行事業者として登録する必要があります。この登録は税務署や登録センターで、登録申請書を提出することで申請可能です。また、e-Taxに対応しているため、自宅や事業所から遠隔で申請できます。
ただ、適格請求書発行事業者に登録すると、課税事業者として消費税の申告・納税が必要です。登録以前は免税事業者であった場合、税負担や対応のための手間が増えてしまいます。
このようなことから、適格請求書発行事業者に登録する前に自社にどのような影響があるかを整理しておく必要があるでしょう。
インボイス制度の2割特例とは?特徴を紹介
2割特例は、売上税額の2割を仕入税額控除としてみなす制度です。適格請求書発行事業者となる小規模事業者の負担を軽減する措置で、事務処理が大幅に簡略化されています。ただ、適用期間が定められており、2023年10月1日〜2026年9月30日の期間内しか特例を利用できません。
利用できれば十分なメリットがある一方で、条件や注意点もあることから、特例の特徴を把握しておくことが大切です。
ここでは、インボイス制度の2割特例の特徴について紹介します。
①対象は免税事業者から適格請求書発行事業者に登録した事業者
2割特例の対象者のおもな条件は以下のとおりです。
- インボイス制度の開始にともない、免税事業者から課税事業者(適格請求書発行事業者)へ移行
- 基準期間の課税売上が1,000万円以下であること
- 2023年10月1日以前に課税事業者として登録していないこと
- 課税期間を短縮する特例を適用していないこと
2割特例はよく簡易課税制度と比較されますが、異なる仕組みであることから注意が必要です。
②売上税額の2割を仕入税額とできる
2割特例における消費税額の計算は下記のとおりです。
|
売上にかかる消費税額-売上税額の8割=納付する消費税額(売上税額の2割) |
一般課税では仕入時の実額で計算、簡易課税では事業別に計算する必要があります。2割特例では一律2割を納付するため、計算が簡略化され事務負担の軽減が見込めます。
インボイス制度の免税事業者の仕入に関する経過措置とは?2割特例との違いも紹介
仕入税額控除は本来、仕入先のインボイスが必要ですが、経過措置により適格請求書発行事業者以外からの仕入税相当額の一定割合を仕入税額とみなし、控除しています。この経過措置は、インボイス制度の導入による大きな変化を緩和するために設けられています。
なお、経過措置の適用にあたっては、以下の対応が必要です。
- 免税事業者発行の区分記載請求書などと同様の事項が記載された書類の保存
- 2割特例の適用を受ける旨を記載した帳簿の保存
ここでは、インボイス制度の免税事業者の仕入に関する経過措置について、2割特例との違いも交えて紹介します。
①対象は、買い手側の課税事業者
経過措置は、適格請求書発行事業者ではない事業者からの仕入れをおこなう買い手側(課税事業者)を対象としています。免税事業者との取引について、適用期間内は仕入税額控除が受けられるようになります。
このように経過措置は買い手を対象としたものでありますが、売り手側から見れば免税事業者であることを理由に取引が減少・消失してしまうリスク回避につながります。この経過措置期間を利用して、適格請求書発行事業者への登録を検討しましょう。
②免税業者からの仕入れにかかる負担を軽減
経過措置では、仕入税額の80パーセントや50パーセントの控除が受けられます。この割合は期間で変動します。
免税事業者からの仕入で仕入税額控除を受けられないことは、買い手の事業経営に大きな影響を与えるでしょう。税負担が増えることで、事業運営に支障を来す可能性もあります。
経過措置を利用すれば、このような課題を一定期間クリアできるでしょう。
③3年ごとに80パーセント、50パーセントと控除割合が減少する
経過措置はインボイス制度開始から3年間は80パーセント、その後3年間は50パーセントの控除があります。3年ごとに控除割合が減少するため、控除を受ける場合は把握しておきましょう。
2割特例よりも控除の期間が長く、また段階的に以下のように控除割合が変更されます。
50パーセントに低下する2026年10月までや、控除不可となる2029年10月までを目安として、買い手・売り手がお互いに納得できるよう相談していきましょう。
状況に応じて2割特例と経過措置を使い分けよう
インボイス制度の導入により、免税事業者との取引は買い手・売り手の双方に大きな影響を及ぼします。適切に対応するためには、2割特例と経過措置を状況に応じて使い分けることが重要です。
どちらを使い分けるべきかについて、以下の表にまとめているため、あわせて参考にしてください。
|
制度名 |
適用期間 |
利用を検討すべき状況 |
|
2割特例 |
2023年10月1日~2026年9月30日 |
免税事業者が適格請求書発行事業者(課税事業者)になる際 |
|
経過措置 |
80%:2023年10月1日~2026年9月30日 50%:2026年10月1日~2029年9月30日 |
適格請求書発行事業者(課税事業者)が免税事業者から仕入をおこなう際 |
2割特例・経過措置のどちらも適用期間があるため、計画的に対応を進める必要があります。
まとめ|経過措置は適用期間に注意して、計画的にインボイス制度に対応しよう
本記事では、インボイス制度の2割特例と免税事業者の仕入に関する経過措置について解説しました。
インボイス制度が施行され、多くの事業者がインボイス制度を利用しています。免税事業者であった事業者にとっては、大きな選択を迫られる制度ともいえるでしょう。
これからインボイス制度の登録を検討する事業者は、基本的なルールだけでなく、本記事で紹介した「2割特例」や「免税事業者の仕入に関する経過措置」の概要やメリットを理解しておくことがおすすめです。
事業運営をよりスムーズに進めるためにも、計画的にインボイス制度に対応していきましょう。










