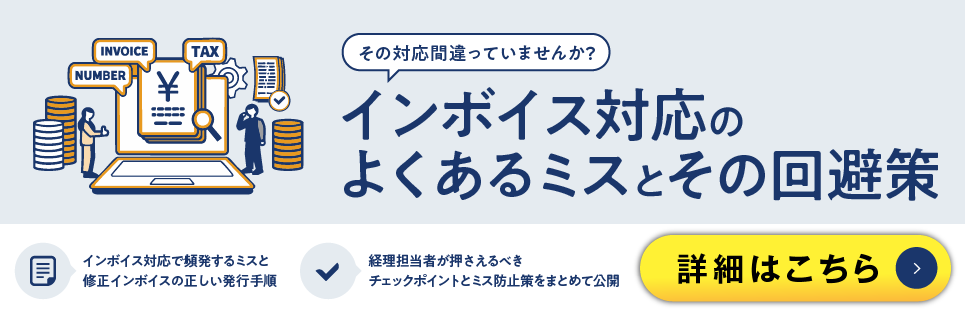インボイス(適格請求書)のルールとは?記載例や注意点も解説
更新日:2025.12.24
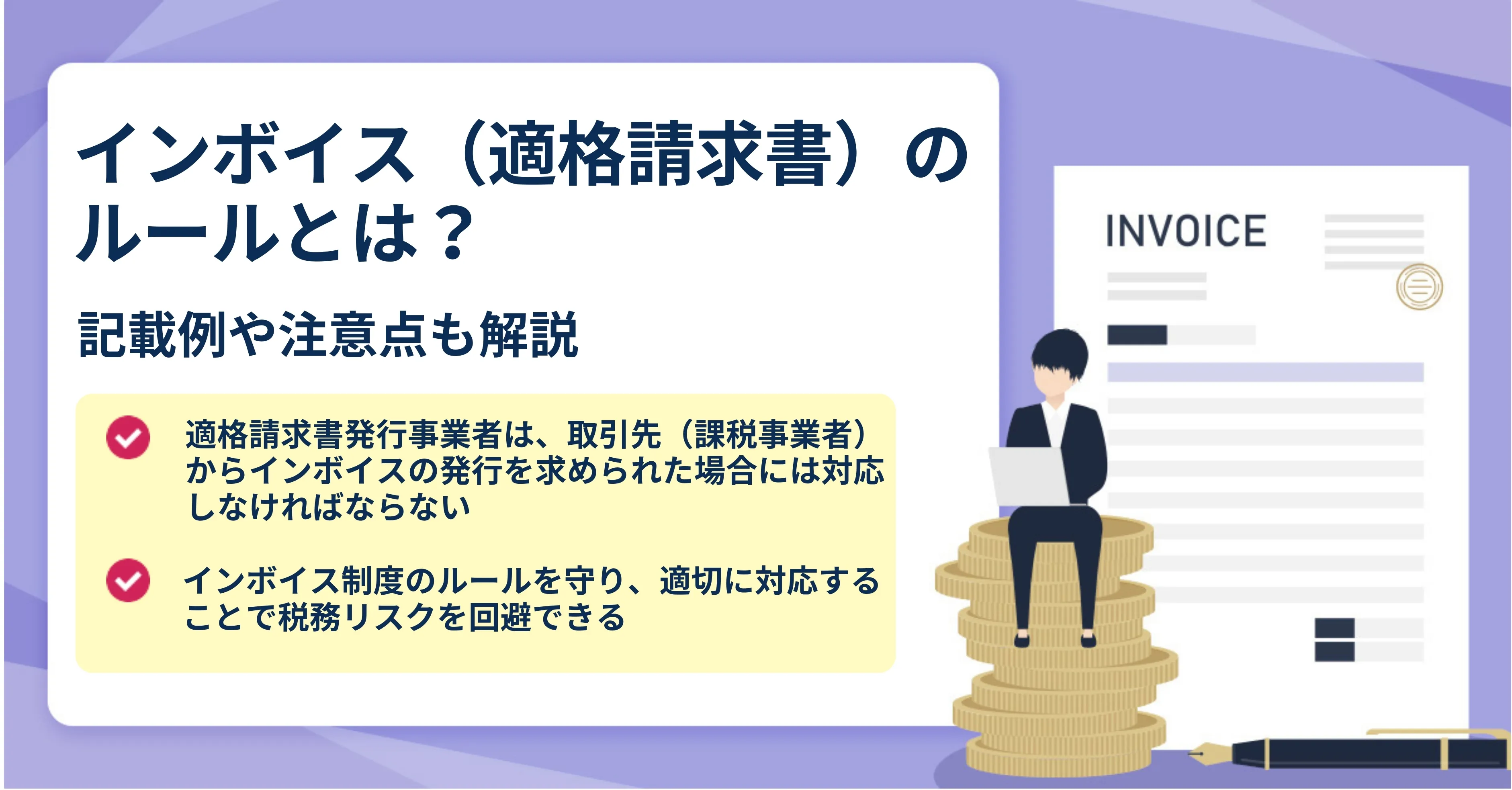
ー 目次 ー
インボイス制度の開始により「インボイス(適格請求書)」の記載方法や保存方法などのルールが定められました。この制度の要件を満たすことで、売上にかかる税金から仕入れに支払った税金を差し引く仕組みである「仕入税額控除」が適用できます。
インボイスのルールは細かい点も多く、ミスした場合には自社だけでなく、取引先に影響を及ぼすおそれがあるため注意が必要です。インボイス制度の対応にはルールの把握と遵守が重要です。
本記事では、インボイス(適格請求書)のルールと記載について、記載例や注意点も交えて解説します。
【基本】インボイス(適格請求書)とは?
インボイス(適格請求書)には、記載や計算の方法がしっかりと定められており、正しい発行や保存を把握する必要があります。インボイスの3つのポイントは以下のとおりです。
- 発行するには「適格請求書発行事業者」への登録が前提
- 「インボイス」の発行・保存が義務付けられている
- 「仕入税額控除」を適用するために必要な書類
インボイスには通常の取引で使用するものだけでなく、「簡易インボイス(適格簡易請求書)」や「返還インボイス(適格返還請求書)」などがあります。
これらは、役割や使用するタイミングなどが異なるため、これからインボイス制度での対応をおこなう場合には事前に把握しておきましょう。
ここでは、インボイス(適格請求書)の種類と違い、使用するタイミングを解説します。
インボイス(適格請求書)とは、適用税率や消費税額などを明記した書類
「インボイス(適格請求書)」は、インボイス制度によって請求書の記載事項や消費税の計算方法などが定められた書類です。具体的な記載事項が定められており、満たしていない場合にはインボイスとして扱われません。
インボイスは脱税防止や税務調査に必要な情報を保持するために、適切な発行・保存が求められています。
関連記事:適格請求書とは?インボイス制度開始に向けて準備すべき点をわかりやすく解説
簡易インボイス(適格簡易請求書)とは、インボイスの記載事項を省略した書類
インボイス制度では、不特定多数との販売をおこなう業種に対して「簡易インボイス(適格簡易請求書)」の発行も可能としています。これは、通常の「インボイス」と比べ、以下のような点で記載事項が簡易的になっています。
- 宛先省略可
- 適用税率か税額のどちらかを記載で良い
ただ、「不特定多数との販売をおこなう業種」に該当しなければ、簡易インボイスの発行ができない点に注意が必要です。
関連記事:適格簡易請求書(簡易インボイス)を交付できる業種|記載項目と具体例、例外を紹介。
返還インボイス(適格返還請求書)とは、値引きや返品が発生した場合に交付する書類
商品の値引きや返品が発生した際には、「返還インボイス(適格返還請求書)」の発行が必要です。この返還インボイスではインボイスと同様に、記載事項や保存のルールが定められています。
返還インボイスは、割引や販売奨励金を支払った場合などでも発行が必要です。
関連記事:返還インボイスとは?支払通知書で代用できるのか問題や記載が必要となる項目など解説
修正インボイスとは、インボイスに誤りを訂正するための書類
すでに発行したインボイス(適格請求書)の内容に誤りがあった場合、「修正インボイス」による訂正が義務付けられています。修正インボイスの対応は、再交付や修正事項を追記するなどの方法があります。
修正インボイスを発行しなければ、インボイスの受領者は仕入税額控除を受けられないため、もし誤りを確認した場合には迅速に修正インボイスの対応をおこないましょう。
関連記事:修正インボイスとは?対応方法や適格返還請求書との違いなど解説
インボイス(適格請求書)の書き方とは?記載事項と記載例を交えて紹介
インボイス制度によって、従来の記載方式から「適格請求書等保存方式」に変更されました。この変更にともなって、仕入税額控除を適用するために必要であった記載事項が変わっています。
記載事項のなかには細かなルールも存在するため、これからインボイス(適格請求書)の発行をおこなう場合にはそれぞれの記載事項のルールを把握しておきましょう。
ここでは、インボイス(適格請求書)の記載事項について、以下7点を解説します。なお、記載例もまとめているため、インボイスの発行時の参考にしてください。
- 発行者の氏名・名称
- 適格請求書発行事業者の登録番号
- 取引年月日
- 支払期日
- 取引内容
- 取引金額
- 受領者の氏名・名称
|
発行日:20〇〇年〇〇月〇〇日 請 求 書 株式会社〇〇 御中 〒 ◇◇◇株式会社 〒 登録番号 T1234567890123 下記のとおり、ご請求申し上げます。
振込先:〇〇銀行××支店 支払期限:20〇〇年〇〇月〇〇日
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①発行者の氏名・名称
事業者を特定できるよう、インボイス(適格請求書)発行事業者として申請した正式名称を記載します。
なお、発行者の氏名・名称、住所だけでなく、電話番号やメールアドレスなど、取引先が問い合わせができる連絡先を記入しておきましょう。
②適格請求書発行事業者の登録番号
インボイス(適格請求書)には発行者の氏名・名称だけでなく、インボイス発行事業者の登録番号を記載します。
この登録番号は「T」からはじまり、法人の場合は「T+法人番号」で、個人事業主の場合は個人番号と被らない数字となります。
③取引年月日
取引をおこなった日を記載しましょう。
なお、複数の取引をまとめて請求する場合は、取引年月日と取引内容を、取引ごとに把握できるように記載します。
④支払期日
請求書には支払期日を記載します。契約書を交わす際に取り決める場合も多く、取引先と相談して日程を決めることが重要です。
下請業者への支払期日は「下請代金支払遅延等防止法」によって60日以内、かつ限りなく早くの期間が推奨されており、これは遅延に対し両者の合意があっても守らなければいけません。
⑤取引内容
取引先に提供したサービスや商品の内容を記載します。
軽減税率対象の品目があれば、その旨を記載しなくてはなりません。税率の項目を設けるか「※印」をつけ、軽減税率対象である旨を記載することが一般的な記載方法です。
⑥取引金額
商品やサービスの対価として受け取る金額を記載する必要があります。
インボイス(適格請求書)として発行する場合には、商品金額だけでなく、適用税率と税率ごとに合計した取引金額と消費税額も記載しましょう。
⑦受領者の氏名・名称
インボイス(適格請求書)を受け取る側の事業者名を記載します。請求相手の名称が曖昧な場合は、取引先に確認します。
株式会社を「㈱」のように省略せずに正式な名称を記載のうえ、「御中」や「様」などの敬称も忘れないようにしましょう。
インボイス(適格請求書)を扱う際に知っておきたいルールと注意点
インボイス制度の対応にはルールの把握が不可欠です。発行するインボイス(適格請求書)にミスがあると確認や修正などの余計な手間が増え、ミスが続くと取引先からの信用を失うおそれがあります。また、税務調査にも影響し、国税庁によるペナルティを受けるリスクも孕んでいます。
このような事態に陥らないためにも、インボイス制度の基本的なルールや注意点を把握し、適切な対応をおこなうようにしましょう。
ここでは、インボイス(適格請求書)を扱う際に知っておきたいルールと注意点を解説します。
①適格請求書発行事業者(課税事業者)のみが発行
「インボイス(適格請求書)発行事業者」に登録しなければ、インボイス(適格請求書)は発行できません。この登録は事前におこなう必要があり、登録後は課税事業者と同様に消費税の申告・納付が必要になります。
このような点から免税事業者への影響が大きいため、免税事業者は登録前に慎重に検討しましょう。
②インボイスの発行・保存義務
インボイス(適格請求書)発行事業者は、取引先からインボイスの発行を求められた場合には対応する義務があります。
一方で、買い手として仕入税額控除を利用する場合、取引先が発行したインボイスを保存しなければなりません。インボイスは税務調査で提出を求められるケースがあるため、適切な保存が求められます。
なお、インボイスは発行側、受領側ともに7年間保存が必要です。
③仕入税額控除は仕入先のインボイスが必要
取引の詳細な情報が記載されているため、インボイス(適格請求書)は取引の証明が可能です。仕入税額控除には受領したインボイスの保存が必須で、インボイスが保存されていない場合には仕入税額控除が適用されません。
これは免税事業者との取引にも大きな影響を与える一方で、インボイス制度では経過措置を定めています。具体的には、2029年までであれば、免税事業者からの仕入れに対して、一定割合の控除が可能という内容です。
④取引先のインボイス登録状況の確認
仕入税額控除を受けるには、取引先がインボイス制度に登録をしているかの確認が必要です。
確認方法はいくつか存在しますが、登録番号を把握していれば国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で、登録番号を入力すると登録状況を確認できます。登録番号を把握していない場合は、取引先に直接確認しましょう。
⑤インボイス対応で請求書業務の増加
インボイス(適格請求書)における対応は、テンプレートの変更や受領したインボイスの内容確認などの業務が多く生じます。従来の方式と比べても請求書業務が増加してしまうため、担当者の業務負担を調整する必要があります。
なお、帳票作成システムやサービスが提供されており、活用すれば発行や送付、管理などの手間を大幅に省くことが可能です。導入後に得られるメリットとの費用対効果を踏まえて、検討しましょう。
まとめ|適格請求書の発行ルールを守り、スムーズに対応しよう!
本記事では、インボイス(適格請求書)のルールと記載について、記載例や注意点も交えて解説しました。
インボイス制度を正しく理解し、インボイス(適格請求書)の発行・保存・仕入税額控除のルールを守って対応することが重要です。取引先が適格請求書発行事業者であるかを確認し、免税事業者との取引による影響を考慮して対応します。
会計システムの見直しや経理業務の効率化を進め、スムーズに対応できるよう準備しましょう。