電子帳簿保存法で納品書の電子化は義務化された?保存要件や保存期間、注意点を解説
更新日:2025.03.27
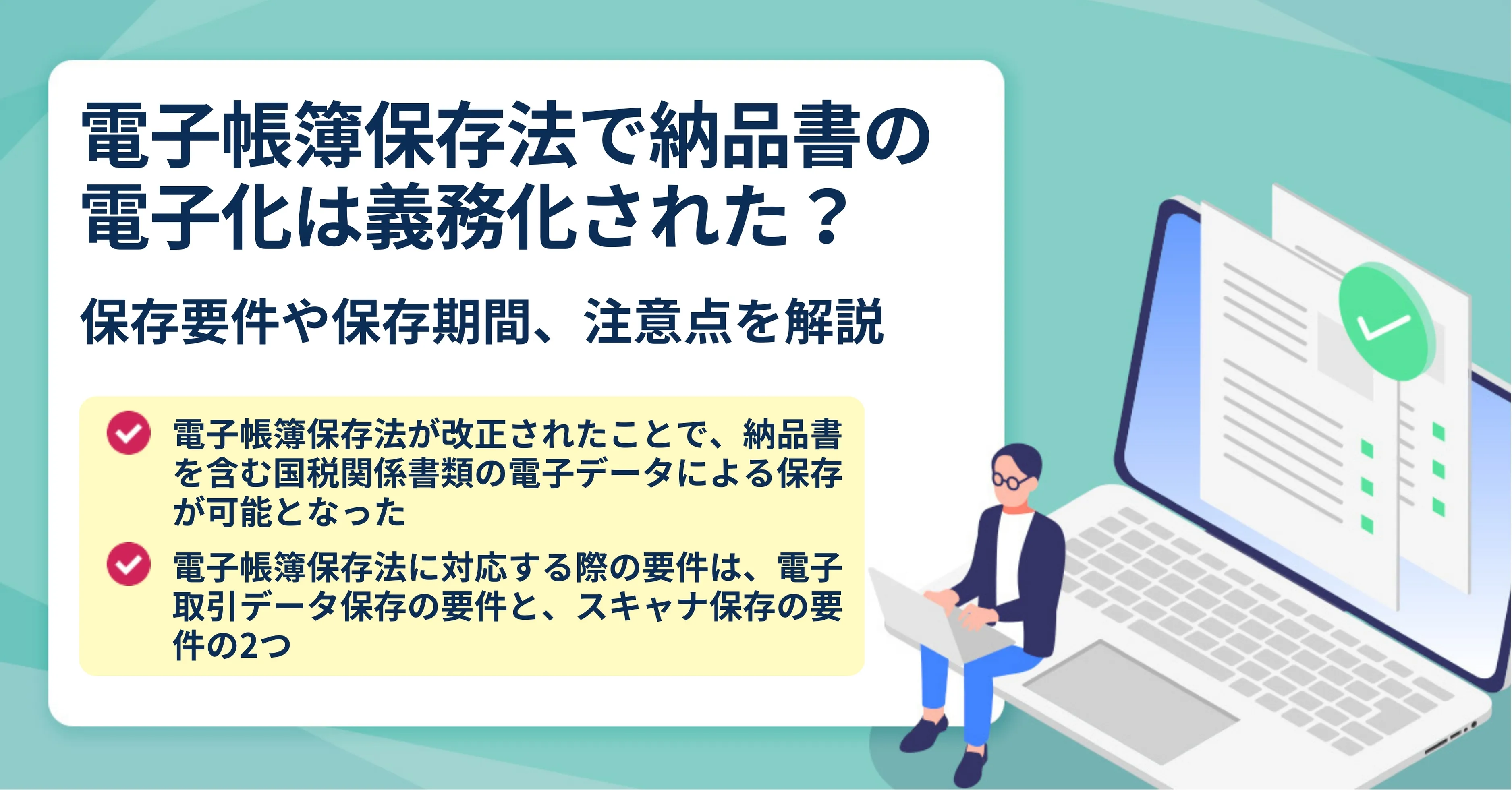
ー 目次 ー
2022年1月1日に施行された電子帳簿保存法の改正によって、納品書の電子データ保存が可能となりました。さらに、近年はペーパーレス化が進んでいることから、納品書をPDFとして受領するケースも増えています。また、2024年1月1日以降は電子取引における電子保存が義務化され、メールやクラウド上で受領した納品書の電子保存が必須となりました。
このように電子帳簿保存法は何度も改正が繰り返されており、最新のルールを把握していない事業者が一定数存在します。定められた要件にもとづいて適切に納品書を保管するには、電子帳簿保存法の最新のルールを把握することが重要です。
本記事では、電子帳簿保存法に基づいた納品書の保存方法や保存期間、保存する際の注意点について解説します。
【結論】納品書は電子帳簿保存法の対象に含まれる!
2022年1月1日に電子帳簿保存法が改正されたことで、納品書を含む税務関係における書類の電子データによる保存が可能となりました。さらに、2024年1月1日以降は電子取引における電子データの保存が義務化され、電子取引による税務関連の書類は必ず電子データとして保存しなければなりません。
納品書は税務関連の書類の1つであり、資金や物の流れに直結する重要な書類とみなされます。また、電子帳簿保存法の対象となる具体的な書類は以下のとおりです。
- 請求書
- 領収書
- 見積書
- 納品書
- 契約書
このなかでも電子データとしてスキャナー保存が可能な書類は、記載された金額が3万円未満のものに限ります。スキャナー保存の適用を受けるには税務署長の承認を受ける必要がありましたが、2022年1月1日以降は任意のタイミングではじめられます。
なお、紙で受領した納品書については、従来どおり、紙として保存しても問題ありません。
電子帳簿保存法に対応する際の2つの要件
電子帳簿保存法に対応するにあたって、該当する書類を電子データとして保存することが必要です。
とくに、電子取引で受領した納品書に関しては、電子データとしてそのまま保存しなければなりません。一方、紙で受領した納品書は、スキャナーで読み取ることで電子データとして保存できます。
どちらの方法も定められた要件を満たす必要があるため、あらかじめ要件を把握しておくことが重要です。
ここでは、電子帳簿保存法に対応する際の2つの要件について解説します。
- 電子取引データ保存の要件
- スキャナー保存の要件
①電子取引データ保存の要件
メールやクラウド上で送付された納品書は、電子取引データ保存の対象です。そのため、法人・個人事業主を問わず、すべての事業者は定められた要件を満たす必要があります。
また、副業をおこなう事業者で所得を雑所得として申告し、前々年分の雑所得の収入金額が300万円を超えている場合も対応しなければなりません。
電子取引データ保存の要件は以下のとおりです。
- 改ざん防止の措置をおこなっている
- ディスプレイ・プリンタを備え付けている
- 「取引年月日」「取引金額」「取引先」の記録項目で検索できる
要件を理解して、電子取引データを適切に保存しましょう。
関連記事:電子取引はこれを読めば完璧!電子帳簿保存法の電子データの保存方法
②スキャナー保存の要件
紙で受領した納品書を電子保存する場合は、スキャナーで読み取ったうえで電子データとしての保存が求められます。要件を満たしたうえでスキャナー保存をおこなえば、原本は破棄が可能です。
スキャナー保存には以下の要件があります。
- 入力期間の制限
- 一定水準以上の解像度およびカラー画像による読取
- タイムスタンプの付与
- 読取情報の保存
- ヴァージョン管理
- 帳簿との相互関連性の確保
- 見読可能装置の備え付け等
- 電子計算機処理システムの概要書等の備え付け
- 検索機能の確保
スキャナー保存の要件は複雑なため、漏らさず対応することが重要です。
関連記事:電子帳簿保存法のスキャナー保存完全ガイド【一問一答】よくある質問・解説付き
電子帳簿保存法における納品書の保存期間は?
納品書を含む税務関連の書類の保存期間は、法人・個人事業主によって異なります。
法人に関しては、確定申告の提出期限の翌日より7年間の保管が必要です。ただし、欠損金の繰越控除を受ける場合は、納品書を10年間保管しなければなりません。
一方、個人事業主では白色申告・青色申告のどちらであるかを問わず、確定申告の提出期限の翌日より5年間の保管が必要です。
関連記事:電子帳簿保存法の保存期間をかんたん解説|対象書類と注意点まとめ【永久保存版】
納品書を電子データとして保存する際の注意点
納品書を電子データとして保存する際の注意点を把握していれば、法律違反をはじめとしたトラブルを未然に防げます。電子帳簿保存法に適切に対応するためにも、必要な情報を確認することが重要です。
ここでは、納品書を電子データとして保存する際の注意点を解説します。
- 法規制を確認してから電子データ化する
- アクセス制限をおこなう
- セキュリティ対策を徹底する
①法規制を確認してから電子データ化する
電子帳簿保存法では、今後も法律や要件が変わる可能性があります。法規制の確認を怠ると、意図せず法律に違反してしまう場合があるため注意しなければなりません。
とくに、納品書をはじめとした重要書類では、見積書や注文書などの一般書類よりも規制が多くなっています。そのため、納品書の取り扱いを誤ると、青色申告の取り消しや追徴課税などの罰が科せられる可能性があります。
納品書を電子データとして保存する際には、法規制が変わっていないかをその都度確認しましょう。
②アクセス制限をおこなう
納品書を電子データとして保存する場合は、IP制限や2段階認証などのアクセス制限が必須です。適切にデータ管理がおこなえていないと、情報漏えいやハッキングなどの被害に遭いかねません。
第三者の不正アクセスを防ぐには、データ管理の担当者のみにアクセス権限を付与することが重要です。
また、電子データへのアクセスログを管理するシステムの導入も効果が期待できるでしょう。
③セキュリティ対策を徹底する
取引先から受領した納品書には、販売情報や顧客情報などの重要な情報が含まれています。第三者に情報を漏えいさせないためには、セキュリティ対策の徹底が必須です。
たとえば、電子データに対するパスワードの設定や暗号化された通信の使用などが、情報漏えい対策として効果的でしょう。
また、情報漏えいが発生した場合に備えて、納品書を含む電子データは定期的にバックアップを取る対策がおすすめです。
電子帳簿保存法における納品書の取り扱いに関してよくある質問
最後に、電子帳簿保存法における納品書の取り扱いに関してよくある質問を紹介します。
①PDFをダウンロードできない場合はどうすれば良い?
納品書のPDFをダウンロードできない場合は、取引画面のスクリーンショットを電子データとして代用可能です。
たとえば、インターネット通販を利用すると、納品書のPDFをダウンロードできない場合があります。この場合は、画面に表示された納品書のスクリーンショットを保存しましょう。
ただし、「取引年月日」「取引金額」「取引先」がわかる取引画面のスクリーンショットを保存する必要があります。
②PDFと紙の納品書を受領した場合、どちらか一方の保存は不要?
PDF(電子データ)と紙の納品書の2種類を受領した場合、原則として電子取引データのみの保存で問題ありません。また、電子データを保存しているのであれば、紙の納品書は破棄が可能です。
ただし、双方の内容が一致していない場合は、どちらも保存する必要があるため注意してください。
③1つの取引で納品書と請求書を受領した場合、両方とも保存しなければならない?
1つの取引で納品書と請求書を受領した場合、電子帳簿保存法に則って両方とも保存が必要です。
それぞれの書類に関して「取引年月日」「取引金額」「取引先」の検索要件を満たすように保存しましょう。
まとめ|電子帳簿保存法の要件を押さえて、適切に納品書を管理しよう
本記事では、電子帳簿保存法に基づいた納品書の保存に関して、保存要件や注意点も交えて解説しました。
電子帳簿保存法の改正によって、紙の納品書は電子データとしての保存が可能です。
しかし、電子データとして保存するには要件があり、内容を把握していないと法律違反をはじめとしたトラブルが発生する可能性があります。くわえて、オンライン上で書類を保存することから、セキュリティ対策の徹底も必須です。
上記のようなことから、電子帳簿保存法への対応を検討している方は、本記事で解説したルールを踏まえて、適切に納品書を電子化して管理しましょう。










