水道料金はインボイス制度の対象!処理方法や仕訳例もあわせて解説
更新日:2026.01.13
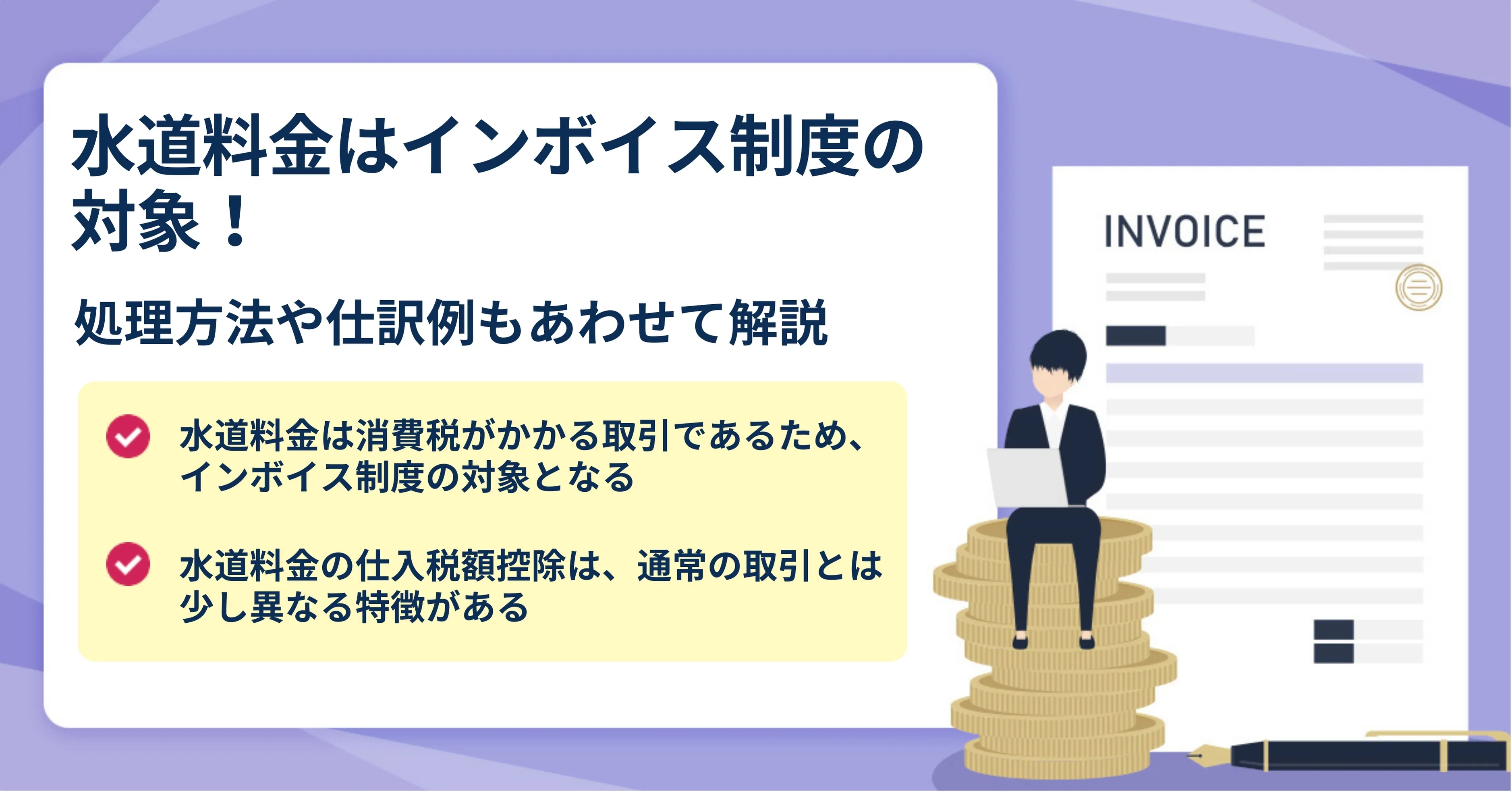
ー 目次 ー
2023年10月に開始されたインボイス制度は、企業の経理処理に大きな変化をもたらしました。多くの事業者が経費処理の方法を見直す中で、水道料金のような公共料金の扱いにも疑問を持つ人が増えています。
水道料金は一般的な取引とは異なり、検針時期の関係で請求が遅れるのが特徴です。期末時点で確定額がわからないケースも多く、適切な対応をしないと仕入税額控除を受けられなくなるリスクがあります。また、水道局でインボイス(適格請求書)の発行方法が異なるため、取得方法や保存方法も確認することが必要です。
本記事では、インボイス制度における水道料金の取扱いについて、処理方法や具体的な仕訳例もあわせて解説します。
インボイス制度は、消費税の計算をより正確におこなうための制度
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、2023年10月1日から開始された消費税の計算をより正確におこなうための制度です。この制度は消費税の透明性向上や適正な徴収を目的としており、事業者間の取引に大きな影響を与えています。
売上にかかる消費税から、仕入れに支払った消費税を差し引く「仕入税額控除」を受けるためには、一定の要件を満たした「インボイス(適格請求書)」の保存が必要です。また、インボイスは「インボイス発行事業者」に登録した事業者のみが発行できます。
インボイスには、以下の項目を記載する必要があります。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目の場合はその旨も記載)
- 税率ごとに区分した合計金額および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額
- 受領者の氏名または名称
【結論】水道料金はインボイス制度の対象になる!知っておきたい3つのポイントとは?
水道料金は消費税の支払いが必要なため、インボイス制度の対象に含まれる取引です。事業として使用している水道料金の仕入税額控除は、最終的には確定額が記載されたインボイス(適格請求書)の保存が必要ですが、課税期間の末日時点では見積額での計上が認められています。
ここでは、水道料金とインボイス制度に関する3つの重要なポイントについて、それぞれ解説します。
関連記事:水道光熱費のインボイス請求書の取得・保存方法について徹底解説。
水道料金は見積額で仕入税額控除が受けられる
水道料金は検針に時間がかかるため、課税期間の末日までに確定額がわからないことがあります。この場合は、適正に見積もった金額で仕入税額控除が受けられます。
多くの水道局は適格請求書発行事業者に登録している
多くの地方自治体の水道局はインボイス(適格請求書)発行事業者に登録し、登録番号を取得しています。水道局によっては「媒介者交付特例」を適用して、上水道と下水道の両方の請求を1つの登録番号でまとめて発行するケースもあります。
媒介者交付特例とは、売り手側と買い手側の間に入る媒介者(仲介者)が、売手側に代わってインボイスを発行できる制度です。これにより、利用者は1つのインボイスだけを保存すれば、上水道と下水道の両方の仕入税額控除を受けられます。
水道料金のインボイス(適格請求書)はさまざまな方法で取得できる
水道料金のインボイス(適格請求書)の形式や入手方法は水道局ごとに異なるため、どの書類がインボイスとなるかを確認して、適切に保存することが重要です。
おもな入手方法は、以下のとおりです。
|
料金請求書そのものがインボイス |
通常どおり請求書を受領・保存する |
|
検針票がインボイス |
料金請求書と同じように受領・保存する |
|
専用Webサイトからダウンロードする |
Webサイトに定期的にログインしてダウンロード・保存する手順が必要 |
|
サービス提供事業者に別途申請する |
申請を忘れると満額の仕入税額控除が受けられないため注意が必要 |
水道料金における仕入税額控除の2つの処理方法とは?
水道料金の仕入税額控除は、通常の取引とは少し異なる特徴があります。水道料金の仕入税額控除の基本的な流れは、以下のとおりです。
- 課税期間末日時点での処理
- 確定額が分かった後の処理
水道料金の仕入税額控除を適切におこなうためには、取引先の水道局がどのような方法でインボイス(適格請求書)を発行しているかをあらかじめ確認して、正しい手順での入手・保存が重要です。
ここでは、水道料金の仕入税額控除における2つの処理方法について、それぞれ解説します。
①見積額が記載されたインボイスがない場合
水道光熱費のような継続的におこなわれる取引では、見積額が記載されたインボイス(適格請求書)は一般的に発行されません。この場合の処理は、以下のとおりです。
- 課税期間末日の状況から適正に金額を見積りをもらう
- その見積額にもとづいて仕入税額控除を適用する
- 後日、確定額が記載されたインボイスを受け取り保存する
- 見積額と確定額に差がある場合には、差額を調整する
金額の見積もりは、過去の使用実績や検針日までの使用日数などから合理的に算出します。
②見積額が記載されたインボイスがある場合
水道局から見積額が記載されたインボイス(適格請求書)が発行されるケースもあります。この場合の処理方法は、以下のとおりです。
- 見積額が記載されたインボイスを受け取り保存する
- その見積額にもとづいて仕入税額控除を適用する
- 後日、確定額が記載されたインボイスを受け取り保存する
- 見積額と確定額に差がある場合は調整する
確定額が見積額よりも大きい場合は、その差額分を確定した日の属する課税期間の仕入税額に加算して、確定額が見積額よりも小さい場合は、その差額分を確定した日の属する課税期間の仕入税額から減算します。
インボイス制度を利用した場合の水道料金の仕訳の手順
インボイス制度下での水道料金の仕入税額控除には、適切な仕訳処理が重要です。期末時点では確定額が不明なケースが多いため、合理的に見積もった金額で計上して、後日確定額にもとづいて調整する必要があります。
ここでは、水道料金の具体的な仕訳手順と実際の仕訳例について解説します。
①期末時点での見積額による仕訳
12月決算の会社が12月分の水道料金を15,000円(税抜)と見積もった場合の仕訳例は、以下のとおりです。
|
借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
|
水道光熱費 |
15,000円 |
未払費用 |
16,500円 |
|
仮払消費税 |
1,500円 |
ー |
0円 |
|
合計 |
16,500円 |
合計 |
16,500円 |
この仕訳は、期末時点でまだ水道料金が確定していない場合におこなうものです。過去の使用実績や検針日までの使用日数などから合理的に算出した金額を「水道光熱費」として計上します。消費税分(10%)は「仮払消費税」として別に計上して、合計額を「未払費用」として処理します。
この時点ではインボイス(適格請求書)がなくても、合理的な見積額があれば仕入税額控除が認められる点が重要です。
②確定額にもとづく調整仕訳
確定額が判明した後は、見積額との差異を調整する仕訳が必要です。
翌年1月に確定額が17,500円(税抜)で見積額より大きかった場合の調整仕訳は、以下のとおりです。
|
借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
|
水道光熱費 |
2,500円 |
未払費用 |
2,750円 |
|
仮払消費税 |
250円 |
ー |
0円 |
|
合計 |
2,740円 |
合計 |
2,750円 |
見積額より確定額が大きかった分を追加で「水道光熱費」として計上し、同時に消費税分も追加で「仮払消費税」に計上して、合計額を「未払費用」に追加します。この段階でインボイス(適格請求書)を入手し保存することが必須です。
一方で、確定額が14,500円(税抜)で見積額より小さかった場合の調整仕訳は、以下のとおりです。
|
借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
|
未払費用 |
550円 |
水道光熱費 |
500円 |
|
ー |
0円 |
仮払消費税 |
50円 |
|
合計 |
550円 |
合計 |
550円 |
見積額が確定額を上回っていたため、その差額を「水道光熱費」から減額して、同様に消費税分も減額して「仮払消費税」を修正し、合計分「未払費用」を減らします。見積りが大きかった分を調整する仕訳となるため、確定額が見積額より大きい場合と比較すると借方と貸方が逆になります。
③実際の支払時の仕訳
水道料金が確定して、確定額17,500円を支払う場合の仕訳は、以下のとおりです。
|
借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
|
未払費用 |
19,250円 |
現金預金 |
19,250円 |
|
合計 |
19,250円 |
合計 |
19,250円 |
「未払費用」から確定額を減らして「現金預金」から支払いをおこなったことを記録します。これにより、水道料金の支払いが完了したことになります。
水道料金のインボイス対応は請求書管理サービスで効率化できる
水道料金を含む公共料金のインボイス(適格請求書)対応は、複数の取引先が存在する場合や複数拠点を持つ企業にとって事務負担が大きくなりがちです。そこで、専用の請求書管理サービスの利用がおすすめです。
おすすめの請求書管理サービスには以下のようなものがあります。
- OneVoice公共
- Misoca
- マネーフォワード クラウド請求書
- 弥生のクラウドサービス
請求書管理サービスの活用で、インボイスの取得漏れや保存ミスのリスクを低減して、確実に仕入税額控除を受けられる対応が実行できます。とくに、水道局ごとに異なるインボイスの発行に対応する際に便利です。
まとめ|水道料金のインボイス対応をスムーズにおこなって仕入税額控除を受けよう
本記事では、水道料金とインボイス制度の関係について、処理方法や仕訳例もあわせて解説しました。
水道料金もインボイス制度の対象であり、仕入税額控除を受けるにはインボイス(適格請求書)の保存が必要です。水道料金の特徴として、検針の関係で期末に確定していないことが多い点があります。しかし、合理的な見積額をもとに仕入税額控除を計上して、後で確定額との差額を調整する方法が認められています。
複数の水道局との取引がある場合や複数拠点を持つ企業では、請求書管理サービスの利用で効率化を図ることが可能です。適切なインボイス対応で確実に仕入税額控除を受けて、税負担を適正化することが重要です。










