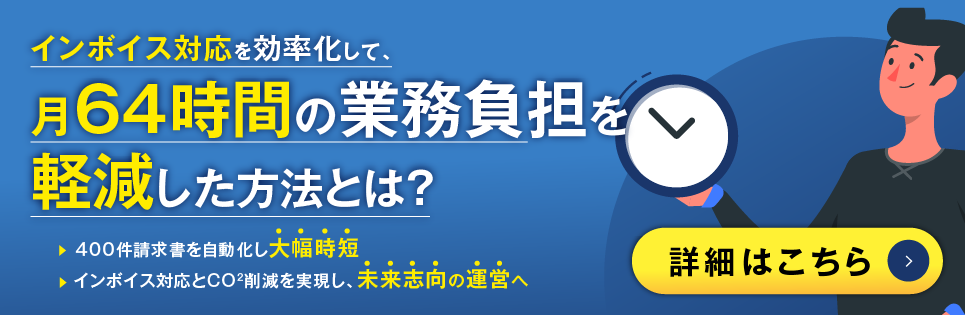タクシー代にインボイスは必要?3万円ルールと経費処理の正解を解説!
更新日:2025.12.21
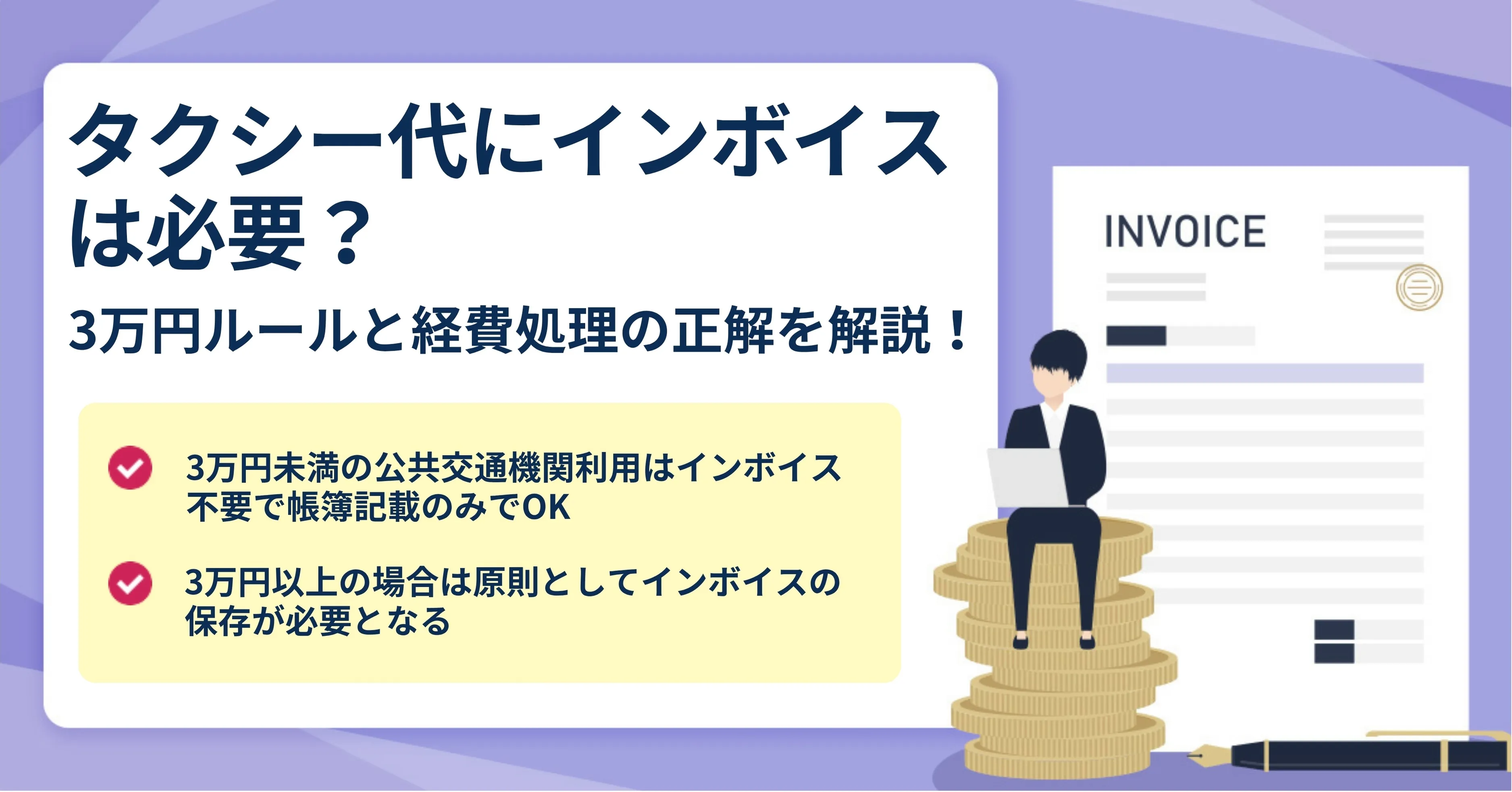
ー 目次 ー
タクシー代のインボイス対応、特に3万円未満の扱いに迷っていませんか?結論から言うと、タクシー代の経費処理においてインボイスは「原則必須」です。 電車やバスに適用される「3万円未満の公共交通機関特例」は、タクシーには適用されません。本記事を読めば、インボイス制度の基本から、タクシー利用時の「公共交通機関特例」により3万円未満ならインボイスが不要となる理由、具体的な経費処理方法まで全てわかります。3万円以上の場合の対応や領収書の扱いなど、あなたの疑問をスッキリ解決します。
はじめに タクシー利用とインボイス制度の基本
2023年10月1日から開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、多くの事業者にとって経費処理のあり方を見直すきっかけとなりました。特に、日常業務や出張などで利用機会の多いタクシー代の取り扱いについては、戸惑う方も少なくないでしょう。この章では、まずインボイス制度の基本的な概要と、タクシー利用がどのように関わってくるのかを解説します。
インボイス制度とは何か簡単に解説!
インボイス制度とは、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式で、正式名称を「適格請求書等保存方式」といいます。事業者が消費税の仕入税額控除を受けるためには、原則として「適格請求書(インボイス)」の保存が必要となります。
適格請求書とは、売手が買手に対して発行するもので、適格請求書発行事業者の登録番号等の情報が記載された請求書や領収書などを指します。(適格請求書には、定められた項目が記載されている必要があります。詳細は後ほど「保存方法と期間」の章で確認していきましょう。)
この制度の導入により、企業は受け取った請求書や領収書が適格請求書の要件を満たしているかを確認し、適切に保存・管理することが求められます。
タクシー代は課税取引?非課税になるケースはある?
タクシーの利用料金は、消費税法上「役務の提供」に該当し、原則として消費税の課税対象となります。つまり、タクシー会社や個人タクシー事業者は、乗客から受け取る運賃に対して消費税を納める義務があり、乗客側(事業者)はその支払った消費税額について、一定の要件を満たせば仕入税額控除の適用を受けることができます。
消費税が非課税となる取引は、土地の譲渡や貸付け、有価証券の譲渡、社会保険医療の給付など、法律で限定的に定められています。タクシーのような旅客運送サービスは、これらの非課税取引には該当しません。
したがって、タクシー代が消費税の非課税取引となるケースは基本的にありません。経費精算においては、タクシー代は課税仕入れとして処理するのが一般的です。
3万円未満ならインボイス不要!公共交通機関特例の内容を解説
インボイス制度が始まり、経費精算のルールも変わりました。特に日常的に利用する機会のあるタクシー代については、「3万円未満ならインボイスが不要」という特例があるのをご存存知でしょうか。この章では、その「公共交通機関特例」について、対象範囲や具体的な取り扱いを詳しく解説します。
公共交通機関特例とは?制度の概要と対象範囲
インボイス制度では、仕入税額控除を受けるために原則として適格請求書(インボイス)の保存が必要です。しかし、一部の取引については、事業者の実務上の負担を考慮してインボイスの保存が免除される特例が設けられています。「公共交通機関特例」もその一つです。
この特例は、税込3万円未満の公共交通機関による旅客の運送について、インボイスの保存がなくとも、一定の事項を帳簿に記載することで仕入税額控除が認められるというものです。インボイスの発行が難しい、または実用的でない公共交通機関の利用を想定しています。
対象となる公共交通機関には、以下のようなものが含まれます。
- 船舶による旅客の運送
- バスによる旅客の運送
- 鉄道(電車など)による旅客の運送
- タクシーによる旅客の運送
これらの交通機関を利用し、その料金が1回の取引につき税込3万円未満であれば、この特例の対象となります。
出張や通勤で使ったタクシー代は特例対象になる?
はい、出張や通勤で利用したタクシー代も、その金額が1回の利用につき税込3万円未満であれば、公共交通機関特例の対象となります。
例えば、従業員が出張先での移動にタクシーを利用し、その代金が5,000円だった場合、会社はそのタクシー代についてインボイスの保存がなくても、帳簿への適切な記載によって仕入税額控除を受けることができます。これは、従業員が立て替えた経費を会社が精算する際にも適用されます。
通勤でタクシーを利用した場合も同様に、税込3万円未満であれば特例の対象です。ただし、通勤手当として定額を支給している場合は、給与としての扱いとなりインボイスは関係ありません。ここでいうのは、実費精算する場合のタクシー利用です。
タクシー代が3万円未満の場合の具体的な取り扱い
タクシー代が1回の利用につき税込3万円未満の場合、インボイスの受領・保存は不要です。仕入税額控除を受けるためには、以下の事項を帳簿に記載する必要があります。
|
記載事項 |
内容・記載例 |
|
取引の年月日 |
例:2023年11月15日 |
|
取引の内容 |
例:タクシー代(株式会社ABC訪問のため) |
|
支払先の氏名または名称 |
例:〇〇交通株式会社、個人タクシーの場合は運転手の氏名など。領収書に記載があれば記載します。不明な場合や記載がない場合は「タクシー代」などと記載することも考えられますが、可能な限り詳細を記録しましょう。 |
|
支払対価の額(税込) |
例:4,800円 |
|
特例の対象である旨 |
例:「公共交通機関特例」、「3万円未満の公共交通機関による旅客の運送」など |
重要なのは、インボイスの保存は不要であっても、経費としての証拠書類である領収書(レシート)は必ず保存しておく必要があるという点です。領収書には、利用日、金額、利用区間(可能な範囲で)、タクシー会社の名称などが記載されているため、税務調査などで経費の妥当性を証明するために不可欠です。帳簿への記載と合わせて、適切に管理しましょう。
タクシー代が3万円以上の場合はどうなる?
タクシー代が3万円未満の場合は「公共交通機関特例」によりインボイスの保存がなくても仕入税額控除が認められるケースがありますが、3万円以上の場合は原則としてインボイス(適格請求書)の保存が必要となります。ここでは、3万円以上のタクシー代に関するインボイス対応と、インボイスがない場合のリスクについて詳しく解説します。
3万円以上のタクシー代のインボイス対応
支払ったタクシー代が税込3万円以上になる場合、仕入税額控除を受けるためには、原則として適格請求書発行事業者から交付されたインボイスを保存する必要があります。タクシー会社や個人タクシー事業者が適格請求書発行事業者であるかを確認し、インボイスの発行を依頼しましょう。多くの場合、レシートがインボイスの要件を満たしているか、別途手書きの領収書などで対応されます。
インボイスとして認められるためには、主に以下の項目が記載されている必要があります。
|
記載が必要な主な項目 |
内容例 |
|
適格請求書発行事業者の登録番号 |
T1234567890123 |
|
取引年月日 |
2023年10月26日 |
|
取引内容(軽減税率の対象品目である旨) |
タクシー代として |
|
税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率 |
10%対象 30,000円 |
|
税率ごとに区分した消費税額等 |
消費税額等 2,727円 |
|
書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 |
〇〇株式会社 |
もし利用したタクシー事業者が免税事業者であるなど、適格請求書発行事業者でない場合はインボイスが発行されません。その場合、原則として仕入税額控除を受けることはできませんので注意が必要です。
インボイスが発行されないタクシー利用時のリスク
3万円以上のタクシー代について、適格請求書発行事業者からインボイスの交付を受けられなかった場合、またはインボイスを紛失してしまった場合、原則としてその取引にかかる消費税の仕入税額控除ができません。これにより、納付すべき消費税額が増加する可能性があります。
具体的には、以下のような影響が考えられます。
|
状況 |
仕入税額控除の可否 |
影響 |
|
インボイス(適格請求書)がある場合 |
可能 |
支払った消費税額を控除できる |
|
インボイスがない場合(※) |
原則不可 |
支払った消費税額を控除できず、消費税の納税負担が増える可能性がある |
※タクシー事業者が免税事業者である場合や、インボイスの要件を満たさない書類しか受け取れなかった場合などを含みます。
経費として計上すること自体は可能ですが、消費税の申告・納税においては不利になる点を理解しておく必要があります。企業によっては、インボイスがない場合の経費精算ルールを別途定めていることもありますので、自社の経理規定を事前に確認しておくことが重要です。
タクシー代の正しい経費処理方法をわかりやすく解説
タクシー代を会社の経費として処理する際には、インボイス制度の導入により、いくつかの注意点があります。この章では、タクシー代に関する領収書やインボイスの取り扱い、具体的な経費処理の手順、そしてインボイスがない場合でも経費として認められるケースについて、わかりやすく解説します。
領収書やインボイスの保存方法と期間
タクシー代の経費処理において、証拠書類となる領収書やインボイス(適格請求書)の適切な保存は非常に重要です。これらの書類は、税務調査の際に経費の正当性を証明するために必要となります。
インボイス制度開始後は、原則として適格請求書の保存が仕入税額控除の要件となります。タクシー会社から受け取るレシート形式の領収書がインボイスの要件を満たしているか確認しましょう。インボイスには、適格請求書発行事業者の登録番号、取引年月日、取引内容(「タクシー代として」など)、税率ごとに区分した消費税額等、書類の交付を受ける事業者の氏名または名称(タクシー利用の場合は省略可能な場合あり)が記載されている必要があります。
これらの書類は、紙で受け取った場合は原則として紙のまま保存します。電子帳簿保存法の要件を満たすことで、スキャナ保存や電子データでの保存も可能です。
保存期間については、法人税法および消費税法により定められています。以下の表を参考にしてください。
|
書類の種類 |
保存期間(原則) |
備考 |
|
適格請求書(インボイス) |
事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間 |
仕入税額控除の適用を受けるために必要 |
|
上記以外の領収書(インボイス非対応) |
事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間 |
経費計上の証拠書類として必要 |
|
帳簿(仕訳帳、総勘定元帳など) |
事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間 |
青色申告の承認を受けている法人で欠損金額が生じた事業年度等は10年間 |
個人事業主の場合も、所得税法に基づき、同様に原則5年間または7年間の保存義務があります(帳簿の種類や白色申告・青色申告により異なる)。
インボイスがある場合の経費処理の手順
タクシー会社から適格請求書(インボイス)を受け取った場合の経費処理は、仕入税額控除を受けるために正確に行う必要があります。基本的な手順は以下の通りです。
- インボイスの確認と保存
受け取った領収書がインボイスの要件(登録番号、適用税率、消費税額等)を満たしているか確認し、適切に保存します。 - 帳簿への記載
会計ソフトや帳簿に、以下の事項を記載します。 - 取引の相手方(タクシー会社)の氏名または名称
- 取引年月日
- 取引内容(例:「タクシー代」「〇〇株式会社への移動」など)
- 支払った対価の額
- インボイスに記載された登録番号
- 適用税率および消費税額
- 仕訳処理
経費科目(通常は「旅費交通費」)で処理します。消費税は仮払消費税として区分します。
(例)タクシー代 5,500円(うち消費税500円)を現金で支払った場合
|
借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
|
旅費交通費 |
5,000円 |
現金 |
5,500円 |
|
仮払消費税等 |
500円 |
この処理により、支払った消費税額を仕入税額控除の対象とすることができます。
インボイスがない場合でも経費にできるケースとは
タクシーを利用した際に、必ずしもインボイス(適格請求書)が発行されるとは限りません。例えば、運転手が個人タクシーで免税事業者の場合などです。インボイスがない場合でも、タクシー代を経費として計上すること自体は可能です。ただし、仕入税額控除の取り扱いには注意が必要です。
- 3万円未満の公共交通機関特例の利用
1回の取引金額が3万円未満の公共交通機関(電車、バス、船舶など)による旅客の運送については、インボイスの保存がなくとも帳簿への一定事項の記載で仕入税額控除が認められる「公共交通機関特例」があります。タクシー代もこの特例の対象となる場合があります。この特例を利用する場合、帳簿には「公共交通機関特例」など、特例の対象である旨を記載する必要があります。 - 経過措置の利用(免税事業者からの仕入れ)
インボイス制度開始から一定期間は、免税事業者やインボイスを発行できない事業者からの課税仕入れについても、一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。タクシー事業者が免税事業者であった場合、この経過措置を適用できる可能性があります。
|
期間 |
仕入税額相当額のうち控除できる割合 |
|
2023年10月1日~2026年9月30日 |
80% |
|
2026年10月1日~2029年9月30日 |
50% |
この経過措置の適用を受けるためには、区分記載請求書等保存方式と同様の事項が記載された請求書等(領収書)の保存と、帳簿への経過措置の適用を受ける旨の記載が必要です。
- 仕入税額控除を諦めて経費計上
上記の特例や経過措置の対象とならない場合や、適用が難しい場合は、仕入税額控除はできません。しかし、業務に関連する支出であれば、領収書(インボイスの要件を満たさないもの)を保存し、帳簿に記載することで、法人税や所得税の計算上、経費(損金)として計上することは可能です。この場合、消費税額を含めた全額を経費として処理します。
いずれの場合も、タクシー代が業務上必要な支出であることを証明できるよう、領収書の保存と適切な帳簿記載が重要です。従業員が立て替えた場合は、立替経費精算書など社内規程に沿った処理を行いましょう。
参考:インボイス制度における事業者登録番号なしの領収書の扱い|経費精算の応用知識| 株式会社JTBビジネストラベルソリューションズ
Q&A|タクシー代のインボイス対応でよくある質問
個人タクシーでインボイスなしの場合はどうなる?
個人タクシーの運転手が「適格請求書発行事業者」の登録を受けていない場合、インボイス(適格請求書)は発行されません。この場合の経費処理と仕入税額控除の扱いは以下のようになります。
まず、支払ったタクシー代が3万円(税込)未満であれば、「公共交通機関特例」の対象となる可能性があります。この特例に該当する場合、インボイスの保存がなくても、帳簿への一定事項の記載(利用年月日、利用区間、支払金額など)のみで仕入税額控除が認められます。この特例は、適格請求書発行事業者以外の事業者からの課税仕入れについても適用されます。
一方、タクシー代が3万円(税込)以上で、運転手が適格請求書発行事業者でない場合、インボイスは発行されません。この場合、原則として仕入税額控除を受けることはできません。ただし、インボイス制度開始後の経過措置として、免税事業者等からの課税仕入れについても一定割合の仕入税額控除が認められる場合があります(期間によって控除割合は異なります)。経費としての計上は、領収書や利用明細などを保存し、帳簿に取引内容を正確に記録することで可能です。
複数人でタクシーを利用した場合のインボイスは?
複数人でタクシーを利用し、一人が代表して料金を支払った場合、インボイスはその支払いを行った人が受け取ることになります。会社経費として精算する際の対応は、状況によって異なります。
代表して支払った従業員が自社の経費として精算する場合、その従業員がインボイス(または3万円未満の場合は公共交通機関特例の適用を受けるための領収書等)を入手し、会社の経理規程に従って処理します。インボイスには、発行事業者の登録番号や適用税率、税額などが記載されている必要があります。
もし、参加者それぞれが経費精算を行う必要がある場合(例:異なる部署の社員が参加し、それぞれが自部署の経費として処理する場合や、取引先との共同利用など)、インボイスは1枚しか発行されないため、工夫が必要です。この場合、代表して支払いインボイスを受け取った人が、他の参加者に対して「立替金精算書」を作成し、インボイスのコピーを添付して渡す方法が考えられます。立替金精算書には、元のインボイスに記載された取引内容(日付、内容、金額、発行事業者の登録番号など)と、誰がいくら負担したかを明確に記載することが重要です。これにより、各参加者がそれぞれの経費として適切に処理できるようになります。
タクシー代は非課税ですか?
結論から申し上げますと、タクシー代は基本的に「課税対象」です。
日本国内でのタクシー利用は、消費税法上の「国内において事業者が事業として対価を得て行う役務の提供」に該当するため、運賃には標準税率である10%の消費税が含まれています。
- 勘定科目:一般的に「旅費交通費」を使用します。
- 税区分:「課税仕入(10%)」として処理します。
- インボイス:仕入税額控除を受けるためには、適格請求書(インボイス)の発行に対応した領収書等の保存が必要です。
なお、海外出張時の現地タクシー利用などは「不課税(消費税の対象外)」となる場合がありますが、国内移動であれば「課税」と覚えておいて問題ありません。
まとめ
タクシー代の経費処理においては、金額やインボイスの有無によって対応が大きく異なります。
3万円未満であれば「公共交通機関特例」により、インボイスがなくても帳簿記載で対応可能です。一方で3万円以上になると、原則としてインボイスの保存が求められます。
今回ご紹介したポイントを押さえておけば、慌てずに正しく処理できますので、ぜひ日々の業務にお役立てください。