課税事業者がインボイス制度に登録しないとどうなる?登録手順や活用できる制度も解説
更新日:2025.12.06
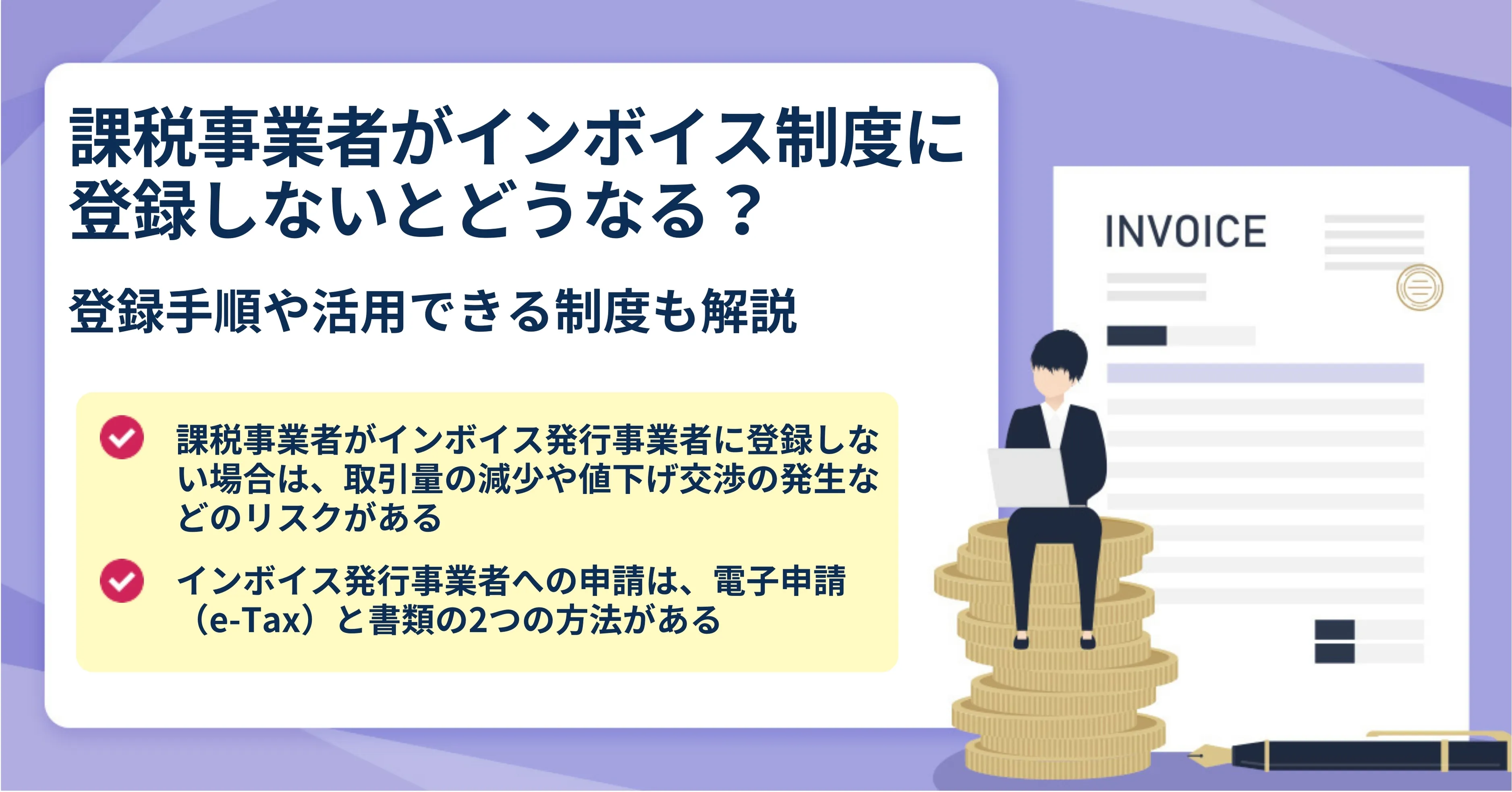
ー 目次 ー
2023年10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されて、多くの事業者に影響を与えています。課税事業者であっても、インボイス制度の対応をおこなう場合にはインボイス(適格請求書)発行事業者への登録が必要です。
もし、課税事業者がインボイスに登録しない場合は、取引先との関係性に影響を与えるおそれがあり、取引量の減少や値下げ交渉の発生などのリスクが懸念されます。
このようなことから、インボイス制度に登録する場合は、基本的なルールだけでなく、登録しない場合のリスクや申請手順などを正しく理解しておくことが大切です。
本記事では、課税事業者がインボイス制度に登録しない場合の影響と登録手順、活用できる制度について解説します。
インボイス制度についておさらい
2023年10月1日から開始されたインボイス制度は、消費税に関する請求書の記載方式や計算方法などを定めたルールです。この制度は、複数税率に対応した消費税の計算をより正確におこなうための仕組みであり、売上にかかった消費税額から仕入れにかかった消費税額を差し引ける「仕入税額控除」を受けるための要件を定めた新しいルールとなります。
ここでは、インボイス制度について解説します。
インボイス制度のおもな内容
インボイス制度は正式には「適格請求書等保存方式」と呼ばれ、軽減税率の導入にともなう複数税率に対応し、消費税の計算をより適正におこなうために導入されました。
この制度では、売り手側はインボイス(適格請求書)の発行と写しの保存が必要です。一方、買い手側はインボイスを受け取って保存することで仕入税額控除が受けられます。
ただし、インボイスは「インボイス(適格請求書)発行事業者」に登録した事業者のみ発行できるルールが定められているため、注意が必要です。
インボイス(適格請求書)の記載事項
インボイス(適格請求書)の記載事項には、従来の請求書から追加された項目があり、記載要件を満たすことで取引先が仕入税額控除を受けられるようになります。インボイスのおもな記載事項は、以下のとおりです。
- 発行者の氏名または名称および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率対象品目の場合はその旨も記載)
- 税率ごとに区分した合計金額および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額
- 受領者の氏名または名称
インボイスの「登録番号」はインボイス発行事業者への登録申請をした際に付与される「T+13桁の番号」です。また、税率は標準税率(10%)と軽減税率(8%)を明確に区分し、税率ごとに消費税額を個別に計算・記載しなければなりません。
これらの項目に記載漏れや誤りがあると仕入税額控除が受けられなくなるため、注意が必要です。
課税事業者がインボイス制度に登録しないとどうなる?リスクや影響を解説
課税事業者がインボイス(適格請求書)発行事業者に登録しない場合は、取引量の減少や値下げ交渉の発生などのリスクがあります。インボイス発行事業者への登録は任意であるものの、取引状況や将来の事業展開を考慮した判断が重要です。
ここでは、課税事業者がインボイス制度に登録しないとどうなるのか、リスクや影響について解説します。なお、以下の関連記事では、インボイス制度による免税事業者への影響について解説しているため、あわせて参考にしてください。
関連記事:インボイス制度による免税事業者への影響は?経過措置や特例もあわせて解説
①取引量が減少する
取引先は、仕入税額控除が受けられる事業者との取引を優先する傾向があります。そのため、インボイスに登録していない課税事業者との取引は避けられる可能性が高いです。
この影響は新規取引の獲得が困難になる可能性があるだけではなく、長期的な取引関係でも見直しの対象になることがあります。とくに、取引先が大企業や公共機関の場合は、税務コンプライアンスを重視する傾向があるため、インボイス制度の未登録業者との取引を避ける可能性が高いでしょう。
②価格交渉が発生する
取引先は、仕入税額控除が受けられない分の負担を価格に反映するよう求めてくることがあります。
この影響を緩和するために、国税庁は免税事業者との取引をおこなっても控除割合が変わらない経過措置を実施しています。この経過措置を活用すれば、一定期間までは消費税の負担が軽減されるようになっているため、価格交渉の影響は現段階では大きくないといえるでしょう。
③取引条件が変更になる
課税事業者がインボイス制度に登録しないと支払条件が厳しくなり、ほかの取引先の中での優先順位が下がるおそれがあります。優先順位が下がってしまうと、発注量や発注頻度の減少となり、結果的に事業売上の低下につながりかねません。
このように、インボイス制度に登録しないことで取引条件に影響を与える可能性があります。
インボイス(適格請求書)発行事業者に登録する手順
インボイス(適格請求書)発行事業者への申請は、電子申請(e-Tax)と書類の2つの方法があります。電子の場合はいつでもどこでも申請ができ、また登録までの期間が約1か月と、書類での手続きと比べて短い期間で済みます。
このようなことから、申請をする場合には、電子申請(e-Tax)での手続きがおすすめです。なお、電子申請の手続き手順は以下のとおりです。
- 申請書の準備
- 提出
- 審査と登録
準備も多くなく、「適格請求書発行事業者の登録申請書」と本人確認書類(マイナンバーが好ましい)を用意していればすぐに手続きが可能です。
登録完了後には登録通知書が発行され「T」からはじまる13桁の登録番号が付与されます。この登録番号は、インボイスを発行する際に記載する必要があるため、忘れないためにも大切に保管しましょう。
関連記事:インボイス制度の登録方法とは?申請のやり方や注意点を解説
事前の申請があればインボイス制度に登録後も簡易課税制度が利用できる
対象期間の課税売上高が5,000万円以下で、インボイス制度に登録する前に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、簡易課税制度を利用できます。
簡易課税制度では「納税額=売上税額-(売上税額×みなし仕入率)」で納税額を算出します。みなし仕入率を採用して、簡易的に消費税の計算ができるため、事務面での負担を大幅に軽減可能です。なお、みなし仕入率は業種ごとに異なり、以下のとおりです。
- 第1種事業(卸売業): 90%
- 第2種事業(小売業): 80%
- 第3種事業(製造業など): 70%
- 第4種事業(サービス業など): 60%
- 第5種事業(不動産業など): 50%
- 第6種事業(金融・保険業など): 40%
注意点として、簡易課税制度は一度選択してしまうと、原則として2年間は継続して利用しなければなりません。実際の仕入率がみなし仕入率よりも高い場合は、本則課税の方が有利な可能性があるため、事前に計算して比較しておくと良いでしょう。
なお、簡易課税制度を選択している場合でもインボイス(適格請求書)の発行義務はあります。ただし、仕入税額控除を利用しないため、仕入れ先からのインボイスの保存は不要です。
まとめ|自社の事業状況に合わせてインボイス制度に登録するか判断しよう
本記事では、課税事業者がインボイス制度に登録しない場合の影響と登録手順、活用できる制度について解説しました。
課税事業者がインボイス制度に登録しない場合、取引量の減少や値下げ交渉などのリスクがあります。一方で、登録した場合、消費税の申告・納付義務が生じ、税務面・事務面の双方で負担が増加します。
インボイス制度の導入にともなって、特例や経過措置、また簡易課税制度などのさまざまな制度の利用も可能です。このようなことから、インボイス制度への登録は、自社の事業や取引先の状況、特例や経過措置などの活用を踏まえて慎重に検討しなければなりません。










