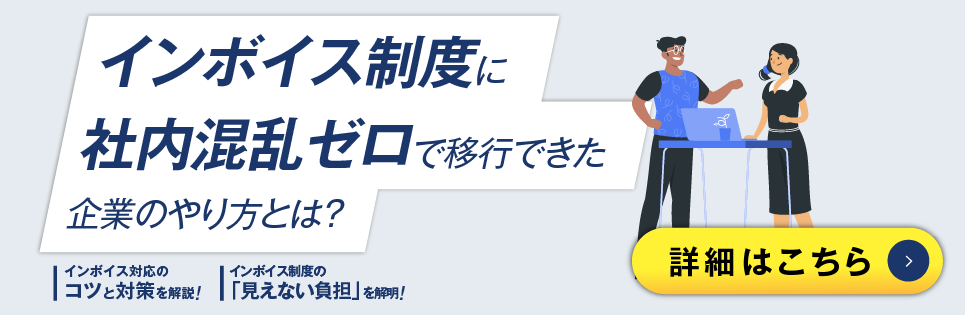個人事業主はインボイス制度に登録すべき?影響や登録を判断するポイントも紹介
更新日:2026.01.15
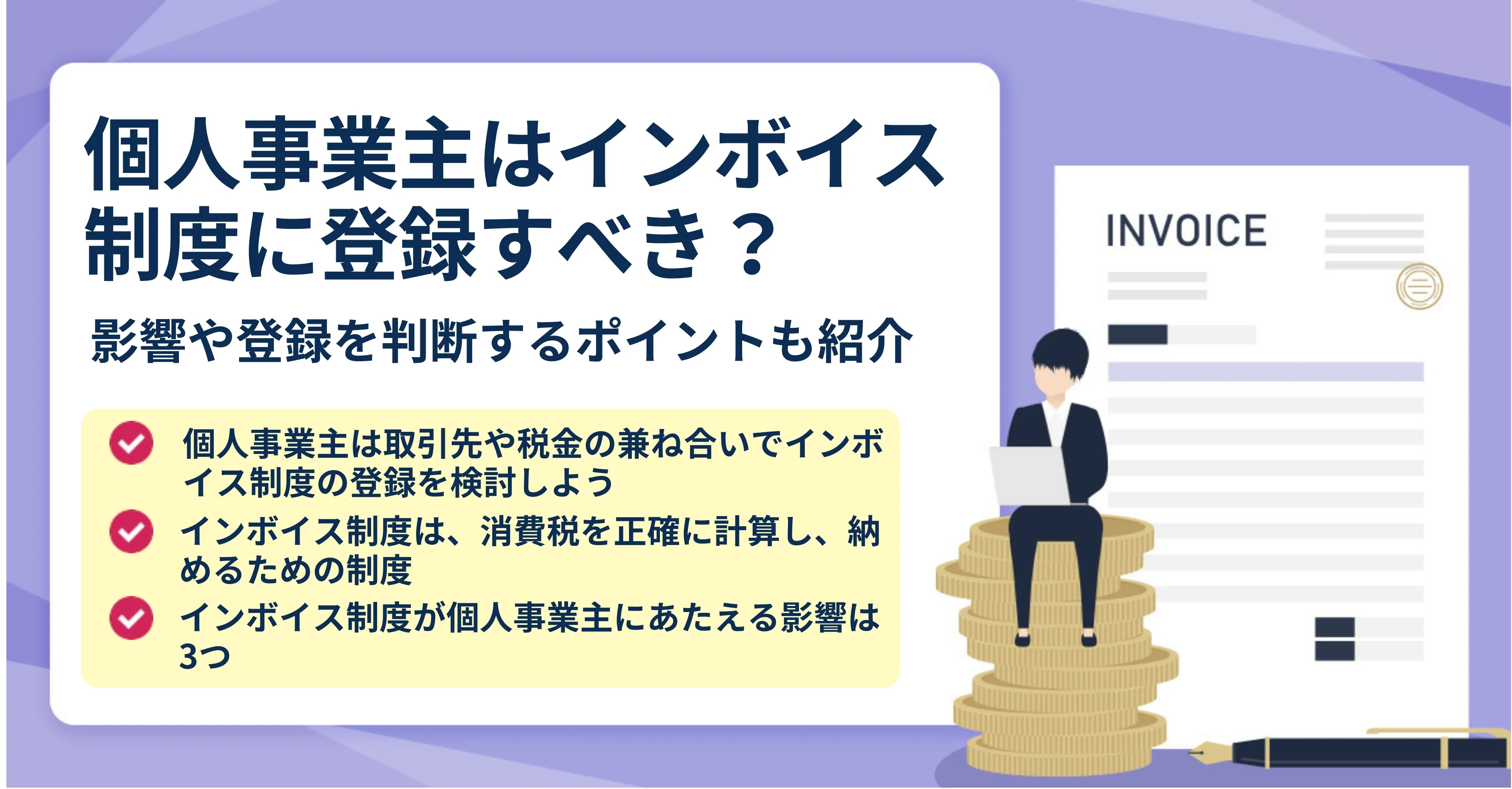
ー 目次 ー
2023年10月施行の「インボイス制度」はすべての事業者に影響を与える新しいルールです。これは個人事業主や副業も例外ではなく、インボイス制度の登録をめぐって、さまざまな影響を受ける可能性があります。
影響によっては現在の事業運営が厳しくなったり、事務負担が大きくなったり、ということが考えられるため、これからインボイス制度の登録を検討していれば、全体像やルール、またメリット・デメリットを知っておく必要があるでしょう。
本記事では、個人事業主はインボイス制度に登録すべきかについて、影響や登録を判断するポイントを解説します。
【結論】個人事業主は取引先や税金の兼ね合いでインボイス制度の登録を検討しよう!
インボイス制度では、取引当事者どちらもインボイス制度に登録しておく必要があります。これはインボイス(適格請求書)の発行をおこなうために、インボイス制度の登録番号が必要であるためです。
もし、登録されていなければ、インボイスの発行・保存ができず、自身だけでなく取引先も「仕入税額控除」が適用されません。このようなことから、取引においてインボイス制度に登録している事業者が優遇される可能性が高くなり、高いでしょう。既存の取引であっても打ち切られるリスクも懸念されます。
上記の状況を踏まえて、個人事業主は取引先や税金の兼ね合いでインボイス制度の登録を検討する必要があります。
インボイス制度とは?個人事業主に与える3つの影響
2023年10月に施行された「インボイス制度」は、事業者が消費税を正確に計算し、納めるための制度です。具体的には、請求書の記載や扱い方、また消費税の計算方法などを定めたルールとなっています。
このインボイス制度は、個人事業主にも大きな影響を与えます。この内容によってはインボイス制度の登録が必要な事業者も存在するため、全体的な影響を把握しておくことが大切です。
ここでは、インボイス制度について、個人事業主に与える3つの影響を解説します。
- インボイス(適格請求書)の発行・保存が求められる
- インボイス発行事業者になると消費税の免除がなくなる
- 仕入税額控除にはインボイス(適格請求書)が必要となる
①インボイス(適格請求書)の発行・保存が求められる
インボイス制度は「インボイス(適格請求書)」をもとに消費税額の計算を定めたルールです。このようなことから、インボイスの発行・保存が定められています。
もし、インボイス制度に登録している事業者と取引をおこなう際には、通常の請求書ではなく、インボイスの発行・保存が必要です。
②インボイス発行事業者になると消費税の免除がなくなる
インボイス制度ではインボイスの発行・保存に、インボイス発行事業者への登録が要件となっています。
ただ、このインボイス発行事業者は課税事業者であるため、消費税の申告・納付が必要です。これまでに免税事業者であった個人事業主であっても、このルールが適用されることから注意が必要です。
③仕入税額控除にはインボイス(適格請求書)が必要となる
インボイス制度では、売上の消費税額から仕入で支払った消費税額を差し引ける「仕入税額控除」が受けられます。ただ、仕入税額控除にはインボイス(適格請求書)の発行・保存が必要です。
このような背景から、インボイスが発行できる事業者の場合に優遇される可能性があります。
個人事業主がインボイス制度に登録するメリットとは?
もしインボイス制度に登録していない場合には、自身が抱える取引先や事業規模などによって、インボイス制度の登録を検討する必要があります。消費税の申告・納付が必要になる一方で、関係性の維持や信頼感の向上などのメリットが得られます。
ここでは、インボイス制度に登録する場合のメリットについて解説します。
①課税事業者の取引先との関係性を保ちやすい
インボイス制度に登録すれば、取引先は仕入税額控除を受けることが可能です。仕入税額控除は消費税の負担を軽減する可能性が高く、インボイス制度に登録していることによって良好な関係性を保ちやすくなります。
②課税事業者との新規取引に繋がりやすい
課税事業者との新規取引では、インボイス制度に登録しているかを確認されるケースがあります。この際に、もしインボイス制度に登録していれば、新規取引が成約となる可能性が高められます。
③事業者としての信頼感が増す
インボイス制度は税務上の不正やミスを防ぎ、透明性のある取引ができる環境を整えることが目的となっています。また、国税庁のホームページによって、登録した事業者の氏名や登録番号などの情報を公表しています。
このような背景から、インボイス制度に登録していれば事業者としての信頼感を増すことが可能です。
【注意点・対策も】個人事業主がインボイス制度に登録するデメリットとは?
インボイス制度には登録するメリットがある一方で、デメリットも存在します。内容によってはインボイス制度に登録しないほうが良い事業者もいるため、事業の規模や取引先の状況などを把握しておく必要があるでしょう。
なお、インボイス制度には影響を緩和するための特例や経過措置なども実施されています。そのため、デメリットだけでなく、デメリットへの対策も理解してくことが大切です。
ここでは、インボイス制度に登録するデメリットとその注意点や対策を解説します。
①課税事業者になるため、課税売上に関係なく消費税の申告・納付義務が発生する
通常、一定期間の課税売上が1,000万円以下の事業者であれば、消費税の申告・納付義務は免除されます。しかし、インボイス制度に登録すれば、課税事業者になるため、課税売上と関係なく消費税の申告・納付が必要になります。
消費税の申告をおこなうための手続きの手間や、消費税を納付するための経済的な負担があるため、このデメリットは理解しておかなければなりません。
なお、2026年9月までは、売上税額の一律2割を納付とする「2割特例」が実施されています。特例を活用すれば、税負担・事務作業の軽減が図れます。
関連記事:【何パーセント?】インボイス制度の2割特例を解説!免税事業者の仕入に関する経過措置も
②経理業務の負担が大きくなる
インボイス制度に登録した場合、インボイス(適格請求書)の発行・保存をしなければなりません。このインボイスは従来の記載方式と異なることから、発行時には記載方式にあわせて請求書を作成しなければならず、また保存時には記載方式を満たしているかの確認が必要です。
もし自身で経理業務に対応していれば、その業務量が増えてしまいます。
ただ、経理業務の負担に関しては、インボイス制度に対応したシステムやサービスの利用で軽減することが可能です。取引先への迅速な対応も可能になるため、自社の状況にあわせて導入を検討しても良いでしょう。
関連記事:インボイス制度が与える経理業務への影響とは?【請求書の会社インボイスが解説】
個人事業主がインボイス制度に登録する際のポイント
もし、これからインボイス制度の登録を検討していれば、おさえておきたいポイントを把握しておきましょう。
最後に、個人事業主がインボイス制度に登録する際のポイントについて、解説します。
①課税対象となる事業状態
消費税の課税対象となる期間は、個人事業主の場合、原則的に前々年の1年間です。また、この期間とは別に「特定期間」も定められており、前年の1〜6月までの期間も存在します。どちらかの期間中で課税売上が1,000万円を超えていた場合には課税事業者となります。
もし課税事業者となる場合には、インボイス制度の登録有無に限らず、消費税の申告・納付が必要です。
そのため、課税事業者となり得る事業状態であれば、インボイス制度の登録を検討しても良いでしょう。
②取引先の状態
インボイス(適格請求書)の発行・保存には、取引当事者のどちらもインボイス制度に登録している必要があります。そのため、取引先によっては仕入税額控除の適用のために、インボイス制度への登録を求めている可能性があります。
このような取引先を多く抱えていれば、インボイス制度の登録を検討しても良いかもしれません。
③氏名の公表
インボイス制度に登録すると、国税庁のホームページで氏名や登録番号が公表されます。これは登録したすべての事業者が対象であるため、公表しないという選択肢がありません。
もし、公表されたくない状況である場合には、インボイス制度の登録は避けるべきでしょう。
参考:国税庁「インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイト」
まとめ|個人事業主はインボイス制度への登録を検討し、計画を立てよう!
本記事では、個人事業主はインボイス制度に登録すべきかについて、影響や登録を判断するポイントを解説しました。
インボイス制度は消費税にまつわる制度であり、個人事業主にも影響を与えます。とくに、取引先に関することはこれからの事業運営を大きく左右する問題であるため、この機会にインボイス制度への登録を検討することが大切です。
なお、もしインボイス制度の登録をおこなう場合には、登録するための手続きや請求書の記載方式などのルールの理解も必要です。登録する前に基本的な知識は知っておくようにしましょう。