軽減税率とインボイス制度の関係性とは?請求書の書き方や注意点を解説
更新日:2025.03.27
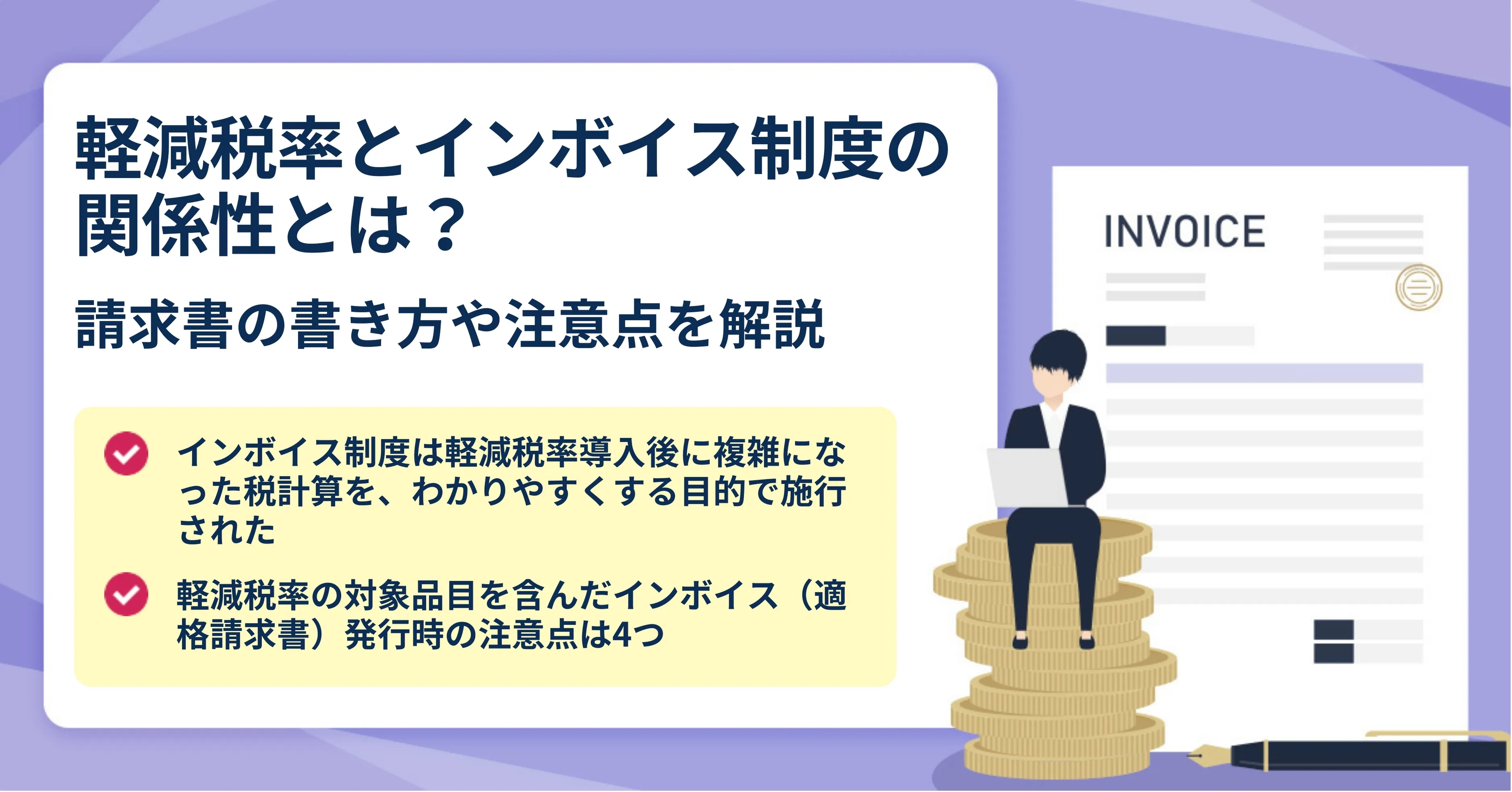
ー 目次 ー
2019年10月に導入された軽減税率は、消費者にかかる税負担を減らす目的として、食料品や新聞などの特定品目の税率を増税の対象に含めない(8%にする)制度です。この軽減税率が導入され、商品ごとの税率が異なるようになったため、事業者は消費税の計算が複雑になりました。
このような背景もあり、2023年に複雑になった消費税を、事業者が正しく納めるための目的で「インボイス制度」が施行されました。この制度では消費税にまつわる計算方法や請求書の書き方などのさまざまなルールに影響を与えています。
本記事では、軽減税率とインボイス制度の関係性や請求書の書き方を解説します。
インボイス制度は、軽減税率導入後も消費税を正しく納税するための制度!
2019年の軽減税率の導入で、1つの請求書に複数の税率の商品が混在することになり、事業者にとって消費税の計算が複雑になりました。
このような背景のなかで「インボイス制度」が施行されました。この制度は請求書の記載方法や消費税の計算方法などのルールを定めた制度であり、軽減税率の導入後も事業者が消費税を正しく納税できるようにする目的があります。
ここでは、インボイス制度と軽減税率の概要について解説します。
軽減税率とは、増税による消費者の負担を軽減するルール
軽減税率は、2019年10月1日より施行された消費税増税による消費者の負担を軽減するための制度です。飲食料品や新聞など、生活に欠かせないものを軽減税率の対象にすることで、消費者の負担軽減を目的としています。
軽減税率の対象品目は、以下のとおりです。
- 一般的な飲食料品
- テイクアウト・宅配食品
- 学校給食・有料老人ホームなどで提供される飲食料品
- 定期購読の契約をした週2回以上発行される新聞
- 条件を満たした一体資産
なお、軽減税率では同じ飲食物でもイートインとテイクアウトで税率が異なります。両方の方式を採用している事業者は、とくに注意が必要です。
インボイス制度とは、事業者が消費税を正確に納めるためのルール
インボイス制度は、2023年10月1日より施行された複数税率でも事業者が消費税を正確に納めるための制度です。
インボイス制度では「適格請求書等保存方式」を採用しており、この方式にしたがって記載された書類を「インボイス(適格請求書)」と呼びます。インボイスでは取引内容を軽減税率・標準税率にわけ、それぞれの税率ごとに消費税額や取引の合計金額を記載しなければなりません。
インボイスが適切に発行・保存されていれば、売上にかかる消費税から仕入れに支払った消費税を差し引ける「仕入税額控除」が適用されます。
なお、インボイス(適格請求書)を発行するためには、事前に税務署へ「適格請求書発行事業者」の登録が必要です。
軽減税率の対象品目を含んだインボイス(適格請求書)の書き方
インボイス制度では、軽減税率の対象品目を含んだインボイス(適格請求書)を発行する際に、記載するべき項目が定められています。軽減税率の対象品目が明確になるようルールもあるため、理解しておくことで作成時の混乱を防げるでしょう。
ここからは、軽減税率の対象品目を含んだインボイス(適格請求書)の書き方やテンプレートを紹介します。
- 請求書発行者の氏名や名称
- 登録番号
- 取引年月日
- 取引内容
- 取引金額
- 請求書を受け取る事業者の氏名や名称
|
請求書 取引先企業名 自社の企業名 ご請求金額 ¥2,180 -(税込)
※印は軽減税率の対象 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①請求書発行者の氏名や名称
インボイス(適格請求書)には、税務署に申請した企業の正式名称や個人事業主の本名を記載しましょう。正式名称が記載されていない場合、インボイスの要件を満たせません。
インターネット上の取引であっても、ペンネームや屋号ではインボイスを発行できないため注意しましょう。
②登録番号
税務署に適格請求書発行事業者として申請することで、事業者ごとに異なる登録番号が発行されます。
登録番号は「T」と「13桁の数字」から構成されており、法人の場合は法人番号、個人事業主の際は法人番号と被らない数字となっています。
③取引年月日
取引年月日は、取引をおこなった日を記載しましょう。ひとつの書類で複数の取引をまとめて請求する際は、取引ごとの日付を記載する必要があります。
なお、取引年月日と請求書の発行日は異なるため、混同しないよう注意が必要です。
④取引内容
取引内容には、取引先に提供したサービスや商品の内容を記載しましょう。
軽減税率の対象品目には、商品名に「※」をつけることが一般的です。あわせて、備考欄に「※は軽減税率の対象品目」と記載しておけば、取引先も判断しやすくなります。
⑤取引金額
取引金額には、商品・サービスの対価として受け取る金額を記載しましょう。
インボイス(適格請求書)では商品金額以外にも、税率ごとの合計金額や消費税額も必要です。
⑥請求書を受け取る事業者の氏名や名称
インボイス(適格請求書)には、取引先が適格請求書発行事業者として申請した正式名称を記載します。
自社の判断で記載すると誤っている可能性があるため、取引先に確認しておきましょう。
軽減税率の対象品目を含んだインボイス(適格請求書)発行時の注意点とは?
インボイス(適格請求書)は、事前に適格請求書発行事業者として登録していなければ発行できません。また、商品ごとの税率が明確になるよう、軽減税率の対象品目に「※」をつけるような注意点もあります。
ここからは、軽減税率の対象品目を含むインボイス(適格請求書)発行時の注意点を解説します。
①発行には事前に適格請求書発行事業者として登録が必要
インボイス(適格請求書)の発行が可能なのは、適格請求書発行事業者のみです。
このことから、インボイスを発行したい事業者は、事前に税務署へ適格請求書発行事業者の登録をしておく必要があります。申請することで登録番号が発行され、インボイスの記載項目を満たせるようになります。
登録番号の発行には、e-Taxの申請であれば1か月、郵送の場合は1か月半ほどかかるため、急ぎの場合はe-Taxを選びましょう。
関連記事:インボイス制度の登録方法とは?申請のやり方や注意点を解説
②商品ごとの税率を明確にする
請求書では、商品ごとの税率を明確にしましょう。軽減税率の対象品目には、商品名の後ろに「※」をつけるか、税率別で分けて記載することが一般的です。
記号を使用する際は、「※は軽減税率対象品目」と備考欄に記載することで、取引先も税率を判断しやすくなります。
③税率ごとの消費税金額を明記する
インボイス制度では請求書に、税率ごとの商品の合計金額と、消費税額を明記する必要があります。1枚の請求書に複数の税率の商品が混在する場合は、必ず消費税を分けて記載しましょう。
なお、請求書内の税率が1つのときは、商品の適用税率が明確であれば、税率ごとに記載欄をわける必要はありません。
④消費税の端数計算は税率ごとに1回まで
インボイス制度施行後は、消費税の端数計算の回数が税率ごとに1回までと定められています。
端数計算の方法は、「切り捨て」「切り上げ」「四捨五入」から事業者が選択できます。ただし、一般的には切り捨てが採用されています。
まとめ|インボイス(適格請求書)発行時は軽減税率の対象品目を明確にしよう
本記事では、軽減税率とインボイス制度の関係性や請求書の書き方を解説しました。
インボイス(適格請求書)を発行する際は、軽減税率の対象品目が明確になる記載方法を選ぶ必要があります。ほかにも、インボイス制度施行のタイミングで消費税の端数計算の回数や請求書の記載項目が変更されており、これらのルールやポイントを理解しておかないと取引先からの信頼を失うおそれがあります。
このように軽減税率に関するルールは細かい点も多いため、もし軽減税率を含めたインボイスの発行に悩む際には本記事を参考に書類を作成しましょう。










