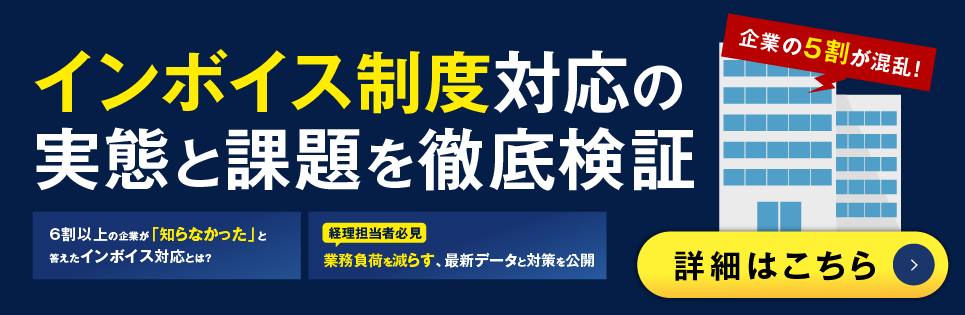インボイス制度の農協特例はずるい?理由や特例の内容を解説
更新日:2025.12.24
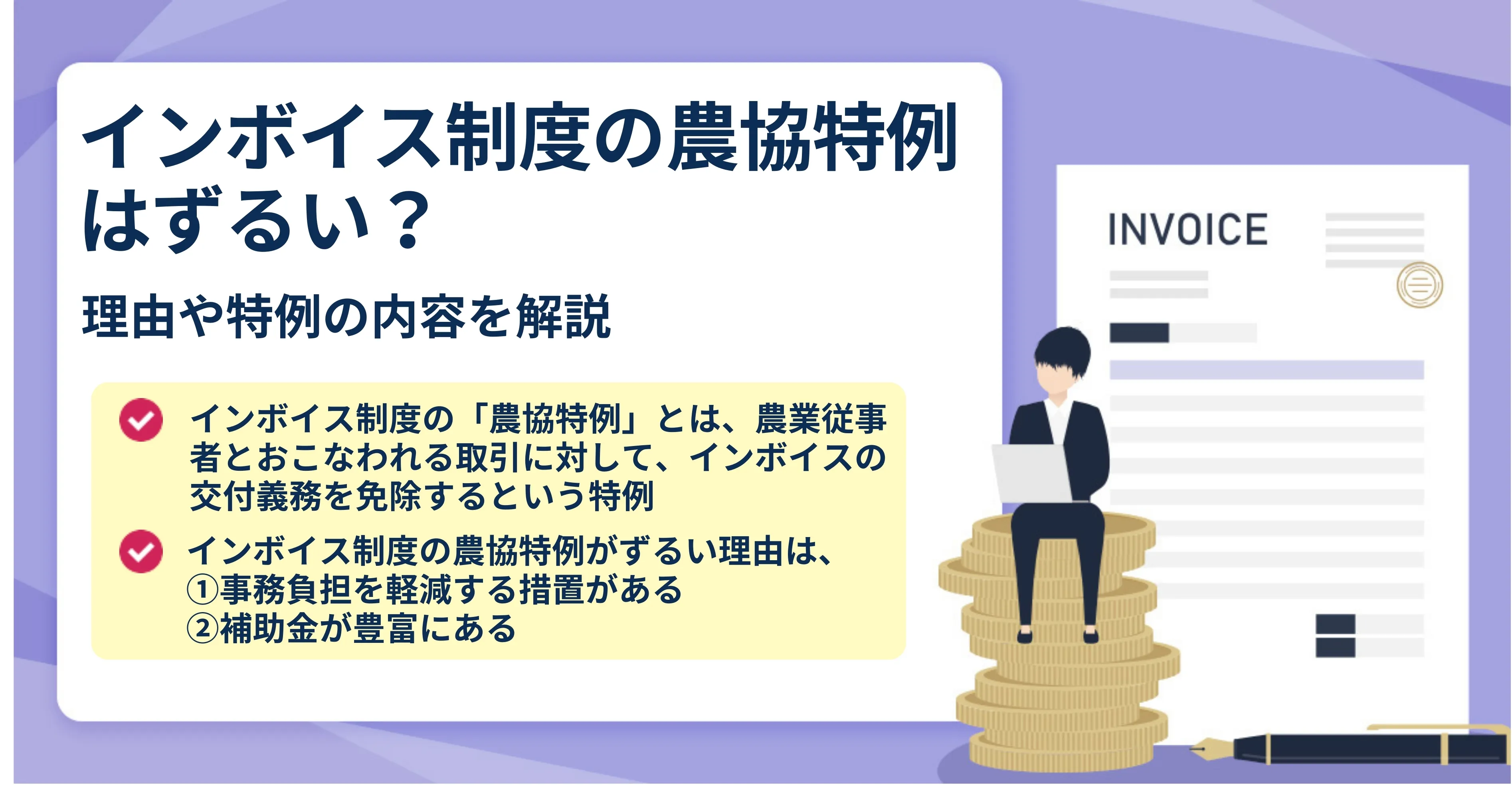
ー 目次 ー
2023年10月、消費税にまつわる計算や請求書の作成方法などを定めた「インボイス制度」がスタートしました。このようななかで、政府は事務負担軽減の目的から農業従事者との取引に対して「農協特例」を実施しています。
しかし、この特例の内容が原因で大きな反感を買ってしまい、一部の事業者からは「ずるい」という声が挙がっています。ただ、これらの声は農業従事者の実態や、日本が抱える課題を正しく理解できていない可能性が高いといえるでしょう。
インボイス制度の施行によって大きくルールが変わったなかで、誤解によって事業運営に支障を来たさないためにも、正しい情報を理解しておくことが大切です。
本記事では、インボイス制度の農協特例は「ずるい」という声に対して、その理由や特例の内容を解説します。
インボイス制度の農協特例とは、インボイスの交付義務を免除するもの
インボイス制度の「農協特例」とは、農業従事者(農協の組合員)とおこなわれる取引に対して、インボイス(適格請求書)の交付義務を免除するという特例です。この特例によって、農業従事者と取引をおこなった買い手は、その事業者が所属の農協が発行する書類をもって仕入税額控除が受けられます。
このように農協特例を利用すれば、買い手・農業従事者の双方の事務負担を抑えることが可能です。
なお、この特例は農業従事者のインボイス制度の登録有無を問わず、買い手が農協に所属する事業者と取引をおこなえば適用されます。ただ、以下のような要件も定めており、要件を満たしていない場合には特例が適用されないため注意が必要です。
- 無条件委託方式による販売
- 代金を共同計算方式によって精算
インボイス制度の農協特例がずるい理由とは?その反論も紹介
インボイス制度の農協特例は、農業従事者の事務負担を軽減するために講じられているものです。
ただ、農業と関係のない事業者からは「ずるい」という声が挙がっています。このような声は特例の主旨や農業が抱える課題などを適切に理解できていない可能性が高いと考えられるでしょう。
ここでは、インボイス制度の農協特例がずるい理由について、解説します。
- 事務負担を軽減する措置がある
- 補助金が豊富にある
①事務負担を軽減する措置がある
インボイス制度の農協特例は、農業従事者の事務負担を軽減するための特例です。一方で、農業と関係のない事業者に対してはこのような特例や措置が少なく、これが要因で「ずるい」という声が挙がっています。
ただ、農業従事者は農産物を生産したり、出荷したりなどのさまざまな負担があります。このようななかでインボイス制度が施行されたことによって、農業従事者により大きな負担を与える懸念がありました。
農協特例は、上記のような懸念点を解決するために実施されたものとなります。
②補助金が豊富にある
農業に関する事業には、さまざまな補助金が国や地方自治体から提供されています。一般的なほかの業種の事業と比べると、大きなアドバンテージがあるように見受けられるでしょう。
ただ、提供されている補助金は、日本の自給率や農業人口の減少などの課題を解決するために実施されている背景があります。補助金は農業を活性化させるための支援であり、制度主旨や農業の課題を的確に捉えなければなりません。
インボイス制度において、このように「農業が優遇されている」という偏見から「ずるい」といわれているおそれがあります。しかし、上記のとおり、農業に関して提供される補助金は、日本の大きな課題を解決するためのものという点を理解することが大切です。
インボイス制度に対して農業従事者はどうするべき?判断すべき要素を紹介
農業従事者には農協特例があるため、インボイス制度の登録が不要と考える事業者は少なくありません。しかし、農協特例の内容でカバーできていない課題や問題もあるため、事業の内容や取引先によっては登録したほうが良いケースも存在します。
このようなことから、必ず自身の事業状況を確認し、インボイス制度を登録すべきかの検討を慎重におこないましょう。
ここでは、インボイス制度に対して農業従事者の判断すべき要素を、紹介します。
①課税対象となる売上はどのくらい?
インボイス制度の「適格請求書発行事業者」は、消費税の申告・納付が求められます。これまで免税事業者であった場合には消費税の申告・納付が不要であるため、インボイス制度への登録は注意すべきポイントといえるでしょう。
そもそも、課税事業者あるいは免税事業者の判断は、基準となる期間内の課税売上によって決められます。課税売上が1,000万円未満の場合には免税事業者、1,000万円超の場合には課税事業者となります。
上記のような点から、まず事業における課税売上がどのくらいあるのかを確認しましょう。
もし、課税事業者であった場合には、インボイス制度の登録にかかわらず消費税の申告・納付が必要であるため、事務的な負担は大きくは変わりません。一方で、免税事業者であった場合には税負担と事務負担の増加が想定されるため、インボイス制度の登録をしない選択肢もあります。
②取引先の数と状況は?
農業を運営するにあたって、肥料や機材などの仕入れは必ずおこなうものです。インボイス制度では、この仕入れで支払った消費税を売上にかかる消費税から差し引ける「仕入税額控除」が受けられます。
上記のような点から、取引相手にインボイス制度に登録した事業者が多ければ、自身も登録しておくと、仕入税額控除が適用されて、税負担の軽減が図れる可能性があります。必ず自身と取引をしている取引先の数や状況を確認しておきましょう。
インボイス制度の登録が必要な場合は、サービスやシステムに頼るのもアリ!
もし、インボイス制度に登録した場合、インボイス(適格請求書)のフォーマット作成や、インボイスの管理ができる環境を整えておく必要があります。
近年では、帳票の作成・送付などの代行サービスや、帳票の作成・送付・管理が自動化できるシステムなどが提供されています。これらのサービス・システムを活用すれば、自身の事業運営に集中できる環境が整うでしょう。
ただ、サービスによって料金や解決できるニーズ・悩み、機能・サービスやサポートなどが異なります。そのため、自身の事業や取引先の状況にあったものを見つけることが大切です。代表的なサービス・システムのなかから、おすすめのものを以下にピックアップしています。
- OneVoice明細
- @トバス
なお、導入する前に、税理士やサービスの専門スタッフなどに相談しておくと失敗するリスクを減らせます。
関連記事:インボイス制度で導入すべきシステム4選!導入するべき理由も紹介
まとめ|インボイス制度の農協特例は、実情にあった特例!
本記事では、インボイス制度の農協特例は「ずるい」という声に対して、その理由や特例の内容を解説しました。
インボイス制度の「農協特例」は、農業従事者とその買い手の事務負担を軽減するための特例です。そのため、特例が実施された背景や、日本が抱える課題などを理解せずに、批判するような声・意見を挙げることは避けるべきといえるでしょう。
さまざまな課題を抱える日本において、事業をスムーズに運営するためには正しい情報を理解しておく必要があります。本メディアではインボイス制度をはじめとした税制に関する知識・ノウハウなどを提供しているため、正しい情報を理解する際の参考にしてください。