インボイス制度で値引き時の請求書の書き方とは?違法性や消費税の扱いを解説
更新日:2025.12.06
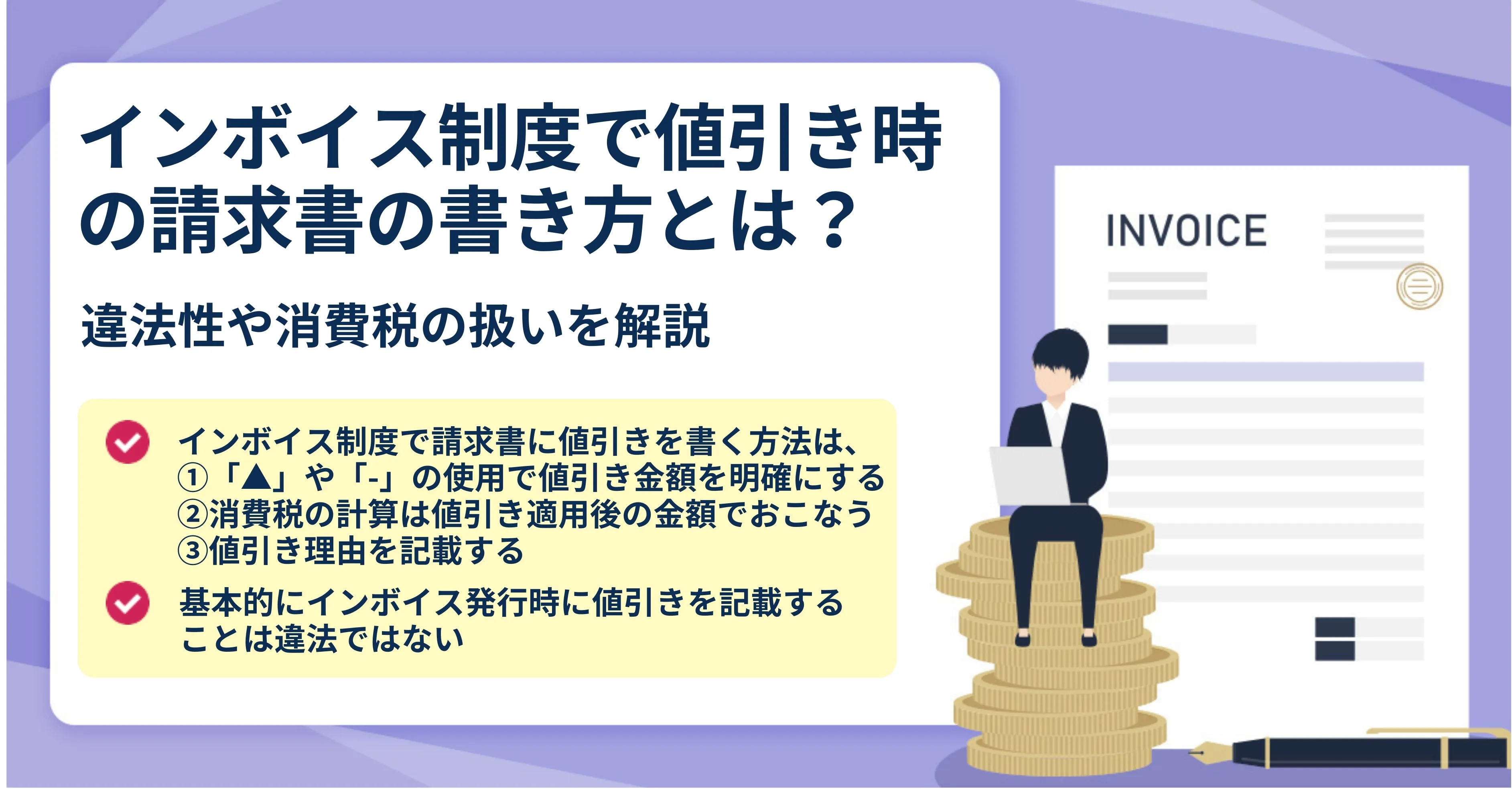
ー 目次 ー
ビジネスシーンでは商品の返品やサービスの提供中止などが発生した際に、請求金額から値引きをするケースがあります。
インボイス制度ではインボイス(適格請求書)発行前に値引きが決定する場合、値引きをおこなった旨をインボイスに記載します。一方で、インボイス発行後に値引きが決まった際は返還インボイス(適格返還請求書)を発行しなければなりません。
インボイス制度は消費税にまつわるルールであるため、正しい値引きの方法を理解していなければ、税務に関するトラブルに発展しかねないことから適切な対応が求められます。
本記事では、インボイス制度で値引きをおこなう際の請求書や返還インボイスの書き方を解説します。
【見本】インボイス制度で請求書に値引きを書く方法
インボイス制度では、商品やサービスの値引きをおこなった際のインボイス(請求書)の書き方を定めています。このルールにしたがわずに発行した請求書はインボイスとして認められず、取引先が仕入税額控除を受けられないおそれがあるため注意が必要です。
ここでは、インボイス制度で請求書に値引きを書く方法について、解説します。なお、以下は値引きをおこなった際のインボイスの見本を掲載しているため、参考にしてください。
- 「▲」や「-」の使用で値引き金額を明確にする
- 消費税の計算は値引き適用後の金額でおこなう
- 値引き理由を記載する
|
請求書作成日 請求書 取引先企業名 自社の企業名 ご請求金額 ¥2,000-(税込)
※印は軽減税率の対象 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①「▲」や「-」の使用で値引き金額を明確にする
請求書に値引きを記載する際は、差し引く金額の前に「▲」や「‐」などの記号を記載します。値引き金額の前に記号を記載しておくことで、書類が取引先に届くまでの過程で数字の改ざんや訂正などのトラブルを防げます。
なお、金額の値引きがあるからといって、値引き金額を赤字にする対応は一般的ではないため避けましょう。
②消費税の計算は値引き適用後の金額でおこなう
請求書に記載する消費税の計算は、基本的には実際に取引先へ請求する値引きを適用した金額でおこないます。消費税の計算を値引き前の金額でおこなうと、消費税の金額が異なる可能性があります。
消費税の計算をおこなうタイミングは社内で決めておき、申告時に混乱を招かないよう注意しましょう。
③値引き理由を記載する
請求書内に値引きを記載する際は、内容に違法性がないことを証明するため理由を記載します。理由を記載しておけば、取引先が目を通した際にも理解しやすい書類となり、確認する手間を減らせます。
値引きの理由は差し引く金額の前に「〇〇 ▲500円」と記載しましょう。
【結論】インボイス発行時に値引きしても違法ではない
基本的に、取引先との合意で決定された値引きは、インボイス(適格請求書)に記載しても違法にはなりません。ただし、値引きの理由が買い手の立場を利用した過度な価格交渉ならば、下請法違反に抵触する可能性があります。
なお、違法性のある値引きとは、不当な代金の減額や返品を指します。たとえば、商品やサービスの対価が同業種の他社と比べて明らかに低い値引きを要求するようなケースが該当するでしょう。
このような点から値引きをおこなう際には、独占禁止法や下請法のルールを踏まえた対応が必要です。
インボイス交付時に値引きが確定しているパターンと書き方とは?
インボイス(適格請求書)を発行する前に値引きが決定しているならば、書類のなかで値引き対応ができます。このようなケースは必要な対応を発行するインボイス内でおこなえるため、返還インボイス(適格返還請求書)を発行する必要はありません。
このようにインボイス制度のなかには、知っておくと事務負担を減らせるルールもあります。取引先とのスムーズな取引を進めていくためにも、値引きのパターンごとに対応するインボイスの書き方を知っておくと良いでしょう。
ここでは、インボイス交付時に値引きが確定しているパターンと書き方を解説します。
①大量注文
取引先から商品・サービスの注文を大量に受けた場合は、大量注文を理由に値引きをおこなう可能性があります。
大量注文は請求書段階で告知するのではなく、事前に取引先へ数量と値引き額の関係を説明しておくことで、取引先も値引き目的で発注をかけやすくなります。
大量注文を請求書に記載する際は、対象商品・サービスの下の行に「値引き ▲〇〇円」と記載しましょう。
②相殺の発生
前月以前におこなった取引で返金が発生している際は、次月以降の取引で金額を差し引く「相殺」が発生します。返金額を相殺で処理することで、自社・取引先どちらも入出金にかかる業務や確認作業を減らせます。
相殺をおこなう際は、事前に取引先に相談しておきましょう。取引先への相談もなく相殺をおこなえば、取引先の事務負担が増えるおそれがあります。
請求書内で相殺を処理する際は、「相殺 ▲〇〇円」と記載します。
③納期調整
商品・サービスの納期が遅れた際は、お詫びの意味で値引きをするケースがあります。納期調整が理由の値引き金額は、事前に詳細が定められていないため、取引先と相談して決定しましょう。
請求書では、「納期調整による値引き ▲〇〇円」と記載します。
④端数調整
端数調整とは、請求金額が「110,120円」のように、端数がある場合にサービスで端数分を値引きするシーンのことを指します。請求時に端数の「120円」を値引きすることで、入金金額のキリが良くなります。
端数を調整した際は、「端数調整による値引き ▲120円」と記載しましょう。
【テンプレートあり】発行後の値引きは返還インボイスの対応が必要!
すでにインボイス(適格請求書)を発行している際の値引きは、返還インボイス(適格返還請求書)を発行する必要があります。
返還インボイスとは、インボイス発行後に値引きを実施した場合に発行される書類です。インボイス制度では返還インボイスを発行する際に、記載項目をはじめとしたルールが定められているため、記載の漏れがないように注意が必要です。
返還インボイスを作成する場合は、以下の記載要件を満たしましょう。
- 適格請求書発行事業者の氏名・名称
- 書類作成者の登録番号
- 取引年月日
- 取引内容
- 取引金額、税率ごとの合計金額
- 商品・サービスごとの消費税額、税率ごとの消費税の合計金額
なお、返還インボイスが必要になるのはインボイス発行後の値引きのみのため、作成段階で値引きが確定している場合は発行する必要がありません。また、税込1万円以上の値引きがない場合は返還インボイスの交付義務が免除されているため、取引先から求められなければ発行は不要です。
返還インボイスの発行が必要になった際、自社にあわせたテンプレートを用意しておくことでスムーズに作成できます。以下では、返還インボイスのテンプレートを紹介します。
|
書類作成日 支払明細書 取引先企業名 〇月分 21,800円(税込)
※印は軽減税率の対象 自社の企業名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
まとめ|インボイス制度での値引きは状況次第で発行する書類が異なる
本記事では、インボイス制度で値引きをおこなう際の請求書や返還インボイスの書き方を解説しました。
インボイス制度後の値引きはインボイス(適格請求書)を発行の有無で、返還インボイス(適格返還請求書)の必要性が異なります。インボイス発行段階で値引きが確定していれば、値引きをおこなった旨をインボイスに記載します。
ただし、インボイス発行後であっても、1万円以下の値引きであれば返還インボイスは必要ありません。
返還インボイスが必要か悩む際は本記事を参考に、書類を作成しましょう。










