NPO法人のインボイス制度対応ガイド|領収書発行ルールも徹底解説
更新日:2026.01.13
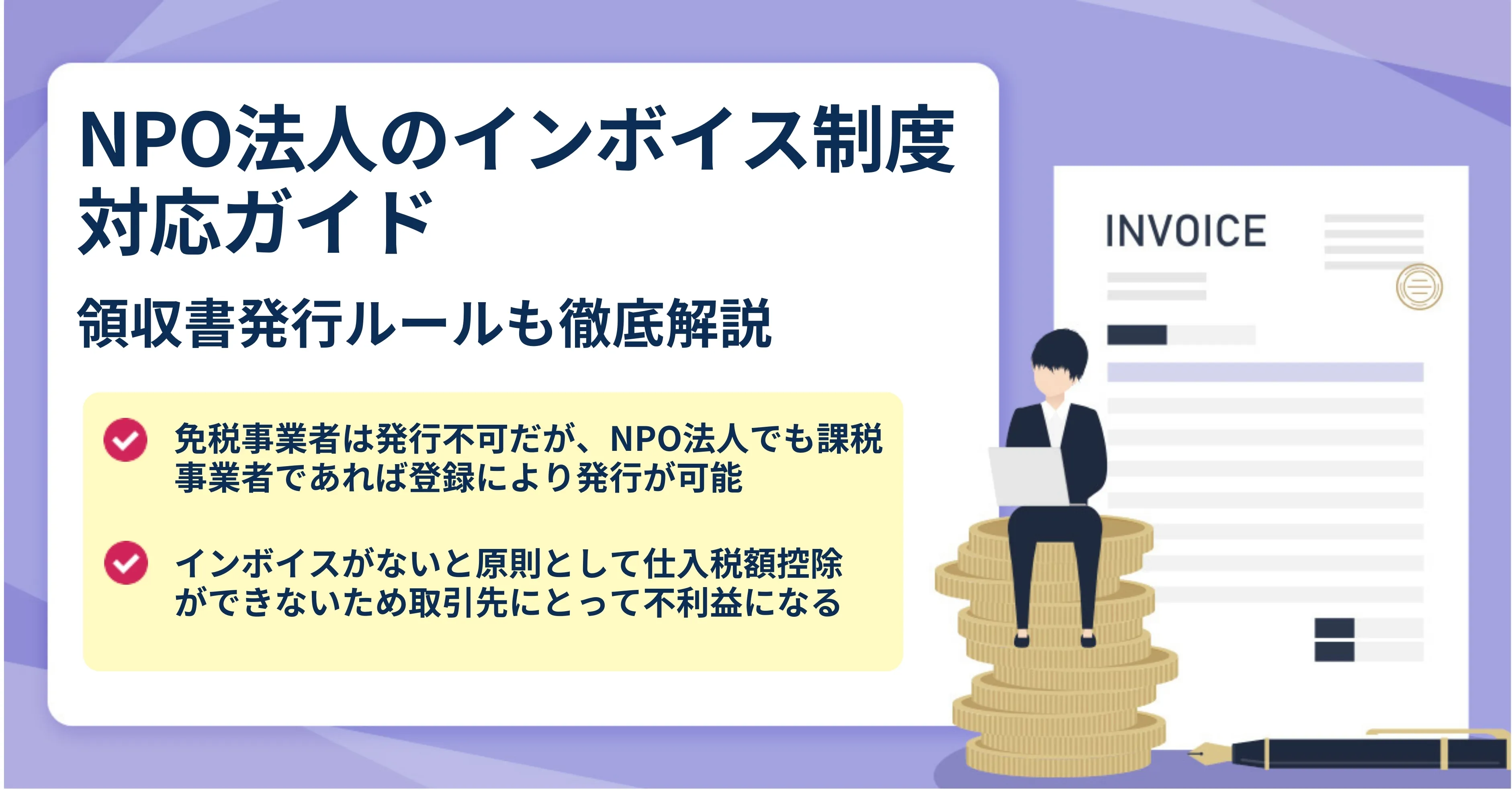
ー 目次 ー
本記事では、NPO法人がインボイス制度の対象となるか、領収書の発行ルールや経理・会計への影響、登録申請の手順などをわかりやすく解説します。最新の実務対応や注意点も網羅しており、NPO法人関係者が制度対応に迷わず備えるための情報が得られます。
NPO法人とインボイス制度の基本を解説!
NPO法人とは何か
特定非営利活動法人(NPO法人)は、営利を目的とせず、社会貢献活動や福祉、文化、教育、環境保全など幅広い分野で公益的な活動を行う団体です。法人格を取得することで、法的な責任や権利を持ち、銀行口座の開設や資金調達、助成金の申請、契約行為などを法人名義で行えるようになります。NPO法人は、収益を活動目的のために使うことが求められ、社員総会・理事会による組織の適正な運営も義務付けられています。
日本におけるNPO法人は「特定非営利活動促進法」に基づいて認証・設立され、非課税や優遇税制の対象となることも多く、ボランティア活動や寄付、行政との連携など幅広い経済活動が認められています。
インボイス制度の概要
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、2023年10月より日本国内で導入された消費税の仕入税額控除の方式です。事業者が消費税の納付額を正確に計算するために、取引先から「適格請求書(インボイス)」を受け取り、保存することが必要となりました。インボイスとは、所定の要件を満たした明細書・請求書等であり、発行できるのは「適格請求書発行事業者」に限られます。
この制度により、仕入先や協力会社から適正な消費税額が記載された請求書・領収書を受領・保存しなければ、仕入税額控除が受けられなくなる可能性があります。NPO法人であっても、課税事業者であればインボイス制度の影響を受けることになるため、制度のポイントを理解することが重要です。
適格請求書発行事業者の定義
インボイス(適格請求書)を発行できるのは、税務署に申請して「適格請求書発行事業者」として登録された事業者のみです。この登録は消費税課税事業者が申請可能で、免税事業者は登録できません。適格請求書発行事業者になることで、取引先に対してインボイスを発行し、取引先が仕入税額控除を受けられるようになります。
|
区分 |
説明 |
|
登録要件 |
消費税の課税事業者であること 税務署への登録申請が必要 |
|
主な義務 |
インボイス(適格請求書)の発行・保存 適切な記帳・会計管理 |
|
対象外となる場合 |
免税事業者(基準期間の課税売上高が1,000万円以下等) 税務署へ登録申請を行っていない場合 |
したがって、NPO法人であっても課税事業者であり、かつ適格請求書発行事業者として登録すればインボイスを発行できます。一方で、寄付や補助金、助成金等の非課税収入が主体の場合は、制度の影響が限定されることもあります。しかし、対価を伴う取引を行う場合は対応が不可欠となります。
NPO法人はインボイス制度の対象になる?
インボイス登録義務の有無
NPO法人は法人格を持っていますが、インボイス発行事業者となる義務は一律にはありません。インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、課税事業者のみが登録申請により「適格請求書発行事業者」となり、インボイス(適格請求書)を発行できる仕組みです。したがって、「課税事業者」に該当するNPO法人は、登録すればインボイスを発行できますが、「免税事業者」のままではインボイス発行ができません。
多くのNPO法人は収益事業の規模が小さいため免税事業者であることが多いですが、委託事業(行政受託など)や物品販売などで一定金額以上の売上がある場合、課税事業者となり、この制度の対象となります
また、免税事業者であっても、今後の取引や事業展開、行政補助金・委託事業の採択条件などによっては、インボイス登録を検討する必要が生じる場合があります。特に取引先(協力企業や自治体など)が仕入税額控除のために「インボイス」を必要とする場合、NPO法人がインボイス発行事業者であることが取引継続の前提となる場面もあります。
|
区分 |
消費税納付義務 |
インボイス発行資格 |
NPO法人への主な影響 |
|
課税事業者 |
あり |
登録申請が必要 |
インボイス発行事業者になれる。仕入先や取引先から求められることがある。 |
|
免税事業者 |
なし |
発行不可(インボイス登録しない限り) |
インボイスを発行できず、取引先からの取引が制限されるリスクがある |
インボイス登録に関わるNPO法人の判断基準の例
|
状況 |
登録判断ポイント |
|
民間企業や自治体にサービスや商品を販売する |
取引先が仕入税額控除を受けられるように、インボイス登録が有利となる場合がある |
|
寄付金や助成金が主な収入 |
消費税課税対象でない収入が主であれば、登録不要のケースが多い |
|
今後新たに収益事業を開始する予定がある |
売上規模に応じて将来的な登録が必要となる可能性がある |
NPO法人としては現状の事業収入・活動内容・主要な取引先のニーズや今後の事業展開を踏まえて、インボイス発行事業者への登録を検討することが重要です。また、インボイス登録による消費税の納税義務や事務負担の増加も十分考慮する必要があります。
領収書発行ルールとインボイス制度との関係!
領収書とインボイスの違い
日本の税制において「領収書」と「インボイス(適格請求書)」は、取引証拠書類としての役割は似ていますが、法的要件や記載内容、発行の目的に大きな違いがあります。
|
項目 |
領収書 |
インボイス(適格請求書) |
|
役割 |
受領金額の証明 |
消費税仕入税額控除の要件 |
|
発行者 |
誰でも可 |
適格請求書発行事業者のみ |
|
必須記載事項 |
受領日、金額、宛名、発行者 |
登録番号、消費税率・税額、取引内容等 |
|
消費税対応 |
税額表示は任意(基本的に金額合計のみ) |
税率ごとに区分、消費税額表示必須 |
NPO法人が発行すべき書類の具体例
NPO法人が日常業務で発行する主な書類には、会費や寄付金受領時の「領収書」、物品販売やサービス提供時の「請求書」・「領収書」などがあります。インボイス制度導入により、消費税の課税取引については、適格請求書(インボイス)の発行が求められる場面が増えます。なお、寄付金や会費は消費税の課税対象外ですが、物品や役務の提供を伴う場合は課税取引となるため、注意が必要です。
|
取引内容 |
該当する書類 |
インボイス発行義務 |
備考 |
|
寄付金の受領 |
寄付金領収書 |
不要 |
消費税非課税 |
|
会費の受領 |
会費領収書 |
不要 |
消費税非課税 |
|
物品販売(例:グッズ・書籍) |
領収書、請求書 |
必要(課税取引の場合) |
インボイス要件要確認 |
|
サービス提供(例:ワークショップ、講演) |
領収書、請求書 |
必要(課税取引の場合) |
適格請求書発行事業者のみ可 |
|
物品購入・外部委託 |
受領した請求書や領収書 |
仕入税額控除のために相手先から必要 |
インボイス取得必要性あり |
寄付金領収書の取り扱い
NPO法人が受領する寄付金は、所得税法上の「特定寄附金」や法人税法上の「指定寄付金」として、寄付者が税制上の優遇措置(寄附金控除など)を受けるために寄付金領収書の発行が求められます。しかし、寄付金そのものは消費税の非課税取引に該当するため、インボイス(適格請求書)の発行義務はありません。また、寄付金領収書には、寄付日、金額、寄付者名、受領者名(NPO法人名および代表者名)が必要です。
ただし、現物寄付や対価性のある取引(例:寄付のお礼として物品を贈与した場合)では消費税の課税対象となるケースもあるため、具体的な取引内容に応じた正確な処理が必要です。こうした場合には、領収書やインボイスの発行要否を税理士や専門家に確認することが安全です。
NPO法人の会計はどう変わる?インボイス制度と消費税の会計実務
会計ソフト・記帳方法の変更点
インボイス制度(適格請求書等保存方式)の導入により、NPO法人の経理・会計業務には従来と異なる点がいくつか生じます。具体的には、取引ごとに「インボイス(適格請求書)」が発行・受領されているかどうかを明確に管理する必要があり、従来の領収書や請求書のみの管理では不十分となります。
このため、仕訳帳・出納帳に加えて、インボイス管理用の台帳やエクセルシートの導入や、インボイス制度対応の会計ソフトの活用が推奨されます。インボイスの番号管理、受領したインボイスの原本保存、電子帳簿保存法への対応もあわせて確認すべきポイントです。
|
従来の経理業務 |
インボイス制度対応後 |
|
請求書・領収書の保存 |
適格請求書(インボイス)の保存・番号管理 |
|
消費税区分の記載なしでも可 |
8%・10%等の適用税率と税額を記載 |
|
各種台帳の手動管理 |
インボイス対応済みの会計ソフト利用推奨 |
|
帳票の紙保存主流 |
電子保存や電子帳簿保存法にも留意 |
消費税の仕入税額控除の影響
インボイス制度により、課税事業者であるNPO法人は、仕入先や外注先から受領した「適格請求書」(インボイス)がなければ、その取引について仕入税額控除が認められなくなります。「課税売上高1,000万円超」の法人や、課税事業者選択届出をしている場合は特に注意が必要です。
インボイス発行事業者以外からの取引(個人事業主・小規模な協力先等)や、ボランティア謝金、講師謝礼などについても、経費計上・控除要件が変更となる可能性があります。従来慣れていた支出の管理方法を、インボイスの有無で分ける必要が生じるため、業務フローの見直しが求められます。
|
取引先 |
インボイス発行の有無 |
仕入税額控除 |
|
インボイス発行事業者 |
有 |
控除可能 |
|
免税事業者(インボイス発行不可) |
無 |
原則控除不可 ※経過措置あり(2029年9月まで一部控除) |
経理担当者・理事会へのインボイス制度の理解と体制整備
インボイス制度への対応は、経理担当者だけでなく、NPO法人全体のガバナンスや情報共有体制にも関わるため、理事会・事務局レベルでの理解と役割分担が重要です。契約書類や仕入先への対応方針、事務手続きマニュアルの策定、関係書類の保存管理体制の整備など、NPO法人の経理業務全体を見直す契機となります。
また、会員管理、助成金申請、寄付受入の帳票類や領収書発行にも、インボイス制度への正しい理解が欠かせません。社内研修や専門家(税理士・行政書士等)への相談体制の強化も検討しましょう。
NPO法人がインボイス制度対応で準備すること
周知や関係者への説明方法
インボイス制度導入に伴い、NPO法人がスムーズに移行できるよう、理事・会員・取引先・寄付者など関係者に対して制度の概要や対応方針を丁寧に周知することが大切です。法人内で説明会や勉強会を開催し、役員や職員が制度の基礎知識と自法人の方針を理解できるようにしましょう。取引先業者やボランティアスタッフにも自法人のインボイス制度への登録状況を明確に伝えることも重要です。
パンフレット作成や、公式ウェブサイト・メール・ニュースレターなどで案内情報を提供することも有効です。寄付者向けには、寄付金領収書が適格請求書に該当しない場合があること、仮にインボイス登録事業者でない場合は消費税控除を受けられない旨を周知し、誤解を防ぎましょう。
会計業務・事務フローの見直し
仕入先、委託先、外注先との取引においてインボイス対応の書類を入手できるか確認し、帳票管理方法を見直す必要があります。出金伝票、支払伝票、請求書などのフォーマットや保存業務が追加となるため、経理担当者への教育も含めた事務手続きの整理が求められます。
|
準備すること |
ポイント・注意点 |
推奨ツール・備考 |
|
請求書フォーマットの確認・修正 |
適格請求書の要件(登録番号・税率ごとの金額・消費税額等)を満たしているか |
会計ソフト、Excelテンプレート |
|
帳票管理の見直し |
インボイス書類の原本保存要件対応 |
電子ファイリングシステム |
|
仕入先・外注先のインボイス登録状況の確認 |
課税仕入れに係る消費税控除対象か判定 |
国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト |
|
経理担当への研修・教育 |
新制度による会計処理の流れ理解を徹底 |
社内研修、専門書 |
会計ソフト・システムの対応状況確認
インボイス制度対応のためには、導入している会計ソフトウェアやクラウド会計システムのバージョンや機能が新制度に対応しているかのチェックが不可欠です。とくに、適格請求書の発行・保存、消費税計算、登録番号の記載などに関するソフト側の機能やサポート内容を事前に確認しましょう。
社内規程や内部統制の見直し
インボイス制度対応にともない、社内の会計規程や支払い規程、文書管理規程をチェック・必要に応じて改訂しましょう。電子帳簿保存法やインボイス保存義務に基づく管理の強化も必要です。内部統制の観点からも、適切な承認フローの整備や証憑管理の徹底を図るべきです。
今後の制度変更への備え
インボイス制度は今後も運用ルールが見直されることが予想されます。国税庁やNPOサポート機関などから発信される最新情報を定期的にチェックし、新たな法令・通達への対応方針を決めておきましょう。定期的な内部監査や専門家(税理士、公認会計士)への相談も体制として整えていくと安心です。
特に「仕入税額控除の経過措置」「電子インボイス」「寄付金領収書等の特殊論点」など、今後の変更点に備えた情報収集と対応フローの柔軟な見直しを怠らないことが重要です。
外部専門家や支援窓口の活用
専門的な判断が必要となる場面では、税理士やNPO専門会計士、認定NPO法人を支援する全国NPO会計税務研究会などの機関を活用しましょう。他団体の事例や、自治体のNPO支援担当窓口からもアドバイスや情報提供が受けられる場合があります。国税庁の公式サイトやFAQも最新情報を得るために活用可能です。困った時には早めの相談が円滑な制度対応につながります。
NPO法人がインボイス制度に対応する際の注意点
適格請求書(インボイス)の発行要件
NPO法人がインボイス制度に対応する上で最も大切なのは、「適格請求書発行事業者」として登録された場合、取引先に対して要件を満たした適格請求書(インボイス)を発行しなければならないことです。適格請求書に記載すべき主な項目は、以下の通りです。
|
記載項目 |
内容 |
備考 |
|
適格請求書発行事業者の氏名又は名称および登録番号 |
法人名・登録番号を正確に記載 |
法人名は特定非営利活動法人を明記 |
|
取引年月日 |
課税資産の譲渡等の年月日 |
日付の誤記に注意 |
|
取引内容 |
商品の種類や役務提供の内容 |
具体的に記載 |
|
受領者の氏名又は名称 |
相手方の正式名称 |
法人・個人名 |
|
税率ごとの対価の額(税込)及び適用税率 |
8%/10%など消費税率ごとに分けて金額を記載 |
区分記載が必須 |
|
消費税額等 |
税率ごとに消費税額を記載 |
端数処理の統一を |
上記の項目が全て漏れなく記載されていなければ、仕入税額控除の要件を満たさないため、取引先に迷惑をかけてしまう可能性があります。記載項目の誤りや記載漏れがないか、発行前に必ず確認しましょう。
登録申請の手順と必要書類
NPO法人が適格請求書発行事業者の登録を希望する場合、以下の手順と必要書類を確認しておくことが重要です。
- 国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」にアクセス
- 所轄国税庁に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出
- 審査・登録完了後、登録番号が交付される
必要書類は原則以下の通りです。
|
書類名 |
内容 |
提出先 |
|
適格請求書発行事業者の登録申請書 |
登録を希望する旨の申請書 |
所轄税務署 |
|
定款の写し |
NPO法人の場合は定款が必要 |
必要に応じて |
|
法人登記簿謄本 |
法人格証明書類 |
必要に応じて |
申請書は紙だけでなく、e-Taxでの電子申請も可能です。手続き開始から登録完了までに時間を要する場合があるため、余裕をもって書類を準備しましょう。
源泉徴収や消費税計算への影響
インボイス制度の導入により、消費税の計算や源泉徴収業務にも影響があります。NPO法人の場合、主に以下のポイントに注意が必要です。
- 消費税計算の複雑化:
課税取引と非課税取引、非課税収入(補助金、会費、寄付金など)が混在している場合、インボイス制度導入により各取引ごとに適用税率や控除可否を正確に区分・管理する必要が生じます。特に、非営利活動と営利活動が並行する場合、帳簿と証憑書類の精緻な整理が求められます。 - 源泉徴収との関係:
講師謝金や外部委託への支払いが発生する場合、インボイス発行義務や源泉徴収義務の範囲が混同されやすいため、それぞれの制度の適用要件に注意が必要です。源泉徴収の対象であってもインボイス発行義務がある取引、またはその逆もあり得ますので、最新の法令・通達を確認しましょう。 - 仕入税額控除の適用対象:
インボイスがない支払いの場合、取引先(受領者)が仕入税額控除を行えない場合があり、法人としても経済的な影響を受ける可能性があります。免税事業者のままの場合、取引減少リスクも考慮する必要があります。特に企業・団体取引が多いNPO法人では注意が欠かせません。
これらの点について会計担当者や外部専門家(税理士等)との連携を強化し、帳簿や内部規程の整備を進めることが重要です。また、法令改正や通達も定期的に確認し、対応漏れがないよう十分注意しましょう。
Q&A|インボイス制度に関するよくある質問
インボイスがない場合の取引はどうなりますか?
インボイス(適格請求書)が交付されていない場合、仕入税額控除が原則として認められません。
ただし、経過措置期間中(2023年10月1日から2029年9月30日まで)は、一部控除が認められる場合もあります。
ボランティアへの謝礼や交通費支給はインボイスが必要ですか?
ボランティアへの謝礼や交通費の支給は「給与等」や「非課税取引」に該当することが多く、インボイスの発行は不要です。
寄付金領収書とインボイスの違いは何ですか?
寄付金領収書は、主に寄付者が税制優遇措置(寄付金控除等)を受けるために使われます。一方、インボイスは消費税の仕入税額控除に必要なもので、寄付の場合は消費税の課税対象外です。そのため、寄付金領収書にインボイス要件を盛り込む必要はありません。
適格請求書発行事業者の登録に必要な手続きは?
NPO法人がインボイスを発行するには「適格請求書発行事業者」の登録が必要です。国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で申請用紙をダウンロードし、必要事項を記載のうえ税務署に提出します。登録番号が付与されるとインボイスの発行が可能となります。
NPO法人で免税事業者のままでいるリスクは?
NPO法人が免税事業者のままだと、取引先(主に課税事業者)からインボイスが発行できないことによる取引縮小や契約見直しのリスクがあります。
これまでの請求書や領収書はそのまま使えますか?
従来の請求書・領収書では、インボイス制度下での仕入税額控除要件を満たしません。請求書や領収書には、登録番号や税率ごとの消費税額明示など新たな記載内容が必須となるため、フォーマット変更が必要です。
ボランティア保険など非課税取引の取り扱いは?
ボランティア保険料や損害保険料、社会保険料などは消費税の非課税取引に該当するため、インボイスの発行は不要です。
まとめ
NPO法人もインボイス制度の対象となる場合があり、課税事業者か免税事業者かで対応が異なります。消費税の仕入税額控除や領収書の発行ルールも変化するため、会計処理や関係者への周知が重要です。










