これで安心!インボイス対応の納品書と請求書の違いと書き方
更新日:2026.01.29
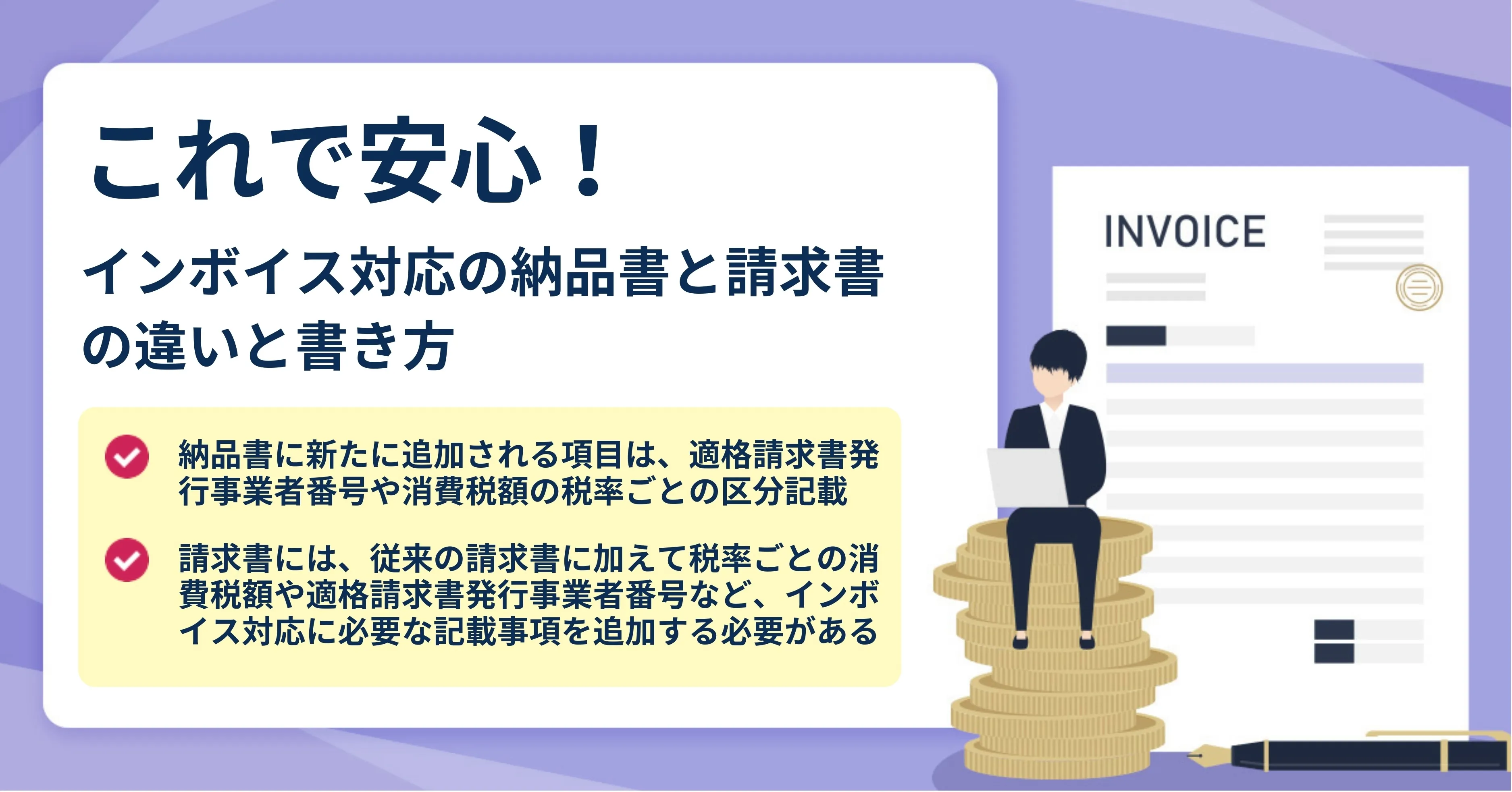
ー 目次 ー
2023年10月に導入されたインボイス制度は、納品書や請求書の書き方や運用に大きな変更をもたらしました。
本記事では、「納品書」と「請求書」の違いや具体的な書き方、注意点を解説します。特に、適格請求書発行事業者番号や税率ごとの消費税額明記など、インボイス制度下で新たに求められるポイントをわかりやすく説明します。
さらに、実務に役立つノウハウとして効率化を図るツールやサービスの活用方法まで網羅していますので、この記事を読み終えるころにはインボイス制度に完全対応した納品書・請求書の発行が安心して行える知識とノウハウが身につきます。
インボイス制度とは
インボイス制度の基本概要
インボイス制度は2023年10月に導入された新しい消費税の仕組みで、正式名称を「適格請求書保存方式」と言います。この制度は、消費税額の正確な把握と適正な税額控除を目的としています。具体的には、売買や取引における請求書や納品書などの帳票類において、必要な情報を記載した「適格請求書(インボイス)」を発行・保存することが求められます。
消費税を納める事業者が、仕入の際に納めた消費税を差し引く「仕入税額控除」を行うためには、インボイス制度に基づいた請求書や納品書を取引先から受領し、それを適切に保存する必要があります。これにより、課税事業者同士が正確かつ透明な消費税の納付プロセスを確保できるようになります。
インボイスが納品書や請求書に与える影響
インボイス制度が導入されることで、特に請求書や納品書の作成方法に大きな影響があります。これまでの形式的な帳票ではなく、制度が指定する記載事項を満たす「適格請求書」として認められる内容でなければなりません。
影響の大きなポイントとして、以下の点が挙げられます。
|
項目 |
具体的な影響 |
|
適格請求書発行事業者番号 |
適格請求書発行事業者として登録された事業者には、税務署から発行された「登録番号」を記載する義務があります。 |
|
税率別の消費税額 |
税率ごとに区分した消費税額を明記する必要があります。複数税率が存在する場合、それぞれの税率適用商品ごとに記載する義務があります。 |
|
取引内容の詳細 |
取引に関わる品目や単価、数量、金額も明確に記載しなければなりません。 |
さらに、インボイス制度の導入に伴い、事業者側の帳票管理や書類発行業務の負担が増加することが予想されています。このため、正確な理解と効率的な業務フローの構築が重要になります。
納品書と請求書の違い
納品書の役割と目的
納品書は、商品やサービスが確かに取引相手に引き渡されたことを証明するための書類です。主に取引内容の詳細が記載されており、誰が何を何個受け取ったかが明確になります。納品書を発行することにより、取引の完了状況を確認し、トラブルが起こりにくくなるメリットがあります。また、特に商品取引では発送後の確認ツールとしても重要な役割を果たします。
納品書にはお金の請求に関する情報は含まれないことが一般的です。値引きや支払い期日などの詳細は記載されないため、納品書は「商品が確かに納品されたことを示すための記録」という性質が強い書類です。
請求書の役割と目的
請求書は、取引の対価としての支払い金額を相手から受け取るために発行される書類です。請求金額だけでなく、支払い方法や期限、振込先の情報なども記載されており、取引の金銭的な内容を明確にする役割を果たします。
請求書を発行する段階は、納品が完了した後が一般的です。ただし、場合によっては請求書の発行と納品が同時に行われることもあります。これはサービス業やプロジェクトベースのビジネスにおいて顕著です。請求書には「いつまでにどのように支払えば良いか」といった具体的な情報が記載されるため、金銭管理や経理業務において重要な役割を担います。
納品書と請求書の作成タイミング
納品書と請求書は、作成されるタイミングが異なるという点で大きな違いがあります。
納品書の作成タイミングは、商品やサービスを取引相手に引き渡す直前または引き渡しと同時です。一方、請求書は、納品が完了した後に作成されるのが通常です。これにより、取引の進行に沿って書類がスムーズに作成される仕組みが整えられています。特に契約によって取引が記録される業界では、このタイミングの順序が守られることが一般的です。
納品書と請求書を使い分ける重要性
納品書と請求書を正しく使い分けることは、事業活動を円滑に進める上で非常に重要です。それぞれの書類は異なる目的に基づいて作成されるため、混同すると取引先との間で誤解や混乱を生む可能性があります。
例えば、納品書に記載された商品が間違っていた場合は、そのタイミングで修正を依頼することが可能です。一方で、請求書が間違っていると、支払い金額や消費税計算に関する誤解が起こる可能性があります。これにより、信用を損なったり、経理処理が大幅に遅れるリスクがあります。
さらに、インボイス制度が導入されてからは、各書類に記載すべき項目が細かく決められているため、非適格な書類を発行すると、取引先に迷惑をかけるだけでなく、自社の受け取る消費税還付にも影響を及ぼす可能性があります。そのため、両者を的確に使い分けることで、取引先との信頼関係を維持しながら経営効率を向上させることが重要です。
|
項目 |
納品書 |
請求書 |
|
役割 |
商品やサービスの引き渡しを証明 |
取引に対する支払いを請求 |
|
作成タイミング |
納品時または納品直前 |
納品後 |
|
記載内容 |
商品名、数量、単価など |
金額、支払期日、振込先情報など |
|
適用の範囲 |
取引の完了の確認 |
支払いのお願い |
インボイス制度が納品書と請求書に与える影響
適格請求書とは
適格請求書とは、インボイス制度の導入に伴い、消費税の仕入税額控除を受けるために必要な書面のことを指します。適格請求書発行事業者として登録された事業者のみが発行できるもので、請求書や納品書など一連の取引書類で、一定の条件を満たしている必要があります。
この書類には、適格請求書発行事業者番号、税率区分別の消費税額やその合計額など、詳細な情報が記載されていることが求められます。これらの記載事項を満たしていない請求書や納品書は、仕入税額控除が認められなくなる可能性があるため、注意が必要です。
インボイス対応で求められる記載事項
インボイス制度が適用される請求書や納品書においては、以下の内容が記載されていることが必須です。これらは「適格請求書」として認められるための条件でもあります。
適格請求書発行事業者番号の必要性
適格請求書発行事業者番号は、国税庁から発行される固有の登録番号で、これにより発行元が適格請求書発行事業者であることを証明します。この番号を記載しない場合、取引先が仕入税額控除を受けられないリスクが生じるため、必ず記載することが求められます。
税率ごとの消費税額の明記
取引に適用される各税率ごとに区分した消費税額を個別に計上し、それらの合計額を記載する必要があります。現行の消費税率では、標準税率(10%)と軽減税率(8%)の二つが主に該当します。
その他必須情報
インボイスに必要なその他の必須情報には、以下の内容が含まれます。
- 取引年月日
- 取引内容の詳細(品目やサービスの具体的な説明)
- 取引金額(税抜金額)
- 発行者の氏名または名称と、その連絡先情報
これらを漏れなく記載することで、適格請求書として認められる書類を作成することができます。
日常業務での変更点
インボイス制度の導入に伴い、日常業務にもさまざまな変更点が発生します。特に納品書や請求書の作成において、これまでのフォーマットでは不十分になるケースが多いため、適格請求書に対応した新しい書式に移行する必要があります。
また、以下のような点に注意が必要です。
- 適格請求書発行事業者への登録手続き:登録を怠ると、取引先に影響を与える可能性があります。
- 会計ソフトや請求書作成ツールのバージョンアップ:新しい規定に対応しているか確認する必要があります。
- 顧客や取引先とのコミュニケーション:適格請求書が必要な取引においては、事前に取引条件を確認することが重要です。
特に中小企業やフリーランスにおいては、インボイス制度の導入による業務負担を軽減するために、早めの対応と準備が求められます。正確かつ効率的に対応することで、取引先との信頼関係を維持し、事業運営を円滑に進めることが可能です。
|
必須記載事項 |
記載例 |
|
適格請求書発行事業者番号 |
T1234567890123 |
|
取引年月日 |
2023年10月10日 |
|
税率ごとの消費税額 |
標準税率 10%:1,000円、軽減税率 8%:800円 |
|
取引内容 |
商品A(10個)、商品B(5個) |
|
発行者情報 |
株式会社〇〇、〒123-4567 東京都品川区〇〇1-2-3 |
インボイス対応の納品書の書き方
従来の納品書フォーマットとの違い
インボイス制度導入前の納品書のフォーマットでは、商品名や数量、金額程度の基本的な情報を記載していれば問題ありませんでした。しかし、インボイス制度が開始されると、書類の正確性が一層重要になります。特に、消費税計算の正確性や、適格請求書発行事業者としての登録番号を含む記載事項が求められます。
これにより、納品書が請求書の要素を兼ねるケースも考えられるため、これまで以上に正確で詳細な情報を記載する必要があります。
納品書を適格請求書として扱うための必須項目
登録番号の記載方法
インボイス制度では、発行事業者自身の「適格請求書発行事業者番号」を納品書に記載する必要があります。この番号は、税務署から発行される13桁の番号で、書類の中の見やすい位置に記載するのが一般的です。
例えば、「適格請求書発行事業者番号:T1234567890123」のように記載します。この番号を記載しない場合、取引先が受け取る消費税控除に影響を与える可能性がありますので、注意が必要です。
発行者情報
納品書の発行者情報として、「事業者名」「住所」「電話番号」「メールアドレス(必要に応じて)」を記載します。これにより、取引先が発行元を確認しやすくなります。特にインボイス対応では、信頼性を高めるためにも明瞭に記載することが重要です。
取引内容の詳細
納品書には、以下の情報を明記します:
|
項目 |
例 |
|
取引日 |
2023年10月1日 |
|
品名 |
商品A |
|
数量 |
10個 |
|
単価 |
1,000円 |
|
合計金額 |
10,000円 |
これらの項目を明確かつ正確に記載することで、取引先が納品内容を容易に確認できるようになります。
消費税の取り扱い
インボイス対応の納品書では、取引ごとの税率ごとに分けて消費税額を明記する必要があります。日本では現在、標準税率10%と軽減税率8%の2種類の税率が適用されていますので、それぞれについて金額を分けて記載します。
例えば:
|
税率 |
課税対象額 |
消費税額 |
|
10% |
9,000円 |
900円 |
|
8% |
1,000円 |
80円 |
このように税率別に記載することで、書類の正確性が向上し、取引先の消費税計算や税務処理の手助けになります。
品目ごとの詳細情報の書き方
納品書には商品の詳細を記載する必要があります。具体的には、以下のような情報を含めるのが望ましいです:
- 品名:具体的な商品名やサービス名を一覧で記載。
- 品目コード:取引先との共通識別コードがあれば記載。
- 数量:商品ごとの数量を具体的に記載。
- 単価:税抜または税込の単価を明示。
- 金額:各品目の小計金額(合計金額との整合性が取れるように)。
これらの情報を詳細に記載することで、誤解を減らし、スムーズな取引を実現します。
納品書作成時の注意点
納品書を作成する際は、以下の注意点を守ることが重要です:
- 記載漏れがないように、作成後に必ず確認を行う。
- 税率や消費税金額に誤りがないか検算する。
- 登録番号が正確に記載されていることを確認する。
- 取引先の情報が最新のものであることを事前に確認する。
- クラウドサービスや会計ソフトを活用して、記載ミスを防ぐ。
これらのポイントを押さえることで、インボイス制度対応の納品書を正確に作成し、トラブルを防ぐことができます。
関連記事:インボイスの交付は納品書のみで可能!適用条件や注意点を解説
関連記事:【書かない?】納品書に消費税が必要な理由を解説!インボイス対応のテンプレートも紹介
インボイス対応の請求書の書き方
従来の請求書フォーマットからの変更点
インボイス制度導入以前は、請求書には取引内容や金額、発行日などの基本的な情報を記載するだけで問題ありませんでした。しかし、インボイス制度のもとでは、これに加えて税法上の要件を満たす「適格請求書」としての記載事項が求められます。具体的には、適格請求書発行事業者番号や税率ごとに区分した消費税額の明記が必要になります。これにより、仕入税額控除を受けるための書類として適合することが求められます。
請求書を適格請求書として扱うための必須項目
適格請求書発行事業者番号
請求書には、発行者が登録された適格請求書発行事業者番号を必ず記載する必要があります。この番号は、国税庁に登録申請を行い、認可を受けた事業者にのみ付与されるものです。事業者番号は、確認がしやすい場所に明示し、誤記がないように注意してください。この情報が不足している場合、受領者は仕入税額控除を受けることができなくなる可能性があります。
税率別の消費税額の明記
取引に適用された税率ごとに、税抜金額と消費税額を分けて記載する必要があります。例えば、標準税率10%と軽減税率8%が適用される取引がある場合、それぞれの税率に基づいた詳細を明記する必要があります。以下に一例を示します。
|
品目 |
数量 |
単価 |
税率 |
税抜金額 |
消費税額 |
|
商品A |
10 |
1,000円 |
10% |
10,000円 |
1,000円 |
|
商品B |
5 |
500円 |
8% |
2,500円 |
200円 |
請求内容の明細
請求書に記載する取引内容は、詳細にわたるものが求められます。記載内容としては品目名、数量、単価、適用される税率、金額が含まれるべきです。また、商品やサービスの名称は受取側にとって明確かつ理解しやすいものとしてください。特に、税率の異なる商品を扱う場合には、区別して表示することで誤解を防ぎます。
正しく書けているかを確認するポイント
請求書の記載内容が適格請求書として要件を満たしているかを確認することは、法的リスクを回避するために重要です。以下のチェックポイントを活用してください:
- 適格請求書発行事業者番号が記載されているか確認する。
- 取引内容の記載漏れや誤記がないか確認する。
- 税率ごとに税込金額・消費税額を分けて正確に記載しているか確認する。
- 請求書の発行日や取引の日付が正しいか確認する。
- 発行者情報(事業者名、住所、連絡先など)が明記されているか確認する。
これらのチェックによって記載ミスを未然に防ぎ、取引先との信頼関係を損なうことを防ぎます。また、専用の会計ソフトやクラウド請求書管理ツールを活用することで、人為的ミスのリスクを軽減することができます。
手間を減らすためのツールとサービスの活用
インボイス対応が可能な一般的な会計ソフト
インボイス制度に対応するためには、会計ソフトを活用することが非常に有効です。最近の主要な会計ソフトでは、適格請求書の発行に必要な機能が搭載されており、手作業を大幅に減らせます。
例えば、弥生会計やフリー(freee)、マネーフォワードクラウドは、多くの企業や個人事業主に支持されている会計ソフトです。これらのソフトは、登録番号の管理や税率ごとの消費税集計、適格請求書のフォーマット作成がスムーズに行えます。
これらのソフトを利用することで、インボイス制度に準拠した請求書や納品書の作成が自動化されるだけでなく、税務申告や取引先との調整も効率的に行えるため、ミスを減らすことができます。
おすすめのクラウド請求書管理ツール
クラウド型の請求書管理ツールを使用すると、請求書・納品書の作成から発行、送付、保存までを一括管理することができ、紙での処理が不要になるため業務効率をさらに高めることが可能です。
以下におすすめのシステムを4つ紹介します。
① Gi通信
Gi通信は、毎月送られてくる通信費に関する請求書の業務を効率化できるシステムサービスです。通信費の請求書受取から仕訳、支払い、保管までをまとめて管理してくれるため、経理部や総務部が抱える業務の悩みを解消できます。
通信会社から発行された複数の請求書を、Gi通信がまとめて1枚の適格請求書として発行するため、確認作業が一回で済むのも特徴的です。15,000社ほどの経理・総務部担当者が導入した実績もあるため、信頼度の高いシステムです。
② OneVoice公共
OneVoice公共は水道・電気・ガスなど、インフラ設備に関する請求書を1枚で一括管理ができるシステムサービスです。請求書にかかる処理業務を90%も削減ができるため、業務効率化が可能です。
請求書は紙と電子のどちらも対応しているため、インボイス制度の保存方法や電子帳簿保存法のどちらも問題なく利用できます。インフラ設備の請求書に関する経理・総務の担当者の悩みを解決できるでしょう。
③ 弥生会計
弥生会計は、適格請求書の発行や電子帳簿保存法に合わせた保存などを一括管理・対応してくれる会計ソフトです。簿記の知識がない方でも、日付や金額を入力するだけで記帳作業や決算資料の作成ができます。
「スマート憑依管理」や「会計オンライン」などの関連ソフトでは、請求書の仕分けや保存にも対応しており一元管理が可能です。最新の法改正にも対応しているため、インボイス制度の変更や電子帳簿保存法などの変更があっても安心して利用ができるでしょう。
④ freee経理
freee経理は、インボイス制度に対応した請求書の発行や保存方法ができるシステムです。現在使用している会計ソフトを使用したまま、適格請求書の発行・保存が可能です。
専門の導入支援担当がシステム導入のサポートをするため、不明点があっても問題なく利用できます。セキュリティも高い水準で対策を施しているため、情報漏洩の対策も安心できるでしょう。
これらのツールを利用することで、複数税率に対応した請求書や納品書を作成・発行する際の手間を削減できます。また、データはクラウド上に安全に保管され、税務調査や取引先への提出時にも迅速に対応できます。
外部サービスを利用する際の注意点
外部サービスを利用するときには、機能や価格だけでなく、以下のポイントにも注意することをおすすめします。
まず第一に、インボイス制度への完全対応が実現しているかを確認しましょう。例えば、適格請求書発行事業者番号を正確に登録・出力できる機能が必須です。また、税率ごとの消費税額を自動計算し、請求書や納品書に明記できるかも重要なポイントです。
次に、データ管理の安全性を考慮する必要があります。クラウド業者のセキュリティ対策が十分か、個人情報や取引情報が暗号化されているかを確認しましょう。
さらに、サービスの利用コストも注意が必要です。初期費用や月額料金だけでなく、取引量や機能追加に伴う追加料金が発生する場合があります。予算に合わせて選びましょう。
最後に、カスタマーサポートの充実度も考慮したい点です。特に、業務フローに新しいツールを導入する際は、セットアップやトラブル発生時にサポートを受けられるかが重要です。
これらの注意点を意識しながら自社に最適なツールやサービスを選定し、インボイス時代に対応できる柔軟な業務環境を整備しましょう。
よくある質問とその解答
インボイス対応は全ての事業者が必要なのか
インボイス対応は「適格請求書発行事業者」として登録する事業者が対象です。
2023年10月1日から開始されたインボイス制度において、消費税を適正に控除するためには、取引先に対して適格請求書(インボイス)を発行する義務があります。ただし、この義務は「適格請求書発行事業者」として税務署に登録した事業者に限られます。
インボイス登録をしていない免税事業者や、消費税の課税対象とならない事業者は登録の義務自体はありません。しかし、適格請求書を発行できない場合、取引先が消費税の仕入税額控除を受けられない可能性があり、取引先との取引条件に影響を与える可能性もあります。そのため、免税事業者や個人事業主であっても、インボイス制度への準備が求められるケースがあります。
フリーランスや個人事業主が取るべき対応
フリーランスや個人事業主であっても、取引先に適格請求書を必要とされる場合は、インボイス対応が求められます。
具体的には、以下の手順を踏む必要があります。
|
対応手順 |
詳細 |
|
1. 事業内容の確認 |
現在の取引先や、新規で取引を考えている顧客設定を確認し、適格請求書の発行が必要か判断します。 |
|
2. 適格請求書発行事業者の登録申請 |
必要に応じて税務署に登録申請を行います。申請には事業主の基本情報や、事業者区分などの情報が必要です。 |
|
3. 既存請求書フォーマットの見直し |
適格請求書に必要な項目(登録番号、税率ごとの消費税額など)を追加で記載できるように、既存の請求書や納品書を見直しましょう。 |
|
4. 業務支援ツールの導入検討 |
会計ソフトや請求書作成ツールを活用することで、日常業務での対応を効率化できます。 |
特に、事業規模が小さい場合、登録の義務はありませんが、インボイスを発行しないことで取引先に迷惑をかける可能性があるため注意が必要です。
インボイス対応を怠るとどうなるか
インボイス対応を怠った場合、特に適格請求書を発行する義務がある事業者に該当している場合は、法的なペナルティが発生する可能性があります。
具体的なリスクとして以下が挙げられます。
|
リスク |
影響 |
|
法定違反 |
適格請求書が求められる取引において発行を怠ると、法令違反となり、場合によっては税務署からの指導や処罰を受けることがあります。 |
|
取引先との信用損失 |
取引先が仕入税額控除を受けられない場合、取引条件の見直しや契約解除に至る可能性があります。 |
|
事業機会の喪失 |
インボイス対応ができていない場合、新規の取引先との商談が制限され、事業機会を逃す恐れがあります。 |
一方で、免税事業者がインボイス対応を行わずそのまま事業を継続する選択をする場合もあります。この場合、課税事業者に比べて取引上の不利を受ける可能性があるため、事業戦略の見直しが必要となります。
まとめ
インボイス制度は2023年10月に施行され、多くの事業者にとって納品書や請求書の書き方が大きく変わる重要な制度です。特に、適格請求書発行事業者番号や税率ごとの消費税額の明記など、新しい記載事項への対応が求められます。
この記事で解説した通り、納品書と請求書はそれぞれ異なる役割を持つため、インボイス制度に即した形で正確に作成することが重要です。会計ソフトやクラウド請求書管理ツールなどのツールを活用すれば、これらの手間を大幅に減らすことが可能です。改めて、自身の業務フローを見直すことで、インボイス対応をスムーズに進めましょう。










