個人事業主は「請求書」を会社に送付することで「給料」を得られる!書き方についても解説。
更新日:2025.07.25
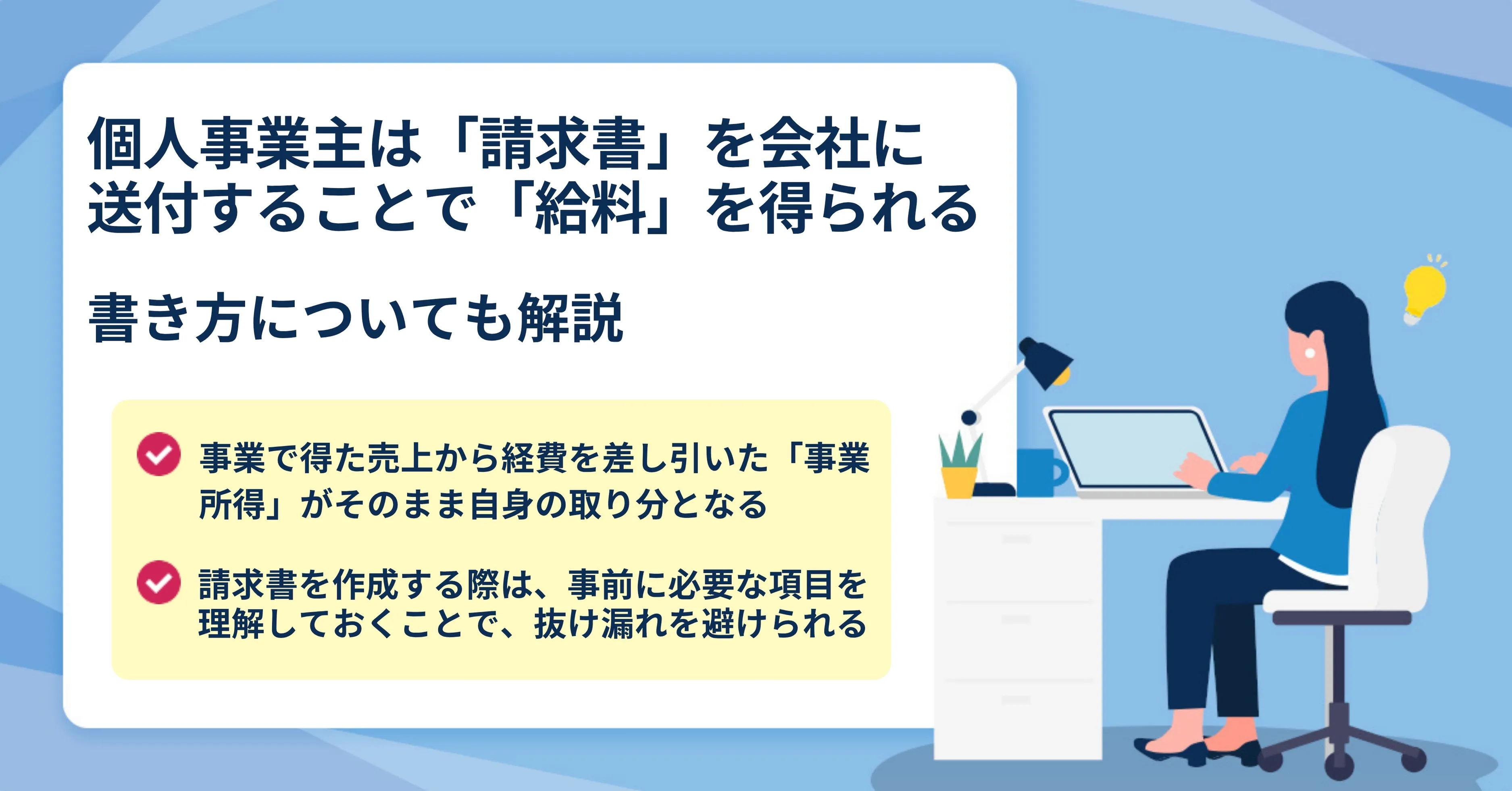
ー 目次 ー
企業とアルバイトの立場で業務委託契約を結んでいる場合、給与を支払うために請求書の発行を求められるケースがあります。請求書を発行する際は、記載事項や企業に確認するべきことを理解しておけばスムーズに作成が進みます。
なお、誤った書き方で請求書を発行した場合、取引先から再発行を求められる可能性があるため注意しましょう。
本記事では、給与を求める請求書の書き方や確認するべき事項を解説します。
給料とは企業から従業員に支払われる労働の対価を指す
そもそも給料とは、企業から従業員に支払われる労働の対価です。
一般的には、企業に雇用されて正社員やアルバイトとして勤務している場合は、請求書を発行する必要がありません。一方で企業に雇用されず業務委託契約を結んでいる際は、請求書を発行して報酬を受け取る必要があります。
契約内容の関係で企業から請求書の発行を求められた場合は、指示に従って作成しましょう。
個人事業主の『給料』に当たるものは「事業所得」
個人事業主は会社員と異なり、「給料」という形では報酬を受け取りません。事業で得た売上から経費を差し引いた「事業所得」がそのまま自身の取り分(報酬)となります。つまり、自分自身に給料を支払うという概念はなく、収益がそのまま生活費や貯蓄に使われる仕組みです。
個人から会社へ報酬をもらうための請求書の書き方とは?
企業から給与を支払うために請求書の発行を求められた際は、請求書を作成しなければなりません。請求書の作成方法を理解していない場合、必要な項目が抜けてしまい、再発行を求められる可能性があります。
ここからは、会社から報酬をもらうための請求書の書き方を解説します。
①請求書に必要な項目を確認する
請求書を作成する際は、事前に必要な項目を理解しておくことで、抜け漏れを避けられます。請求書に必要な項目は、一般的に下記のとおりです。
- 宛名
- 発行者情報
- 請求日
- 取引年月日
- 取引内容
- 小計・消費税・合計金額
- 支払期日
- 振込先
ただし、税務署に適格請求書発行事業者として登録している場合は、インボイス制度の記載方式にしたがった適格請求書(インボイス)を作成しなければなりません。適格請求書には記載事項のルールが定められているため、作成前には記載すべき事項を確認しておきましょう。
インボイス制度に対応した、適格請求書の作成方法は下記の記事で解説しているため、本記事とあわせて参考にしてください。
関連記事:【ひな形あり】インボイスに対応した請求書の作り方を解説
②振込手数料や支払期日を確認しておく
請求書を作成する前に、振込手数料をどちらが負担するか確認しましょう。
振込手数料は、給与を支払う側が負担することが一般的です。業務委託契約を結ぶ際の契約書に記載されていなければ、直接担当者に確認しておきましょう。
ほかにも、給与の支払期日も確認しておくことで、認識の齟齬が防げます。一般的には「月末締め翌月払い」や「月末締め翌々月払い」が多いものの、企業によって異なります。
【テンプレート】請求書の書き方
請求書を作成する際は、事前にテンプレートを用意しておくことで作成時の請求業務の手間を減らせます。請求業務のたびに1から作成すれば、時間がかかるうえ必要な項目を漏らしてしまう可能性もあるでしょう。
ここでは、請求書のテンプレートを2パターンに分けて解説します。
①成果物の納品やサービス提供時の請求書テンプレート
成果物の納品やサービスの提供時に給料が発生する場合は、数量や単価が細かく記載された請求書が発行されます。取引先に提供した商品・サービスにあわせて、項目を記載しましょう。
|
請求書 取引先企業名 自社の企業名 ご請求金額 ¥〇,〇〇〇-(税込)
※印は軽減税率の対象 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②時給での請求書テンプレート
プログラマーやコンサルティングなどの技術を提供する仕事は、成果物ではなく勤務時間にあわせて給料が支払われます。時給制で勤務している際は、数量の部分に働いた時間を記載し、単価に時給を設定しましょう。
|
請求書 取引先企業名 自社の企業名 ご請求金額 ¥〇,〇〇〇-(税込)
※印は軽減税率の対象 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
【注意】個人から個人への請求書の書き方にも大きな違いはない
取引先の状況や契約形態によっては、業務委託契約を結ぶ相手が個人事業主の可能性もあるでしょう。個人事業主宛の請求書の場合も、記載項目は企業と大きく異なる部分はありません。
企業宛の請求書としてフォーマットを作成している際は、内容を変更せずに使用できます。ただし、企業では「御中」としている部分を、個人事業主宛の請求書では「様」と記載しましょう。
個人事業主宛の請求書を作成する方法は下記の記事でも解説しているため、あわせて参考にしてください。
関連記事:個人から個人の請求書の作成方法とは?注意点やおすすめ会計ソフトも紹介
請求書の作成なら請求書作成サービスや会計ソフトの利用がおすすめ
請求書の作成が必要になった際は、請求書作成サービスや会計ソフトを利用しましょう。請求書作成サービス・会計ソフトには書類のテンプレートが用意されており、必要事項を入力するのみで書類が作成できます。
作成した請求書はシステムのなかに保管されるため、自宅で紛失する心配もなくなります。請求書以外の書類を作成できるサービスも多いことから、ほかの書類が必要になった際にも役立つでしょう。
請求書を作成するために役立つ請求書作成サービス・会計ソフト3選!
請求書作成サービスや会計ソフトは多数存在するため、それぞれの特徴を理解しておくことで自分にあったサービスを見つけやすくなります。導入してからあわないことが発覚すると、余計なコストがかかってしまうため注意しましょう。
ここからは、請求書を作成するために役立つサービスや会計ソフトを解説します。
- OneVoice明細
- freee会計
- Misoca
①OneVoice明細
OneVoice明細は、請求書や納品書などのさまざまな帳票を発行できる請求書作成システムです。
小規模ユーザーでも利用しやすいよう、低価格のプランが用意されています。無料のトライアル期間も設けられているため、使用感やサービス内容を試してから自身にあうかどうかの判断が可能です。
用意されたテンプレートは複数あり、自分の好みにあわせて請求書を作成できます。
②freee会計
freee会計は、書類作成機能が搭載された会計ソフトです。請求書以外にも見積書や領収書などが作成でき、企業からほかの書類を求められた際にもスムーズに発行が可能です。
会計ソフト内で作成した内容は、連携した会計ソフトに記帳できるため、内容のミスや漏れを少なくできます。取引先が請求書の郵送を希望した場合でも、ワンクリックで対応でき、送り忘れを防げるでしょう。
③Misoca
Misocaは、すべての機能が無料から使用できる請求書作成サービスです。請求書以外にも見積書・納品書・領収書のテンプレートがあり、さまざまなデザインから書式を選べます。
このサービスは弥生会計と連携ができるため、作成した請求書の情報はそのまま会計ソフトに記帳できます。二重記帳や内容の入力ミスを防げ、確実に帳簿がつけられるでしょう。
まとめ|請求書の書き方を理解してアルバイト先に送付しよう
本記事では、給与を求める請求書の書き方や確認するべき事項を解説しました。
企業と業務委託契約を結んでアルバイトをする場合、給与を支払うために請求書の発行を求められる可能性があります。請求書を作成する前に必要な項目や確認するべき事項を理解しておくことで、作成業務がスムーズに進みます。
請求書の作成に悩む際は本記事を参考に、自身にあった作成方法を選びましょう。










