注文書と請求書の金額が違う場合の対応とは?書類の役割や原因も解説!
更新日:2025.03.03
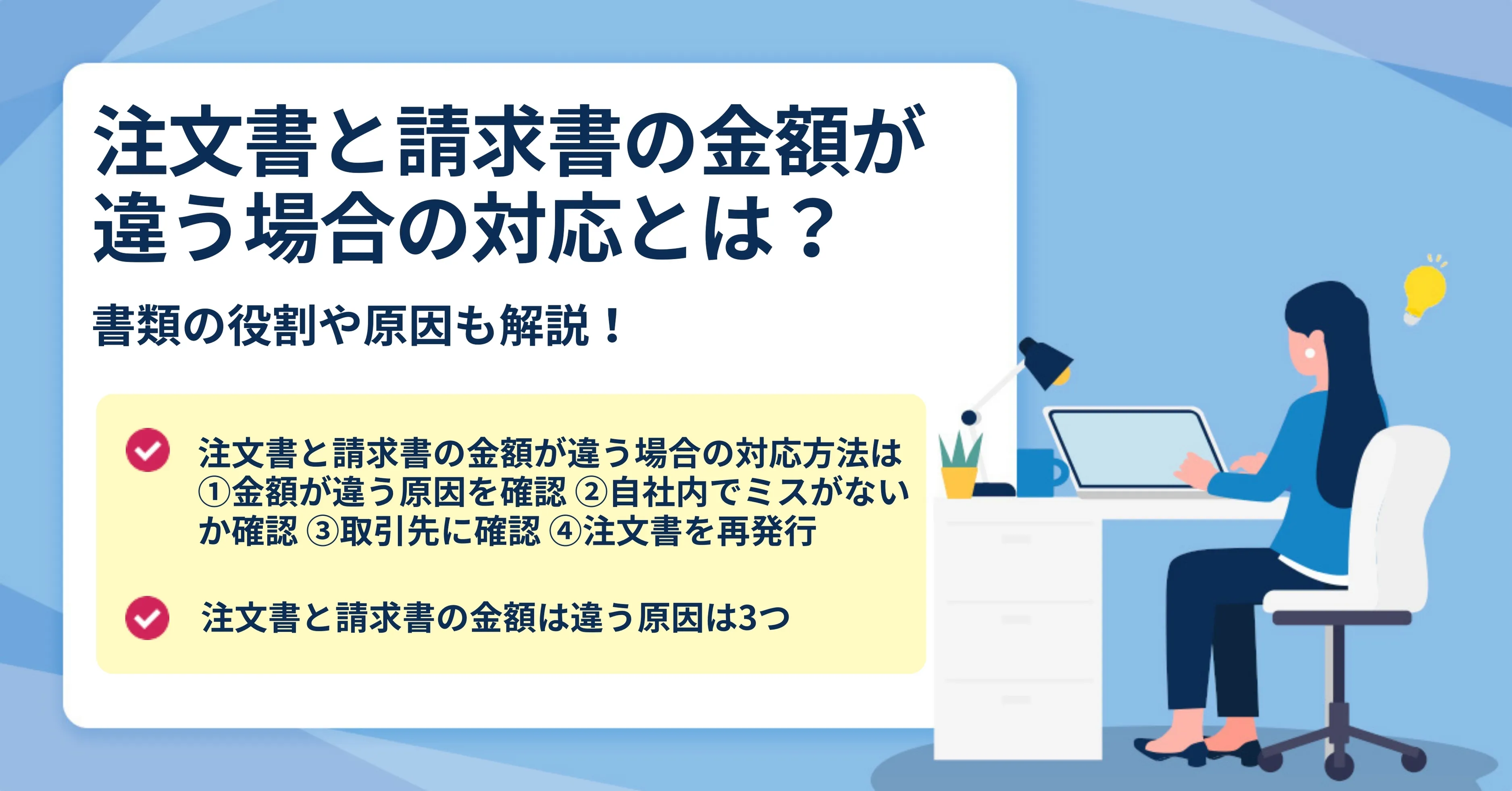
ー 目次 ー
見積書や注文書、請求書や領収書など、ビジネスではさまざまな書類を取引で利用します。そのなかで「注文書」は発注者が取引の依頼の際に、「請求書」は取引内容の対価の支払いを依頼する際に発行する書類です。
基本的に、注文書と請求書の金額は一致することが前提となっています。しかし、この2つの書類で金額が異なった場合にどのような対応が必要なのかを正しく理解しておかないと、税制上のトラブルに発展するおそれがあるため注意が必要です。
本記事では、注文書と請求書の金額が違う場合の対応について、書類の役割や原因を交えて解説します。
【おさらい】見積書や注文書、請求書のそれぞれの役割とは?
見積書や注文書、請求書はビジネスシーンで頻繁に利用される書類であり、それぞれで役割が異なります。また、書類によって法律が定めるルールが異なることもあるため、知っておかなければ大きなトラブルを生じさせるリスクがあります。
そのため、書類ごとの役割を理解したうえで、それぞれのルールを覚えるようにしましょう。
ここでは、見積書や注文書、請求書の役割について、解説します。
見積書は、取引の内容と求める対価を伝えるための書類
「見積書」は商品・サービスの種類や数量、単価などをまとめ、取引をおこなった際の内容や対価を取引先に伝えるための書類です。通常、取引先はこの見積書をもとに、取引を依頼するかを検討します。
見積書は取引をはじめる前に、当事者同士で取引内容の認識を相違させない役割を担っています。当事者同士が同じ認識を持つことにより、取引開始以降のトラブルを防ぐことが可能です。
また、見積書は法律上でも役割を担っており、業界によっては発行義務が科せられています(※)。
(※)参考:e-Gov 法令検索「建設業法」
関連記事:インボイス制度で見積書の扱いはどうなる?必要な内容やよくある質問に回答
注文書は、注文した内容に相違がないようにするための書類
「注文書」とは、取引の当事者同士が注文した際の内容に相違がないように示すための書類です。取引においては見積書を踏まえて、発注者が受注者に対して注文を依頼する際に使われています。
注文書は発注者が依頼した内容を、受注者に正しく認識してもらうための役割を担っています。受注者が依頼内容を理解しておけば、数量や種類、また納期などを発注者が指定したとおりに納品することが可能です。
税制上は、あくまでも「申込事実を記載した書類」としています。ただ、記載内容によっては法的な効力を有する「契約書」として扱われる可能性があります(※)。
(※)参考:国税庁「申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い」
関連記事:インボイス制度で注文書や発注書の対応は変わる?消費税のルールや保存方法、テンプレートを紹介
請求書とは、取引が完了した際に取引先に支払いを依頼する書類
「請求書」とは、取引における商品やサービスの提供が完了した際に対価の支払いを依頼するために発行する書類です。基本的には、受注者が発注者に対して発行し、発注者は請求書の内容をもとに支払いをおこないます。
請求書は、取引当事者が完了した取引の内容に相違がなかったことを示すための役割を担っています。受注者は提供した取引内容に対する対価を正しく認識するため、発注者は支払う内容が取引時に決まった内容であったかを確認するために、請求書が必要です。
また、請求書は2024年10月にスタートした「インボイス制度」の影響を大きく受ける書類でもあります。このように請求書は税制面においても大きな役割を担っている書類です。
注文書と請求書の金額が違う原因とは?
注文書と請求書の金額は、原則、一致していなければなりません。ただ、取引の内容や状況に応じて、注文書と請求書の金額が異なるケースが存在します。このような際に、自社と取引先との取り決めを確認し、金額が違う理由を追求することが大切です。
ここでは、注文書と請求書の金額が違う原因について、以下の3点を解説します。
- 取引内容に変更が生じた
- 取引の提供が遅れた
- 取引内容に問題があった
①取引内容に変更が生じた
取引では、注文書時点の取引内容から商品・サービスの数量や種類の変更・追加などが生じるケースがあります。このようなケースでは注文書で決まった取引内容が変わってしまっているため、請求書との間に金額の差が生じてしまいます。
このようなケースであれば、取引先からの連絡がメールやチャットなどの履歴で残っている可能性が高いです。そのため、取引担当者との連絡履歴を確認し、取引内容に変更があったかを確認すると良いでしょう。
②取引の提供が遅れた
注文書に記載された納期から遅れて商品・サービスの提供があった場合に、計上月を翌月に繰り越しておこなうケースが存在します。このようなケースでは請求書に記載された金額は、注文書の金額よりも低くなっている可能性が考えられるでしょう。また、商品・サービスの一部の提供が遅れた場合も同様です。
このようなケースであれば、社内における取引内容の状況を確認することが必要です。
③取引内容に問題があった
たとえば、取引内容や提供方法などで受注者側で問題が生じた場合に、請求金額が減額されるケースも存在します。取引を締結する際に当事者同士で取り決めをしていれば、請求金額の減額は可能です。
このようなケースが考えられる場合には、商品・サービスの納品状況や取引先の検収状況を確認する必要があります。
注文書と請求書の金額が違う場合の対応方法とは?
注文書と請求書の金額が違う場合、原因によって対応方法が異なります。ただ、対応方法を誤ってしまうと、取引先とのトラブルになりかねません。
このようなトラブルを防ぐ意味でも、正しい対応方法を理解し、適切な行動を起こすことが大切です。
ここでは、注文書と請求書の金額が違う場合の対応方法について、以下の4点を解説します。
- 金額が違う原因を確認する
- 自社内でミスがあったかを確認する
- 取引先に確認する
- 注文書を再発行する
①金額が違う原因を確認する
注文書と請求書の金額が違う理由によって、選択すべき対応方法が異なります。そのため、まずは金額が違う原因について確認することが大切です。
このような問題に対して考えられる点として、以下のようなケースが挙げられます。
- 取引内容に変更が生じた
- 取引の提供が遅れた
- 取引内容に問題があった
取引先や取引内容などによって考えられる原因はさまざまあります。そのため、自社や取引先の状況を踏まえた確認が必要です。
②自社内でミスがあったかを確認する
取引を進めていると、取引内容の納品遅れや請求書の記載内容の誤りなどのケースも想定されます。このような原因で取引先に連絡をしてしまうと、信用を失いかねません。
そのため、取引先に確認する前に、まず自社で問題がなかったのかを確認しましょう。取引内容に直接影響する部署や担当者などへのヒアリングが有効な手段として挙げられます。
③取引先に確認する
自社に問題がなく、かつ取引内容に変更がなかった場合には、取引先に確認しましょう。
取引先に確認する際には、注文書と請求書の金額が違う旨や、自社内で確認したうえで問題がなかった旨を丁寧に伝えます。そのうえで、取引先内で原因がないかを確認してもらうように依頼してください。
丁寧かつ慎重な対応をおこなわないと、今後の取引に悪影響があるかもしれません。
④注文書を再発行する
取引の内容変更や減額対応などで請求書の金額が違った場合には、注文書を再発行しておくと書類の整合性が保たれます。とくに、税務調査があった際には正しい対応をしていることを調査官に示すことが可能です。
このようなことから取引先に連絡し、請求書の金額にあわせた形で注文書の再作成を依頼しましょう。
まとめ|取引先に失礼がないよう、正しい対応をおこなおう!
本記事では、注文書と請求書の金額が違う場合の対応について、書類の役割や原因を交えて解説しました。
本記事で解説したように、見積書や注文書、請求書はそれぞれ取引における重要な役割を担っています。そのため、書類ごとの役割を理解したうえで、それぞれのルールに適した対応が必要です。
また、もし書類に不備があった場合であっても、丁寧にかつ慎重に対応することが大切です。取引先にも対応を依頼するケースも存在するため、その際には失礼がないよう正しい対応をおこないましょう。










