インボイス制度で注文書や発注書の対応は変わる?消費税のルールや保存方法、テンプレートを紹介
更新日:2026.01.29
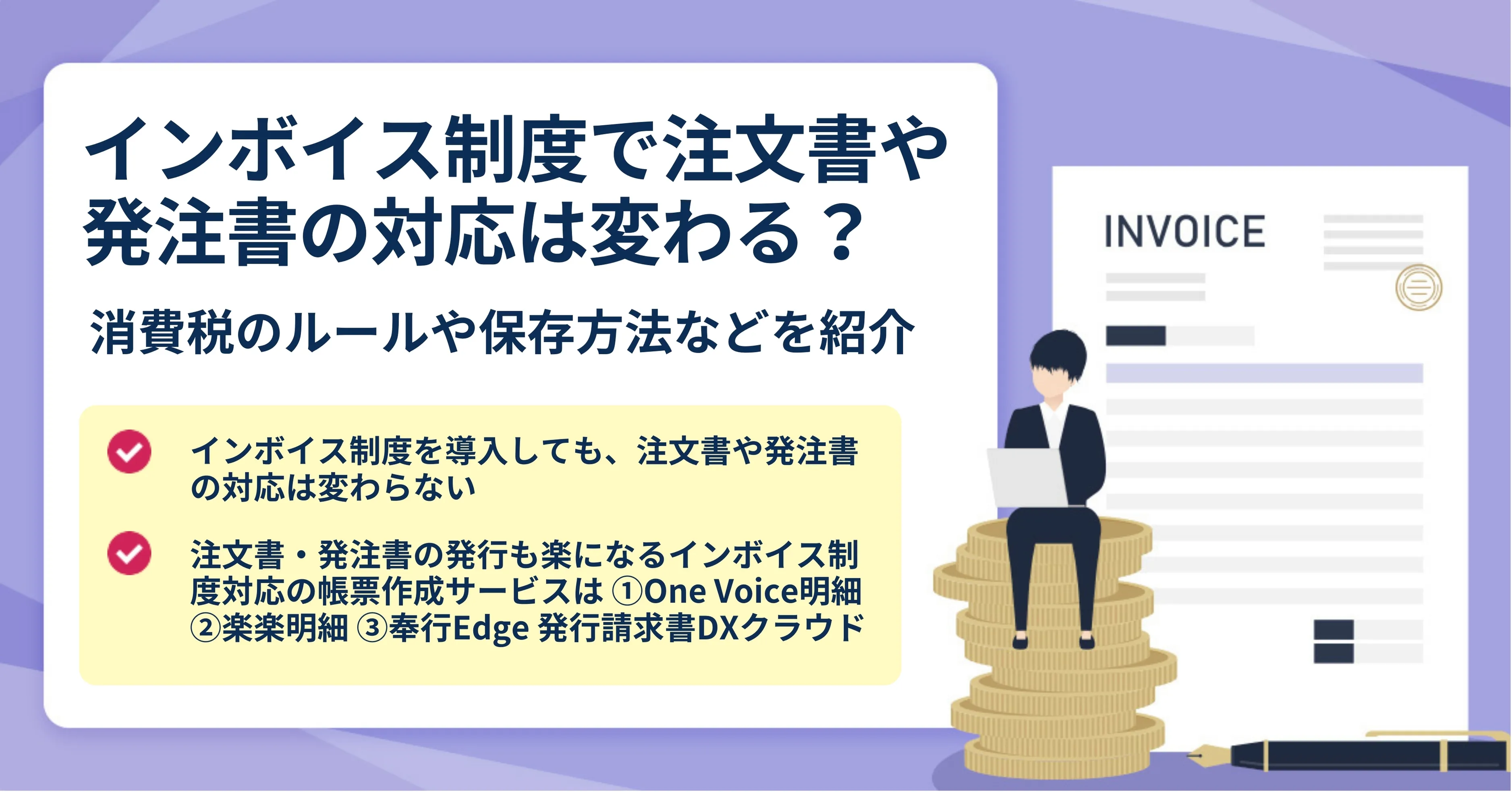
ー 目次 ー
インボイス制度がスタートし、請求書や納品書、領収書などの証憑の記載方式が大きく変更されました。ただ、すべての書類がインボイス制度の影響を受けるわけではなく、たとえば注文書や発注書のルールが変更されたかで疑問を抱く方は少なくありません。
このようなインボイス制度にまつわるルールや変更点を知っておかなければ、税金に関するトラブルや取引先とのトラブルに巻き込まれる可能性があります。正しい知識を理解し、自社の企業運営を健全におこなえるようにしましょう。
本記事では、インボイス制度の導入による注文書や発注書の影響について、消費税のルールや保存方法をあわせて解説します。
【結論】インボイス制度を導入しても、注文書や発注書の対応は変わらない!
インボイス制度は、あくまでも請求書をもとにした書類の記載方式や保存方法を定めたルールです。そのため、本来、契約の申込事実を記載した書類にすぎない注文書や発注書のような書類は対象外となります。
よって、インボイス制度を導入したとしても、注文書や発注書の記載事項や保存方法が変更されることはありません。
一方で、納品書や領収書のような支払いに関する書類は、記載方式を満たせば「適格請求書(インボイス)」として扱えるため、その点には注意が必要です。
注文書や発注書の役割は?それぞれのポイントや違いについても紹介
そもそも注文書や発注書の役割を理解しておけば、インボイス制度への理解が深まりやすくなります。また、同じようなシーンで利用される書類との違いも理解し、それぞれの書類に関する業務にあたるようにしましょう。
ここでは、注文書や発注書の役割について、それぞれのポイントや違いを解説します。
注文書・発注書は、注文した内容に相違がないようにするための書類
注文書とは、取引の当事者同士が注文した際の内容に相違がないように示すための書類です。注文書は取引先との信頼を担保する役割をになっています。また、「発注書」とも呼ばれており、注文書とは大きな違いはありません。
なお、注文書や発注書は、本来、契約の申込事実にすぎないことから、基本的にはインボイス制度の対象外となります(※)。
(※)参考:国税庁「申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い」
注文請書とは、受注書の意思を確認するための書類
注文書と似たような書類で「注文請書」が存在します。
注文請書は受注者が注文した内容に対して、"受け取る意思があるか"を示すための書類です。契約時に取引の当事者同士で注文書と注文請書を利用することで、お互いの取引に対する意思を確認できます。また、お互いの手元に取引内容を明示した書類があるため、情報の相違がないまま取引を進められます。
注文書に記載すべき内容は?テンプレートも
注文書や発注書にあたってはインボイス制度の影響を受けません。ただ、取引をスムーズに進めるためには、記載すべき事項を守ったフォーマットで作成する必要があります。
作成する際には以下の記載事項がそろっているかを確認して作成にあたりましょう。
- 宛先
- 文書の発行日
- 発行元の基本情報
- 納期
- 納入場所
- 支払方法
- 合計金額
- 商品・サービス名
- 商品・サービス名の数量
- 商品・サービス名の単価
- 商品・サービス名の金額
- 消費税額
- 備考
なお、上記にしたがったテンプレートもあるため、あわせて参考にしてください。
発行日:20XX年XX月XX日 注文書 〇〇株式会社 御中 自社名 担当者名 自社住所 件名:〇〇のご注文について 下記のとおりで注文いたします。
|
インボイス制度でフォーマットが変わる書類とは?具体的な変更点も
インボイス制度とは消費税にまつわるルールであり、請求書をはじめとした支払いに関する書類の記載方式や保存方法を定めたものです。まだ対応できていない場合には、インボイス制度の導入や変更となるフォーマットなどを理解し、自社で対応すべきかどうかを検討しましょう。
ここでは、インボイス制度で変更となった書類について、具体的な変更点も交えて紹介します。
①適格請求書(インボイス)
インボイス制度では従来の記載方式から「適格請求書等保存方式」に変更となりました。この変更にともなって、インボイスの登録番号や適用税率、税率ごとの消費税額などの以下の項目を明記して、請求書を作成しなければなりません。
- 発行者の氏名または名称
- 登録番号
- 取引年月日
- 取引の内容(軽減税率対象の品目はその旨も)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額
- 適用税率
- 消費税額
- 受領者の氏名または名称
注:太字は追加された事項
上記のように追加された箇所もあるため、インボイス制度を導入時には自社のフォーマットを変更する必要があります。
②納品書
納品書においても記載方式を満たしていれば、「適格請求書」として同様に扱えます。
なお、一度の取引に複数の書類が必要なときは、すべてを適格請求書にする必要はありません。インボイス制度を利用するためには、取引に使用した書類のどれか1つが適格請求書になっていれば利用可能です。
③領収書
インボイス制度では領収書も記載方式を守っていれば、「適格請求書」として扱えます。また、手書きで作成した領収書であっても適格請求書としての利用が可能です。
なお、小売店や飲食店などの一定の事業では、記載方式が簡略化された「適格簡易請求書」の発行も可能です(※)。もし自社事業が該当する場合には適格簡易請求書も検討しておきましょう。
(※)参考:国税庁「手書きの領収書による適格簡易請求書の交付」
注文書・発注書の発行も楽に!インボイス制度対応の帳票作成サービスとは?
注文書や発注書、また請求書や納品書などの帳票の作成業務は、手間がかかるだけでなく、記載内容や送付先を誤ってしまうと大きなトラブルになりかねません。そのような問題に対して、インボイス制度対応の帳票作成サービスを利用することがおすすめです。
ここでは、インボイス制度対応の帳票作成サービスについて、3つ紹介します。
①One Voice明細
One Voice明細は請求書をはじめとしたさまざまな帳票の作成や割り当て、発行などを一括で対応できるサービスです。
このサービスでは請求先に応じて、さまざまな方法で発行ができるため使い勝手の良さで人気があります。また、無料トライアルも用意しており、試験的な運用をおこなってからの検討も可能です。
試験運用中の導入コストを気にせず、実際の使用感やサポートを見てから利用できる点ではじめての方でも安心して利用できるでしょう。
②楽楽明細
楽楽明細は請求書や納品書などの帳票をインターネット上で発行し、自動で取引先に送付できるクラウドサービスです。
作成にあたっての操作も簡単で、パソコン1台あれば、紙の印刷や郵送に必要な手間がすべて省けます。また、請求先の開封状況もわかるため、請求書が手元に届いたかどうかの心配も不要です。
累計導入件数が10,000社を超えており、シェア率は業界のなかでもトップクラスとなります。
③奉行Edge 発行請求書DXクラウド
奉行Edge 発行請求書DXクラウドはあらゆる基幹システムとの連携から、請求書業務を完全自動化できるサービスです。
既存の導入システムを変更することなく、このサービス1つですべてを自動連携できる機能が備わっています。また、管理機能も充実しており、銀行データを用いての支払い確認も可能です。
ガイドやコミュニティサイトも用意されており、サービスの導入・運用面のサポートも充実しています。
まとめ:システム・サービスの導入で、インボイス制度の対応をスムーズに!
本記事では、インボイス制度の導入による注文書や発注書の影響について、消費税のルールや保存方法をあわせて解説しました。
インボイス制度の施行にともなって、経理・会計周りのさまざまな業務で大きな影響があります。とくに、請求に関する業務では、請求書のフォーマット変更や保存方法の準備などのさまざまな対応が必要です。
このような対応には、帳票も作成してもらえる「帳票作成サービス」の導入がおすすめです。帳票作成や発行、管理などの面倒な手間を一括でき、業務の効率化だけでなく、ヒューマンエラーによる大きなトラブルを未然に防げます。
導入コストを抑えらえるサービスも存在するため、経理の守りを整える意味でも検討してみてください。










