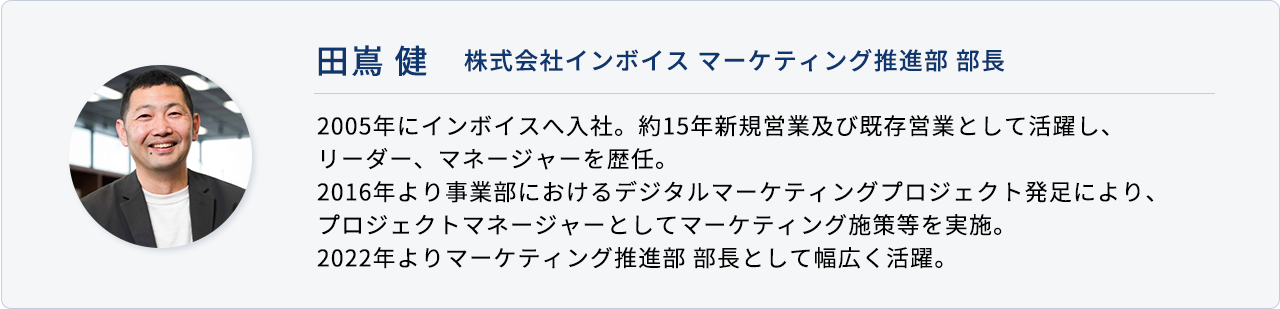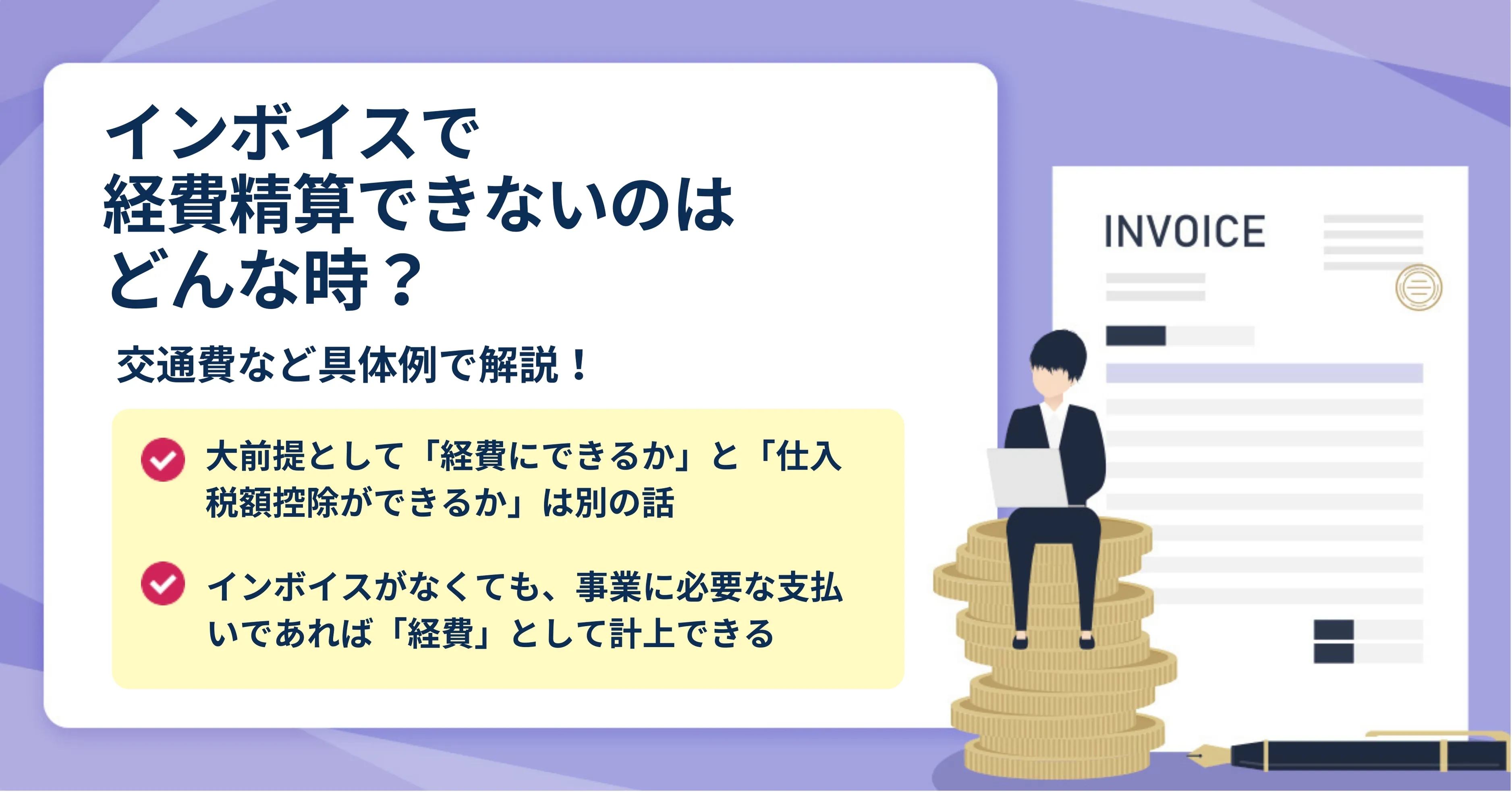インボイス制度は誰が決めた?政府の動きと導入背景をやさしく解説
更新日:2025.12.18
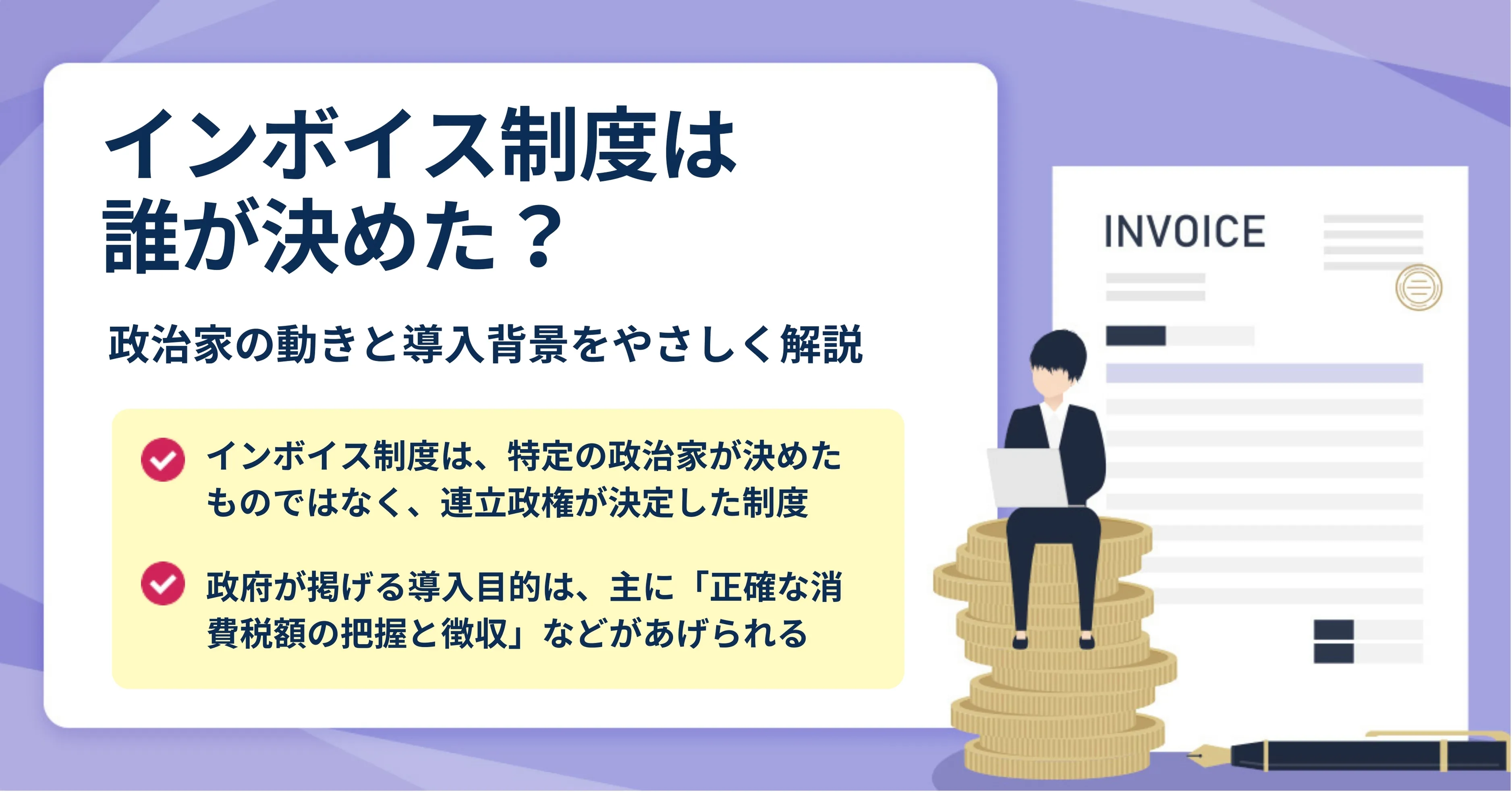
ー 目次 ー
2023年10月から始まったインボイス制度について、「一体誰が、何のために決めたのか」と疑問に思っていませんか。結論から言うと、インボイス制度は自民党と公明党の連立政権が決定しました。この記事では、制度決定の中心となった財務省や与党税制調査会の役割から、安倍政権で骨子が固まり岸田政権で開始に至るまでの具体的な政治の動きを時系列でやさしく解説します。さらに、政府が掲げる導入目的、多くの事業者から「ひどい」と批判される理由、今後の見直しや廃止の可能性まで、インボイス制度をめぐるあなたの疑問を解消します。
【結論】インボイス制度は「自民党・公明党」の連立政権が決めた
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、2016年(平成28年)の税制改正において、当時の自民党・公明党の連立政権によって導入が決定されました。消費税率を10%へ引き上げる際、食料品などに適用される軽減税率(8%)も同時に導入されたため、複数税率に対応する仕組みとしてインボイス制度の導入が盛り込まれたのです。
法案が国会で可決され、数年間の準備・周知期間を経て、2023年10月1日から制度が開始されました。
中心的な役割を担ったのは財務省と与党税制調査会
日本の税制は、一般的に政府・与党が一体となって決定プロセスを進めます。インボイス制度においても、法案の原案を作成する財務省と、それを審議・決定する与党税制調査会(通称:税調)が中心的な役割を担いました。具体的な役割分担は以下の通りです。
|
役割 |
主な組織 |
概要 |
|
制度設計・法案原案作成 |
財務省(主税局) |
税制の専門家集団として、制度の具体的な内容や法律の条文を作成します。 |
|
政策決定・与党内合意形成 |
与党税制調査会 |
自民党と公明党の税制調査会が合同で審議し、与党としての方針を「税制改正大綱」としてまとめます。事実上の最高決定機関とされています。 |
|
法案審議・可決 |
国会(衆議院・参議院) |
政府が提出した税制改正法案を審議し、可決・成立させます。 |
このように、官庁である財務省が実務的な設計を行い、与党である自民党・公明党が政治的な判断を下すという流れで、インボイス制度の導入が決定されました。
野党や国民の反対はあったのか?
インボイス制度の導入決定から施行までには、様々な立場からの意見や反対がありました。
制度の骨子が固まった2016年当時は、消費税率10%への引き上げと軽減税率導入が主な論点であり、インボイス制度自体への反対は現在ほど大きなものではありませんでした。当時は「複数税率を正確に計算するための事務的な手続き」という側面が強く認識されていたためです。
しかし、制度開始が近づくにつれて、これまで消費税の納税が免除されていた免税事業者(特にフリーランスや個人事業主)への影響が明らかになると、状況は一変します。取引から排除されるリスクや、課税事業者になることによる納税・事務負担の増加を懸念する声が急速に高まりました。
現在では、事業者団体や労働組合、市民団体などが制度の延期や廃止を求める大規模な反対運動を展開しています。また、立憲民主党、日本共産党、れいわ新選組といった野党も、インボイス制度に反対の立場を明確にしています。
インボイス制度はなんのために導入された?政府が掲げる3つの目的
インボイス制度の導入は、特定の政治家や政党の独断で決まったわけではなく、政府が掲げる明確な目的がありました。ここでは、制度導入の背景にある3つの主要な目的について、一つひとつわかりやすく解説します。
目的1 正確な消費税額の把握と徴収
インボイス制度が導入された最大の目的は、消費税の仕組みをより正確に運用することです。2019年10月に消費税率が10%に引き上げられた際、食料品など一部の品目には軽減税率8%が適用される「複数税率」が導入されました。
これにより、一つの取引の中に10%と8%の税率が混在するケースが増え、事業者が納めるべき消費税額の計算が複雑になりました。従来の請求書では、どの商品にどの税率が適用されているかが不明確な場合もあり、計算ミスや意図的な不正のリスクが指摘されていました。
インボイス(適格請求書)では、商品ごとに適用税率と消費税額を明記することが義務付けられます。これにより、買手側は仕入税額控除(売上にかかる消費税から仕入れにかかった消費税を差し引くこと)を正確に行えるようになり、国全体として消費税の徴収を透明化し、公平な税負担を実現することを目指しています。
目的2 免税事業者にまつわる益税問題の解消
インボイス制度には、長年課題とされてきた「益税」の問題を解消する狙いもあります。
益税とは、消費者が支払った消費税の一部が国に納められず、事業者の利益として手元に残る状態を指します。これまで、年間売上が1,000万円以下の免税事業者は、顧客から消費税を受け取っても、それを国に納める義務がありませんでした。一方で、取引相手である課税事業者は、免税事業者への支払いであっても消費税相当額を仕入税額控除できていたため、この「ズレ」が益税として問題視されていました。
インボイス制度導入後は、原則としてインボイスがなければ仕入税額控除ができません。免税事業者はインボイスを発行できないため、取引を継続するために課税事業者への転換を選択するケースが増えます。これにより、これまで納税が免除されていた消費税が適切に国庫へ納められ、事業者間の公平性が保たれるとされています。
|
項目 |
制度導入前 |
制度導入後(原則) |
|
免税事業者の納税義務 |
なし |
課税事業者になれば納税義務が発生 |
|
取引先(買手)の仕入税額控除 |
免税事業者からの仕入れでも控除可能 |
インボイスがなければ控除不可 |
|
益税の状態 |
発生しやすい構造 |
解消される方向へ |
目的3 取引のデジタル化推進
インボイス制度は、日本社会全体のデジタル化を推進する役割も担っています。請求書を電子データでやり取りする「電子インボイス(デジタルインボイス)」の普及を後押しすることが、3つ目の目的です。
紙の請求書は、作成、印刷、封入、郵送といった手間とコストがかかり、受け取った側も会計システムへの手入力など非効率な作業が発生していました。電子インボイスが普及すれば、請求から支払い、会計処理までの一連のプロセスをデジタル上で完結させることが可能になります。
これにより、ペーパーレス化によるコスト削減はもちろん、人的ミスの防止や経理業務の大幅な効率化が期待できます。政府は、国際的な標準規格「Peppol(ペポル)」に準拠した電子インボイスの仕組みを推進しており、インボイス制度をきっかけに事業者の生産性向上と、社会全体のDX(デジタルトランスフォーメーション)を加速させることを目指しています。
インボイスは誰が決めた?具体的な政府の動き
インボイス制度は、ある日突然決まったわけではありません。消費税率の引き上げと軽減税率の導入という大きな税制改正の流れの中で、複数の政権にまたがって段階的に議論が進められ、導入が決定されました。
ここでは、どの政権下で、どのような政治的な動きがあったのかを時系列で具体的に解説します。
安倍政権下で制度の骨子が決定
インボイス制度の導入が本格的に決まったのは、安倍晋三元首相が率いる第二次安倍政権のときです。大きなきっかけは、2019年10月の消費税率10%への引き上げと、それに伴う「軽減税率制度」の導入でした。
食料品など一部の品目の税率を8%に据え置く軽減税率が導入されると、取引の中に10%と8%の税率が混在することになります。この複数税率の状況で、事業者が納めるべき消費税額を正確に計算し、不正を防ぐための仕組みとして「インボイス(適格請求書)」が必要不可欠とされました。
この方針は、自民党と公明党の与党税制調査会が中心となって議論を重ね、2016年(平成28年)に公表された「平成29年度税制改正大綱」でインボイス制度の導入が正式に盛り込まれました。つまり、制度の基本的な骨子はこの時点で決定されたのです。
|
時期 |
主な出来事 |
|
2016年12月 |
与党(自民党・公明党)が「平成29年度税制改正大綱」を公表し、インボイス制度の導入を正式に決定。 |
|
2019年10月 |
消費税率10%への引き上げと軽減税率制度が開始。インボイス制度導入の前提となる環境が整う。 |
菅政権・岸田政権を経て制度開始へ
安倍政権で決定された方針は、その後の菅義偉政権、岸田文雄政権へと引き継がれました。菅政権下では、2023年10月の制度開始に向けて、事業者が準備を進めるための期間と位置づけられました。
具体的には、2021年10月からインボイス発行事業者になるための登録申請受付が開始されるなど、実務的な準備が進められました。そして、岸田政権下の2023年10月1日にインボイス制度はスタートしました。
ただし、制度開始が近づくにつれて、特に免税事業者やフリーランスからの反対の声が強まりました。これを受け、岸田政権は事業者の負担を軽減するための「激変緩和措置」を導入することを決定。制度の骨格は維持しつつも、一部修正を加える形で制度開始に至ったのが現状です。
|
時期 |
主な出来事 |
関連政権 |
|
2021年10月 |
適格請求書発行事業者の登録申請受付が開始。 |
菅政権末期〜岸田政権 |
|
2022年12月 |
「令和5年度税制改正大綱」で、事業者の負担を軽減する「激変緩和措置」の導入が決定。 |
岸田政権 |
|
2023年10月1日 |
インボイス制度が開始。 |
岸田政権 |
インボイス制度の今後と見直しの可能性とは?
2023年10月に開始されたインボイス制度ですが、導入後も多くの事業者から負担増を懸念する声が上がっています。こうした状況を受け、政府は事業者の急激な負担を和らげるための「激変緩和措置」を設けています。ここでは、現在の緩和措置の内容と、制度自体の見直しや廃止に向けた政治の動きについて解説します。
激変緩和措置とはどのような内容か
激変緩和措置は、インボイス制度の導入に伴う小規模事業者の税負担や事務負担を軽減するために設けられた、期間限定の特例措置です。主な措置として以下の3つが挙げられます。
|
措置の名称 |
主な内容 |
対象者 |
適用期間 |
|
2割特例 |
売上にかかる消費税額の2割を納付すればよい特例。事前の届出は不要で、確定申告書に付記するだけで適用可能。 |
インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった事業者 |
2023年10月1日~2026年9月30日 |
|
少額特例 |
税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくても帳簿のみで仕入税額控除が可能。 |
基準期間(2年前)の課税売上高が1億円以下の事業者など |
2023年10月1日~2029年9月30日 |
|
少額な返還インボイスの交付義務免除 |
税込1万円未満の値引きや返品、割戻しなどを行った際に、返還インボイスを交付する義務が免除される。 |
すべての事業者 |
定めなし |
これらの措置は、あくまで時限的なものです。特に影響の大きい「2割特例」は2026年9月までのため、対象となる事業者はその後の対応を検討しておく必要があります。
制度の廃止や延期を求める声と政府の反応
インボイス制度に対しては、フリーランスや個人事業主、小規模事業者を中心に、依然として根強い反対の声があります。「事務負担が重すぎる」「免税事業者が取引から排除されるリスクがある」「実質的な増税だ」といった点が主な批判の理由です。声優やアニメ・漫画業界などの団体も反対の声を上げており、オンライン署名やデモ活動なども行われています。
こうした国民の声に対し、政治の反応は与野党で分かれています。
与党である自民党・公明党は、制度を維持する方針を基本としています。ただし、事業者の声に配慮する形で、前述の激変緩和措置を導入しました。岸田政権は「事業者の実情をきめ細かく把握し、丁寧に対応する」としており、今後の状況次第では追加の支援策が検討される可能性もあります。
一方、立憲民主党や日本共産党などの野党は、制度の廃止や延期を強く求めています。国会ではインボイス制度廃止法案が繰り返し提出されるなど、制度の根本的な見直しを求める動きが続いています。今後、緩和措置の適用期間が終了に近づくにつれて、制度のあり方をめぐる議論が再び活発化することが予想されます。
Q&A|インボイス制度に関するよくある質問
ここでは、インボイス制度に関して多くの人が抱く疑問について、Q&A形式で分かりやすく解説します。
海外ではインボイス制度ってどうなっているの?日本との違いは?
インボイス制度と同様の仕組みは、付加価値税(VAT)として世界170カ国以上で導入されており、国際的には標準的な税制度です。特にEU(欧州連合)では、共通のVAT制度として早くから導入されています。
ただし、日本のインボイス制度と海外の制度では、免税事業者の扱いなどに違いが見られます。主な国との比較は以下の通りです。
|
国・地域 |
制度の概要 |
免税点(年間売上高) |
特徴 |
|
日本 |
適格請求書等保存方式(インボイス制度) |
1,000万円 |
・免税事業者からの仕入れは原則、仕入税額控除が不可。 ・複数税率(10%、8%)に対応。 |
|
EU(欧州連合) |
付加価値税(VAT) |
国により異なる(例: ドイツ約350万円、フランス約1,400万円) |
・加盟国間で共通のルールがある。 ・インボイス(VAT請求書)の発行・保存が義務。 |
|
韓国 |
付加価値税 |
約820万円(8,000万ウォン) |
・電子タックス・インボイス制度が普及。 ・デジタル化が進んでいる。 |
このように、多くの国で免税点が設定されていますが、その金額は国によって様々です。日本のインボイス制度は、複数税率に対応する必要がある点や、免税事業者との取引に大きな影響を与える点で、海外の制度と比較して小規模事業者にとって厳しい側面があるという指摘もあります。
なぜ「インボイス制度はひどい」と言われるのか?批判の理由
インボイス制度が「ひどい」と批判される主な理由は、これまで消費税の納税が免除されていた年間売上1,000万円以下の免税事業者(フリーランスや小規模事業者など)に、大きな負担を強いる可能性があるためです。具体的な批判の理由は、事業者それぞれの立場から挙げられています。
免税事業者側の視点
免税事業者にとっては、実質的な増税や事務負担の増加につながる点が大きな問題とされています。
- 収入減少のリスク:取引先からインボイスの発行を求められた場合、課税事業者になる必要があり、新たに消費税の納税義務が生じます。免税事業者のままでいることを選ぶと、取引先から消費税分の値下げを要求されたり、最悪の場合は取引を打ち切られたりするリスクがあります。
- 事務負担の増大:課税事業者になるための登録手続きや、インボイスの要件を満たした請求書の作成、消費税の計算・申告など、経理に関する事務作業が大幅に増加します。
課税事業者側の視点
取引先に免税事業者がいる課税事業者にとっても、新たな対応が必要になります。
- 納税額増加の可能性:免税事業者からの仕入れについては、原則として仕入税額控除が適用できなくなります。これにより、自社が納める消費税額が増加する可能性があります。
- 取引の見直しと経理の複雑化:納税負担を避けるため、取引相手がインボイス発行事業者かどうかを確認し、場合によっては取引先を見直す必要が出てきます。また、受け取った請求書がインボイスの要件を満たしているかを確認・保存する手間も増えます。
これらの理由から、特に体力のない小規模事業者や個人事業主の経営を圧迫する制度であるとして、多くの反対意見や見直しを求める声が上がっています。
まとめ
インボイス制度は、特定の政治家一人が決めたものではなく、自民党と公明党の連立政権が決定した制度です。具体的には、財務省と与党の税制調査会が中心となり、複数税率導入に伴う正確な税収確保を目的として議論が進められました。政府が掲げる導入目的は、主に「正確な消費税額の把握と徴収」「免税事業者にまつわる益税問題の解消」「取引のデジタル化推進」の3点です。しかし、免税事業者や小規模事業者を中心に「事務負担の増加」や「取引からの排除リスク」などを理由とした強い反対の声が上がっており、現在も制度の廃止や見直しを求める動きが続いています。