任意団体はインボイス制度の登録が必要?対応するべきケースや注意点を解説
更新日:2025.12.07
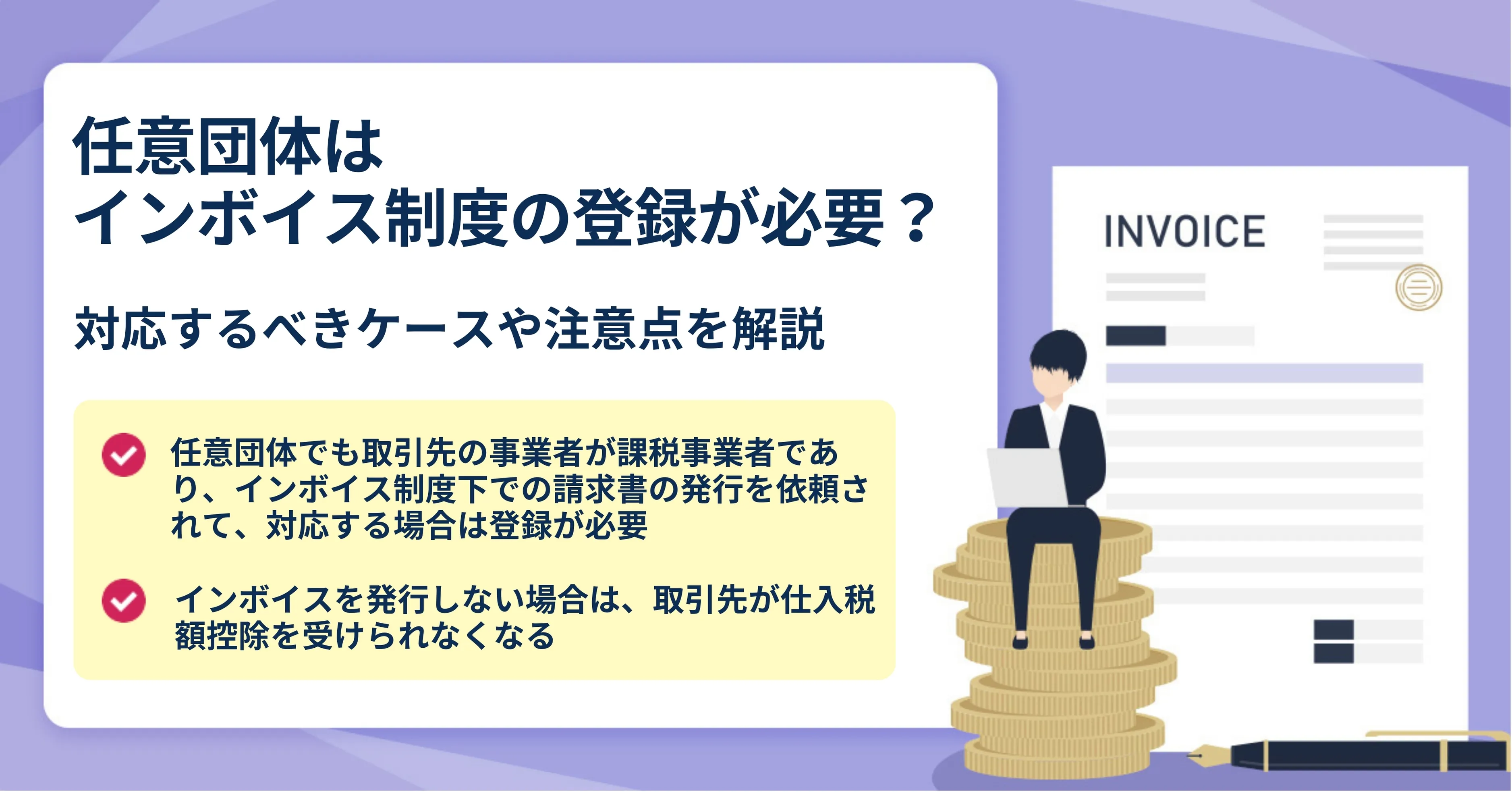
ー 目次 ー
2023年10月に「インボイス制度」が導入され、すべての事業者の取引に対して適格請求書(インボイス)にまつわる対応が求められています。任意団体には関係ないように思えるこの制度ですが、取引先との状況によっては登録が必要になるケースも少なくありません。
インボイス制度の登録が必要になる基準や注意点を理解しておくことで、インボイス制度の対応をおこなう際にスムーズに対応できるようになるでしょう。
本記事では、任意団体のインボイス制度の対応について、基本的な考え方から注意点まで解説します。
【前提】インボイス制度とは、消費税に関する計算や請求書作成・保存のルール
インボイス制度とは、消費税の計算や請求書の記載を定めたルールです。事業者が売上に含まれている消費税を適切に納税することを目的に開始されました。
インボイス制度では「適格請求書(インボイス)」の発行・管理が必要です。このインボイスを受け取った事業者は、「仕入税額控除」を受けられるため、消費税額の負担を軽減できます。
インボイスを発行するには、インボイス発行事業者として税務署に登録する必要があります。しかし、登録すると同時に課税事業者となり、消費税の納税義務が発生する点には注意しましょう。
登録は任意であるものの、取引先にも影響するルールであるため、各事業や取引先の状況を踏まえて検討が必要です。
任意団体でもインボイス制度の登録が必要となる可能性がある
取引している相手が課税事業者の場合、適格請求書(インボイス)を依頼されることがあります。もし、取引先の要望に応えるには、インボイス発行事業者への登録が必要になります。
発行事業者として登録していない場合、正式なインボイスの発行ができないためです。
もしインボイスを発行できなければ、取引先の事業者は控除を受けられなくなり、税負担が増えてしまいます。結果として、取引を打ち切られてしまうリスクがあるため、任意団体であっても場合によっては登録を検討する必要があります。
任意団体が理解しておきたい課税事業者と免税事業者の違いとは?
インボイス制度ではさまざまな用語が存在しており、その意味や内容を理解していないと取引先との税務面でのトラブルに発展するおそれがあります。トラブルを未然に防ぐためにも、インボイス制度の基本的な知識をおさえておくことが大切です。
ここでは、任意団体が理解しておきたい用語を解説します。
課税事業者とは、消費税を納める義務がある事業者
課税事業者とは、消費税を納める義務が発生する事業者のことです。任意団体では、以下のいずれかの条件に当てはまる場合に課税事業者となります。
- 基準期間(前々年度)の課税売上高が1,000万円を超えている
- 特定期間における課税売上高または支払った給与等の額が1,000万円を超える
- 消費税課税事業者選択届出を提出してインボイス発行事業者になる
もし、発行事業者になると、同時に課税事業者になるため消費税の納税が求められます。
免税事業者とは、消費税の納税義務がない事業者
免税事業者とは、消費税の納税義務がない事業者のことです。課税事業者の条件を満たさない場合は免税事業者として事業を運営できます。商品やサービスの価格にかかる消費税について、国に納める必要はありません。
しかし、インボイス制度では「免税事業者=インボイスを発行できない事業者」なため、取引先が仕入税額控除を受けられなくなるデメリットが発生します。
適格請求書発行事業者とは、インボイスを発行できる事業者
適格請求書発行事業者とは、適格請求書(インボイス)を発行できる事業者のことです。適格請求書発行事業者がインボイスを発行することで取引先が仕入税額控除を受けられます。
インボイス発行事業者として事業を進めたい場合、税務署への登録が必要です。この登録が完了すると、税務署から登録番号が付与され、インボイスの発行が可能となります。
ただ、インボイス発行事業者になると、消費税の申告・納付義務が発生することも覚えておきましょう。
任意団体がインボイス制度を登録する際の2つの方法とは?
任意団体としてインボイス制度に登録する場合は、関係者全員がインボイス発行事業者でなければなりません。もし、インボイス制度の登録について理解が曖昧な場合、手続きに手間取ってしまうおそれもあるでしょう。
関係者全員がスムーズにインボイス制度へ登録するためにも、事前にどのような手順で進めるのかを理解しておくことが大切です。
ここでは、インボイス制度を登録する際の2つの方法を解説します。
①電子申請(e-Tax)での登録手順
電子申請(e-Tax)によるインボイス制度の登録は、以下の手順で進めます。
- e-Taxソフトまたはe-Taxソフト(WEB版)にアクセス
- 「申請・届出手続」から「適格請求書発行事業者の登録申請手続」を選び、必要事項を入力
- 入力内容を確認し、申請データを送信する
- 登録完了後、「T+法人番号(13桁)」の登録番号が通知される
e-Taxの利用には、本人のマイナンバーカードまたは通知カードと身元確認書類を用意する必要があります。
②書面での登録手順
書面によるインボイス制度の登録手続きは、以下の流れです。
- 国税庁の公式サイトから「適格請求書発行事業者の登録申請書」をダウンロードする
- 申請書に法人名、所在地、代表者情報など必要事項を記入する
- 記入済みの申請書を、所轄の税務署またはインボイス登録センターに郵送する
- 通常、申請から約1.5か月後に「登録通知書」が郵送されるため保管する
書面での申請はインターネットに抵抗がある方や、複雑なシステム操作に不慣れな方に向いています。通知書の再発行は原則できないため、紛失しないよう注意しましょう。
任意団体がインボイスを登録する際の4つの注意点
取引先からインボイスを求められた結果、発行事業者になろうと検討している任意団体も少なくありません。しかし、注意点を理解していないと税金や事務の負担が増えてしまうおそれがあります。
そのため、インボイス制度に登録する前に以下の注意したいポイントを押さえておきましょう。
ここでは、任意団体がインボイスを登録する際の4つの注意点を解説します。
- 登録時には団体全員が発行事業者になる必要がある
- 取引先が未対応の場合、仕入税額控除を受けられない
- インボイス制度の対応により、事務負担が増える
- 消費税の支払いによる負担が増える
①登録時には団体全員が発行事業者になる必要がある
任意団体の場合、組合としてインボイス制度を活用するには、全員がインボイス発行事業者でなければ登録できません。
組合としてインボイス制度を活用するためには「任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出書」を提出する必要があります。また、新規メンバーが加わったり、誰かが抜けたりする際にも追加で届出を提出する必要があることも覚えておきましょう。
②取引先が未対応の場合、仕入税額控除を受けられない
インボイス制度に登録すると課税事業者になります。
もし、発注側として取引している事業者がインボイス制度に未登録の場合、その取引では仕入税額控除を受けられません。そのため、免税事業者が取引先に多い場合には、インボイス制度の登録によって税負担が増えるケースも想定されるでしょう。
自団体の事業状況を考えて、総合的に判断することが大切です。
③インボイス制度の対応により、事務負担が増える
インボイス制度では、請求書や納品書の記載内容や保存方法について、これまで以上に厳格なルールが定められています。また、従来の方法から変更された対応もあるため、その対応のために事務負担が増えてしまうリスクがあります。
たとえば、これまでの請求書のフォーマットから、適格請求書(インボイス)のフォーマットに変更しなければなりません。また、保存方法も変更となったため、電子帳簿保存法の要件を満たしたシステムやサービスの使い方を把握する必要もあります。
これらの対応は、とくに事務担当者が少ない小規模な任意団体にとっては大きな負担となるでしょう。
④消費税の支払いによる負担が増える
インボイス制度を利用するために課税事業者となると、売上に対する消費税の納付が必要になります。これまで免税事業者として消費税の納税義務がなかった団体にとっては、負担となるでしょう。
たとえば、年間売上が500万円の任意団体の場合、消費税率10%として単純計算すると、50万円の消費税を納めなければなりません(※)。
インボイス制度への登録を検討する際には、このような経済的負担の増加も十分に考慮した上で判断することが大切です。
(※)仕入税額控除を含めない場合
まとめ|任意団体でもインボイス制度が必要な場合は速やかに登録しましょう
本記事では、任意団体のインボイス制度の対応について、基本的な考え方から注意点まで解説しました。
任意団体は取引先の状況によってインボイス制度の登録が必要になるケースがあります。しかし、発行事業者になると同時に課税事業者となるため消費税額の負担が発生します。
このようなことから、取引先との関係性のみに限らず、コストや事務負担など総合的に考慮してインボイス制度の登録を検討しましょう。また、インボイス制度に登録する場合には、適切な対応ができるような準備を進め、税務上のトラブルが起こらないような対策も必要です。










