Uber Eatsの配達員はインボイス制度への登録が必要?制度の概要や対応を解説
更新日:2026.01.13
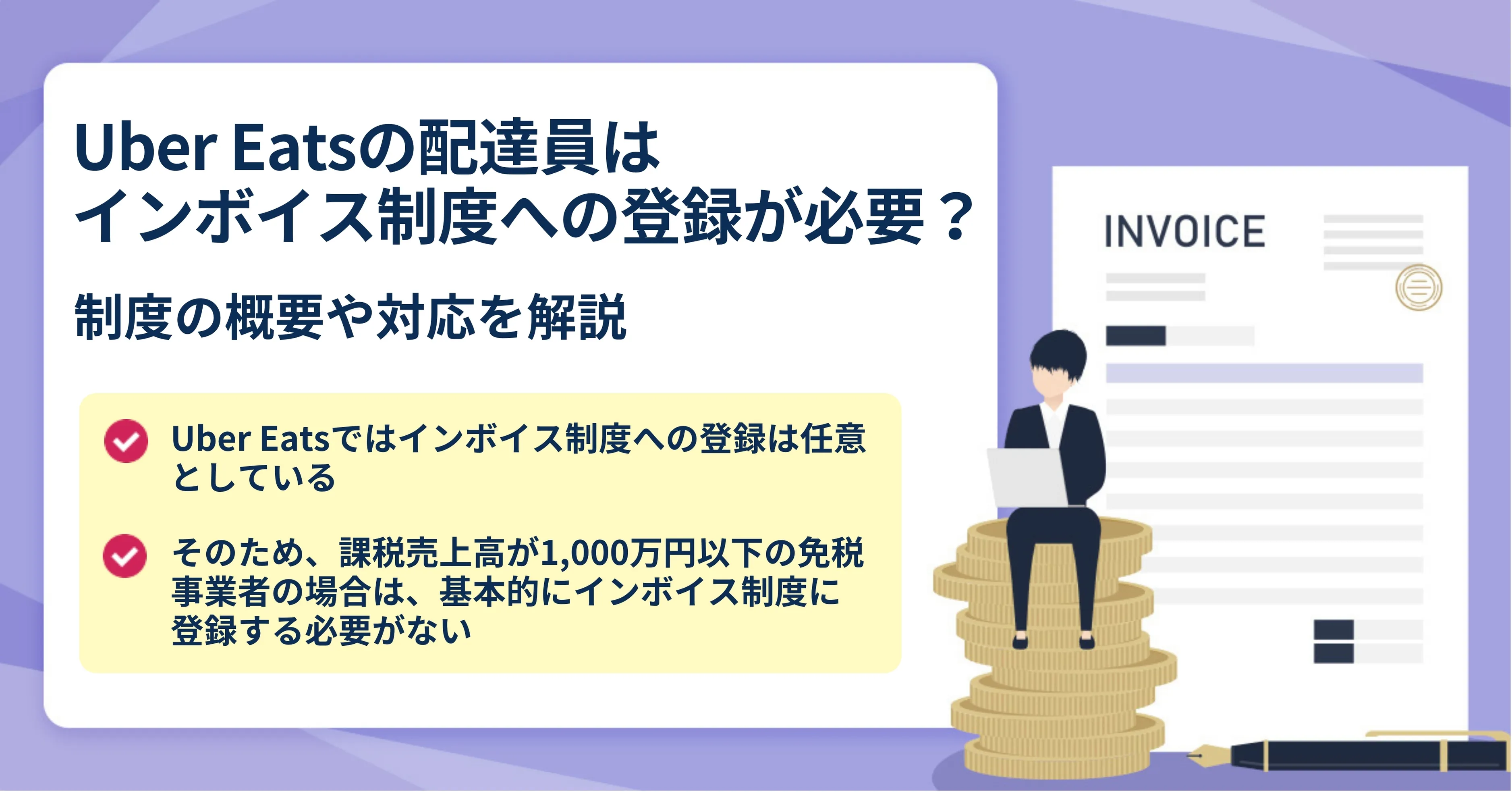
ー 目次 ー
2023年10月1日から、消費税にまつわるルールを定めた「インボイス制度」がはじまりました。この制度は、Uber Eatsをはじめとするフードデリバリーサービスにも影響を与える可能性があります。
とくに、インボイス制度によって、Uber Eatsの報酬面にかかわる影響が危惧されています。そのため、Uber Eatsの配達員として稼働を続けるうえでは、インボイス制度の概要を把握することが重要です。
本記事では、Uber Eatsの配達員がインボイス制度に登録すべきかや制度の概要、選択できる対応方法について解説します。
インボイス制度とは、消費税にまつわる対応方法を定めたルール
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、2023年10月1日からはじまった新しい制度です。現在、日本の消費税率は8%と10%の2種類であり、納付税額の透明性を担保するためにインボイス制度が導入されました。
インボイス制度によって消費税額を適切に計算することで、仕入税額控除を正確に適用できます。制度が開始された2023年10月1日以降、仕入税額控除を適用するには取引先からインボイス(適格請求書)を交付してもらわなければなりません。
インボイスとは売手が買手に対して、正確な消費税率や消費税額を伝えるためのものです。法律で定められたインボイスを発行するには、インボイス制度への登録申請が必要となります。
ただ、課税売上高が1,000万円以下の免税事業者であっても、インボイス制度に対応するためには消費税の納付・申告が必要となる点に注意しましょう。
【結論】Uber Eatsの配達員はインボイス制度に登録しなくても問題ない
Uber Eatsの発表によれば、インボイス制度を利用しない配達員に対して報酬から消費税の相当額を除くことはありません。また、インボイス制度への登録はUber Eatsから求めるものではなく、任意としています。
そのため、課税売上高が1,000万円以下の免税事業者の場合は、基本的にインボイス制度に登録する必要はありません。
ただし、Uber Eats側が消費税を負担している状況であり、この対応がいつまで続くのかは不明です。将来的に報酬に影響が出る可能性があるため、現在、インボイス制度に登録する予定がない方も制度の概要を知っておくことが大切です。
Uber Eatsの配達員として選べる2つの選択肢とは?
現状、Uber Eatsの配達員として選べる選択肢は、インボイス制度に登録するかしないかの2つです。どちらを選択するにしても、メリット・デメリットが存在します。
そのため、自身の状況にあわせてインボイス制度に登録すべきか、免税事業者として働くかを決めることが大切です。
ここでは、Uber Eatsの配達員として選べる2つの選択肢について解説します。
- インボイス制度に登録する
- インボイス制度に登録しない
①インボイス制度に登録する
Uber Eatsではインボイス制度への登録を配達員に要請していませんが、自主的に登録することが可能です。登録して適格請求書発行事業者になれば、将来的にUber Eatsの対応が変更した場合でも焦らずに済みます。
他社フードデリバリーサービスでは、インボイス制度に登録済みの配達員にのみ消費税を上乗せして報酬を支払うケースがあります。そのため、Uber Eatsとほかのサービスを掛け持ちする場合は、インボイス制度への登録の検討が必要です。
ただし、インボイス制度に登録すると、課税売上高が1,000万円以下の免税事業者であっても、消費税の納付・申告義務が発生します。
また、消費税額の計算やインボイス発行などの事務処理も負担となるため、慎重に検討することが重要です。
②インボイス制度に登録しない
2025年4月現在、Uber Eatsの配達員にインボイス制度への登録は求められていません。そのため、インボイス制度に登録していなくても、今までどおり配達員として働き続けられます。
現状では運営元のUberが消費税を負担しているため、報酬が減る心配はないでしょう。
免税事業者で年間の報酬額を20万円以下に抑えているなら、これまでどおり確定申告の必要がなく、事務処理の手間が増えずに済みます。Uber Eatsの対応が変わらないのであれば、インボイス制度に登録しないメリットのほうが大きいです。
ただし、今後の対応に変更がある場合は、インボイス制度への登録要請や報酬の減額などの可能性があることを覚えておきましょう。
Uber Eatsで1,000万円の売上があれば、インボイス制度への登録がおすすめ!
年間の売上高が1,000万円を超えるUber Eatsの配達員は、インボイス制度への登録を検討するのがおすすめです。年間の売上高が1,000万円を超える場合、課税事業者の対象となる可能性があります。
また、Uber Eatsでは不要でも、ほかの副業や仕事でインボイス制度への登録を求められる可能性がある方も検討しておくべきでしょう。
ただし、インボイス制度に登録すると、Uber Eatsの報酬から消費税を納付しなければならず、手取り収入が減ることになります。また、インボイス制度への登録にともなって課税事業者になった場合、課税期間の初日から起算して2年間は免税事業者に戻れません。
今後のことも考慮して、インボイス制度に登録するかを慎重に検討しましょう。
Uber Eatsの配達員がインボイス制度に登録する方法・流れ
Uber Eatsの配達員がインボイス制度に対応するためには、制度への登録とドライバーアプリへの登録が必要です。それぞれの手順を把握していれば、スムーズに登録できます。
また、現在登録する予定がない方も、将来的な登録に備えて流れを押さえておきましょう。
ここでは、Uber Eatsの配達員がインボイス制度に登録する方法・流れを解説します。
- Uber Eatsの配達員がインボイス制度に登録する方法
- Uber Eatsにインボイス番号を登録する方法
①Uber Eatsの配達員がインボイス制度に登録する方法
インボイス制度に登録するには、納税地を管轄する税務署長への登録申請が必要です。登録申請はe-Taxまたは書類の郵送にておこなえます。
e-Taxは24時間いつでも登録申請ができるため、書類での申請と比べても利便性が高いです。e-Taxから申請するには、マイナンバーカードと利用者識別番号が必要となります。
スマートフォンを使ったe-Tax申請の手順は以下のとおりです。
- マイナンバーカードを使ってe-Taxにログインする
- ログインしたら、利用者識別番号を取得・登録する
- 画面にしたがって、登録申請データの作成に必要な情報を入力する
- データ作成が完了したら、電子署名をおこなってデータを送信する
e-Taxで登録申請をおこなったあとは、登録したメールアドレスに通知が届いているかを確認しましょう。
②Uber Eatsにインボイス番号を登録する方法
Uber Eatsでは、ドライバーアプリからインボイス番号の登録が可能です。以下ではインボイス制度に登録したあとの対応方法を紹介します。
- Uber Eatsのドライバーアプリにあるメニューから「アカウント」を選択する
- 「税務情報」の項目から「税の設定」を選び、必要な情報を入力する
- ボックスにチェックを入れて、インボイス番号を入力する
- 免責事項に同意して「送信」をタップする
インボイス制度に登録済みの方は、上記の方法でUber Eatsにインボイス番号を登録しましょう。
【Q&A】Uber Eatsのインボイスに関してよくある質問
最後に、Uber Eatsのインボイスに関してよくある質問を紹介します。
①Uber Eatsの配達員がインボイスに登録しないとどうなる?
Uber Eatsの配達員がインボイス制度に登録しなくても、とくに問題はありません。今までどおり稼働を続けられます。
②Uber Eatsの配達員は課税事業者になるべき?
ほとんどのUber Eats配達員は、インボイス制度に登録して課税事業者になる必要はありません。
ただし、課税売上高が1,000万円を超える課税事業者は、インボイス制度への登録を検討したほうが良いケースがあります。
③インボイス制度でUber Eatsの配達員は手取りが減る?
インボイス制度に登録しない場合、Uber Eats配達員の手取りが減る心配はありません。
ただし、インボイス制度に登録して課税事業者になると、消費税の納付義務が発生して手取りが減る場合があります。
まとめ|Uber Eatsの配達員もインボイス制度の概要を把握しておこう
本記事では、Uber Eatsの配達員がインボイス制度に登録すべきかや制度の概要、選択できる対応方法について解説しました。
2025年4月現在、Uber Eatsの配達員はインボイス制度に登録しなくても良いでしょう。
インボイス制度に登録しているかにかかわらず、これまでどおり消費税を含む報酬が支払われます。インボイス制度に登録していない場合でも、稼働に大きな影響はありません。
ただし、現状では運営元のUberが消費税を負担しており、今後の対応が変更される可能性があります。現時点でインボイス制度に登録する必要はありませんが、Uber Eatsの配達員は制度の概要を理解しておきましょう。










