タクシー事業者がインボイス制度に対応するメリットとは?ルールや領収書の書き方も解説
更新日:2025.03.27
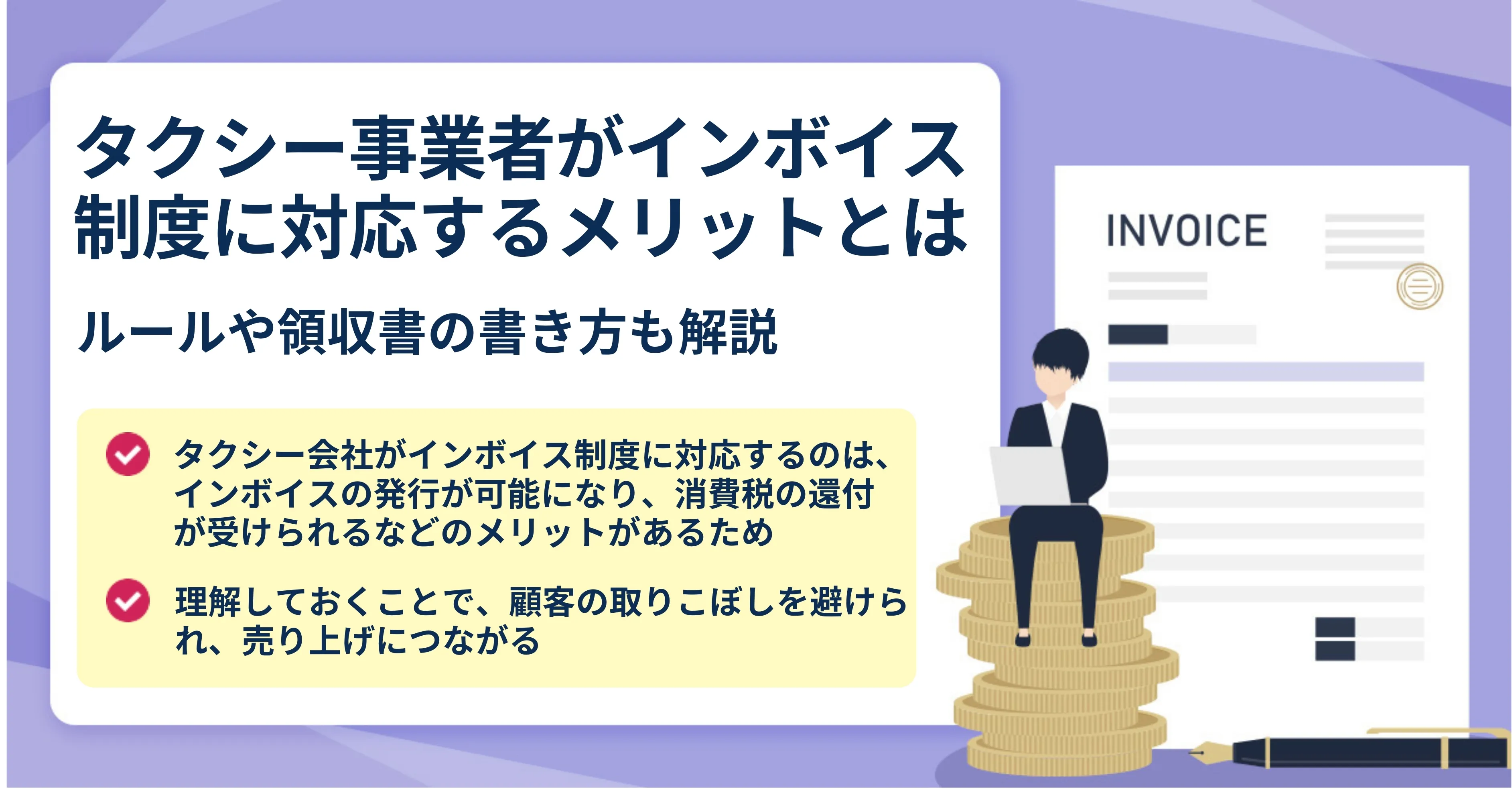
ー 目次 ー
2023年に施行されたインボイス制度は、複数の税率でも事業者が消費税を正しく納めるためのルールを定めた制度です。この制度の施行にともなって「インボイス(適格請求書)」が導入され、請求書の記載方法や消費税の計算方法にルールが定められました。
インボイス制度では、インボイスを発行するための要件として「適格請求書発行事業者」への登録が必要です。このことから、タクシー事業者もインボイス(適格請求書)を発行したい場合、税務署やインボイス登録センターに適格請求書発行事業者として登録しなければなりません。
このようにインボイス制度はタクシー事業者においても大きな影響を与えるルールです。消費税に関する大切なルールであることから、基本的なルールやインボイスの取扱いなどの理解が求められます。
本記事では、インボイス制度がタクシー事業者に与える影響やメリット・デメリットを解説します。
【前提】インボイス制度とは、領収書や請求書などに影響がある消費税の制度
インボイス制度とは、2023年に施行された事業者が消費税を正しく納税するためのルールを定めた制度です。この制度では「インボイス(適格請求書)」によって、請求書の書き方や消費税に関するルールを定めています。
ただ、このインボイスを発行するためには、事前に税務署へ適格請求書発行事業者として登録申請する必要があります。これはインボイスの発行・保存の両方において必要な要件であるため、インボイス制度を利用したい場合には登録手続きをおこないましょう。
なお、インボイス制度の要件にしたがってインボイスの発行・保存をした場合、売上にかかる消費税から仕入れにかかる消費税を差し引ける仕入税額控除が適用されます。
タクシー事業者へのインボイス制度の影響とは?具体的な対策や注意点も
インボイス制度がタクシー事業者に与える影響は、乗客の減少や申請の手間などが考えられます。これは個人事業主として事業をおこなうタクシードライバーであっても同様です。
まだインボイス制度の登録をおこなっていない場合には、制度が与える影響を理解しておくことで、登録するべきかの判断がしやすくなるでしょう。
ここでは、タクシー事業者へのインボイス制度の影響を解説します。
①乗客が減少するおそれがある
タクシーの乗客は、一般消費者以外にも個人事業主や法人のような事業者が想定されます。
もし、事業者の乗客が仕入税額控除の利用を考えている際、インボイス(適格請求書)が発行できないタクシーの利用は避けられるおそれがあります。結果的に、利用してもらえる乗客数が減ってしまい、収益が減少するかもしれません。
このことから、乗客を減らさないためにもインボイス制度への登録の検討が必要といえます。
②インボイス(適格請求書)を発行するには事前申請が必要
インボイス(適格請求書)は、税務署に登録した適格請求書発行事業者のみが発行できます。また、仕入税額控除を適用してもらう場合にも、インボイスの保存が必要であり、保存についても適格請求書発行事業者でなければなりません。
このような要件があることから、もしインボイス制度に対応したい場合には、必ず適格請求書発行事業者への登録をおこないましょう。
なお、登録手続きは郵送での申請で約1か月半、e-Taxの利用でおよそ1か月の期間を要するため、インボイス制度の対応を検討していれば注意が必要です。
③事務対応が増加する
インボイス(適格請求書)は従来の請求書と比べて、記載項目が追加されています。そのため、インボイスを発行するためには、自社の請求書や領収書のテンプレートを変更する必要があります。
また、インボイス制度に登録すれば、消費税の申告・納付が必要です。
このように従来まで不要であった事務対応が増加する可能性が高く、この点には注意しなければなりません。
タクシー事業者がインボイス制度に対応するメリット
適格請求書発行事業者に申請することで、インボイス(適格請求書)の発行が可能になる、消費税の還付が受けられるなどのメリットがあります。メリットを理解したうえでインボイス制度に対応すれば、税務上のトラブルを未然に防げるだけでなく、事業者の乗客の取りこぼしを避けられ、売上につながるかもしれません。
ここでは、タクシー事業者がインボイス制度に登録するメリットを解説します。
①インボイス(適格請求書)の発行が可能になる
インボイス制度に登録すれば、インボイス(適格請求書)の発行が可能です。
インボイス制度に登録した乗客は仕入税額控除を受けられ、税負担の軽減につながります。そのため、タクシー代で仕入税額控除を受けたい事業者は、インボイスを発行できるタクシー会社を積極的に選ぶ可能性が高まるでしょう。
結果的に、顧客を取りこぼす心配がなく、売上の向上につながる可能性があります。
②消費税の還付が受けられる可能性がある
消費税の申告・納付をおこなったうえで、仕入れに支払った消費税が売上にかかる消費税よりも大きい場合には消費税の還付が受けられます。事業者であれば、設備投資や新規事業の立ち上げなどで大きなコストを支払っていれば、税負担の大幅な軽減が図れるでしょう。
ただ、仕入れに支払った消費税が少なければ、消費税の還付のメリットはあまり受けられない点に注意が必要です。
タクシー事業者がインボイス制度に対応するデメリット
インボイス制度に申請する際は、経理担当者の負担増加が想定されます。ほかにも、消費税の納税義務が増え、収入が減少するケースもありえるでしょう。
ここでは、タクシー事業者がインボイス制度に申請するデメリットを解説します。
①経理担当者の負担が増える
インボイス制度に対応したインボイス(適格請求書)では、記載する項目や消費税の計算方法のルールが細かく定められています。適格請求書発行事業者へ登録後は、請求書の書式変更や納税時に消費税の計算などの手間がかかります。
個人事業主としてタクシーの事業を営む場合でも、経理の業務フローを見直す必要があるでしょう。
②消費税の納税義務が生まれる
適格請求書発行事業者として登録した事業者は、消費税の申告・納付義務が生じます。そのため、これまでは免税事業者として事業を営んでいる場合には、税負担や事務負担の増加が懸念されます。
なお、免税事業者がインボイス制度のタイミングで課税事業者になった場合には、納付する消費税の8割が控除される「2割特例」の利用も可能です。
タクシー事業者では簡易インボイス(適格簡易請求書)の発行が可能
インボイス制度に対応する請求書の様式では、インボイス(適格請求書)の利用が基本です。ただし、不特定多数が対象のタクシー事業は、記載項目が一部免除されている「簡易インボイス(適格簡易請求書)」の発行が可能です。
インボイスでは、発行する際に受取事業者の正式名称を記載する必要があります。一方で、簡易インボイスでは受取事業者の名称を省略でき、ドライバーの負担が増える心配はありません。
インボイス制度に対応する際は簡易インボイスのテンプレートを作成しておくことで、発行時の負担を大幅に軽減できます。
【見本】タクシー事業者が簡易インボイス(適格簡易請求書)を発行する際の書き方
簡易インボイス(適格簡易請求書)には記載項目が定められているため、事前に確認しておくことで発行時のミスを防げます。あわせて、自社にあわせたテンプレートを作成しておき、発行をスムーズにしましょう。
ここでは、簡易インボイスを発行する際の書き方とタクシー事業者向けのテンプレートを解説します。
- 自社の名称・登録番号
- 料金が支払われた日
- 取引内容
- 取引金額
- 適用税率
|
領収書 取引年月日 基本運賃 〇〇円 消費税率 10% |
①自社の名称・登録番号
簡易インボイス(適格簡易請求書)を発行する際は、税務署に申請した自社の正式名称を記載しましょう。個人事業主の場合は、本名を記載する必要があります。
あわせて、税務署に申請した後に発行された登録番号の記載も必要です。登録番号は「T+13桁の数字」で構成されるため、Tから記載しておくことで乗客が見た際にわかりやすくなります。
②料金が支払われた日
簡易インボイス(適格簡易請求書)には、タクシーが利用された日付を記載しましょう。なお、乗車時間と降車時間で日付をまたぐ際は、降車した日を記載することが一般的です。
③取引内容
取引内容には、タクシーでの利用とわかる旨を記載しましょう。たとえば、「基本運賃」「迎車料金」と記載すれば、項目ごとに発生している料金が明確になります。
④取引金額
取引金額には、乗客から領収した金額を記載しましょう。簡易インボイス(適格簡易請求書)では、適用税率と税込金額が記載されていれば税抜金額の記載は免除されます。
なお、タクシー代は一般的に内税のため、税抜金額で記載する必要はありません。
⑤適用税率
簡易インボイス(適格簡易請求書)でも、商品・サービスの適用税率を記載する必要があります。タクシー代は軽減税率の対象外のため、標準税率を記載しましょう。
まとめ|タクシー事業者は簡易インボイス(適格簡易請求書)で対応しよう
本記事では、インボイス制度がタクシー事業者に与える影響やメリット・デメリットを解説しました。
タクシー事業者がインボイス制度に対応する場合、メリット・デメリットがあるため、理解したうえで申請するかを判断しなければなりません。とくに、免税事業者は、インボイス制度の影響で顧客の減少や消費税の納付で収入が大幅に変わる可能性があります。
適格請求書発行事業者の申請後もインボイス(適格請求書)を発行する際は自社にあわせたテンプレートが必要なため、本記事を参考に用意しましょう。










