インボイス制度で販売手数料はどう扱う?経理処理方法をやさしく解説
更新日:2025.12.06
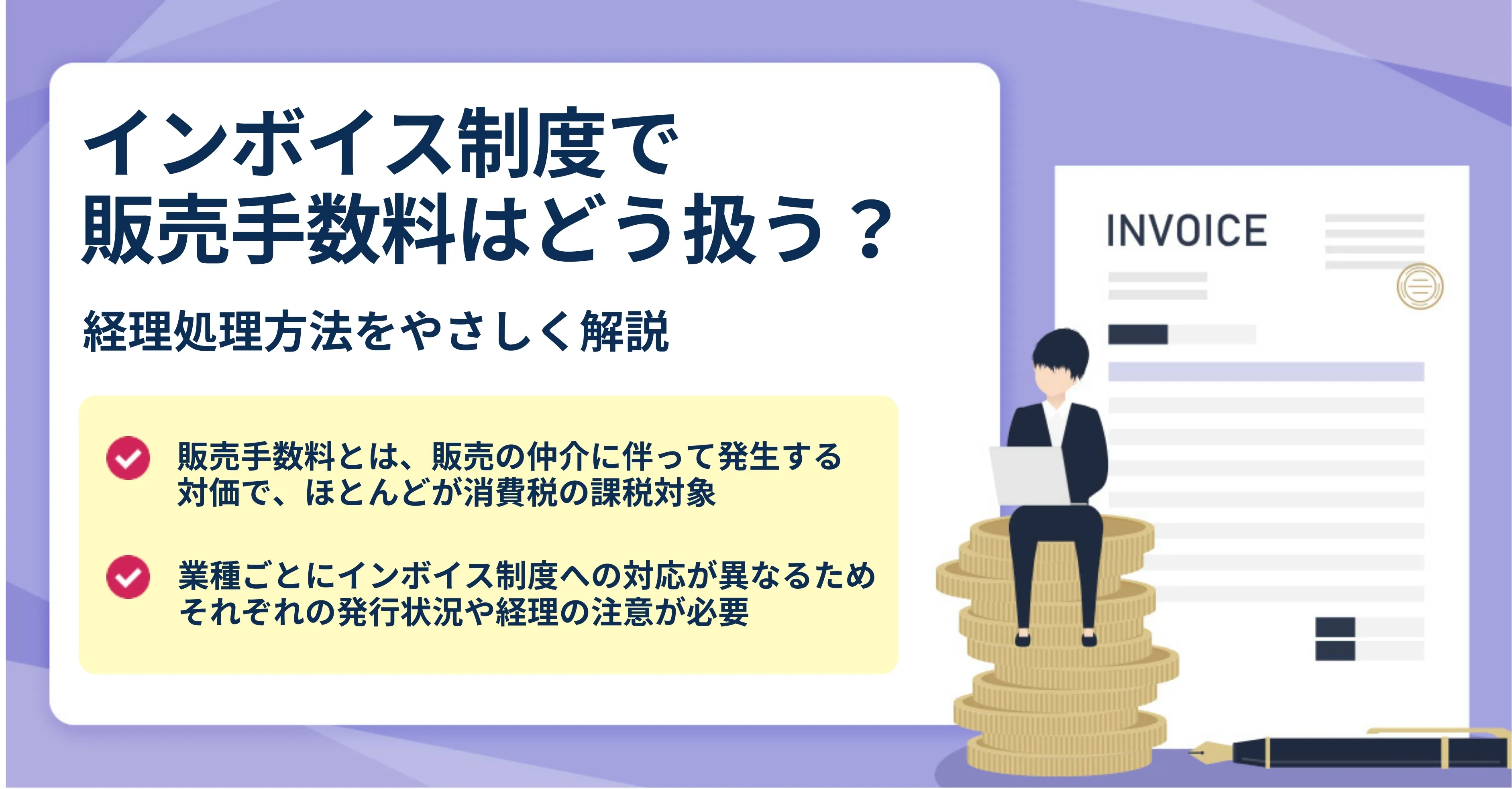
ー 目次 ー
インボイス制度の開始により、Amazonや楽天などで発生する販売手数料の経理処理が複雑化しています。本記事では、手数料に関する消費税の取扱い、帳簿処理、正しい仕訳方法とともに、免税事業者との取引リスクや適格請求書の要否についてやさしく解説します。
インボイス制度とは?
適格請求書等保存方式の概要
インボイス制度とは、2023年10月1日から日本国内で本格導入された新しい仕入税額控除の方式で、正式には「適格請求書等保存方式」と呼ばれます。この制度の目的は、消費税における仕入税額控除の適正な運用を確保することであり、消費税の課税取引に対して「適格請求書(インボイス)」を発行・保存することを求める仕組みです。
この制度の導入により、消費税の仕入税額控除を受けるためには、取引先から交付された「適格請求書」を保存する必要があります。また、インボイスを発行する事業者は、税務署に登録申請を行い、「適格請求書発行事業者」としての登録を受けなければなりません。
導入された背景と目的
インボイス制度が導入された背景には、消費税制度の透明性と公平性の向上があります。従来の「区分記載請求書等保存方式」では、免税事業者との取引においても仕入税額控除が認められており、不公平な扱いが生じていました。
また、不正な仕入税額控除や架空取引などの問題が確認されたこともあり、政府はより厳格な制度への移行を決定しました。これにより、課税事業者は今後、適格請求書発行事業者からのインボイスがなければ、仕入税額控除を受けることができなくなります。これに伴い、請求書の管理や経理処理の方法も大きく変化しました。
発行事業者と免税事業者の違い
インボイス制度では、取引の相手方が「適格請求書発行事業者」であるかどうかが極めて重要なポイントになります。ここでは、その違いについて解説します。
|
区分 |
定義 |
主な特徴 |
|
適格請求書発行事業者 |
税務署へ登録申請を行い、登録番号を取得した課税事業者 |
インボイスの発行が可能/取引先に仕入税額控除を認めさせることができる |
|
免税事業者 |
年間売上高が1,000万円以下の小規模事業者など、消費税の納税義務が免除されている事業者 |
インボイスを発行できない/取引先に仕入税額控除を認めさせることができない |
つまり、免税事業者と取引をする場合、インボイスが発行されないため、仕入税額控除ができなくなります。その結果、免税事業者との取引が減少する可能性があり、多くの免税事業者が課税事業者への転換や適格請求書発行事業者への登録を検討しています。
なお、インボイス制度の経過措置として、2023年10月から6年間、一部の控除は特例的に認められていますが、時間の経過とともに控除可能な割合は縮小されていきます。したがって、中長期的には適格請求書発行事業者としての登録が重要となります。
また、適格請求書発行事業者の登録状況は、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で誰でも確認可能です。取引先が登録事業者であるかを事前にチェックすることが、今後の事業運営では欠かせないプロセスとなってきます。
販売手数料とは?
販売手数料の代表的な例
販売手数料とは、商品やサービスを第三者(仲介業者やプラットフォーム事業者など)に販売・提供するために支払う対価のことを指します。近年、インターネットを介した取引が拡大する中で、販売手数料は個人事業主から法人まで幅広い事業者にとって一般的な経費となっています。
以下に、代表的な業種とその販売手数料の例を示します。
|
業種・利用形態 |
販売手数料の内容 |
主な提供企業 |
|
EC販売 |
商品の販売額に対して一定比率の手数料をプラットフォーム運営者に支払う |
Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなど |
|
フリマアプリ |
個人間取引に対してサービス提供元に支払う販売手数料 |
メルカリ、ヤフオク!、PayPayフリマなど |
|
不動産業 |
物件の売買または賃貸契約時に支払う仲介手数料 |
不動産仲介業者 |
|
広告代理業 |
広告出稿代行の際の仲介や運用手数料 |
広告代理店、マーケティング会社など |
|
旅行業 |
旅行プラン販売に対する業者からの業務委託手数料 |
旅行代理店、OTA(オンライン旅行代理店)など |
このように、販売手数料は業種ごとに性質が異なるものの、「顧客への販売を成立させるために第三者に支払う費用」という点で共通しています。また、多くの場合、取引金額の一定割合(例:販売価格の10%など)が手数料として算出される仕組みになっています。
販売手数料にかかる消費税の基本知識
販売手数料は原則として課税取引に該当しており、消費税が発生します。これは、手数料という形でサービスの提供が行われているためであり、消費税法においては「役務の提供」として位置づけられます。
具体的には、以下のような分類となります。
|
手数料の内容 |
課税の有無 |
税率区分(2023年10月時点) |
|
販売仲介業務(ECサイトなど) |
課税対象 |
標準税率10% |
|
広告掲載仲介手数料 |
課税対象 |
標準税率10% |
|
海外業者から受けたサービス |
消費税法上の輸入取引(リバースチャージ) |
課税対象(要検討) |
|
非課税取引(例:住宅の賃貸仲介) |
非課税 |
- |
一部、消費税の非課税や免税に該当する手数料もありますが、おおむね日本国内において販売促進や仲介の対価として支払う販売手数料は、消費税法上の「課税取引」となります。
消費税の仕入税額控除を正しく行うためには、この手数料が課税対象であるかどうかを判別することが非常に重要です。
インボイスが必要になるケースとは?
2023年10月1日から施行されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)により、取引先が発行する請求書が「適格請求書」でなければ、消費税の仕入税額控除を受けられないケースが原則となりました。
販売手数料においても、次のような条件に該当する場合、インボイス(適格請求書)が必要です。
- 取引相手が適格請求書発行事業者である
- 販売手数料が課税取引である(標準税率10%など)
- 取引金額に応じて仕入税額控除を受ける予定がある
例えば、AmazonなどのECプラットフォームから毎月請求される販売手数料について、これまで自動計算で経理処理していた場合でも、インボイス制度が導入された以降は「適格請求書を保存し帳簿とともに管理すること」が求められます。
もし、販売手数料の請求元が免税事業者であり、適格請求書の交付が受けられない場合には、その手数料に関連する消費税分の仕入税額控除が行えなくなるため、原価が実質的に増加することになります。
したがって、販売手数料の支払先が「適格請求書発行事業者」であるかを必ず事前に確認し、必要な書類の取得・保存体制を整えることがインボイス制度対応において非常に重要です。
インボイス制度における販売手数料の経理処理!
適格請求書を受け取った場合の処理
販売手数料の支払いにおいて、取引先が適格請求書発行事業者であり、適格請求書(インボイス)を発行している場合には、仕入税額控除を行うことが可能です。これは、仕入れにかかる消費税を、売上にかかる消費税から控除する制度であり、消費税の正確な納付に重要な役割を果たします。
仕訳例と勘定科目の具体例
販売手数料を支払う際の仕訳は、下記のように記録されます。これは例として、1,100円(うち消費税100円)の販売手数料を「楽天株式会社」へ支払った場合の仕訳です。
|
日付 |
借方勘定科目 |
金額 |
貸方勘定科目 |
金額 |
摘要 |
|
2024/04/01 |
支払手数料 |
1,000円 |
普通預金 |
1,100円 |
楽天 販売手数料 インボイス有 |
|
仮払消費税 |
100円 |
このように、販売手数料の本体(支出)部分を「支払手数料」、消費税部分を「仮払消費税」として分けて記帳することで、仕入税額控除が可能になります。
帳簿保存と請求書の管理方法
仕入税額控除を適用するには、インボイス(適格請求書)の保存が義務づけられています。以下の2点の保存が必須です。
- 適格請求書(発行者の登録番号・税率区分等が記載されたもの)
- 帳簿(販売手数料として処理した内容を記載)
請求書は紙媒体または電子データ(PDFなど)で保存可能です。電子帳簿保存法に則って、検索性や保存方法を整備することも大切です。特にクラウド会計ソフト(弥生会計、freee、マネーフォワードなど)を使用している場合は、適格請求書のアップロード機能を活用すると効率的です。
インボイスが発行されていない場合の処理
販売手数料を支払った相手が免税事業者など、インボイスを発行できない立場にある場合、仕入税額控除の適用が制限されます。2023年10月のインボイス制度開始以降、原則として、適格請求書がない取引では仕入税額控除を行うことができません。ただし、経過措置として、一部控除が認められる期間があります。
仕入税額控除の制限について
インボイス制度による経過措置は次の通りです。
|
期間 |
控除可能な割合 |
備考 |
|
2023年10月〜2026年9月 |
80% |
適格請求書がなくても一定の控除が可能 |
|
2026年10月~2029年9月 |
50% |
控除割合が段階的に減少 |
|
2029年10月以降 |
0% |
完全に控除不可 |
該当期間内であっても、インボイス発行事業者との取引が望ましいとされ、税務的リスクを減らすためには可能な限りインボイス対応の取引先を選ぶことが推奨されます。
免税事業者からの仕入れの対応方法
販売手数料を免税事業者に支払った場合には、以下のような仕訳となります。
|
日付 |
借方勘定科目 |
金額 |
貸方勘定科目 |
金額 |
摘要 |
|
2024/05/01 |
支払手数料 |
1,100円 |
現金 |
1,100円 |
個人業者 手数料(インボイス無) |
この場合、「仮払消費税」の計上はありません。税務計算上、消費税控除の対象とならないため、手数料全額を経費として処理し、課税仕入としてはカウントしません。また、経過措置内であれば、法定割合に応じた控除を計算し、申告書で補正を行うこととなります。
このように、販売手数料に関する経理処理は、インボイスが有るか無いかで大きく異なります。経理担当者やフリーランス、小規模事業者にとっては、発行者のステータス確認と正確な帳簿記録が極めて重要となります。
各業種別!販売手数料のインボイス対応例
ECサイト(Amazonや楽天等)での手数料処理
Amazonや楽天市場などの大手ECサイトを利用する事業者は、販売代金から販売手数料が差し引かれる形式で売上が精算されるケースが一般的です。これらの販売手数料に対しても、適格請求書(インボイス)が必要となる場面があります。
たとえば、Amazonが適格請求書発行事業者であるため、手数料に関しては適格請求書が電子的に提供されます。事業者側ではそのインボイスをダウンロード・保存し、仕入税額控除が適用できるように経理処理する必要があります。
ECサイトでのインボイス処理のポイント
- Amazonセラーセントラルや楽天RMSからインボイスのダウンロードが可能
- 販売手数料は「支払手数料」または「販売促進費」などの科目で処理
- インボイスが保存されていないと、販売手数料にかかる消費税の仕入税額控除は不可
仕訳例
|
日付 |
借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
摘要 |
|
2024/04/30 |
支払手数料 |
10,000 |
普通預金 |
11,000 |
Amazon販売手数料(税込) |
|
仮払消費税 |
1,000 |
フリマアプリ(メルカリ・ヤフオク等)での処理対応
個人が多く参加するフリマアプリでは、インボイス制度に未対応のケースも多く見られます。特にメルカリやヤフオク!で発生する販売手数料は、プラットフォーム運営会社である株式会社メルカリやヤフー株式会社が適格請求書発行事業者であるかどうかの確認が重要です。
2023年10月以降、メルカリShopsやヤフオク!で法人向け運用をされている場合、一部の取引においてインボイスが発行されるケースもあります。法人利用であれば、設定画面などで領収書や請求書をPDF形式で取得できるため、それを保存し、経理処理に活用しましょう。
フリマアプリ活用時の注意点
- 領収書や取引履歴のスクリーンショットではインボイスとみなされないことが多い
- インボイス発行に対応していない個人(免税事業者)との取引では、仕入税額控除不可
- 帳簿上で証憑不備がある場合は、摘要欄に取引内容・理由等を詳しく記載
不動産業・広告代理業における手数料処理のポイント
不動産業では、賃貸借契約の仲介手数料や物件管理手数料など、消費税の対象となる手数料取引が多く発生します。広告代理業でも、広告枠の販売に際して他の代理店やメディアと手数料清算が行われることが一般的です。
これらの業界では、取引金額が高額になる傾向があるため、インボイス対応が未対応であると消費税の控除漏れが大きな損失につながる可能性があります。そのため、取引先が適格請求書発行事業者であるかを事前に確認し、請求書のフォーマットや要件が満たされていることを確認した上で取引を行うのが必須です。
業界ごとの発行者例
|
業種 |
主な手数料内容 |
インボイス対応が多い取引先例 |
対応のポイント |
|
不動産業 |
仲介手数料、管理手数料 |
大東建託、ミサワホーム、不動産仲介業者 |
不動産業界の協会発行テンプレートがある |
|
広告代理業 |
広告出稿仲介手数料、制作代行費 |
電通、博報堂、地方広告代理店 |
取引契約書+インボイスで対応 |
処理上の注意点まとめ
- 受け取った請求書に「適格請求書」である旨が記載されているか要確認
- 手数料額が大きくなるため、証憑が不十分な場合は税務調査時に否認リスクあり
- 顧問税理士や会計事務所と相談しながら、書類保存方法を整備することが望ましい
販売手数料を支払う際の注意点
取引先が適格請求書発行事業者かの確認方法
インボイス制度では、販売手数料の支払い先が「適格請求書発行事業者」であるかどうかを確認することが重要です。なぜなら、適格請求書を発行できる事業者からの仕入やサービスに対してしか、仕入税額控除を行うことができないためです。
取引先が適格請求書発行事業者かどうかを確認するには、以下の方法があります。
- 国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で登録番号を検索する
- 取引先から提示される請求書に「登録番号(Tから始まる13桁)」が記載されているかを確認する
公表サイトは無料で利用でき、事業者の登録番号・名称・登録日などが検索可能です。取引先が登録事業者でない場合、その手数料に含まれる消費税は原則として控除できません。
インボイス未対応事業者との取引リスク
販売手数料を支払う際の取引先が、インボイス制度に対応していない免税事業者であった場合、以下のようなリスクが発生します。
- 仕入税額控除ができず、その分実質的なコストが増加する(増税と同様の効果)
- 帳簿・証憑の整備が不十分になることで、税務調査での否認リスクが高まる
- 将来的に優先的に取引を継続するかの判断材料となり、事業の継続性に影響が出る可能性がある
インボイス未登録事業者からの販売手数料支払いに関しては、税抜処理と税込処理の判断を適切に行い、税務上のリスクを軽減するための体制整備が求められます。
税務署対応のための証憑準備
インボイス制度においては、取引の証憑整備が今まで以上に重要視されます。販売手数料を支払った際にも、以下の要素を満たす請求書を受け取り、保存しておく必要があります。
|
必要記載項目 |
内容 |
|
適格請求書発行事業者の氏名または名称・登録番号 |
Tから始まる13桁の番号が記載されている必要があります。 |
|
取引年月日 |
販売手数料の発生タイミングを記載。 |
|
取引内容(販売手数料などの具体的な内容) |
サービス内容が具体的に分かるよう記載されている必要があります。 |
|
税率ごとに区分した消費税額 |
10%や軽減税率との区分が必要。 |
|
支払者の氏名または名称 |
請求先である貴社の情報が記載されていることが必要です。 |
また、電子取引が増えてきている中では、電子保存対応も求められています。特にECサイトやクラウド上でのやり取りにおいては、電子帳簿保存法との整合性を図る必要があるため、保存要件(真実性・可視性・整合性)を満たすシステム管理が必要です。
万が一、税務調査となった場合には、これらの書類および仕訳との整合性を一貫して説明できる体制が求められます。日々の取引記録と連携した証憑保管を徹底することで、不必要な否認リスクを回避することが可能です。
【Q&A】販売手数料とインボイス制度に関してよくある質問
小規模事業者はインボイス対応が必要?
小規模事業者であっても、取引先からインボイスを求められる場合があります。特に、課税事業者と取引をしている場合、その取引先は仕入税額控除を行うために「適格請求書(インボイス)」の発行を求めることがあり、自社が適格請求書発行事業者でないとビジネス機会を失う可能性もあります。
ただし、インボイス発行には登録が必要で、免税事業者としての消費税の納税義務が発生する点も踏まえたうえで判断する必要があります。
インボイス制度に対応しないとどうなる?
インボイス制度に対応しないと、消費税の仕入税額控除が受けられなくなります。これは、事業者が支払った消費税を控除できず、実質的な税負担が増えることを意味します。特に販売手数料を多く支払っている業種では、控除できない消費税額が経費となり、利益を圧迫するリスクがあります。
また、取引先が適格請求書を求める場合、対応していない事業者との取引を停止する動きも見られるため、営業面での影響も考慮すべきです。
過去の取引のインボイス対応は必要?
基本的に、インボイス制度の適用は2023年10月1日以降の取引に限定されています。従って、それ以前の取引についてはインボイスに対応する必要はありません。ただし、制度開始直後で請求書の発行が遅れているケースや、2023年10月1日以降に締め処理された取引については、取り扱いに注意が必要です。
税務上の要件としては、インボイス制度の施行以降の取引に対する対応が求められているため、期をまたぐ販売手数料の支払に関しては明確に経過措置や適格請求書の有無を確認のうえ仕訳処理を行う必要があります。
どのようにして取引先がインボイス発行事業者か確認できる?
国税庁が運営する「適格請求書発行事業者公表サイト」で、法人名や登録番号を検索することで、すぐにインボイス対応かどうかを確認できます。
以下に確認手順を表にまとめます。
|
ステップ |
手順の内容 |
|
1 |
国税庁インボイス制度 公表サイト にアクセスする |
|
2 |
「登録番号」または「名称(商号)」で検索 |
|
3 |
対象の取引先が検索結果に表示されるか確認 |
|
4 |
「登録年月日」や「登録取消し日」があるか確認 |
適格請求書の登録番号は、請求書や領収書にも記載されるので、そちらでも確認できます。
販売手数料の支払い相手が免税事業者だったらどうなる?
免税事業者は適格請求書の発行ができないため、その場合は仕入税額控除が原則できません。ただし、制度の開始から3年間(2023年10月〜2026年9月末)については、80%の控除率が認められる経過措置が設けられています。
|
期間 |
控除可能な割合 |
備考 |
|
2023年10月~2026年9月 |
80% |
経過措置1 |
|
2026年10月~2029年9月 |
50% |
経過措置2 |
|
2029年10月以降 |
0% |
仕入税額控除不可 |
このため、長期的に取引を継続するには、相手方にインボイス登録を促すか、別の適格請求書発行事業者との取引を検討する必要があります。
販売手数料にも源泉徴収は必要?税務処理の注意点は?
販売手数料に関しては、基本的に消費税の課税対象ですが、源泉徴収が必要となるかどうかは手数料の内容や請負の形態によって異なります。たとえば、外部の個人に業務委託として広告宣伝などを依頼し、その成果に対して所定の手数料を支払うようなケースでは、源泉徴収の対象となることがあります。
以下の表は、よくある販売手数料と源泉徴収の関係をまとめたものです。
|
手数料の種類 |
支払先 |
源泉徴収の要否 |
|
ECサイト運営会社への手数料 |
法人 |
不要 |
|
外注ライター等への業務委託料 |
個人 |
必要(税率10.21%) |
|
仲介手数料(不動産・広告代理店等) |
法人 |
不要 |
|
コンサルティングに関する成功報酬 |
個人 |
必要 |
手数料の支払に際しては、源泉所得税の有無とあわせて、適切なインボイス対応がなされているかを確認し、経理処理上のミスを防ぐことが重要です。
フリマアプリ・ECサイト経由の取引でもインボイスは必要?
はい。たとえばAmazon、楽天、市場連携型POSなどを通じて販売する場合、販売者はプラットフォーム提供者から販売手数料などを差し引いた金額で代金を受け取ります。この際、販売手数料には消費税が含まれているため、適格請求書が発行されていない場合は仕入税額控除が受けられません。
多くの大手プラットフォーム(Amazon、楽天、BASE、STORESなど)は、すでにインボイス制度に対応しており、適格請求書はマイページ等からダウンロード可能です。必ず定期的にダウンロードして保存し、帳簿に反映させましょう。
まとめ
インボイス制度の導入により、販売手数料の経理処理には適格請求書の受領・保存が求められます。特にAmazonや楽天、メルカリなどの取引では、手数料支払い先がインボイス発行事業者か確認することが重要です。適切な処理を怠ると仕入税額控除が認められず課税負担が増す可能性があります。取引先の確認と証憑管理を徹底し、制度開始に合わせた正確な対応が不可欠です。










