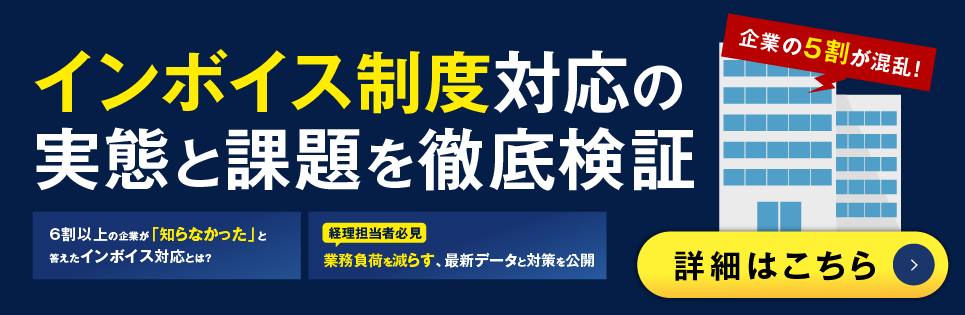インボイス制度は何が問題?理由や廃止の可能性、今後の対処法を解説
更新日:2025.12.24
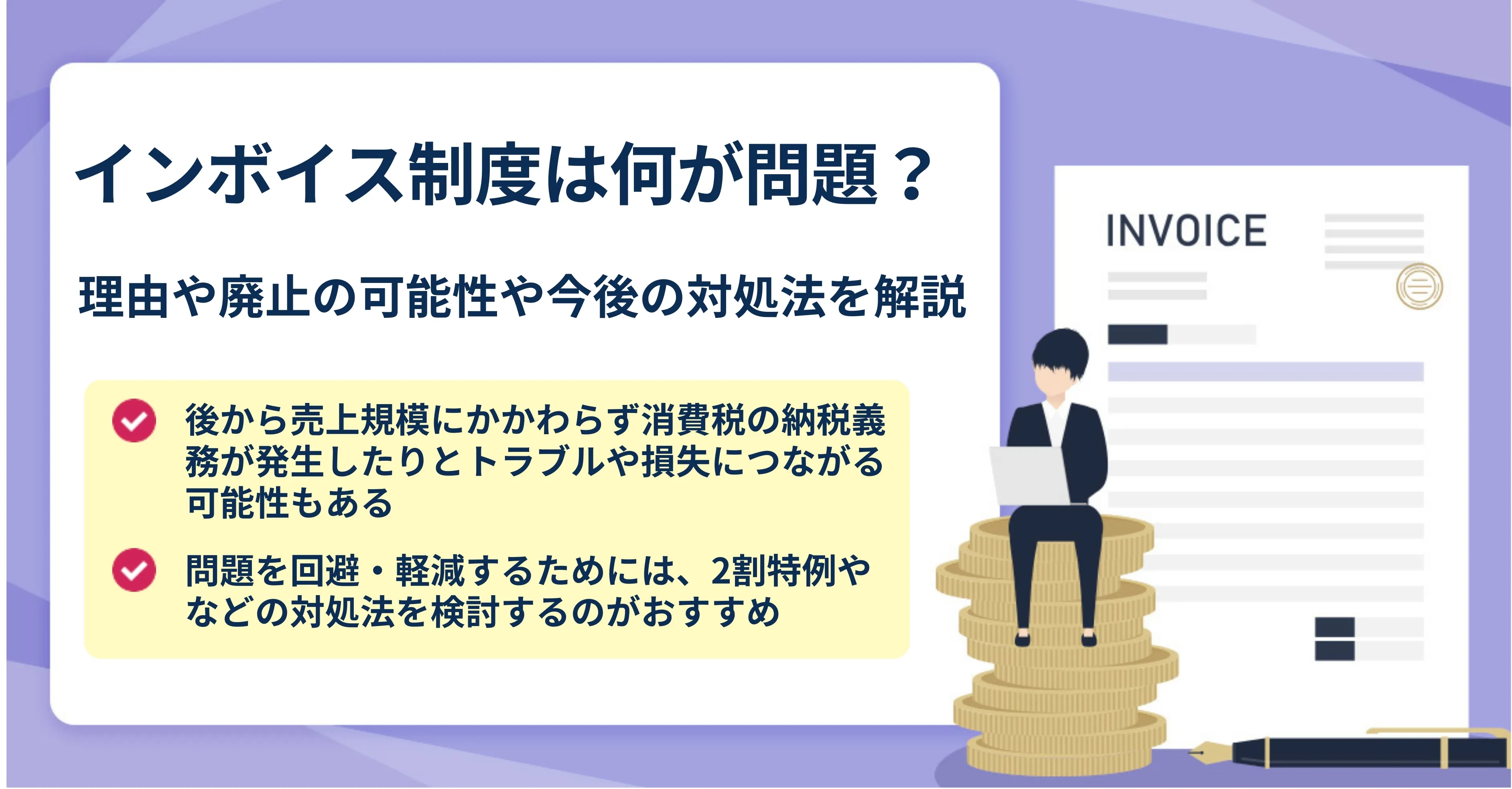
ー 目次 ー
消費税にまつわる書類の作成や計算、管理方法などを定めた「インボイス制度」が2023年10月に施行されました。この制度の導入により事業者の負担が増えるため、多くの中小企業や個人事業主などが反対しています。
しかし、中には「インボイス制度について詳しくないけれど、何が問題なのか」と考えている事業者も少なくありません。インボイス制度の理解が不十分なまま事業を進めると、契約打ち切りや税負担の増大といったトラブルを招くおそれがあります。
それぞれの事業にあった対応をするために、インボイス制度を正しく理解することが大切です。
本記事では、インボイス制度の何が問題なのかについて、基本的な考え方や対処法を交えて解説します。
【前提】インボイス制度とは消費税に関する計算や請求書作成・保存のルール
「インボイス制度」とは消費税にまつわる書類の作成や計算、管理方法などを定めたルールです。この制度の導入目的は、事業者が支払う消費税額を正確に把握することにあります。
インボイス制度では「適格請求書(インボイス)」の発行と保存が必要です。このインボイスを受け取った課税事業者は、納税の際に仕入れにかかる消費税を控除できる「仕入税額控除」が受けられます。
しかし、インボイスを発行するためには税務署に申請して「適格請求書発行事業者」の登録をしなければなりません。また、インボイス制度に登録すると、免税事業者であっても課税事業者となり、消費税の納付義務が発生します。
【何が問題?】インボイス制度はなぜ反対されているのかの5つの理由
インボイス制度は、事業者による納税や事務業務の負担が増加することから反対する意見が多くあります。
もし、制度を理解していない状態で事業を進めてしまうと、納税額の増加や取引への影響などのトラブルにつながるおそれがあります。事前に問題点を理解しておくことでトラブルや損失を回避できるでしょう。
ここでは、インボイス制度はなぜ反対されているのかを5つの理由で解説します。
- 課税売上高に関係なく消費税の納税が必須となるため
- 未登録では取引に影響するおそれがあるため
- 事務作業の負担が増えるため
- 個人情報が公開されてしまうため
- 取引先が未対応の場合、仕入税額控除を受けられなくなるため
①課税売上高に関係なく消費税の納税が必須となるため
本来、課税売上高が1,000万円以下の事業者は「免税事業者」として消費税の納税が免除されます。しかし、インボイス制度を利用するために発行事業者になると、同時に「課税事業者」となり消費税を納める義務が発生します。
これまで消費税の納税が不要であった事業者が課税事業者となるため、売上規模の小さい個人事業主にとっては大幅なコスト増加というデメリットがあるでしょう。
②未登録では取引に影響するおそれがあるため
インボイス制度に未登録の場合、取引に影響するおそれがあります。取引先の課税事業者は「仕入税額控除が受けられない」というデメリットが発生するためです。
仕入税額控除を受けられなくなると、取引先は税務上のメリットが少なくなります。結果として、以下のような取引への影響が起きるおそれがあるでしょう。
- 登録していない事業者として契約を切られる
- 競合他社がすでにインボイス制度に登録済みの場合、新規契約の比較検討にて不利になる
- 契約の支払い額を減らしたいと交渉される
③事務作業の負担が増えるため
インボイス制度では請求書の記載や保管方法まで細かくルールが定められているため、既存の業務フローの変更が必要です。
日本商工会議所の調査によると、2,365社のうち82.2%が「インボイス制度により事務負担が増えた」と回答しています(※)。具体的には、インボイス制度により以下のような事務業務の変更が求められます。
- インボイスに対応した請求書の作成
- 請求書のフォーマット変更
- 請求書の保存・管理
(※)参考:日本・東京商工会議所「中小企業におけるインボイス制度、電子帳簿保存法、バックオフィス業務の実態調査 結果」
④個人情報が公開されてしまうため
インボイス制度を利用するためには税務署に申請して、「適格請求書発行事業者」として登録番号を付与してもらう必要があります。登録すると国税庁のサイトに登録番号と事業者名が掲載されるため、プライバシー面で抵抗を感じる事業者も少なくありません。
しかし、このサイトでは登録番号による検索が基本となっているため、名前から特定することは困難といえるでしょう。
⑤取引先が未対応の場合、仕入税額控除を受けられなくなるため
インボイス制度に登録すると、一定の要件を満たすことで仕入税額控除が受けられます。しかし、自社が発注者側の際に取引先がインボイス制度の未登録事業者であった場合、仕入税額控除が受けられなくなります。
受注側の取引先から要望があるため登録するのではなく、事業全体として必要があるかの判断が大切です。
インボイス制度を活用する2つの大きなメリット
インボイス制度は問題点のみではなく、事業者としてのメリットもいくつかあります。
双方を正しく理解してから事業状況に合わせて検討することで、新規取引の獲得や業務効率化などのメリットが得られるでしょう。
ここでは、インボイス制度を活用する2つの大きなメリットを解説します。
- 取引先の獲得につながる可能性がある
- 電子インボイスを活用することで業務効率化を図れる
①取引先の獲得につながる可能性がある
インボイス制度に登録すると、新規取引の獲得につながる可能性があります。発行するインボイスによって取引先の課税事業者は仕入税額控除を受けられるためです。
とくに、同業他社が未登録の場合、自社が登録済みであれば「仕入税額控除ができる相手」として顧客から優先的に取引相手に選ばれる可能性が高まるでしょう。取引先は仕入税額控除を受けたいと考えていることが多いため、インボイスを発行できる事業者は重宝されます。
②電子インボイスを活用することで業務効率化を図れる
電子インボイスとは、インボイスを書面ではなく電子データ化したものです。
インボイス制度では、紙の請求書だけでなく電子データでの発行も認められています。インボイスを電子化すればクラウド上で管理ができるため、以下のような業務効率化が図れます。
- 請求書作成の自動化
- データ集計の簡略化
- 保管スペースの削減
また、専用の会計ソフトを導入すれば、仕入税額控除の計算を自動化や検索のスピードアップも可能です。
インボイス制度の問題に対する対処法
インボイス制度には問題点がいくつかあり、事業者の負担が増えてしまう内容となっています。しかし、特別措置やシステムを導入することで、負担を軽減して制度の活用も可能です。
もし、問題点が気になってしまい制度を活用しない場合、取引先の減少や新規契約の獲得を逃してしまうことにつながります。制度を正しく活用するためにも対処法を理解しておきましょう。
ここでは、インボイス制度の問題に対する対処法を解説します。
【消費税の負担軽減】2割特例を活用する
「2割特例」は、消費税の納税額を売上税額の2割まで減額できる特別措置です。インボイス制度の登録をきっかけに、免税事業者から課税事業者に変更した事業者を対象としている措置です。
たとえば、年間の売上高が100万円の場合、本来10万円の消費税額を納税する必要があります。しかし、2割特例を活用することで、2万円の納税になります。
2割特例により消費税の負担を軽減できるため、いきなり重い税負担を背負うリスクへの対処が可能です。
関連記事:2割特例とは|対象事業者や計算方法と申請方法について徹底解説。
【事務負担を解消】システムを導入する
インボイス制度に関連する作業においてシステム導入することで、業務効率化が図れるため事務負担の解消ができます。インボイス制度に対応したシステムを導入すると、以下のような理由から事務負担が軽減可能です。
- インボイスの自動作成
- 適切な保存管理
- 自動仕訳
- 入力ミスなどのヒューマンエラーの防止
- 保管スペースの削減
システムを導入する際は、仕様や料金プランをしっかり比較検討し、事業にあった会計ソフトを選びましょう。
もし、会計ソフトの導入を検討している場合は「OneVoice明細」がおすすめです。
OneVoice明細は、領収書や請求書など複数の帳票を一括管理できるクラウドサービスです。インボイス制度に対応した書類を自動で作成できるため、面倒な事務作業を軽減できます。
インボイス制度において何が問題か知りたい際によくある質問
最後に、インボイス制度において何が問題か知りたい際に、よくある質問について解説します。
①インボイス制度は廃止の可能性がありますか?
政府や国税庁はインボイス制度の必要性を主張しており、廃止するといった正式な発表はありません。
新たに導入された制度は、施行後数年は見直しや改善がおこなわれることはあっても、撤廃されるケースは少ないでしょう。
②インボイス制度を廃止した国はありますか?
これまでに多くの国がインボイス制度を導入しましたが、廃止した事例は確認されていません。
実は、OECD加盟国(38か国)のうち、アメリカを除く37か国でインボイス制度が導入されています。そのため、日本のみ特別に廃止に進む可能性は低いと考えられるでしょう。
③インボイス制度導入によって誰が得する?
インボイス制度は、基本的に以下の3つにかかわる人が得をします。
|
立場 |
利点 |
|
国・地方公共団体 |
消費税の税収が適正化される |
|
適格請求書発行事業者 |
取引先からの優先度が上がる |
|
消費者 |
市場の健全化が促進される |
まとめ|事業の状況に合わせてインボイス制度を活用しましょう
本記事では、インボイスの何が問題なのかについて基本的な考え方や対処法を交えて解説しました。
制度への対応を誤ると、取引の減少や予期せぬ税負担など、ビジネスにとって深刻なリスクが生じる可能性があります。
インボイス制度はすべての事業者が関係しており、収入の規模や職種に関係なく、その仕組みや影響を正しく理解することが大切です。制度を活用する際には、リスクを理解した上で自身の事業状況に合わせて検討しましょう。