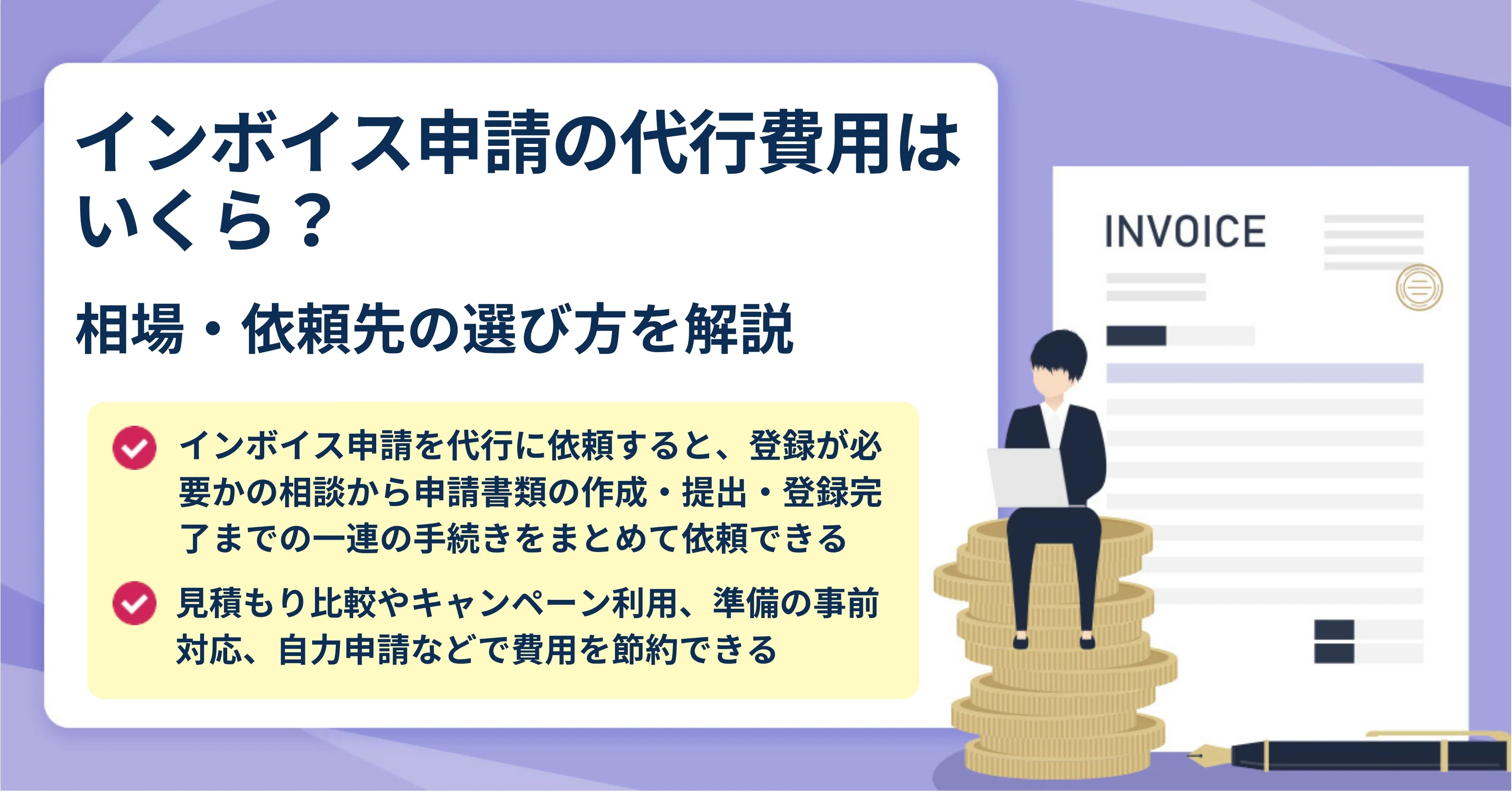【ひな形あり】顧問契約書のインボイス制度対応は必要?書き方や記載例も
更新日:2025.07.28
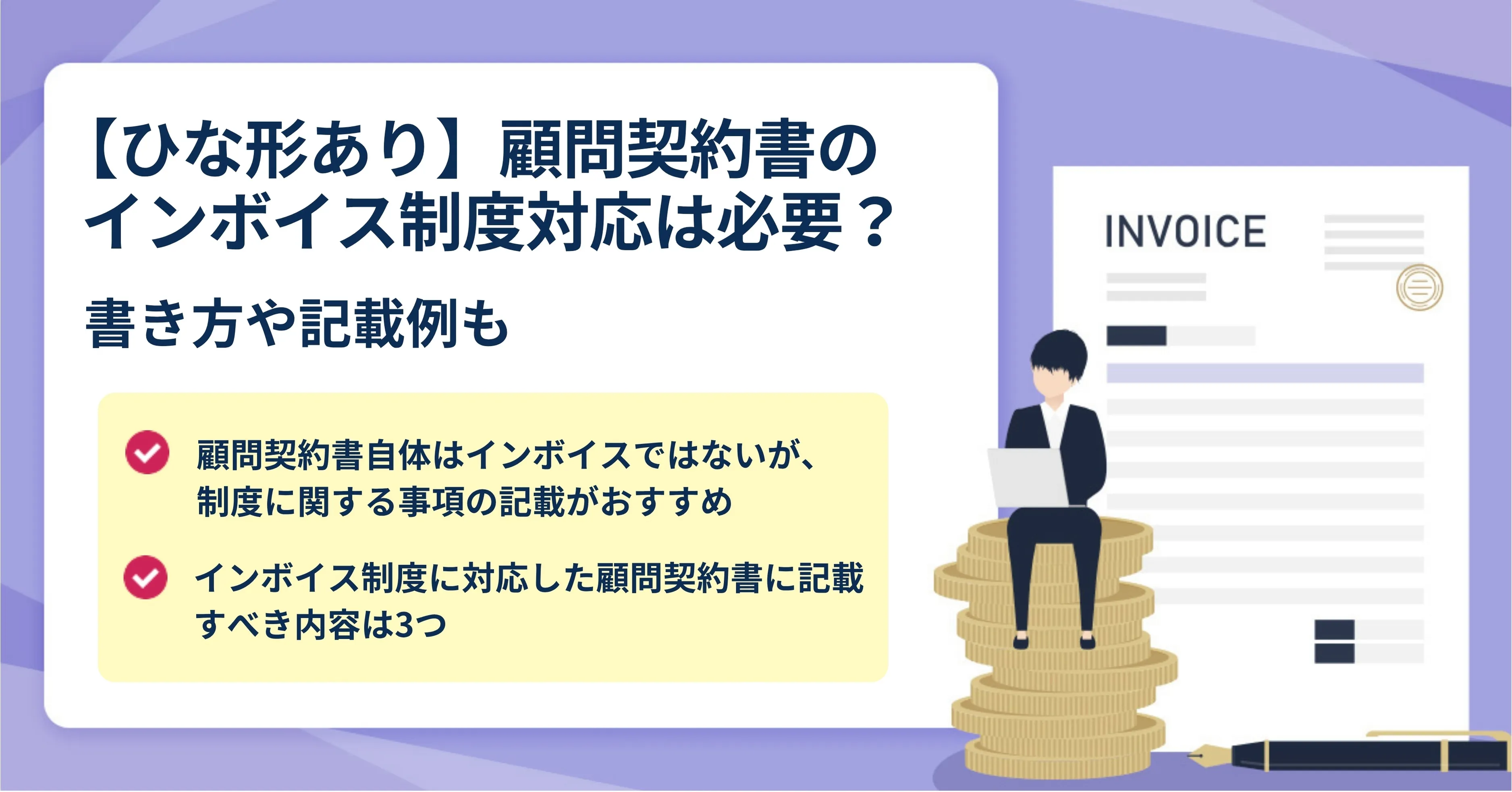
ー 目次 ー
2023年10月のインボイス制度施行にともなって、顧問契約を結ぶ際においても制度への配慮が必要となりました。
そもそも、顧問契約書はインボイス制度の対象となる書類ではありません。しかし、顧問契約書のなかにインボイス制度に関する事項を記載しておくことで、消費税の処理ミスや仕入税額控除の否認、請求書の差し戻しといった契約上のトラブルを防げます。
本記事では、顧問契約書のインボイス制度への対応について、書き方や記載例を交えて解説します。
【結論】顧問契約書自体はインボイスではないが、制度に関する事項の記載がおすすめ!
顧問契約書は、インボイス制度における「インボイス(適格請求書)」には該当しません。
しかし、顧問契約書にインボイス制度に関する事項を記載しておくことで、請求書の差し戻しや仕入税額控除の否認など、実務上のトラブルを回避し、消費税の処理や帳簿の記載におけるミスを防げます。
契約時には以下のような内容をあらかじめ取り決めておくことが重要です。
- 契約相手が適格請求書発行事業者であるかの確認
- インボイスを発行することへの合意
- 報酬額の税込・税込表示の明記
上記のような事項を顧問契約書に記載しておくことで、顧問契約での取引先とのトラブルを未然に防げ、よりスムーズな取引が実現できます。
インボイス制度に対応した顧問契約書に記載すべき内容とは?
2023年10月に開始されたインボイス制度では、請求書の発行時だけでなく、契約段階でも制度に対応した記載を盛り込むことが重要です。
とくに、顧問契約のように継続的な取引がおこなわれる場合、契約書の内容に曖昧さがあると、後々のインボイス(適格請求書)の発行内容との不整合や、仕入税額控除の否認といったリスクを招くおそれがあります。
ここでは、インボイス制度に対応した顧問契約書に記載しておくべき3つのポイントについて解説します。
- インボイス発行に関する合意条項
- 登録番号の通知義務
- 顧問料に対する消費税の明記
①インボイス発行に関する合意条項
インボイス制度において、報酬を支払う側(顧問先)が仕入税額控除を適用するためには、適格請求書(インボイス)の交付を受ける必要があります。
そのため、顧問契約書においても、顧問事業者が「インボイス発行事業者である場合、適格請求書を発行すること」に同意していることを明記しておくと安心です。
また、契約期間中に顧問事業者が登録を失効・取消された場合の対応についても記載しておくことで、請求書の差し戻しが起きる事態を防げます。
②登録番号の通知義務
インボイス制度では、請求書に記載される登録番号が正確であることが、仕入税額控除の適用要件です。
顧問先が適格請求書発行事業者である場合、インボイスには「登録番号」の記載が義務付けられています。
そのため、顧問契約書では登録番号を通知する義務や、変更・抹消があった場合には、速やかに相手方へ通知する義務があることについても記載しておきましょう。
③顧問料に対する消費税の明記
顧問契約書では、報酬額が「税込」か「税抜」かを明確に記載することが重要です。たとえば「月額10,000円(税抜)+消費税」などと記載すれば、請求時の金額に対する認識違いやトラブルを防げます。
また、消費税率が変更された場合の対応も顧問契約書に明記しておくと安心です。変更時の都度協議が不要になり、実務負担の軽減にもつながります。
【ひな形】インボイス制度に対応した顧問契約書
顧問契約書はインボイス(適格請求書)の対象となる書類ではないため、登録番号や税率などの記載が必須ではありません。
しかし、この段階でインボイスの発行ルールや、消費税の扱いを明確にしておくことで、請求処理の手戻りや仕入税額控除の否認、税務調査での書類不備指摘などの税務トラブルを未然に防げます。
以下は、顧問契約書に関するインボイス対応の記載例です。顧問契約書の参考として活用してください。
顧 問 契 約 書株式会社〇〇(以下「甲」という)と、〇〇〇〇(以下「乙」という)は、甲が乙に対し顧問業務を委託し、乙がこれを受託することについて、以下のとおり契約を締結する。 第1条(契約の目的) 甲は乙に対し、以下の顧問業務を委託し、乙はこれを受託する。
第2条(契約期間) 本契約の有効期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。 第3条(報酬および支払方法) 甲は乙に対し、本契約に基づき、月額報酬として XXX,XXX円(税抜:XXX,XXX円/消費税:XX,XXX円) を支払うものとする。 報酬の支払は、毎月末日を締日とし、翌月〇日そまでに乙の指定銀行口座へ振込送金により支払うものとする。振込手数料は甲の負担とする。 第4条(インボイス制度への対応)
第5条(守秘義務) 乙は、本契約の遂行にあたり知り得た甲の業務情報、財務情報その他一切の秘密情報を第三者に漏洩してはならない。 第6条(契約の解除)
第7条(損害賠償) 甲または乙が、本契約に違反しこれにより相手方に損害を与えた場合は、当該損害を賠償する責任を負うものとする。 第8条(協議事項) 本契約に定めのない事項、または各条項に関して疑義が生じた場合には、甲乙協議のうえ、誠実に解決を図るものとする。 上記契約の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。 令和 年 月 日 【甲】(発注者) 【乙】(受託者) |
顧問契約書で確認すべきインボイス制度のポイント
インボイス制度の開始により、顧問契約を結ぶ際には、契約相手が適格請求書発行事業者であるかどうかや、登録番号・消費税の取扱いに関する記載内容の正確性が重要となりました。
とくに、報酬を支払う側が仕入税額控除を受けるためには、制度要件を満たした請求書が必要であり、その前提となる契約内容の整備が欠かせません。
ここでは、顧問契約書で確認すべき3つのポイントについて解説します。
- 相手がインボイス発行事業者かどうか確認する
- 登録番号を正確に記録する
- 電子取引の場合は、電子帳簿保存法に対応する
①相手がインボイス発行事業者かどうか確認する
顧問契約を締結する前に、顧問先がインボイス発行事業者として登録されているかを必ず確認しましょう。
確認には、国税庁「インボイス制度公表サイト」が活用できます。登録されていない場合、発行される請求書はインボイスとしての要件を満たさないため、仕入税額控除が適用できません。
適用できないと消費税を余計に負担したり、帳簿処理や決算に影響が出たりするなど、処理上のトラブルが発生する場合があります。
登録予定があるかも確認しておくと、登録がないまま契約して控除が受けられなかったり、後から契約見直しや請求書の差し替えが必要になったりする事態を防げます。
関連記事:インボイス制度の登録方法とは?申請のやり方や注意点を解説
②登録番号を正確に記録する
インボイス制度では、登録番号の正確な記載が仕入税額控除の要件となっています。登録番号が誤っていたり、記載が漏れていたりすると、控除が認められず、追加納税や経理修正が必要になるリスクがあります。
税率ごとの消費税額の記載ミスや登録番号の誤記があると、請求書の差し戻しや支払い遅延、控除の否認による納税負担の発生といった取引上のトラブルに発展しかねません。
顧問契約書を作成する際は、国税庁が公開している記載事項のチェックリストを活用し、内容に漏れがないかを確認すると安心です。
③電子取引の場合は、電子帳簿保存法に対応する
顧問契約のやり取りをPDFやクラウド上でおこなう場合は、電子帳簿保存法の保存要件
を満たす対応が必要です。
具体的には、インボイスを電子で受け取る場合は、タイムスタンプの付与や訂正削除の履歴保存、検索機能の確保などの保存要件を満たす必要があります。これらの要件を守らずに電子取引をおこなっていると、税務調査で帳簿として認められず、青色申告の取消や追徴課税につながります。
電子契約を導入する場合は、保存要件を満たし法令に対応した電子保存システムの利用が重要です。
まとめ|インボイス制度を理解して信頼できる顧問契約を締結しよう
本記事では、顧問契約書のインボイス制度への対応について、書き方や記載例を交えて解説しました。
インボイス制度に対応した契約内容を事前に取り決めておくことは、登録番号の記載漏れや税込・税抜の混乱といった請求ミスを防ぎ、仕入税額控除の否認を避けるうえで重要です。
とくに、フリーランスや中小企業の経営者にとっては、仕入税額控除の否認や税務調査での追徴課税といった経営への影響を避けるためにも、事前に顧問契約書を整備しておくべきでしょう。
本記事で紹介した記載例や契約条項を参考に、顧問契約の段階で必要な情報を明確にし、取引先との信頼関係を構築してください。