インボイス制度での課税事業者への影響は?免税事業者と比較して解説
更新日:2025.03.27
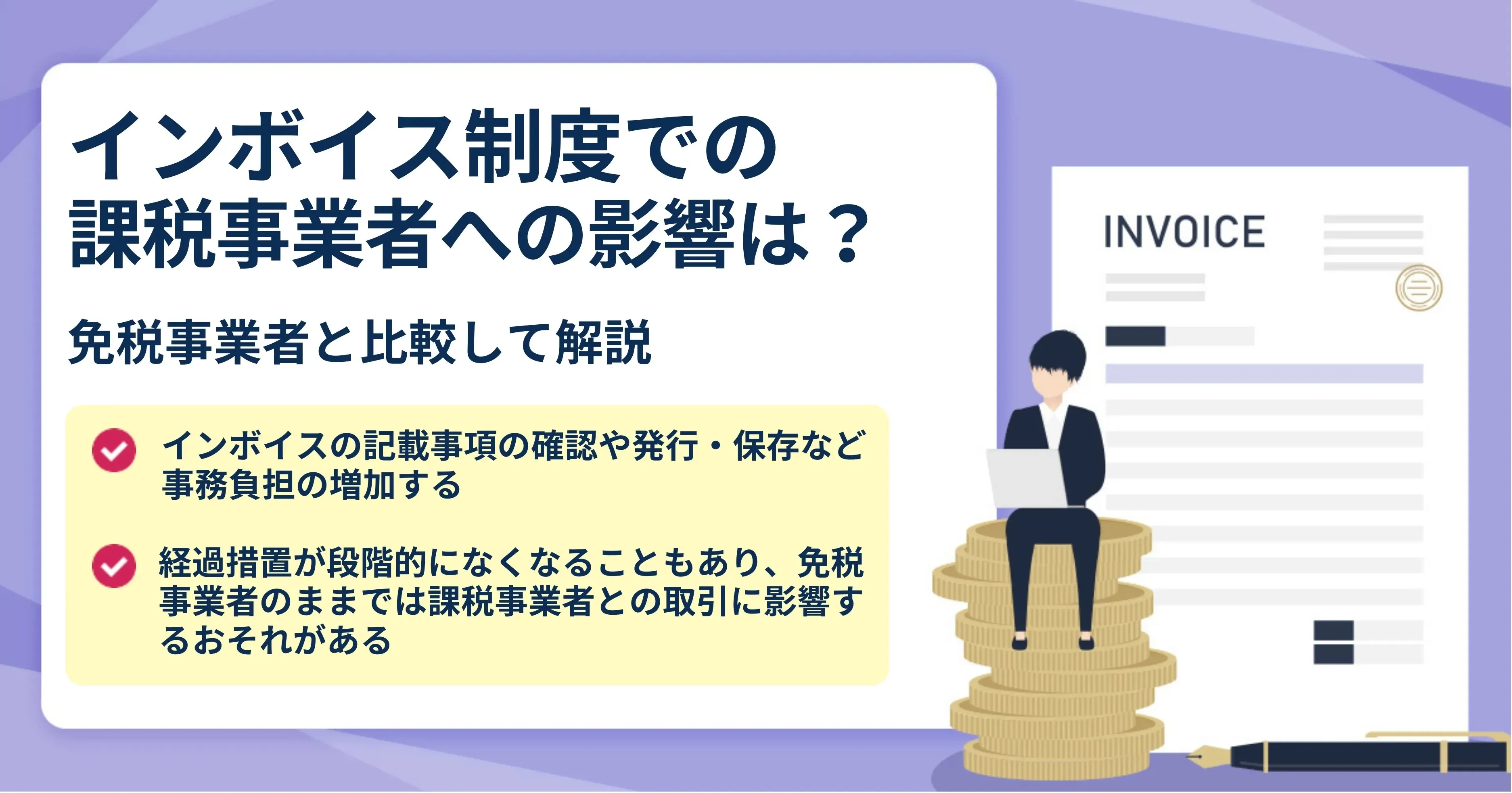
ー 目次 ー
インボイス制度は複数税率に対処する消費税の計算を正確におこない、適正な納税を促進するために施行されたルールです。この制度では「インボイス(適格請求書)」の発行・保存を義務付けており、制度に対応するためには「適格請求書発行事業者」の登録が必要です。
このインボイス制度はすべての事業者を対象にしており、税務にまつわるさまざまな場面で影響を与えています。しかし、その影響は課税事業者と免税事業者の間で大きくわかれています。
課税事業者においては、これまでも消費税の申告・納付が必要であるため、事務面では大きな影響がないように思えるでしょう。しかし、実際にはインボイスの発行や保存のために必要な準備などがあり、事前に把握しておかなければ、税務トラブルが生じるおそれがあります。
本記事では、インボイス制度での課税事業者への影響を免税事業者と比較して解説します。
【重要】インボイス制度の登録で課税事業者と同様に消費税の申告・納付が必要!
インボイス制度は複数税率に対処する消費税の計算を正確におこない、適正な納税を促進するために施行されたルールです。この制度では「インボイス(適格請求書)」の発行・保存をおこなうことで、課税売上にかかる消費税から課税仕入れに支払った消費税を控除できる「仕入税額控除」が利用できます。
ただし、条件として「適格請求書発行事業者」の登録が必要であり、登録をおこなうことで課税事業者と同様の消費税の申告と納付義務が生じます。
すでに課税事業者であれば、もともと消費税の申告・納付が必要であることから、新たに事務対応や税負担が増えるわけではありません。一方で、インボイス制度の登録以前が免税事業者であった場合には事務面・経済面の両方の負担が増えるおそれがあるため注意が必要です。
インボイス制度の「適格請求書発行事業者」とは?ほかとの違いも紹介
インボイス制度の施行にともなって、事業者を区分する用語が増えました。具体的には、これまでの課税事業者と免税事業者にくわえ、「適格請求書発行事業者」と呼ばれる区分が新しく定められました。
これらの区分はインボイス制度の大切なポイントであり、理解していないと自社だけでなく、取引先を交えたトラブルに発展するリスクがあります。
ここでは、インボイス制度の「適格請求書発行事業者」の概要、課税事業者や免税事業者との違いを紹介します。
適格請求書発行事業者とは、インボイスが発行できる事業者
インボイス制度の施行にともなって、「適格請求書発行事業者」という区分が新たに定められました。インボイス制度ではインボイス(適格請求書)を発行・保存の要件として、適格請求書発行事業者への登録を必須としています。
適格請求書発行事業者の登録は管轄の税務署やインボイス登録センターでおこなえ、登録することで「T」からはじまる13桁の登録番号が付与されます。
免税事業者とは、消費税の申告・納付が免除される事業者
免税事業者とは消費税の申告・納付を免除される事業者のことです。基本的には、一定期間の課税売上が1,000万円未満の事業者、あるいは開業から2年を経過していない事業者が対象となっています。
インボイス制度が施行されたことによって、免税事業者が適格請求書発行事業者に登録すると、消費税の申告・納付が義務付けられてしまう点に注意が必要です。
課税事業者とは、消費税の申告・納付が必要な事業者
課税事業者とは一定期間内で課税売上が1,000万円を超えており、消費税の申告・納付が必要な事業者のことです。免税事業者と比べると、事務面や税務面で負担が大きい事業区分となります。
インボイス制度が施行されたことによって、課税事業者が適格請求書発行事業者に登録すると、納税額の負担が軽減される可能性があります。これは課税売上にかかる消費税から課税仕入れに支払った消費税を差し引ける「仕入税額控除」が利用できるためです。
課税事業者がインボイス制度に登録した場合の影響とは?ポイントを解説
課税事業者がインボイス制度に登録すると、事務面と税務面に影響を与えます。内容によってはメリットになり得る点もあれば、デメリットになり得る点もあるため、インボイス制度における影響をしっかりと把握しておくことが大切です。
ここでは、課税事業者がインボイス制度に登録した際の影響とポイントを解説します。
【前提】消費税の申告・納付の対応は変わらない
課税事業者は消費税の申告・納付が義務付けられた事業区分です。そのため、適格請求書発行事業者に登録した場合でも、その申告や納付の方法が異なるわけではないため、事務面での負担に大きな変化はありません。
一方で、インボイス制度では仕入税額控除が適用されるため、税務面の負担については軽減される可能性があります。
① インボイス(適格請求書)の発行・保存が必要
インボイス制度ではインボイス(適格請求書)の発行・保存が義務付けられています。具体的には、以下の記載事項を備えた「インボイス」を発行する必要があり、とくに登録したばかりの段階でテンプレートの変更や会計システムの対応などの事務的な負担が大きくあります。
- 発行者の名称と登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率対象の場合はその旨)
- 取引金額(税率ごとの合計金額および適用税率)
- 税率ごとに区分した消費税額など
- 受領する事業者の名称
(※)インボイス制度で追加された事項を太字にしています。
② 仕入税額控除が受けられる
仕入税額控除とは、課税売上にかかる消費税から課税仕入れに支払った消費税を差し引いて計算する控除の仕組みです。
インボイス制度以前は、免税事業者からの仕入れでも仕入税額控除の適用が可能でありました。しかし、インボイス制度施行後は、受領したインボイス(適格請求書)の保存によって仕入税額控除が適用される仕組みに変更されました。
このような変更点から、取引において「適格請求書発行事業者」に登録しているかが重要になりつつあります。
【注意】免税事業者がインボイス制度に登録すると、事務や経済面での負担が増える!
免税事業者がインボイス制度に登録した場合、以下のような影響があります。
- 登録したら課税売上に関係なく、消費税の申告・納付が必要
- インボイス(適格請求書)の発行・保存などの事務負担の増加
事務面ではインボイスの記載や計算など細かなルールが定められており、対応には時間と手間がかかるでしょう。また、経済面では、免税事業者にはこれまでなかった消費税の納付という負担が生じます。
なお、インボイス制度では2割特例や経過措置などで事務面・経済面の負担を抑えられる対策も講じられています。これからインボイス制度の登録を検討する場合には、あわせて確認しましょう。
関連記事:インボイス制度による免税事業者への影響は?経過措置や特例もあわせて解説
まとめ|インボイス制度と課税事業者の関係を把握して登録を
本記事では、インボイス制度での課税事業者への影響を免税事業者と比較して解説しました。
課税事業者では、インボイス制度の施行によって、仕入税額控除ができないデメリットが大きいといえます。このようなことから、インボイス制度に登録したほうが良いケースが増えていくでしょう。
したがって、インボイス制度の登録を検討する場合、経済的な側面だけでなく、事務的な側面にも注目しておく必要があります。具体的には、インボイス(適格請求書)へのテンプレート変更や、会計システムのアップデート、また受領したインボイスの保存などのさまざまな対応をしなければなりません。
上記を踏まえて、課税事業者として事業運営をしている場合には、本記事や本メディアのほか記事もあわせて、これからのことを考えていきましょう。










