インボイス制度で税金の計算は変わる?基本的ルールや特例の計算例も解説
更新日:2025.01.30
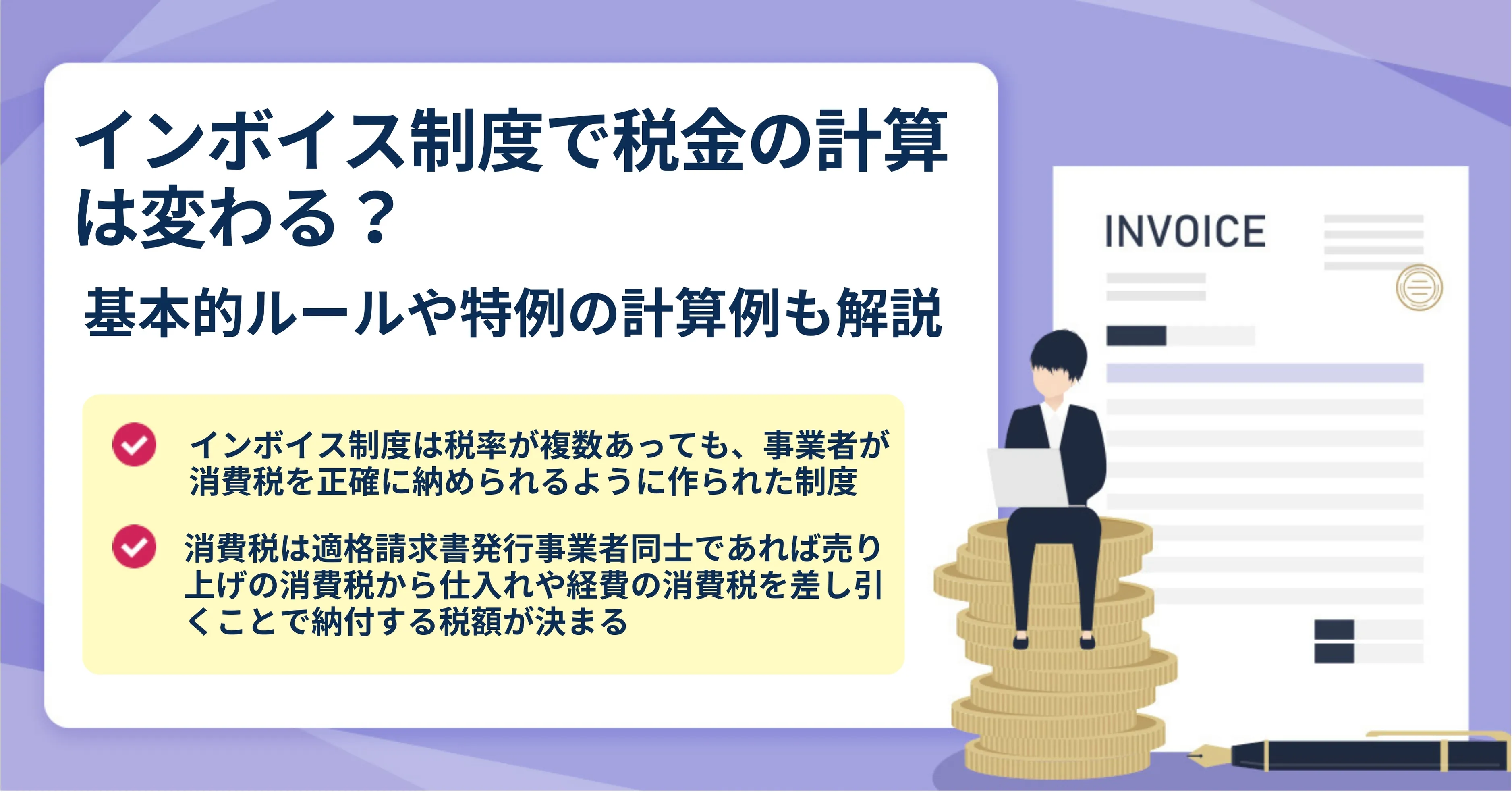
ー 目次 ー
インボイス制度が施行され、請求書の発行や税金の計算などのルールが追加されました。ルールを理解しないまま税金の計算を行ってしまうことで、納税時のミスをはじめとしたトラブルにつながる可能性があります。
本記事では、インボイス制度で変わった税金の計算に関するルールや実際の計算式を解説します。自社が利用するべき税金の計算方法を理解して、確定申告時に備えて準備をしましょう。
インボイスにかかわる税金は消費税
インボイス制度は、2019年10月1日に施行された複数税率の導入によって計算が煩雑になった消費税を、事業者が正確に納められるように作られた制度です。このような背景から、消費税にまつわる書類の発行や計算などのルールが変更となりました。
課税事業者は消費税を納付する義務がありますが、適格請求書発行事業者同士の取引であれば、売上の消費税から仕入れや経費の消費税を差し引くことが可能になります。
そのためには、インボイス制度に対応した適格請求書を取引先に発行してもらうことが必要です。適格請求書には商品ごとの消費税が明記されているため、納税時の計算でミスが起きにくくなる効果が見込めます。
なお、適格請求書発行事業者として税務署に申請していない場合は、インボイス制度後も消費税の扱いに変更はありません。
インボイスで変更された税金の計算に関するルール
インボイス制度で変更された、税金の計算に関するルールは4つです。理解しないまま確定申告の作業を進めてしまうと、納税時のミスにつながる可能性があるため注意しましょう。
ここからは、インボイス制度で変更された税金の計算に関するルールを4つ解説します。
- 適格請求書ひとつにつき端数処理は1回
- 消費税額の計算で積上げ計算が可能になった
- 仕入税額控除は相手が適格請求書発行事業者でないと利用できない
- 複数の書類で適格請求書を発行する場合は端数処理は1回のみ
①適格請求書ひとつにつき端数処理は1回
インボイス制度施行後に使用される適格請求書では、端数処理がひとつの書類につき税率ごとに1回ずつになりました。適格請求書の前に使用されていた区分記載請求書では、明確なルールが決まっておらず、商品ごとに端数処理を行っても問題ありませんでした。
なお、端数処理の方法は「切り捨て」・「切り上げ」・「四捨五入」から事業者が選ぶことが可能です。一般的には、切り捨てが多く選ばれています。
②消費税額の計算で積上げ計算が可能になった
インボイス制度施行後からは、消費税の計算方法で積上げ計算が可能になりました。積上げ計算とは、適格請求書に記載された消費税を都度計算して、確定申告時に納付する消費税の合計額を算出する方法です。
インボイス制度が施行されるまでは、1年間の合計売上金額や合計仕入金額をもとに納付する消費税を決める割戻し計算が採用されていました。
積上げ計算では適格請求書発行段階で端数処理されているため、0円未満の消費税が発生せず、納付額が少なくなりやすい利点があります。
③仕入税額控除は相手が適格請求書発行事業者でないと利用できない
インボイス制度施行後は、仕入税額控除を利用するためには、適格請求書発行事業者同士での取引である必要が増えました。
仕入税額控除とは課税事業者が消費税を納税する際に、仕入れで支払った消費税を売上で預かった消費税から差し引くことが可能な制度です。仕入税額控除は適格請求書発行事業者以外との取引には利用できず、納税額の負担を軽減できません。
仕入税額控除の利用を前提に取引を進める場合は、取引先が適格請求書発行事業者か確認しておくと安心です。また、取引先が適格請求書発行事業者でない場合は、経理部も消費税を計算するときに注意する必要があります。
④複数の書類で適格請求書を発行する場合は端数処理は1回のみ
適格請求書は、請求書と納品書などの、複数の書類で発行することが可能です。複数書類でインボイスを発行する際は、適格請求書の要件を2つの書類で揃えれば問題ありません。
ただし、インボイス施行後は端数処理がひとつの適格請求書で1回のみと定められています。複数の書類でひとつの適格請求書として扱う場合は、端数処理はそのうちのひとつの書類のみでおこなうよう注意しましょう。
ほかにも、適格請求書は必要な項目が多いため、複数の書類でインボイスを発行するときは項目の抜け漏れがないかよく確認することが大切です。
インボイス施行後に選択できる税金の計算式
インボイス制度での消費税の計算方法は複数あるため、それぞれの計算式を理解して自社にあった方法を選ぶことが大切です。
ここからは、インボイス施行後に選択できる税金の計算式について解説します。
- 一般課税
- 簡易課税制度
- 2割特例
①一般課税
一般課税は仕入税額控除を利用するときに、売上の消費税から、実際に仕入れ時に支払った消費税を差し引いて計算する方法です。2割特例の対象外の事業者や、簡易課税制度を申請しなかった事業者に適用されます。
一般課税はほかの計算方法とは異なり消費税の控除が受けられないため、納税額が多くなる可能性があります。一方、仕入れる商品が多い事業は、税金の還付が受けられるため、納税額が少なくなる場合もあるでしょう。
②簡易課税制度
簡易課税は、事業内容ごとに設定された「みなし仕入率」をもとに納税する金額が計算される計算方法です。
|
第1種事業 |
90% |
卸売業 |
|
第2種事業 |
80% |
小売業・農業・林業・漁業 |
|
第3種事業 |
70% |
農業・林業・漁業・鉱業・建設業・製造業・電気業・ガス業・熱供給業および水道業 |
|
第4種事業 |
60% |
第1種事業・第2種事業・第3種事業・第5種事業・第6種事業以外の事業 |
|
第5種事業 |
50% |
運輸通信業・金融・保険業 ・サービス業 |
|
第6種事業 |
40% |
不動産業 |
簡易課税は、売上に対してみなし仕入率が一括で計算されるため、軽減税率の商品を取り扱っている事業者でも消費税の計算がしやすい点がメリットです。
インボイス制度における簡易課税制度の取り扱いは、以下の記事で解説しているため、ぜひ参考にしてください。
関連記事:インボイス制度で簡易課税制度は廃止?2割特例との違いや注意点も解説
③2割特例
2割特例は、インボイス制度開始にともない課税事業者になった人が利用できる制度です。
2割特例を選択することで、納税するべき消費税の8割が控除されるため、金銭的な負担を減らせます。事前に申請も必要なく、確定申告時に利用するかどうか判断が可能です。
ただし、適用できる期間が定められており、期間が過ぎたら一般課税と簡易課税制度のどちらで納税するかを決める必要があります。
まとめ|インボイスで変更された税金の計算ルールを理解して確定申告に備えよう
本記事では、インボイス制度で変わった税金の計算に関するルールや実際の計算式を解説しました。
インボイス制度施行にともない、税金の計算に関するルールは変更された部分が数多くあります。変更点を理解していないと、納税時に金額を誤るといったミスにつながる可能性があります。
仕入税額控除にかかわるルールも変更されているため、課税仕入れがある企業は本記事を参考にルールを確認しておくと安心です。










