インボイス制度で簡易課税制度は廃止?2割特例との違いや注意点も解説
更新日:2025.12.07
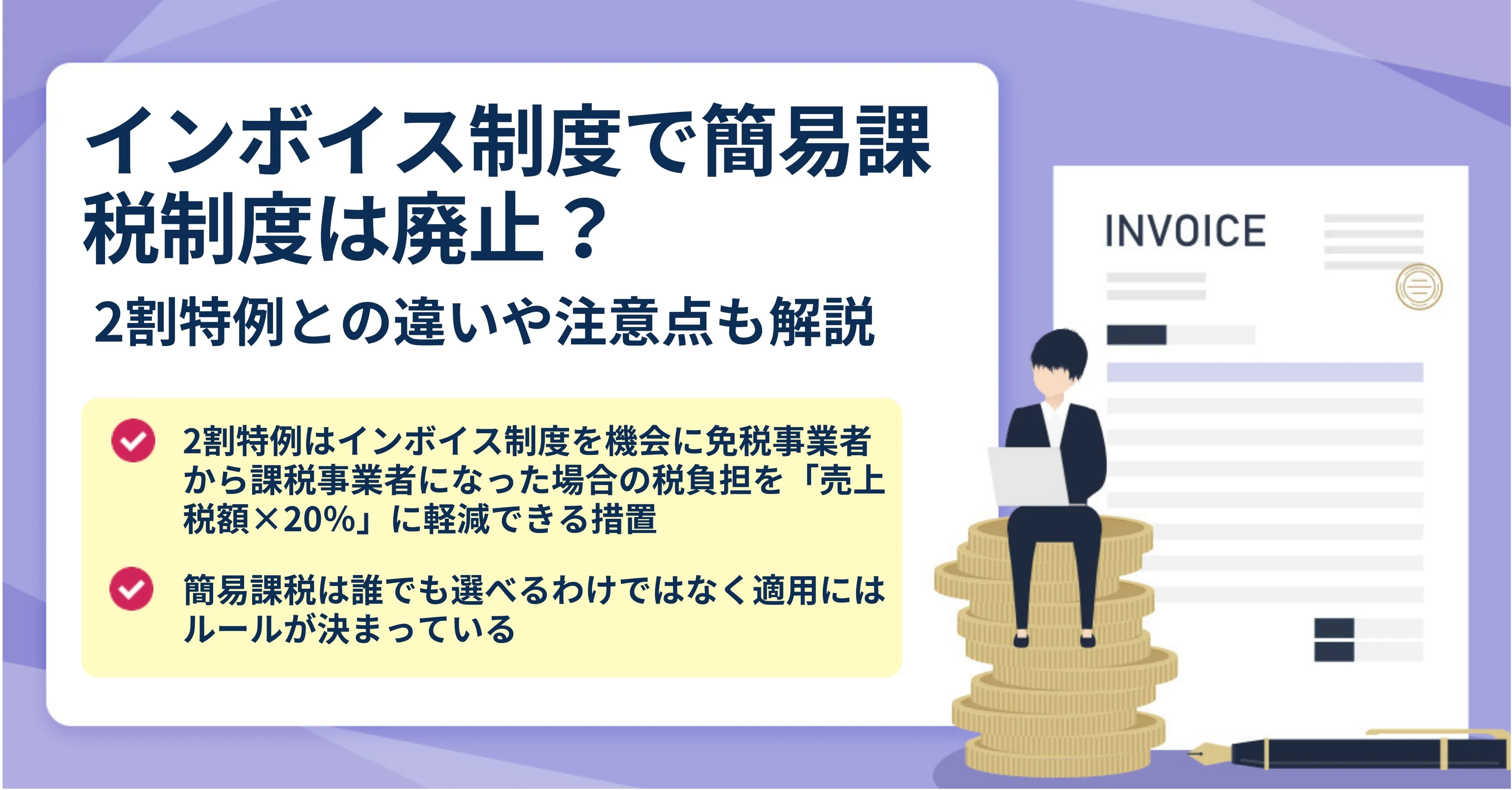
ー 目次 ー
インボイス制度を機会に課税事業者となった場合、「簡易課税制度」や「2割特例」などの制度が施行されて、混乱する事業者も多く存在します。
簡易課税制度は、インボイス制度施行前からある、中小事業者の納税負担を軽減する仕組みです。一方で、2割特例はインボイス制度で課税事業者になった場合の納税負担を軽減するための措置です。
消費税で損をしないためには、それぞれの制度の計算方法の違いやいつまで適用されるのかを理解しておきましょう。
本記事では、インボイス制度施行後の簡易課税制度について、メリットや注意点、2割特例との違いを解説します。
インボイス制度の前に!簡易課税制度の基礎知識
簡易課税制度はインボイス制度施行前からある、中小事業者が納税する消費税の負担を軽減する制度です。簡易課税制度についての知識をつけたうえで、2割特例とどちらを利用するか選ぶと、後悔のない判断がしやすくなります。
ここでは、簡易課税制度の基礎知識を解説します。
- 簡易課税制度は経理・事務作業の負担を少なくするための制度
- 一般課税との違いは消費税の計算方法
- 簡易課税制度を利用していても適格請求書発行事業所の登録は必要
①簡易課税制度は経理・事務作業の負担を少なくするための制度
簡易課税制度はインボイス施行前からある、経理・事務作業の負担を少なくするための制度です。簡易課税制度を利用すれば、売上や仕入れにかかわる消費税を簡易的な方法で計算できます。
消費税の計算は、複数税率の導入から8%と10%の消費税をそれぞれ計算したうえで納税をおこなうため複雑になりました。課税事業者は簡易課税制度を申請することで、消費税を業種ごとの「みなし仕入率」で計算でき、複数税率でも分けて対応する必要がなくなります。
なお、みなし仕入率とは、売上に対して業種ごとにかかると想定された仕入率をもとに決められた控除の割合です。
②一般課税との違いは消費税の計算方法
簡易課税制度と一般課税の違いは、消費税の計算方法です。
- 簡易課税制度:受け取った消費税額×業種ごとのみなし仕入率
- 一般課税:受け取った消費税の額-仕入等の際に支払った消費税の額(軽減税率の商品も含む)
このように、一般課税で売上や仕入れに関する消費税をひとつずつ計算する必要があります。一方で、簡易課税制度では消費税の計算をまとめておこなえるため、経理の負担が大きく減少するでしょう。
③簡易課税制度を利用していても適格請求書発行事業者の登録は必要
簡易課税制度の有無にかかわらず、インボイス制度を利用する場合は、適格請求書発行事業者の登録が必要です。適格請求書発行事業者になることで、国税庁より登録番号が発行されるため、取引をおこなうときは取引先へ伝えましょう。
なお、取引先から適格請求書を発行された場合でも、自社がインボイス制度を利用しない場合は登録が不要です。
【結論】インボイス制度で課税事業者になったら2割特例の対象
インボイス制度を機会に免税事業者から課税事業者になった場合は、2割特例の対象になります。2割特例とは、課税事業者の消費税負担を「売上税額×20%」に軽減できる措置です。たとえば、売上税額が1,000円の場合は、その2割分である200円を納税すれば問題ありません。
なお、売上税額を計算するときは、売上の消費税から仕入れにかかった消費税を差し引きましょう。
インボイス制度によって課税事業者になった場合、いままでかからなかった消費税を納付する必要があるため、事業者の金銭的負担を減らすための制度です。
ただし、2割特例には適用期間があり、個人事業主であれば2023年10月〜2026年分の申告をするまでの4回分が対象になります。法人は、2023年10月〜2024年3月までの申告から2026年の申告までの4回分が対象です。
2割特例の適用期間終了後は、簡易課税事業者になるか一般課税で納付するかを選べます。
インボイス制度後に簡易課税制度の対象となる事業者
簡易課税制度は誰でも希望すれば利用できるわけではなく、適用にはルールが決まっています。自社が当てはまるかを確認したうえで、届出を出すか考えましょう。
①課税売上が5,000万円以下の事業者
簡易課税制度を利用するためには、個人事業者は2年前、法人であれば前々事業年度の売上が5,000万円以下であることが条件です。基本的に5,000万円の金額は税抜で計算されますが、2期前が免税事業者であった場合は税込で計算されるため注意しましょう。
課税売上が5,000万円を超える事業者は、簡易課税制度を利用できないためほかの方法を考える必要があります。
②事前に消費税簡易課税制度選択届出書を提出している
簡易課税制度を利用するためには、対象にしたい課税期間が始まる前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出する必要があります。
個人事業主が提出する場合は、課税期間は1月1日~12月31日が一般的のため、翌年から簡易課税制度を利用したいときは12月31日までに提出しましょう。法人が簡易課税制度を利用したい場合は、自社の課税期間によって提出期限が異なるため確認が必要です。
インボイス施行後の簡易課税事業者の2つのメリット
インボイス施行後に簡易課税制度を利用するか悩んだときは、メリットを理解して決めましょう。メリットを理解したうえで制度の利用を検討すると、判断がしやすくなります。
ここからは、インボイス施行後の簡易課税事業者のメリットを2つ解説します。
- 節税できる可能性がある
- 経理・事務スタッフの負担が減らせる
①節税できる可能性がある
簡易課税制度を利用する場合、実際の仕入率がみなし仕入率よりも少なければ節税が可能です。事業ごとにみなし仕入率が異なるため、自社の事業のみなし仕入率を確認して検討しましょう。
とくに、コンサルティング業や保険業などの仕入れが少なく、人件費が多い事業は簡易課税制度を申請すると納税額が少なくなる可能性があります。
②経理・事務スタッフの負担が減らせる
簡易課税制度を利用すると、消費税の計算にみなし仕入率が適用されるため、事務処理の手間が大幅に減らせます。
一般課税の場合、消費税の計算に軽減税率を考慮する必要があり、一つひとつの計算が複雑になります。一方で、簡易課税制度を利用した計算であれば計算はみなし仕入率が適用されるため、計算だけでなく請求書や収税額を証明する書類管理も簡単になるでしょう。
インボイス施行後の簡易課税事業者の注意点
インボイス施行後の簡易課税制度には注意点もあり、誤れば税金にまつわる重大なミスにつながります。申請後に後悔しないよう、自社に適した制度かきちんと見極めましょう。
ここでは、インボイス施行後の簡易課税事業者の注意点を解説します。
①一度選択すると2年間は一般課税に戻せない
インボイス施行後も、簡易課税制度を選択した場合は原則として2年間は一般課税に戻せません。ただし、2年の間に課税売上高が5,000万円を超えた場合は、その期間が一般課税になります。
2年のうちに事業内容に大きな変化がある場合は、簡易課税制度を申請するか慎重に検討する必要があります。また、2年経って簡易課税制度をやめる場合も、あらためて消費税簡易課税制度選択不適用届出書を提出する必要があるため注意しましょう。
②節税できるとは限らない
簡易課税制度を選択したものの、事業が赤字の場合は必ずしも節税できるとは限りません。赤字の年に簡易課税制度を利用していると、一般課税であれば還付されるはずであった消費税がみなし仕入率で計算されてしまいます。
事業を始めたばかりでマイナスの可能性が考えられる場合は、簡易課税制度ではなく一般課税を選択するのも方法のひとつです。
インボイス制度後の簡易課税制度についてよくある質問
最後に、インボイス制度後の簡易課税制度に関するよくある質問に回答します。
①インボイスの2割特例と簡易課税制度はどっちが得?
インボイスの2割特例と簡易課税制度では、多くの事業者が2割特例のほうが得になります。
ただし、事業内容によってはみなし仕入率が高いため、簡易課税制度を利用するほうが消費税の納付額が少なくなる可能性があります。とくに、卸業者はみなし仕入率が90%のため、簡易課税制度を利用したほうが節税できる確率が高まるでしょう。
②インボイス施行後は簡易課税制度が廃止される?
インボイス制度施行後も、簡易課税制度は廃止されません。
なお、インボイス制度のタイミングに課税事業者になった場合は、2割特例と簡易課税制度どちらで消費税を納付するか選べます。
③インボイスは簡易課税制度に関係ない?
インボイス制度施行後も簡易課税制度は存在するため、関係ないとはいえません。インボイス制度施行のタイミングで課税事業者になった場合は2割特例の利用が可能ですが、経過措置が終わったタイミングで簡易課税制度を利用するか一般課税で納付するか選択する必要があります。
このことから、いまは2割特例を利用している場合でも、適用期間終了後の消費税を納付する方法を考えておかなければなりません。
まとめ|インボイス施行後に簡易課税事業者になるかは慎重に判断しよう
本記事では、インボイス制度施行後の簡易課税制度のメリットや注意点、2割特例との違いについて解説しました。
インボイス制度施行のタイミングで課税事業者になった場合、2割特例が利用できるためすぐに簡易課税制度を申請するか決める必要はありません。しかし、2026年以降は消費税の納付方法を考える必要があるため、直前に焦らないよう検討しておくと安心です。
ただし、簡易課税事業者になった場合、原則2年は一般課税に戻せません。申請後に後悔しないよう、本記事を参考に慎重に決めましょう。










