インボイス制度でシステム改修は必要?発注前の確認ポイントやコストを抑える方法
更新日:2025.10.21
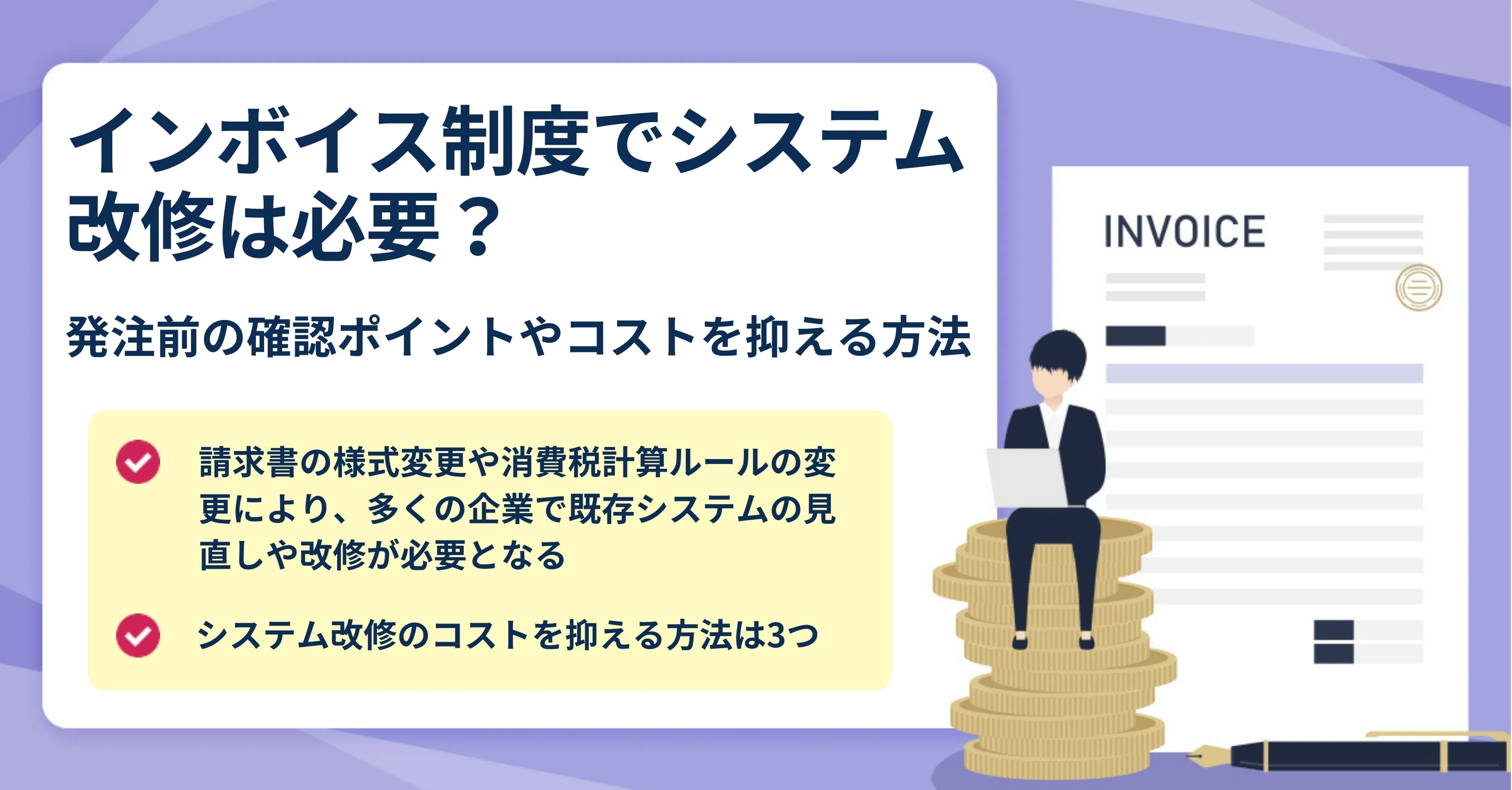
ー 目次 ー
「うちもシステム、直さないとダメかな......」とお悩みの方へ。インボイス制度の導入により、会計・請求業務への影響は避けられなくなってきています。本記事では、システム改修が本当に必要な企業の特徴を、売り手側・買い手側の立場別にわかりやすく解説いたします。加えて、費用の目安や補助金の活用方法、発注時のチェックポイントなども丁寧にご紹介します。読み終える頃には、「自社には改修が必要か」「どう進めるべきか」がすっきり見えてくるはずです。
インボイス制度対応でシステム改修は必須?まず基本を解説
インボイス制度で請求書の発行や受領、消費税の計算方法が変わるため、既存の会計システムや販売管理システムの見直しが急務となっています。本章では、システム改修の要否を判断するために、まずはインボイス制度の基本と、なぜシステム改修が必要になるのかをわかりやすく解説します。
インボイス制度の基本のしくみと導入目的!わかりやすく解説
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、消費税の仕入税額控除の適用を受けるための新しいルールです。制度導入の主な目的は、複数税率(8%と10%)が適用される中で、取引における正確な消費税額と税率を把握することにあります。
この制度下で仕入税額控除を受けるためには、原則として、売り手(適格請求書発行事業者)が発行した「適格請求書(インボイス)」の保存が必要になります。適格請求書には、従来の請求書にはなかった「登録番号」などの記載が義務付けられています。
|
項目 |
概要 |
|
制度開始日 |
2023年10月1日 |
|
目的 |
複数税率下における、仕入税額控除の計算を正確に行うため。 |
|
売り手の対応 |
適格請求書発行事業者の登録を受け、買い手の求めに応じて適格請求書(インボイス)を交付する。 |
|
買い手の対応 |
仕入税額控除の適用を受けるために、原則として適格請求書を保存する。 |
なぜシステム改修が必要になるのか?主な変更点を解説
インボイス制度への対応にあたって、企業の既存システムには大きな見直しが求められます。たとえば、インボイスに対応した請求書フォーマットや消費税の端数処理ルールだけでなく、仕入税額控除の要件変更などにも対応しないといけません。
これらの制度変更に追いつけていないシステムを使い続けると、手作業での確認や修正作業が大幅に増え、業務効率の低下やヒューマンエラーのリスクが高まります。そのため、インボイス制度にスムーズに対応するためにも、システムの改修や再構築が多くの企業で急務となっているのです。
インボイス制度でなぜ「会計ソフトの入れ替え」が必要なのか?
インボイス制度の施行により、「適格請求書発行事業者番号」や消費税率の明示、記載要件の厳格化といった対応が求められるようになりました。
そのため、従来の会計ソフトや請求書作成ツールでは、制度要件を満たせない可能性があります。
具体的には、以下の機能が備わっているソフトでなければインボイス対応が不完全になるリスクがあります。
- インボイス番号の記載・管理機能
- 税率ごとの消費税区分(10%、軽減8%など)の自動集計
- 仕入税額控除に対応した帳簿の出力
- 電子帳簿保存法に準拠した電子保存機能
古いソフトや手作業ベースの帳簿管理では、税務調査時に指摘を受けたり、控除が否認される可能性もあるため、最新のインボイス対応ソフトへの切り替えが現実的な対応策といえるでしょう。
また、インボイス対応済みのクラウド会計ソフトを導入すれば、請求書発行・帳簿管理・電子保存までワンストップで対応可能になり、経理業務の効率化にもつながります。
あなたの会社は大丈夫?インボイスでシステム改修が必要な企業の特徴
インボイス制度への対応は、すべての企業で一律に大規模なシステム改修が必要になるわけではありません。しかし、多くの企業では既存の業務フローやシステムに何らかの見直しが求められます。ここでは「売り手側」と「買い手側」それぞれの立場で、どのような場合にシステム改修が必要になるのか、具体的な特徴を解説します。
売り手側でシステム改修が必要になる場合
請求書を発行する「売り手」の立場では、インボイス制度の要件を満たした「適格請求書」を交付する義務が生じます。現在のシステムがこれに対応できない場合、改修は必須です。
適格請求書の記載要件を満たせない
インボイス制度では、従来の請求書に加えて新たに記載すべき項目が定められています。お使いの請求書発行システムや販売管理システムが、これらの項目を追加・印字できない場合は改修が必要です。
具体的には、以下の項目が追加で必要となります。
|
記載項目 |
従来の区分記載請求書 |
適格請求書(インボイス) |
|
発行事業者の氏名または名称 |
◯ |
◯ |
|
登録番号 |
- |
◯(必須) |
|
取引年月日 |
◯ |
◯ |
|
取引内容(軽減税率の対象品目である旨) |
◯ |
◯ |
|
税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率 |
◯ |
◯ |
|
税率ごとに区分した消費税額等 |
- |
◯(必須) |
|
書類の交付を受ける事業者の氏名または名称 |
◯ |
◯ |
特に「登録番号」と「税率ごとに区分した消費税額等」の2点が大きな変更点です。
税率ごとの端数処理ルールに対応できない
インボイス制度では、消費税額の端数処理に関して厳格なルールが設けられました。それは「一通の適格請求書につき、税率ごとに1回ずつ」というルールです。
例えば、現在お使いのシステムが商品や明細行ごとに消費税を計算し、その都度端数処理を行っている場合、このルールに違反する可能性があります。税率(10%対象と8%対象)ごとに合計した金額に対して、それぞれ1回だけ端数処理を行うよう、計算ロジックの改修が求められます。
買い手側でシステム改修が必要になる場合
請求書を受領して支払いを行う「買い手」の立場では、仕入税額控除を受けるために、受け取った請求書が適格請求書であるかを確認し、正しく経理処理を行う必要があります。この業務が煩雑になるため、システム対応が有効です。
受領した請求書の要件確認が煩雑になる
仕入税額控除を適用するためには、取引先から受け取った請求書が適格請求書の要件を満たしているかを確認しなければなりません。確認すべき主なポイントは以下の通りです。
- 記載されている登録番号が有効か
- 必須の記載事項に漏れがないか
- 消費税額の計算や端数処理は正しいか
これらの確認を手作業で行うのは、取引件数が多い企業ほど膨大な手間と時間がかかり、人的ミスの原因にもなります。会計システムや経費精算システムに、受領した請求書の登録番号を国税庁の公表サイトと照合する機能や、記載要件を自動チェックする機能があれば、業務を大幅に効率化できます。
仕入税額控除の計算や帳簿への記載が複雑化する
インボイス制度開始後は、仕入税額控除の対象となる取引と、対象とならない取引(免税事業者や消費者からの仕入れなど)を明確に区別して経理処理を行う必要があります。特に、免税事業者からの課税仕入れについては、制度開始から6年間は一定割合を控除できる経過措置が設けられており、計算がさらに複雑になります。
こうした複雑な仕訳や計算を手作業で行うのは現実的ではありません。多くの会計システムでは、受け取った請求書が適格請求書か否かを登録し、それに応じて仕入税額控除の計算を自動で行う機能が搭載されています。この機能がない旧来のシステムを利用している場合は、改修や乗り換えの検討が必要です。
インボイス対応でシステム改修が不要なケース
一方で、以下のようなケースでは、必ずしも大規模なシステム改修は必要ないと考えられます。
- 顧客が一般消費者のみのBtoC事業で、請求書の発行を求められることがない場合
- 取引先がすべて免税事業者や消費者であり、仕入税額控除の適用を受けない場合
- すでにインボイス制度に対応済みのクラウド型会計ソフトや請求書発行サービスを利用している場合
- 取引件数が非常に少なく、手書きやExcelのテンプレートで十分に対応できる個人事業主や小規模事業者
ただし、これらの場合でも、将来的に課税事業者との取引が始まったり、事業が拡大したりする可能性を考慮し、いつでも対応できるよう準備しておくことが望ましいでしょう。
個人事業主でも会計ソフトの変更は必要?インボイス対応の実情
インボイス制度の対応は法人だけの話ではありません。
個人事業主であっても「適格請求書発行事業者」として登録する場合、会計ソフトの見直しが必要になるケースがあります。
特に、これまでエクセルや手書きで帳簿や請求書を管理していた場合、インボイスの記載要件(登録番号・税率・消費税額など)を手動で対応するのは現実的ではありません。
また、仕入税額控除を適用するには、帳簿とインボイスの整合性が求められるため、会計ソフトの機能が対応していないと、税務リスクが高まります。
一方で、課税売上が少なくインボイス制度の影響が限定的な事業者であれば、現状のソフトでも問題ない場合もあります。
重要なのは、自身の事業の規模や取引先のインボイス対応状況をふまえて、必要な機能を備えたソフトへ切り替える判断です。
最近では、フリーランス向けのインボイス対応クラウド会計ソフトも普及しており、請求書発行・帳簿記録・電子保存を一元化することで、手間とミスを大幅に減らせます。
インボイスのシステム改修にかかる費用とコストを抑える方法とは?
インボイス制度への対応でシステム改修を検討する際、最も気になるのが「費用」ではないでしょうか。実は工夫次第でコストを大幅に抑えることも可能です。ここでは、システム改修にかかる費用の目安と、コストを抑えるための具体的な方法を解説します。
システム改修にかかる費用の目安
システム改修の費用は、対応方法によって大きく異なります。自社の状況と照らし合わせ、どの程度のコストがかかるのか、以下の表で大まかな目安を確認しましょう。
|
対応方法 |
費用の目安 |
主な特徴 |
|
既存システムのカスタマイズ |
数十万円~数百万円 |
現在利用している販売管理システムや会計システムを改修する方法。システムの複雑さや開発会社の料金体系により費用が変動します。 |
|
インボイス対応パッケージソフトの導入 |
数万円~数十万円 |
インボイス制度に対応した市販のソフトウェアを新たに導入する方法。比較的安価ですが、業務フローをソフトに合わせる必要があります。 |
|
クラウド型会計・請求システムの導入 |
月額数千円~数万円 |
初期費用を抑えられ、法改正にも自動でアップデート対応するサービスが多いのが魅力。ランニングコストが発生します。 |
|
スクラッチ開発 |
数百万円~数千万円以上 |
自社の業務に完全に合わせて、オーダーメイドでシステムを新規開発する方法。費用は高額になりますが、最も自由度が高いです。 |
システム改修のコストを抑える3つの方法
多額の費用がかかるイメージのあるシステム改修ですが、国の補助金を活用したり、システムの選び方を工夫したりすることで、負担を軽減できます。ここでは代表的な3つの方法をご紹介します。
IT導入補助金を活用する
中小企業・小規模事業者がITツールを導入する際に活用できるのが「IT導入補助金」です。インボイス制度への対応もこの補助金の対象となっており、特に「デジタル化基盤導入枠」は、インボイス対応の会計ソフトや受発注ソフト、決済ソフトなどの導入費用を補助してくれます。ソフトウェア購入費やクラウド利用料(最大2年分)などが対象経費となります。公募期間や申請要件があるため、導入を検討する際は早めに公式サイトなどで情報を確認しましょう。
安価なクラウド型サービスに乗り換える
現在オンプレミス型(自社サーバー設置型)のシステムを利用している場合、インボイス対応を機に安価なクラウド型サービスへ乗り換えるのも有効な手段です。クラウド型サービスは、月額数千円から利用できるものが多く、初期費用(イニシャルコスト)を大幅に削減できます。また、制度改正に伴うシステムのアップデートもサービス提供側で自動的に行われるため、将来的なメンテナンスコストを抑えられる点も大きなメリットです。
Excelテンプレートや手作業で対応する
取引先の数が少なく、請求書の発行枚数が限られている個人事業主や小規模事業者であれば、システムを導入せず、Excelなどを活用して対応する方法もあります。国税庁のウェブサイトでは、適格請求書の要件を満たしたExcelテンプレートが無料で提供されています。コストを最小限に抑えられる一方で、手作業による入力ミスや管理の煩雑さといったデメリットも存在します。事業規模が拡大した際の対応も視野に入れ、将来的なシステム導入を検討しつつ、一時的な対策として活用するのが現実的です。
失敗しない!インボイスのシステム改修の進め方と発注前の確認ポイント
インボイス制度に対応するためのシステム改修は、決して小さなプロジェクトではありません。ここでは、システム改修を成功に導くための具体的な進め方と、発注前に必ず確認すべきポイントを解説します。
発注前の確認するポイントと業者選定のコツ
システム改修を外部の業者に依頼する前に、まずは自社の状況を整理し、目的を明確にすることが重要です。以下の3つの観点を確認しておくことで、最適な業者選定やスムーズな導入につながります。
① 現状の業務フローと課題を把握する
まず、請求書の発行・受領から経理処理までの一連の業務フローを洗い出し、現在使用しているシステム(販売管理ソフト、会計ソフトなど)や、手作業で対応している非効率な部分を明確にします。どこをシステムで効率化したいのかをはっきりさせることで、改修の目的がぶれず、導入後の満足度も高まります。
② システムに求める機能(要件)を定義する
次に、インボイス制度に対応するために必要な機能を整理します。たとえば以下のような要件です:
- 適格請求書の発行・保存機能
- 受領請求書の適格性チェック機能
- 税率ごとの消費税額計算と端数処理
- 仕入税額控除の計算や帳簿との自動連携機能 など
このとき、「必須の機能(Must)」と「あると便利な機能(Want)」に分けて整理しておくと、業者との打ち合わせもスムーズに進み、見積もりの精度も高まります。
③ 予算とスケジュールをあらかじめ決めておく
システム改修にかけられる予算の上限や、いつまでに本稼働させたいかといったスケジュール感も事前に設定しておきましょう。
あらかじめ条件を整理しておくことで、業者からの提案内容が現実的かどうかを冷静に判断でき、トラブルの回避にもつながります。
システム開発業者の選定のコツ
インボイス制度に対応するためのシステム改修を外部に依頼する際は、価格や知名度だけで選ぶのではなく、以下のポイントをもとに信頼できる業者かどうかを総合的に判断することが大切です。
① 実績と専門性を確認する
業者選びでまず重視したいのは、制度対応の実績と専門知識です。インボイス制度に関するシステム改修を実際に手がけた経験があるか、自社と同じような業種・規模の企業への導入実績があるかをチェックしましょう。さらに、会計や税務に関する理解があるかも重要なポイントです。
制度に対する理解が深い業者であれば、自社が見落としている課題や改善の余地にも気づき、より良い運用方法を提案してくれる可能性があります。
② 提案内容と見積もりを比較検討する
つづいて、提案の中身と見積もりの明確さを確認します。要件をきちんと満たしているかどうかはもちろん、初期費用・月額費用・追加費用などの内訳がはっきりしているかを見極めましょう。複数の業者から相見積もりを取り、価格だけでなく内容や費用対効果も含めて総合的に比較することが、失敗しない業者選びのコツです。
③ 導入後のサポート体制を確認する
システム導入はゴールではなく、スタートです。長く安心して使い続けるためには、導入後のサポート体制がしっかりしているかどうかを必ず確認しましょう。
たとえば、操作マニュアルやトレーニングが用意されているか、トラブルが発生した際の問い合わせ窓口や対応時間、法改正など将来の変更への対応方針などが明確かどうかが重要です。万が一のときにスムーズな対応が受けられる体制があるかどうかは、業者選定の大きな決め手になります。
インボイスのシステム改修の手順4ステップ!
発注前の準備が整ったら、いよいよシステム改修を具体的に進めていきます。一般的に、システム改修は以下の4つのステップで進行します。
ステップ1:現状分析と要件定義
最初のステップは、自社の現状を正確に把握することです。現在の請求業務の流れを可視化し、インボイス制度に対応するために何が不足しているのか、どこを改善すべきかを洗い出します。その上で、システムに実装すべき機能を具体的にまとめた「要件定義書」を作成します。この要件定義書が、後の業者選定や開発の土台となるため、非常に重要な工程です。
ステップ2:業者選定と見積もり
作成した要件定義書をもとに、複数のシステム開発業者に相談し、提案と見積もりを依頼します。このとき、1社だけでなく複数の業者から話を聞く「相見積もり」を行うのが基本です。各社の提案内容、費用、実績、サポート体制などを比較検討し、自社に最も適したパートナーとなる業者を選定して契約します。
ステップ3:システムの開発・導入とテスト
契約した業者と協力し、システムの開発や導入作業を進めます。パッケージソフトの導入であれば設定作業が中心となり、既存システムの改修やスクラッチ開発であれば設計・プログラミングが行われます。システムが完成したら、本番稼働前に必ずテストを実施します。「適格請求書が要件通りに発行できるか」「税額計算は正しいか」など、実際の業務を想定したシナリオで入念に動作確認を行い、不具合がないかを確認します。
ステップ4:本番稼働と運用・保守
テストで問題がないことを確認できたら、いよいよ本番稼働です。稼働開始直後は予期せぬトラブルが発生することもあるため、すぐに業者に連絡できる体制を整えておくと安心です。また、従業員が新しいシステムをスムーズに使えるよう、操作マニュアルの整備や研修会の実施も重要になります。稼働後も安定してシステムを運用していくために、業者との保守契約を結び、継続的なサポートを受けられるようにしておきましょう。
Q&A|インボイスのシステム改修に関するよくある質問
インボイス制度対応のためのシステム改修を進めるにあたり、多くの企業担当者様や個人事業主様が抱える具体的な疑問について、Q&A形式でわかりやすく解説します。
システム改修費用の勘定科目は何になる?修繕費でいい?
インボイス制度対応のために支出したシステム改修費用は、その内容や金額によって会計処理上の勘定科目が異なります。一概に「修繕費」として処理できるわけではないため、注意が必要です。
会計処理は、その支出がシステムの価値を高める「資本的支出」か、現状を維持するための「収益的支出」かによって判断します。具体的な判断基準は以下の通りです。
|
支出の種類 |
改修内容の例 |
勘定科目 |
会計処理 |
|
資本的支出 |
インボイス対応に伴う新機能の追加、性能を大幅に向上させるプログラムの変更など |
ソフトウェア(無形固定資産) |
資産として計上し、原則として5年で減価償却します。 |
|
収益的支出 |
既存機能の軽微な修正、インボイス制度の要件を満たすための最小限のプログラム修正、バグの修正など |
修繕費、支払手数料など |
支出した事業年度に一括で費用として計上します。 |
ただし、取得価額が10万円未満の場合は、その内容にかかわらず費用として計上することが可能です。また、中小企業者等については、取得価額30万円未満の資産を一括で損金算入できる特例(少額減価償却資産の特例)もあります。
最終的な判断に迷う場合は、改修を依頼するシステムベンダーに支出内容の内訳を確認したり、顧問税理士などの専門家に相談したりすることをおすすめします。
個人事業主もインボイス対応の会計ソフトを使うべき?
結論から言うと、適格請求書発行事業者として登録した個人事業主やフリーランスの方は、インボイス制度に対応した会計ソフトの利用を強く推奨します。
もちろん、Excelのテンプレートを利用したり手書きで作成したりして対応することも不可能ではありません。しかし、インボイス制度では記載要件や消費税の端数処理ルールが厳密に定められており、手作業では記載ミスや計算間違いが起こりやすくなります。
インボイス対応の会計ソフトを利用する主なメリットは以下の通りです。
- 定められた要件を満たした適格請求書(インボイス)を、簡単かつ正確に発行できる
- 売上・仕入にかかる消費税額の計算を自動化でき、手作業によるミスを防げる
- 日々の帳簿付けから確定申告書類の作成まで、経理業務全体を効率化できる
- 電子帳簿保存法への対応も同時に進めやすい
市場には多くの個人事業主向けクラウド会計ソフトが存在します。月額数百円から数千円程度のコストはかかりますが、事務作業の手間や時間を大幅に削減できるメリットを考えれば、十分に投資価値があると言えるでしょう。これらのソフトはIT導入補助金の対象となる場合もあるため、導入コストを抑えることも可能です。
まとめ
インボイス制度への対応は、制度理解だけでなく、実際の業務フローやシステムの見直しが問われる場面です。ご紹介したように、改修が必要かどうかは企業の規模や取引内容によって異なりますが、「何を整備すれば制度にきちんと対応できるのか」を見極めることが大切です。必要に応じて補助金制度やクラウドソフトの活用も検討し、ムリなく進めていきましょう。この記事が、その一歩を踏み出す手助けになれば幸いです。










