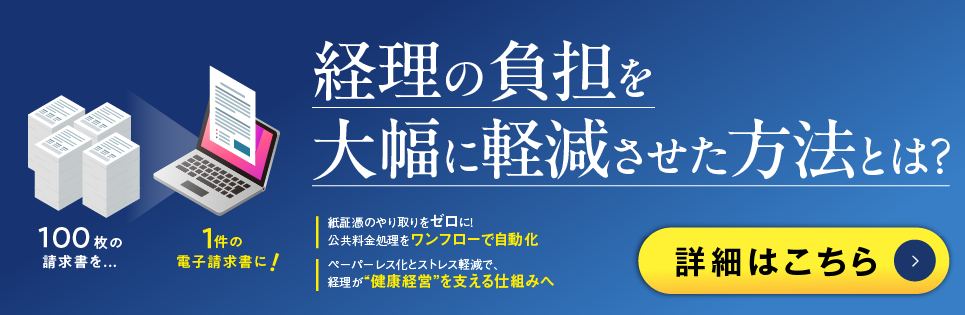知らないと損!インボイス制度で活用できる助成金・補助金一覧
更新日:2026.01.29
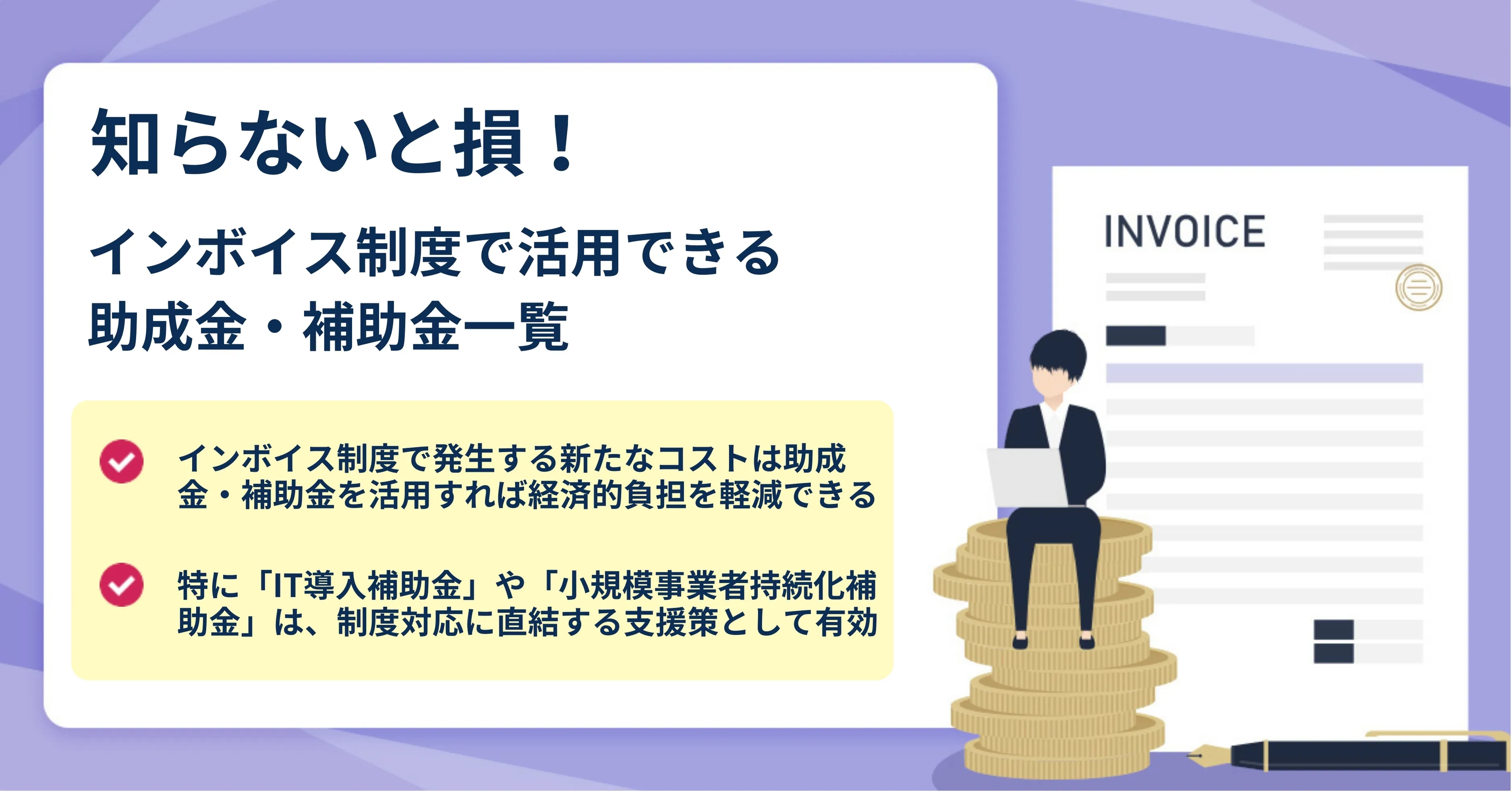
ー 目次 ー
2023年10月から本格導入されたインボイス制度は、中小企業や個人事業主にとって大きな影響を与える一方で、対応にかかるコストを軽減できる助成金・補助金制度も整備されています。この記事では、インボイス対応に必要な費用と、その費用をカバーできる国・自治体の代表的な支援制度を一覧で分かりやすく解説。適切な制度を知り、賢く活用すれば経営への負担を減らすことが可能です。
インボイス制度とは?
インボイス制度の基本的な仕組み
インボイス制度とは「適格請求書等保存方式」のことで、消費税の仕入税額控除を行う際に、一定の要件を満たす請求書(インボイス)を保存することを義務づける制度です。この制度により、仕入先がインボイス登録事業者でなければ、仕入税額控除を適用できなくなります。結果として、小規模事業者やフリーランスも登録を迫られる場面が増えており、ビジネス継続のための準備が急務となっています。
中小企業・個人事業主への影響
インボイス制度は中小企業や個人事業主に大きなインパクトを与えています。特に影響を受けるのは、これまで免税事業者として消費税の納税義務がなかった事業者です。インボイスを発行できるようにするには「適格請求書発行事業者」の登録が必要となり、その登録に伴い自動的に課税事業者となります。
これにより、新たに消費税の申告・納税義務が発生し、事務作業や税務処理の負担が増加することになります。また、登録しなければ、取引先から税務上の不利益を理由に取引の縮小や打ち切りを受けるリスクもあるため、小規模で事業を行っている個人事業主にとっては大きな選択を迫られる問題です。
こうした中小事業者の状況を踏まえ、国や自治体はインボイス対応にかかる費用への補助として、IT導入補助金や持続化補助金などの制度を設けています。次の章では、これらの制度へ対応するにあたって発生する具体的な費用について解説します。
インボイス制度対応で発生する主な費用とは?
事務処理・経理システムの変更コスト
インボイス制度への対応により、従来の帳簿管理・請求書発行方法から、制度に準拠した形式や内容への変更が求められます。これにより、経理ソフトや請求書発行ツールなどのシステム導入・アップデートが必要になる場合があります。
特に、紙ベースで管理していた事業者や、デジタル対応が遅れていた小規模事業者では、新たなITツールの導入と、それに伴う操作研修などのコストが発生します。
|
費用項目 |
具体例 |
概算金額 |
|
経理ソフトの導入・更新 |
クラウド会計ソフト |
年間10,000〜50,000円 |
|
インボイス対応の請求書発行システム |
Misoca、MakeLeapsなど |
月額500〜3,000円 |
|
操作研修・導入サポート |
ITベンダーによるオンサイト研修、オンライン講習 |
1回あたり10,000〜50,000円 |
これらの初期投資は一度で済む場合もありますが、継続的な月額利用料が発生するため、運用コストとしても注意が必要です。
税理士・コンサルタント費用
インボイス制度に対応するためには、適格請求書の発行・保存、税率の正確な計算、仕入税額控除の処理など、専門的な知識が必要とされます。そのため、税理士や中小企業診断士、会計の専門家によるサポートを受ける事業者も少なくありません。
特に複数税率を扱う飲食業や小売業、サービス業では、消費税の計算や処理が煩雑になるため、専門家の関与は大きなメリットになりますが、その分費用も発生します。
|
サービス内容 |
提供者 |
費用目安 |
|
インボイス制度導入コンサルティング |
中小企業診断士、会計事務所 |
1回30,000〜100,000円 |
|
顧問契約による継続対応 |
税理士 |
月額20,000〜50,000円 |
|
スポット契約による記帳・申告支援 |
税理士、会計士 |
案件ごとに10,000~50,000円 |
インボイス制度に伴い、これまで自身で行っていた会計処理をプロに委託する事業者が増えると見込まれており、人的支援のコストも無視できない要素です。
売上減少への対策費
インボイス制度施行により、これまで免税事業者だった小規模事業者が取引先から仕入税額控除の対象とならなくなるリスクがあります。それにより、取引停止や取引条件の悪化(値下げ要請など)が発生し、売上減少につながる可能性があります。
こうした影響を和らげるため、新たな販路開拓、集客プロモーション、取引先の多様化など、売上減少に備えた対策が必要となり、それに伴う費用が発生します。
|
目的 |
対策内容 |
必要経費 |
|
新規顧客獲得 |
ホームページ制作、SNS広告運用 |
50,000〜300,000円 |
|
販路拡大 |
展示会出展、オンラインモール参入 |
出展料・出品料50,000〜200,000円 |
|
サービス改良 |
新商品の開発、価格帯の見直し |
内容により数千~数十万円 |
このように、間接的な影響にも備えるため、制度導入によるメンタル面やビジネスモデルの見直しにもコストが生じる可能性があります。将来的に受けうる経営上のリスクを回避するためにも、戦略的な投資が求められます。
個人事業主も対象!インボイス対応に使える主な助成金・補助金一覧
IT導入補助金(インボイス対応枠)
対象事業者と支給内容
IT導入補助金 は、中小企業や小規模事業者、個人事業主が業務効率化やDX(デジタルトランスフォーメーション)推進のためのITツールを導入する際に利用できる補助金です。とりわけ「インボイス対応類型」では、インボイス制度への対応を目的とした会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフトなどの導入が支援の対象となります。
補助対象となるのは、以下のようなツールやサービスです。
- インボイス対応のクラウド会計ソフト
- 請求書発行・電子保存に対応した販売管理システム
- 経理業務を自動化するRPAツール
- キャッシュレス決済システム
|
支給対象 |
補助率 |
補助上限額 |
|
インボイス対応クラウド会計ソフト など |
1/2 ~ 3/4 |
最大450万円 |
申請の流れと締切期間
IT導入補助金は、まずは登録された「IT導入支援事業者」と連携して導入製品を選定・申請準備を行う必要があります。通常、数回の募集期間が設けられており、それぞれに締切があります。申請書類には導入目的や効果を記載する必要があるため、準備には余裕を持って取り組むことが重要です。
2024年時点の予定では、おおよそ2ヶ月ごとに公募があり、毎回3000件以上の採択実績があります。
小規模事業者持続化補助金(インボイス特別対応型)
交付金額と対象経費
持続化補助金は、商工会議所または商工会を通じて、小規模事業者や個人事業主が営業活動および経営継続の促進に取り組む際に利用できる補助金です。インボイス制度の開始に伴い、「インボイス対応型」として費用の対象範囲が拡大され、制度対応に係る以下のような費用が対象となっています。
- 会計ソフトやレジ等、電子インボイス対応機器の導入費
- 業務効率化システム導入のための外注費
- 税理士等に支払う専門家相談費
- 販路開拓に関わる新たな広告費(インボイス対応による売上減対策)
|
類型 |
補助率 |
補助上限額 |
|
インボイス枠(特例事業者) |
2/3 |
100万円 |
採択されるためのポイント
補助金を獲得するためには、「経営計画書」「補助事業計画書」の内容が非常に重要です。単に物品を購入する内容ではなく、「インボイス制度対応が必要な理由」「その対応によって見込まれる業務効率化や売上回復の効果」を、具体的な数値や業績目標とセットで示すことがポイントです。
また、提出書類に不備があると審査で大きく減点される可能性があるため、地域の商工会・商工会議所の無料相談を活用すると良いでしょう。
インボイス制度対応で利用できる支援制度(2割特例)
2割特例とは、インボイス制度により新たに課税事業者となった免税事業者向けの簡易課税制度で、2023年10月〜2026年9月末までの3年間限定で使える特例措置です。IT導入補助金とこの「2割特例」は、制度の性質が異なるため併用可能です。消費税の納税額を「売上にかかる消費税額の2割」とすることで、仕入税額控除の計算や帳簿整理が不要になり、経理負担を大幅に軽減することができます。
例えば、売上1,100,000円(税込)の場合、消費税は100,000円。その2割である20,000円が納税額となります。
青色・白色申告どちらの個人事業主も対象で、申請には「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が不要です。
なお、2割特例を利用するには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 2023年10月1日以降に「適格請求書発行事業者」として登録した事業者であること
- インボイス制度開始前(2023年9月30日まで)は免税事業者であったこと
- 簡易課税制度を選択していないこと(重複適用は不可)
- 2割特例の適用期間内(2023年10月1日~2026年9月30日)の課税期間であること
この特例は、あくまで「免税事業者から課税事業者へ移行した方の負担軽減」が目的です。そのため、もともと課税事業者であった方や、制度の趣旨に合わない場合は対象外となります。
申告の際には、消費税申告書の「2割特例適用欄」に記載することで簡易に適用でき、特別な届出は不要です。ただし、適用漏れや誤適用を避けるためにも、事前に税理士や最寄りの税務署へご相談いただくことをおすすめします。
ものづくり補助金
ものづくり補助金は、中小企業や個人事業主が行う新製品・新サービスの開発、または生産プロセスの改善に対して支給される補助制度です。インボイス制度そのものとは直接関係ありませんが、インボイス対応に伴って導入が必要となる業務改善ツールや請求管理システムなどが「業務効率化」「DX(デジタル化)」として補助対象になる場合があります。
2025年度も引き続き実施されており、第19次公募は2025年4月25日が締切となります。最大4,000万円まで補助を受けられるケースもあり、ITツールや設備の導入に関する幅広い経費が対象となります。電子申請にはgBizIDプライムが必要なので、早めの準備が重要です。
今後第20次公募が開始される見込みもありますが、具体的な日程はまだ公式には発表されていませんが、過去のスケジュールから推測すると、2025年6月頃に公募開始、8月頃に申請締切となる可能性があります。
第20次公募の詳細なスケジュールや要件については、ものづくり補助金の公式サイトで最新情報をご確認ください。
インボイスに関連する助成金申請時の注意点
申請書類の不備を防ぐ方法
助成金や補助金の申請では、書類の不備や記載ミスが最も多い却下理由のひとつです。特にインボイス制度に対応した助成金は、申請要項が変更されたり、対応する事業内容が多岐に渡るため、記載漏れや添付書類の不足が起きやすい傾向があります。
以下の対策を講じることで、申請書類の不備を防ぐことができます。
|
対策 |
具体的な内容 |
|
公募要領の熟読 |
申請開始前に最新の公募要領を複数回確認し、提出書類や条件を把握する |
|
チェックリストの活用 |
各自治体・補助金事務局が提供しているチェックリストを活用し、漏れなく書類を揃える |
|
専門家によるレビュー |
中小企業診断士や税理士など、補助金申請に精通した専門家に内容確認を依頼する |
|
オンライン申請システムの利用方法の事前確認 |
オンライン提出が必要な場合、システムの動作確認を事前に行い、登録やアップロードに問題がないか確認する |
また、書類の保存形式(PDFやJPEGなど)やファイルサイズの制限に関するルールにも注意が必要です。電子証明書を使う申請では、マイナンバーカードや電子証明書の有効期限切れにも注意しましょう。
スケジュール管理の重要性
助成金の申請では、提出期限直前の駆け込み申請によりエラーや混雑が発生し、不受理や申請エラーにつながるリスクがあります。したがって、計画的なスケジュール管理が不可欠です。
以下のようなステップに分けたスケジュール作成をおすすめします。
|
申請ステップ |
推奨実施時期 |
|
公募要領の確認・必要書類の整理 |
公募開始直後(1週目) |
|
事業計画書の作成・経費の精査 |
2〜3週目 |
|
書類作成および専門家との相談 |
3〜4週目 |
|
事前申請システム登録・電子証明書取得 |
同時並行で進行 |
|
最終チェック・申請提出 |
締切日の1週間前を目安に |
特にIT導入補助金や持続化補助金では「締切厳守」と明記されているため、1日でも遅れると申請が受付不可となることもあります。早め早めの準備と予備日を見込んだ進行が重要です。
交付後の報告義務とペナルティ
助成金や補助金は、交付を受けた後も「事後報告義務」が定められている場合が多く、これを怠ると返還義務やペナルティが科されることがあります。インボイス制度対応の支援金でも同様の義務が課されているため、支給後の対応まで含めて注意が必要です。
具体的には、次のような報告義務があります。
- 実施報告書の提出(導入設備・ソフトの使用状況など)
- 支出証拠書類(領収書、銀行の出金記録など)の保存と提出
- 事業実施効果の報告(売上の推移、業務効率化の成果など)
- フォローアップ調査への協力義務(1年後、2年後のアンケートなど)
これらの義務を怠った場合のペナルティには下記が含まれます。
- 受給額の一部または全額の返還
- 次回以降の助成制度への申請制限
- 企業名・個人名がブラックリストに掲載される可能性
申請前から事後報告の内容を把握し、必要なデータを記録・保管しておくことが、スムーズな運用のカギとなります。特に電子帳簿保存法やインボイス制度と関係するデジタルデータは、一定期間(通常5〜7年)の保管義務があるため、収納環境も整備しておきましょう。
Q&A|インボイスと助成金に関するよくある質問
免税事業者でも補助金の対象になるか
はい、免税事業者であっても、インボイス制度対応に関して必要な支出が発生する場合は一部の助成金・補助金の対象となる可能性があります。特に「IT導入補助金」や「小規模事業者持続化補助金」などは、課税事業者だけでなく、取引の継続や制度への対応意志がある免税事業者も対象に含まれることがあります。
複数制度の併用申請は可能か
一般的に、異なる制度間での助成金・補助金の併用は可能です。ただし、「同一経費の二重申請(補助対象経費の重複)」は厳しく禁止されています。例えば、IT導入補助金で購入した会計ソフトの費用を、別の補助金に再度申請することはできません。
|
補助金名 |
併用の可否 |
注意点 |
|
IT導入補助金 |
条件付きで可 |
同一事業内容・経費での申請は不可 |
|
小規模事業者持続化補助金 |
条件付きで可 |
内容の棲み分けが必要 |
|
地域独自の制度 |
制度による |
自治体により併用制限あり |
個人事業主でも対象になるか
多くのインボイス対応関連補助金・助成金制度では、個人事業主も対象とされています。特に、青色申告をしている事業主や、インボイス登録番号取得予定または既に取得済みの方は対象となる場合がほとんどです。
まとめ
インボイス制度の導入により、中小企業や個人事業主は新たな対応コストが発生しますが、国や自治体の助成金・補助金を活用することで、経済的負担を軽減できます。特に「IT導入補助金」や「小規模事業者持続化補助金」などは、制度対応に直結する支援策として有効です。制度の内容を理解し、スケジュール管理や書類の準備を的確に行えば、補助金を活用しながら円滑に対応できます。早めの準備と情報収集で、賢く負担軽減しましょう。