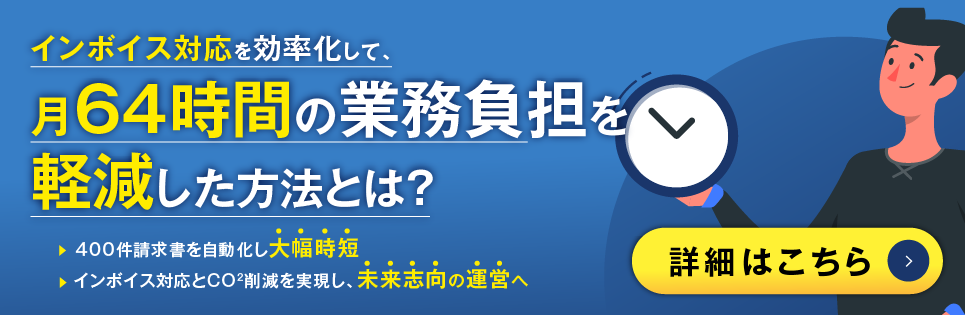インボイス制度で使える簡易課税と2割特例|いつまで使えるかわかりやすく解説!
更新日:2025.12.06
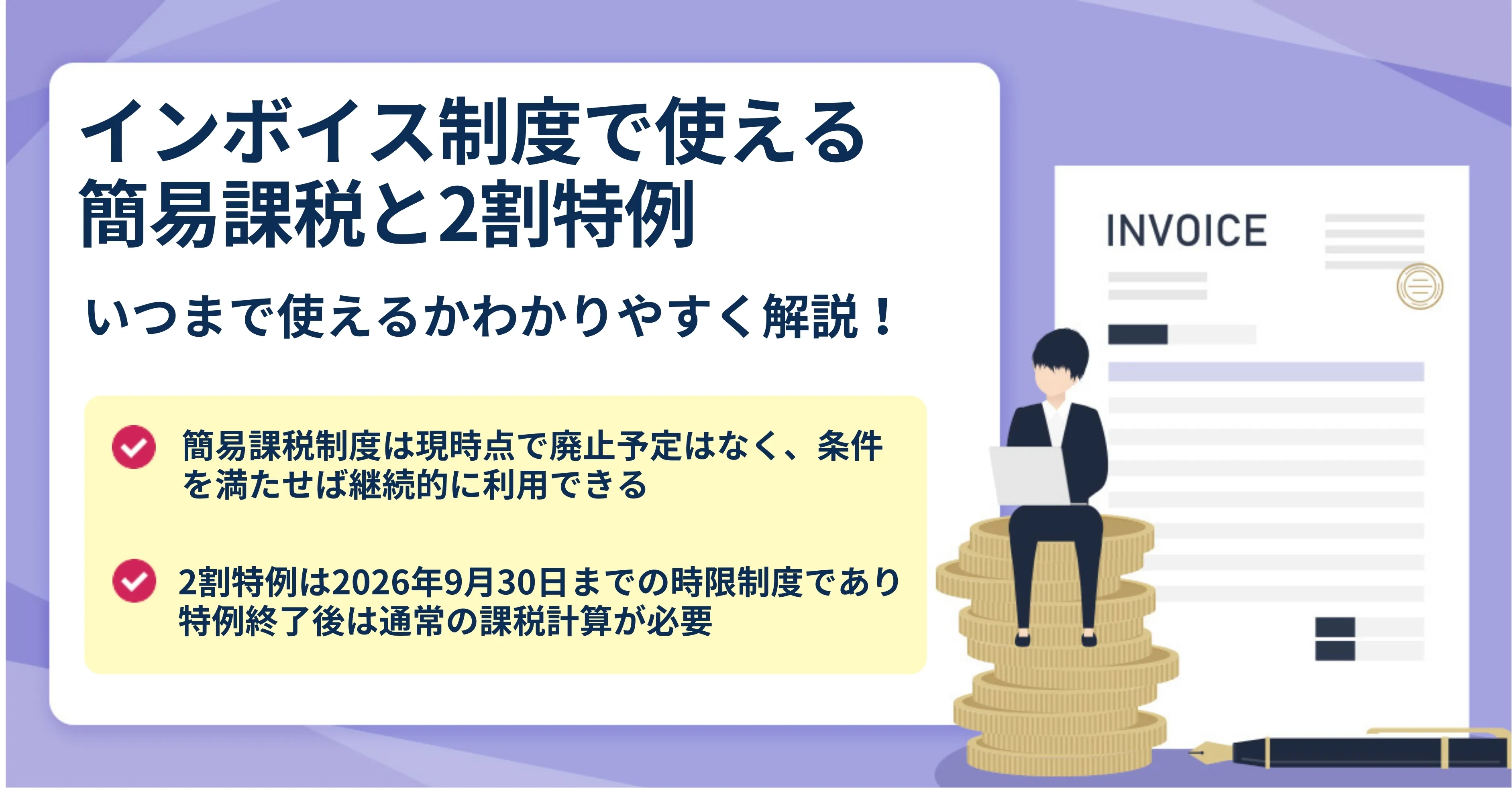
ー 目次 ー
2023年10月に導入されたインボイス制度により、個人事業主や中小企業に大きな影響が出ています。本記事では、「簡易課税制度」と「2割特例」の基礎知識から、両者の違い、使用期限、申請方法、そしてインボイス制度下での最適な選択までを徹底解説します。特に、「簡易課税はいつまで使えるのか」「2割特例の適用期限はいつまでか」といった疑問に対し、令和8年9月30日という明確な期限を示しながら、制度の全体像がわかる内容になっています。
インボイス制度とは?
インボイス制度の概要
インボイス制度とは、正式名称を「適格請求書等保存方式」といい、2023年10月1日から導入された新たな消費税の仕組みです。この制度では、仕入税額控除を行うために税率ごとに区分された消費税額などが記載された「インボイス(適格請求書)」を保存する必要があります。
この制度の導入により、事業者が消費税の申告・納税を正確に行うため、取引ごとに発行・保存される請求書の記載要件が厳格化されました。特に、課税仕入れに対する消費税の控除(仕入税額控除)を適用するには、適格請求書を保存していなければならないという点が大きな特徴です。
適格請求書発行事業者とは
インボイスを発行するには、税務署に「適格請求書発行事業者」として登録申請し、登録を受ける必要があります。適格請求書発行事業者になると、自らの取引先に対してインボイスを発行する義務が発生します。
適格請求書には以下のような要件を満たす必要があります:
- 発行者の氏名または名称(屋号)および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
- 税率ごとの消費税額
- 交付を受ける事業者の氏名または名称(任意)
登録番号は国税庁が管理し、インボイス制度のポータルサイトにて一般公開されています。
制度導入の背景と目的
インボイス制度の導入背景には、複数税率制度への対応と消費税の適正課税があります。2019年10月より、軽減税率制度が導入され、標準税率10%と軽減税率8%が併存する形となりました。それにより、事業者が税率ごとの取引内容や消費税額を明確に記録・申告する必要性が生じました。
従来の帳簿保存方式では、税率ごとの区分管理をしていなくとも仕入税額控除を適用できましたが、これでは正確な税務処理が難しくなるという問題がありました。インボイス制度はこの課題を解決するために導入され、より厳格で透明性の高い消費税制度の実現を目指しています。
また、制度の導入は国際的な消費税制度の基準にも近づける内容であり、不正確な税額の申告・納税を防止し、公正な競争環境を確保するための取り組みとして位置づけられています。
簡易課税制度とは?
簡易課税制度の仕組み
簡易課税制度とは、一定の事業者が消費税の計算において、実際の仕入控除税額を計算する代わりに、売上高に業種ごとに定められた「みなし仕入率」を適用して仕入税額控除を簡便に計算できる制度です。原則的な消費税の計算方法では、課税売上に対する消費税額から仕入れ等にかかる消費税額を差し引いて納税額を算出しますが、簡易課税では個々の仕入税額を把握せずに済むため、帳簿の記帳や税務処理が簡略化されます。
この制度は、主に中小企業や個人事業主など、経理のリソースが限られている事業者の負担軽減を目的としています。
簡易課税が選択できる条件
簡易課税制度を利用できるのは、基準期間(通常は2期前)の課税売上高が5,000万円以下の事業者に限られます。この売上高の要件を満たしていれば、自らの意思で簡易課税制度を選択することが可能です。
また、制度の適用にあたっては、所轄税務署に対して所定の「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。提出期限は、原則としてその適用を受けようとする課税期間の開始日の前日までとされています。たとえば、令和6年1月1日から簡易課税を適用したい場合は、令和5年12月31日までに届出書を提出しなければなりません。
なお、一度簡易課税を選択すると、2年間は原則として原則課税に戻すことはできません。この「継続適用義務」がある点にも注意が必要です。
業種ごとのみなし仕入率
簡易課税制度では、業種に応じてあらかじめ定められた「みなし仕入率」を用いて仕入控除税額を計算します。以下は、主な業種におけるみなし仕入率をまとめた表です。
|
業種区分 |
具体的な業種例 |
みなし仕入率 |
|
第1種事業 |
卸売業 |
90% |
|
第2種事業 |
小売業 |
80% |
|
第3種事業 |
製造業、建設業等 |
70% |
|
第4種事業 |
飲食業、サービス業(宿泊、理容など) |
60% |
|
第5種事業 |
サービス業(第4種に含まれないもの) |
50% |
|
第6種事業 |
不動産業 |
40% |
たとえば小売業を営む事業者の場合、売上に係る消費税額に80%を掛けた金額を仕入税額とみなして控除できます。具体的には、100万円の売上に対し消費税が10万円課税されているとすると、10万円 × 80% = 8万円が仕入税額として控除されたうえで、差額の2万円が納税額となります。
ただし、複数の業種にまたがる事業を営んでいる場合、それぞれの売上高ごとに対応する業種区分を適用する必要があるため、事業の内容や売上構成を正確に分類することが求められます。
さらに、農業や運輸業、情報通信業など特殊な業種については、分類が一般的な判断と異なる場合がありますので、顧問税理士や国税庁の公表資料を確認することが推奨されます。
2割特例とは?
インボイス導入特例としての2割特例
2割特例とは、2023年10月から始まったインボイス制度に関連して導入された、消費税の簡便な計算方式の一つです。正式名称は「適格請求書発行事業者に係る消費税の納税額の特例」で、「2割特例」と俗称される理由は、課税売上高に対する消費税額のおおよそ20%を納付するだけで済む仕組みだからです。
この特例は、主に2023年10月よりインボイス発行事業者として登録した小規模事業者を対象としており、帳簿や仕入税額控除の厳密な計算をせずとも、一定の簡便計算によって消費税の納付が可能になる制度です。
この制度は、免税事業者から新たに課税事業者になることで発生する事務負担への対応として設定されています。インボイス制度に対応する上で、特に記帳や税額計算に慣れていない個人事業主やフリーランス、小規模法人にとっては大きな負担軽減になります。
2割特例が利用できる対象者の条件
2割特例はすべての事業者が利用できるものではなく、以下の条件を満たす事業者のみが利用可能です。
|
対象条件 |
内容 |
|
1. 免税事業者だった |
過去に免税事業者であったが、インボイス制度開始に伴い、2023年10月1日から課税事業者になる必要があった者 |
|
2. 適格請求書発行事業者に登録 |
インボイス制度への対応として、適格請求書発行事業者の登録を行った事業者であること |
|
3. 小規模事業者 |
前々年または前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下の事業者であること |
これらの要件をすべて満たしたうえで、2023年10月以降、消費税の申告において2割特例の適用を選択することで、この特例を利用できます。
2割特例による納税額の算出方法
2割特例では、通常の消費税申告に必要な課税売上高・課税仕入高・仕入税額控除などの複雑な計算を省略できます。具体的な納税額の算出方法は以下のとおりです。
|
項目 |
内容 |
|
課税売上高 |
事業者がその年に得た課税対象売上(消費税対象となる取引)の合計額 |
|
消費税率 |
標準税率10%および軽減税率8%が適用される取引に基づいて計算 |
|
納付税額 |
課税売上に対する消費税の2割(20%)をそのまま納税額とする |
たとえば、課税売上高が500万円で、該当する売上にかかる消費税率が10%であれば、消費税額はおよそ50万円。その20%である10万円が納税額となります。
なお、あくまで「消費税として預かった税額」の20%を納める制度であるため、課税売上高そのものに対する20%を納めるという誤解をしないよう注意が必要です。
この計算方式は、仕入税額控除などを行う必要がないため、記帳作業や証憑管理の手間が大きく軽減されるメリットがあります。
インボイス制度下で簡易課税は使えるのか?
課税事業者登録と簡易課税の併用可否
インボイス制度においても、簡易課税制度は引き続き利用可能です。ただし、その前提として「課税事業者」であることが必須条件となります。つまり、インボイス(適格請求書)を発行するには「適格請求書発行事業者」として登録を行い、同時に簡易課税制度の適用を希望する場合は、事前に「簡易課税制度選択届出書」を税務署へ提出する必要があります。
簡易課税制度は、本則課税とは異なり、実際の仕入税額控除ではなく、業種ごとに定められた「みなし仕入率」に基づいて控除額を算定する方式です。そのため、仕入控除のやり方は変わりますが、インボイス制度対応のために簡易課税が制限されるということはありません。
ただし、免税事業者から新たに課税事業者へ転換する場合、課税事業者となるタイミングと簡易課税の選択タイミングが重要になります。具体的には、課税期間開始前までに「簡易課税制度選択届出書」を提出しなければ、その課税期間での簡易課税の適用は認められません。
インボイス対応のための簡易課税の注意点
インボイス制度下で簡易課税を選択することにより、仕入税額控除の計算が業種ごとのみなし仕入率により一定化されるため、インボイスの有無にかかわらず一定割合の控除が可能になります。これは、小規模事業者や請求書の収集・管理が困難な事業者にとって大きなメリットとなり得ます。
ただし、以下の点に十分留意する必要があります。
|
注意点 |
内容 |
|
適用条件 |
前々年(個人)または前々事業年度(法人)の課税売上高が5,000万円以下であること。 |
|
事前届出 |
適用を希望する課税期間が始まる前に「簡易課税制度選択届出書」の提出が必要。 |
|
取消制限 |
原則として2年間はやめられない。簡易課税選択以降、2年間継続利用が義務。 |
|
非適用業種 |
不動産業など一部の業種では簡易課税が適用不可。 |
|
みなし仕入率 |
実際の仕入れ税額が高くても、業種別みなし仕入率以上の控除は受けられない。 |
また、簡易課税制度を選択していても、インボイス登録事業者でない事業者からの仕入れに対する消費税の控除は、制度上もともと行わないため、インボイスの発行状況に影響を受けにくいという特徴があります。このことは、本則課税の場合と比べ、仕入先がインボイス登録事業者でないことによる控除不可リスクを低下させると言えます。
一方で、販路によっては対応が相対的に不利になる可能性もあります。たとえば、取引先によってはみなし仕入率による納税額よりも本則課税の方が有利となるケースもあるため、年次決算時のシミュレーションを通じて有利・不利の判断を行うことが重要です。
なお、インボイス制度の中では売手・買手双方において制度の正しい理解と処理が求められるため、簡易課税を利用する事業者であっても、発行すべきインボイスの適正な交付と管理は当然必要です。特に、売上に係る税額計算、帳簿記録、請求書の記載事項については、制度上の義務を十分に認識した上で対応しましょう。
簡易課税制度と2割特例の違い!
課税方式の違いと選択のポイント
簡易課税制度と2割特例は、いずれも消費税の納税義務がある事業者に対して負担を軽減する目的で設けられている制度ですが、課税方式が大きく異なります。
簡易課税制度は、課税売上に対して事業ごとの「みなし仕入率」を用いて仕入控除を簡便に計算する仕組みです。一方、2割特例は、年間売上1,000万円以下の免税事業者からインボイス発行事業者へ移行した小規模事業者を対象に、納付税額を売上高の20%に限定する仕組みです。
適用対象や計算方法が異なるため、自身の事業形態や売上規模に応じて、より有利な制度を選択する必要があります。
課税方式の比較表
|
項目 |
簡易課税制度 |
2割特例 |
|
計算方法 |
課税売上 × (1 - みなし仕入率) × 消費税率 |
課税売上 × 消費税率 × 20% |
|
対象者 |
前々年の課税売上が5,000万円以下 |
2023年10月にインボイス登録した免税事業者など |
|
届出の必要性 |
簡易課税制度選択届出書の提出が必要 |
特別な届出不要(確定申告で対応) |
|
適用期間 |
届出から2年間継続適用 |
令和8年9月30日までの期間限定 |
|
途中変更 |
原則不可(2年間継続) |
各年ごとに選択可 |
メリット・デメリットの比較
制度ごとのメリットとデメリットを把握することで、自社に最適な課税方式を選ぶ参考になります。
<簡易課税制度>のメリット
- 仕入控除額の計算が簡単で、記帳負担が軽減される
- 多数の仕入に関するインボイスを保存しなくてもよい場合がある
- 実際の仕入額が少ない場合は有利になる可能性がある
<2割特例>のメリット
- 売上高の20%のみが納税対象となるため、非常に低い納税額となるケースもある
- 制度の利用に特別な届出が不要で、確定申告の際に簡易に適用できる
- 記帳やインボイス保存の負担が一部軽減される
<簡易課税制度>のデメリット
- 業種ごとのみなし仕入率により、実際の仕入額と乖離が生じることがある
- 一度届出をすると原則2年間継続適用が強制される
- 売上の多寡によっては不利になることがある
<2割特例>のデメリット
- 令和8年9月30日までの期間限定であり、長期的な適用ができない
- 業種や売上構造によっては簡易課税より不利となる場合もある
- 制度の終了後に納税負担が増大するリスクがある
どちらを選ぶべきかの判断基準
簡易課税制度と2割特例のどちらを選ぶかは、事業者の売上規模、コスト構造、業種、会計処理の負担軽減の必要性などを踏まえて判断する必要があります。
例えば、仕入れにかかる費用が少ないサービス業(デザイン業、ライター、コンサルタントなど)では、みなし仕入率を活用する簡易課税制度が有利になる可能性があります。一方、インボイス制度開始により初めて課税事業者となった場合で、消費税の申告や計算に不安がある小規模事業者は、2割特例を選択することで負担を軽減できます。
また、簡易課税制度は申請後2年間の継続適用が求められるため、年度ごとの収支見込みを立てたうえで慎重に判断することが重要です。逆に2割特例は、個人事業者であれば令和5年分から令和8年分までの間で確定申告ごとに選択できるため、柔軟な対応が可能です。
将来的にインボイス制度の運用によってコスト構造や売上に変化が見込まれる場合には、制度の恒久性や調整可能性を見据えた対応が求められます。税理士などの専門家に相談しながら戦略的に選択を行いましょう。
簡易課税はいつまで使える?
簡易課税制度の期限と継続利用について
簡易課税制度は、現時点において制度自体に「廃止」や「期限」が定められているものではなく、将来的な税制改正がない限り恒久的に利用できる制度です。つまり、簡易課税は一定の条件を満たす限り、登録し続けることで継続的に適用することが可能です。
ただし、制度の利用に当たっては、事業者が「簡易課税制度選択届出書」を原則として適用を受けたい課税期間の開始日の前日までに税務署へ提出している必要があります。また、簡易課税をやめたい場合には「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出しなければなりません。
事業規模による適用可否の変化
簡易課税制度は、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者であることが適用条件とされています。この「基準期間」とは、個人事業主であれば前々年、法人の場合は前々事業年度を指します。つまり、直近の課税期間で売上が増加し、5,000万円を超えた場合には、その翌々年の課税期間からは簡易課税を適用することができなくなります。
また、基準期間に売上高が5,000万円以下だったとしても、短期間で設立された法人や新たに事業を開始した個人事業者などには、特定期間(前事業年度の前半6か月間など)との兼ね合いもあるため、売上規模の変化には常に注意が必要です。
売上高や取引形態の変化によって簡易課税の適用要否が変わることがあるため、毎年の税務申告の前に、自社の売上状況を正確に把握することが重要になります。
将来的な制度改正の可能性
現在、簡易課税制度には法的な廃止予定などは公告されておらず、制度そのものは存続しています。しかし、政府や国税庁における税制改正・見直しによって、将来的に要件の変更、適用範囲の見直し、または制度の統合などがなされる可能性はあります。
特に2023年10月から導入されたインボイス制度に関連して、税制全体の見直し議論が加速しており、簡易課税制度のあり方についても、実務の負担軽減や公平性の観点から見直し対象になることがあると考えられています。
そのため、制度利用を継続したい場合には、毎年発表される税制改正大綱や国税庁からの最新情報に注意を払う必要があります。
今後の制度変更に向けて備えるべきこと
万が一、簡易課税制度に改正や制限がかかる場合に備えて、以下のような対策を講じておくと安心です。
- 自社の売上規模と取引内容を年間で定期的に確認する
- 消費税の実額精算による一般課税制度の仕組みを理解しておく
- 税理士や会計担当者とともに、制度変更時に適切な判断ができる体制を整える
以上のように、簡易課税制度は「いつまで使えるか」と問われれば、現行の法律上は無期限で使用可能である一方で、今後の税制改正による影響を念頭に置いた経営判断が求められます。
2割特例はいつまで使える?
特例の適用期間と終了時期
2割特例(2割納税特例)は、2023年(令和5年)10月に開始されたインボイス制度の導入に伴って、一定の要件を満たした免税事業者が課税事業者として登録した場合の負担軽減措置として講じられた時限的な特例制度です。この特例は、売上税額に対して2割の金額を納付すればよいという簡易的な方法により、複雑な経理処理や領収書保存の負担を軽減する目的で導入されました。
この2割特例の適用期間は、法令で次の通り明確に定められています。
|
要素 |
内容 |
|
制度開始時期 |
令和5年(2023年)10月1日 |
|
制度終了時期 |
令和8年(2026年)9月30日 |
|
対象期間 |
令和5年度課税期間から、令和8年9月30日までの間に属する各課税期間 |
したがって、2割特例が適用される最後の課税期間は2026年(令和8年)9月30日を含む期間までとなります。ただし、事業者によって課税期間(個人事業主なら暦年、法人であれば事業年度)が異なるため、正確な最終適用年度は当該事業者の課税期間の終了日によって変動します。
令和8年9月30日までの適用期限
2割特例の適用期限は、「適格請求書等保存方式に関する経過措置」として「令和8年9月30日」までと明確に示されています。たとえば、個人事業者で1月~12月の暦年課税期間に該当する事業者であれば、最終的に特例が適用されるのは「令和6年(2024年)」「令和7年(2025年)」「令和8年(2026年)」の各年度となります。法人の場合は、事業年度が「令和8年9月30日」までに終了する場合に限り、対象になります。
以下に、課税事業者の種別ごとの2割特例適用例を示します。
|
課税事業者の形態 |
課税期間 |
2割特例の適用期間 |
|
個人事業主 |
毎年1月1日~12月31日 |
2023年、2024年、2025年 |
|
法人(3月決算) |
毎年4月1日~翌年3月31日 |
2023年4月1日~2026年3月31日までの3年間 |
|
法人(10月決算) |
毎年11月1日~翌年10月31日 |
2023年11月1日~2026年10月31日のうち、2026年9月30日を含む事業年度(2025年11月~2026年10月)は全期間対象外 |
このように、2割特例の「令和8年9月30日まで」という期限は厳格に定められており、事業者が自らの課税期間と照らし合わせることで、いつまで適用されるかを確認する必要があります。
適用終了後の対応方法
2割特例の適用期間が終了した後は、適格請求書発行事業者として通常の仕入税額控除の方法に基づく納税義務が発生します。つまり、帳簿およびインボイス(適格請求書)の保存を要件とした仕入控除計算を行う必要があるということです。
以下は、2割特例終了後に必要となる主な対応事項です。
- 取引先からのインボイス(適格請求書・簡易インボイス)の保存
- 記帳に基づいた売上税額および仕入税額の計算
- 消費税および地方消費税の確定申告
また、簡易課税制度の選択を行うことで、通常方式よりも簡素な方法で消費税申告・納付が可能になる場合があります。売上規模や業種に応じて、簡易課税制度への変更や適用届出書の提出も検討するとよいでしょう。
いずれにしても、特例終了後を見据えた経理体制の整備が不可欠です。特に免税事業者から課税事業者となった中小・フリーランス事業者は、インボイスの保存と帳簿管理の体制を早期に構築することが求められます。
加えて、2割特例の終了が近づくにつれて、税理士や会計ソフト会社によるサポートも増えてくると見込まれるため、余裕をもって準備を進めることが重要です。
簡易課税と2割特例の申請・手続き方法を解説!
簡易課税制度の届出方法
簡易課税制度を利用するには、課税期間の開始前に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。この届出は、最寄りの税務署に対して提出し、当該課税期間の開始日の前日までに届け出ることが条件です。届出書は国税庁のウェブサイトからダウンロードが可能で、郵送またはe-Tax(電子申告)にて提出できます。
なお、一度簡易課税制度を選択すると、原則として2年間は変更できないため、継続的に売上や仕入などの書類保存が必要であることを考慮して、制度の選択を行うことが求められます。
簡易課税制度の届出に関する主な注意点
|
項目 |
内容 |
|
提出書類 |
消費税簡易課税制度選択届出書 |
|
提出期限 |
適用を受けたい課税期間開始日の前日まで |
|
提出先 |
所轄税務署(e-Taxを含む) |
|
留意点 |
2年間は原則として取りやめ不可 |
2割特例の適用手続きの流れ
2割特例は、インボイス制度導入に伴い新たに課税事業者となった免税事業者に対し、事務負担の軽減措置として設けられた特例制度です。2023年10月から適用が開始され、2026年9月30日までの期間限定で適用されます。
2割特例を利用するには、原則として税務署への届出は不要です。ただし、「適格請求書発行事業者」の登録を済ませておくことと、課税売上高が1,000万円以下であるといった条件を満たす必要があります。
確定申告の際には、課税売上に対して2割を乗じた額を消費税として納付すればよいため、帳簿保存などの義務はあるものの、仕入税額控除の計算が不要で、非常に簡便です。
2割特例の申告・手続きを簡単にまとめた表
|
項目 |
内容 |
|
対象者 |
2023年10月1日〜2026年9月30日に課税事業者となった個人・法人で、売上1,000万円以下の方 |
|
適用期間 |
令和5年10月1日〜令和8年9月30日 |
|
事前届出 |
原則不要(ただし登録済みであることが条件) |
|
納税計算 |
課税売上高 × 2割 |
|
申告時対応 |
簡易課税や一般課税と組み合わせ不可。確定申告で2割特例選択 |
申請タイミングと注意点
簡易課税制度と2割特例それぞれで申請や手続きのタイミングが異なるため、十分に注意する必要があります。
簡易課税の申請タイミング
簡易課税制度の選択は、次の課税期間の前日までに「簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があるため、例えば、令和7年1月1日開始の課税期間に適用したい場合、令和6年12月31日までに提出しなければなりません。遅れるとその課税期間には適用されません。また、特定期間判定によって納税義務が発生した場合には、即座に影響を与える場合もあるため、売上見込みに応じた早めの対応が重要です。
2割特例の選択タイミング
2割特例については、届出を要しないため比較的簡便に適用できますが、「適格請求書発行事業者」の登録を済ませることが前提となります。登録の有効開始日は申請後2か月から3か月後が基本であるため、特例の利用を見込む個人事業主は、年内や年度中の課税売上見込みを早急に確認し、遅くとも2026年(令和8年)半ばまでには登録を済ませておくと良いでしょう。
また、2割特例を選んだ場合、簡易課税制度との併用はできないため、どちらが有利であるかをシミュレーションした上で申告の準備を進めることが推奨されます。
まとめ
インボイス制度における簡易課税制度は引き続き利用可能ですが、2割特例は令和8年9月30日までの時限措置です。簡易課税と2割特例は併用できないため、自社の売上規模や業種に応じて有利な制度を選択することが重要です。制度の内容を正しく理解し、計画的に対応しましょう。