インボイス後は簡易課税制度は廃止?いつまで利用できる?2割特例との選び方を解説
更新日:2026.01.29
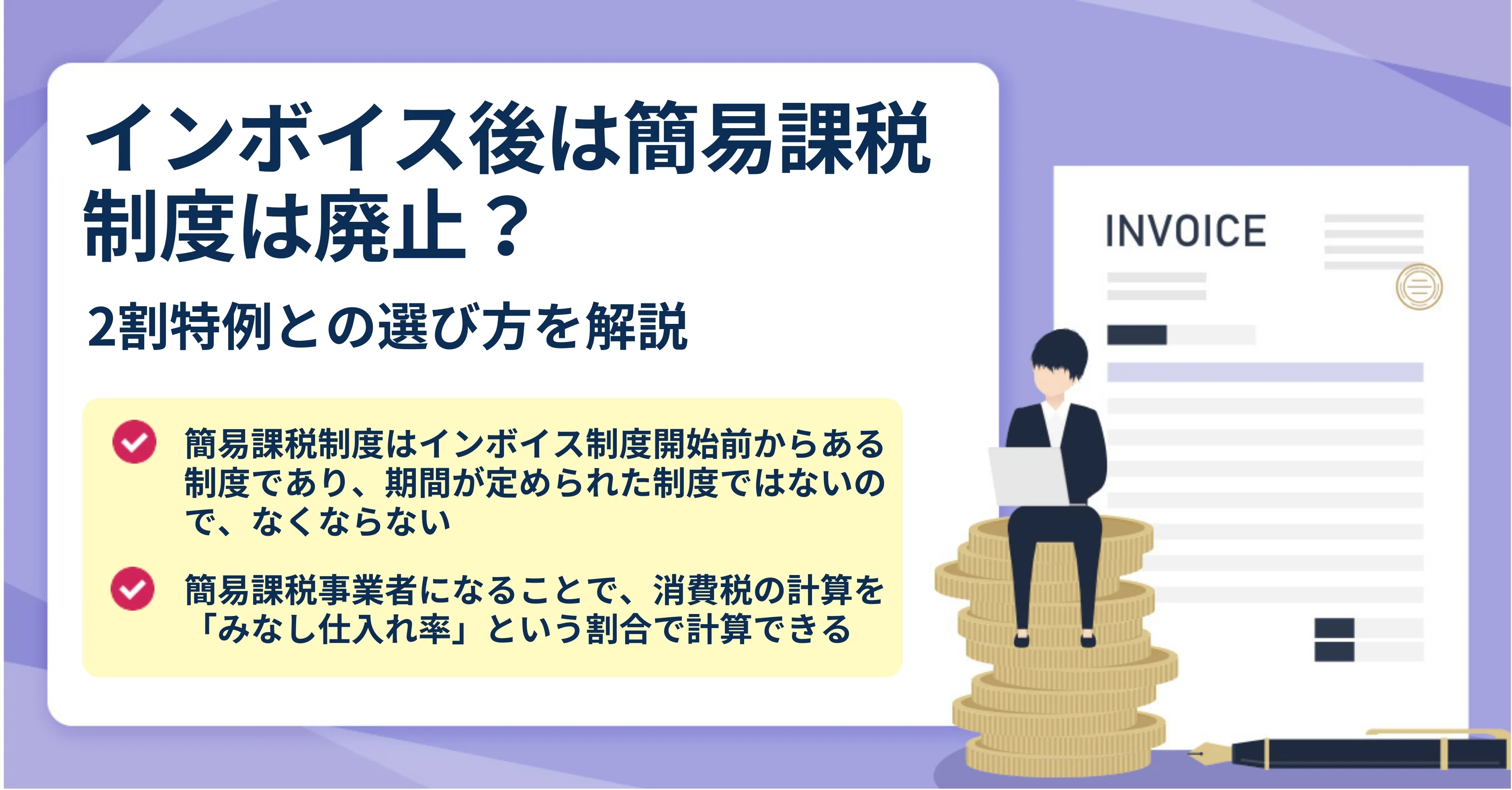
ー 目次 ー
インボイス制度の施行により、従来の「簡易課税制度」以外に新たなルールである「2割特例」が導入されました。簡易課税制度については引き続き適用されるため、2割特例との兼ね合いで疑問を抱く事業者も少なくありません。
これらのルールはインボイス制度に登録するうえで、知っておきたいものといえます。これからインボイス制度の登録を検討していれば、簡易課税制度や2割特例のことも知っておきましょう。
本記事では、インボイス制度施行後の簡易課税制度の扱いや2割特例との違いを解説します。違いを理解したうえで、自社に適した制度を選び、節税につなげましょう。
【結論】インボイス施行後も簡易課税制度は廃止されない
結論として、インボイス制度施行後も簡易課税制度は廃止されません。
インボイス施行と同時に2割特例が開始されたため、似た制度の簡易課税制度が廃止される可能性が危惧されたと考えられます。
しかし、簡易課税制度はインボイス制度開始前から存在する制度であり、期間が定められた制度ではありません。国税庁の簡易課税制度のページを確認しても、2025年1月現在では廃止の予定は記載されていません。
簡易課税制度は経理・事務作業の負担を少なくするための制度
簡易課税制度とは、経理・事務業務の負担を少なくするために、納税する消費税を事業区分ごとに設定された「みなし仕入率」を基準に計算する方法です。
このみなし仕入率とは、「この事業は売上の〇〇%が仕入れに使用されているだろう」と仮定して定められた控除される消費税の割合です。簡易課税制度では、「受け取った消費税額×業種ごとのみなし仕入率」の計算式にもとづき、納付する消費税額を計算します。
一方で、簡易課税制度を利用しない一般課税では、消費税を納付するときに軽減税率の商品もひとつずつ計算する必要があります。一般課税は「受け取った消費税の額−仕入時に支払った消費税の額」を計算するため、取引の数が多い業者の場合は手間がかかります。
インボイス制度以降も簡易課税制度を利用するメリット
インボイス制度施行後も、簡易課税制度には節税できる可能性や経理業務が軽減できるなどのメリットがあります。メリットを理解しておくことで、制度を利用するか判断しやすくなります。
ここでは、インボイス制度以降も簡易課税制度を利用するメリットを解説します。
①節税できる場合がある
インボイス制度施行後も簡易課税制度を利用する場合は、納付する消費税を計算するときに事業ごとのみなし仕入率が適用されます。簡易課税制度を活用することで、実際に支払う消費税が仕入率よりも少ない事業であれば、節税が可能です。
たとえば、コンサル業・保険業などの仕入れが少なく、人件費が多い事業は簡易課税制度を利用することで納税額が少なくなる可能性があります。
②経理業務の軽減が可能
一般課税では、消費税を計算する際に商品ごとの軽減税率を考慮する必要があり、一つひとつの計算が煩雑になる可能性があります。
一方で、簡易課税制度を利用すれば、消費税の計算にみなし仕入率が適用されます。納付する消費税は、総売上税額にみなし仕入率をかけることで計算が可能です。とくに、課税期間の取引が多い企業では消費税の計算を一括化できるため、経理業務の手間を減らせるでしょう。
インボイス以降も簡易課税制度を利用する際の注意点
簡易課税制度にはメリットだけでなく、利用期間や節税が確定されない注意もあります。理解しないまま申請すれば、還付を受けられない可能性や、納付する税金が増えて損をする可能性があるため注意しましょう。
ここからは、インボイス以降も簡易課税制度を利用する際の注意点を解説します。
①2年間は一般課税に戻せない
簡易課税制度を申請した場合は、原則として2年間は一般課税に戻せません。このことから、2年間に事業内容が大きく変わる予定がある場合、簡易課税制度を利用するか慎重に検討する必要があります。
2年経って簡易課税制度を中止する際は、消費税簡易課税制度選択不適用届出書を提出することで、一般課税に戻すことが可能です。
ただし、課税売上高が5,000万円を超えた場合、その期間は一般課税で納税する必要があります。
②必ず節税できるわけではない
簡易課税制度を利用しても、課税売上によっては必ず節税できるとは限りません。期間内の事業が赤字である場合は、一般課税で納税するほうが納付額が少ない可能性が考えられます。
事業が赤字の場合は、税金の一部が還付される可能性があります。しかし、簡易課税制度を利用する際は消費税がみなし仕入率で計算されるため、還付されません。売上が赤字になる可能性が考えられるときは、簡易課税制度ではなく一般課税を選択しておくことで不要な税金を支払う必要がなくなります。
ほかにも、大きな出費を予定している場合は、一般課税で正しい消費税を納付したほうが節税できる可能性があります。
インボイス施行後は簡易課税制度以外に2割特例も選択可能
インボイス制度の施行のタイミングで課税事業者になった場合は、消費税の計算方法に簡易課税制度だけでなく2割特例を選択できます。
2割特例は、インボイス制度のタイミングで免税事業者から課税事業者になった事業者の税負担を「売上税額×20%」に軽減できる措置です。
ただし、2割特例は適用期間が決まっており、個人事業主であれば2023年10月〜2026年分の申告をするまでの4回分が対象になっています。法人の対象期間は2023年10月〜2024年3月までの申告から2026年分の申告までの4回分です。
2割特例と簡易課税制度では、多くの事業者が2割特例のほうが納税額が少なくなります。しかし、卸業者はみなし仕入率が90%のため、簡易課税制度を利用したほうが節税できる可能性があります。
インボイスで簡易課税制度ではなく2割特例を選ぶときの注意点
インボイス施行後に簡易課税制度ではなく2割特例を選ぶときは、事前に注意点を理解しておきましょう。注意点を理解しておくことで、事業が赤字のときや必要な届け出の出し忘れによって後悔する可能性を減らせます。
ここからは、インボイス施行後に簡易課税制度ではなく2割特例を選ぶときの注意点を解説します。
- 適用には条件がある
- 還付はされない
- 簡易課税制度を利用するには別途で届け出が必要
①適用には条件がある
2割特例には、適用に3つの条件があります。
- 基準期間の課税売上高が1,000万円以内の事業者
- インボイス制度が始まるタイミングで課税事業者になった事業者
- 課税期間を短縮する届け出を出していない事業者
2割特例が利用できない場合は、一般課税か簡易課税制度のどちらかで消費税を納付する必要があります。
②還付はされない
2割特例を利用する場合は簡易課税制度と同じく、事業が赤字でも税金の還付がされません。そのため、受け取った消費税よりも支払った消費税が高いときは損をする可能性があります。
このことから、みなし仕入率の高い卸売業や、多くの経費を使用する予定の事業者の利用はおすすめできません。
ただし、2割特例は消費税の確定申告時に利用するかを選択できるため、課税期間後に判断が可能です。
③簡易課税制度を利用するには別途で届け出が必要
2割特例と簡易課税制度は別の制度のため、簡易課税制度の利用を考えている場合は課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要です。
課税期間の初日の前日までに書類の提出が間に合わなければ、簡易課税制度が適用されるのは翌年の課税期間になります。
なお、簡易課税制度・2割特例のどちらも利用しないときは、一般課税で消費税を納めなければなりません。
まとめ|インボイスで簡易課税制度は廃止されない!注意点を理解して利用するか検討しよう
本記事では、インボイス制度施行後の簡易課税制度の扱いや2割特例との違いを解説しました。
インボイス制度の施行により、簡易課税制度が廃止されることはありません。ただし、インボイス施行後は2割特例が利用できる可能性もあるため、自社がどちらを利用するか考えることが大切です。
2割特例は期間や対象が定められているため、本記事を参考に簡易課税制度とどちらを利用するか検討しましょう。










