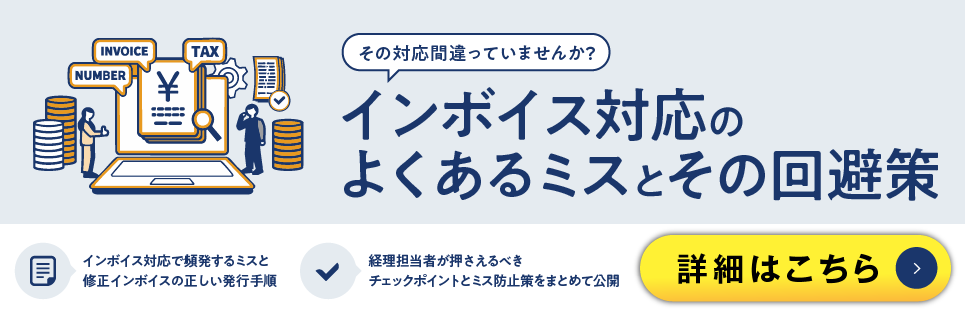副業をしている会社員には影響あり!インボイス制度の会社員への影響を徹底解説
更新日:2026.01.15
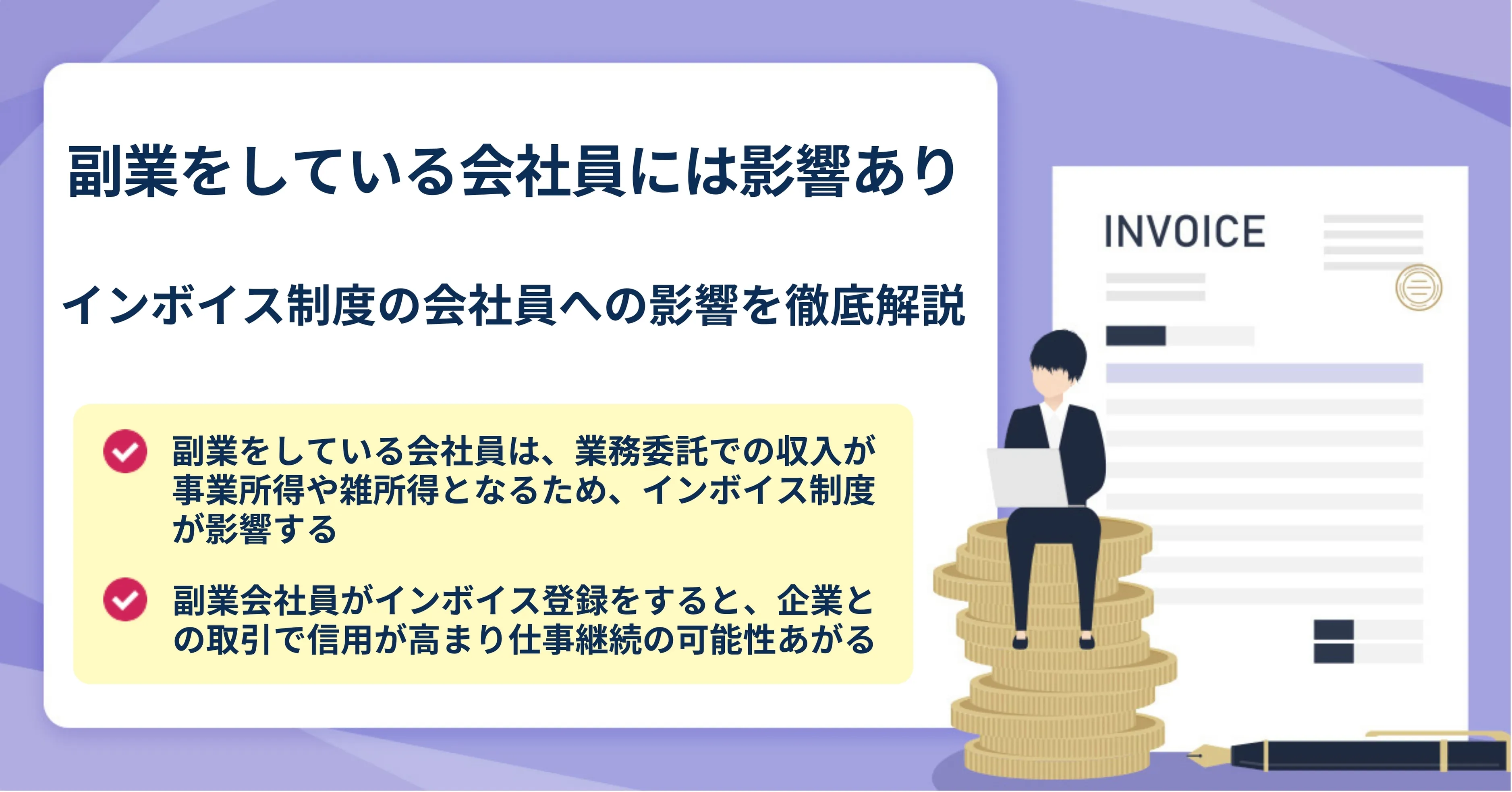
ー 目次 ー
2023年10月に開始された「インボイス制度」は、会社員には無関係と思われがちですが、副業でフリーランスや個人事業を行っている場合、大きな影響が及びます。特に「適格請求書発行事業者」への登録有無が、クライアントからの継続発注や収入、消費税の扱いに直結します。この記事では、副業をしている会社員が知っておくべきインボイス制度の概要から影響の具体例、登録の判断基準まで徹底的に解説します。
インボイス制度とは?
インボイス制度の概要
インボイス制度とは、正式には「適格請求書等保存方式」と呼ばれ、2023年10月1日より日本で導入された消費税の仕入税額控除の方式です。この制度により、事業者が消費税を支払った際に、その税額を控除するためには「適格請求書(インボイス)」の保存が必要となりました。
「適格請求書」とは、所定の情報を記載した請求書や領収書のことで、発行者が税務署に登録した「適格請求書発行事業者」である必要があります。つまり、取引の際に相手方が仕入税額控除を受けるためには、発行者がこの制度に登録していなければいけません。
インボイス制度の主な目的
この制度の導入により、消費税の納税の透明性が高まり、免税事業者との取引における不公平感を是正することが期待されています。また、買い手が仕入税額控除を行う際の要件が厳格になることで、消費税の適正な納付を促進することも目的としています。
インボイス制度の導入背景
インボイス制度の導入背景には、現行の区分記載請求書等保存方式の限界がありました。これまで、仕入税額控除を受ける際は、請求書に記載された税率や税額などが明示的でなくても認められていたため、免税事業者との取引においても控除可能なケースが存在していました。
結果として、課税事業者が納付すべき消費税の一部が間接的に免税事業者の利益となっている形となり、制度上の不公平が生じていました。この問題を是正し、課税公平性を担保する手段としてインボイス制度が導入されたのです。
海外との制度比較
インボイス制度は欧州連合(EU)諸国をはじめとする多くの諸外国ですでに導入されている制度に類似しており、日本でも国際的な取引の透明性や整合性を保つために導入されたという背景もあります。
適格請求書発行事業者とは
「適格請求書発行事業者」は、消費税法に基づいて所轄税務署に申請し、登録された事業者のことを指します。登録された事業者は、取引の際に「適格請求書」を発行することができ、その請求書は仕入税額控除の対象となります。
この登録は任意ですが、登録しなければインボイスを発行することができず、取引先が仕入税額控除を受けることができなくなります。特にBtoB取引では、事業者として登録をしていないことが原因で取引先との契約が終了する可能性もあります。
|
項目 |
登録の有無による違い |
|
登録状況 |
税務署に申請して登録されている事業者のみ登録済み |
|
インボイスの発行 |
登録事業者のみ発行可能 |
|
取引先の控除可否 |
インボイスがあれば仕入税額控除が可能 |
|
契約への影響 |
未登録の場合、取引先から契約を控えられる可能性あり |
登録を受けるためには事業者が課税事業者であることが前提であり、免税事業者だった場合は、課税事業者に変更する手続きを経た上で登録申請を行う必要があります。
登録自体は無料でオンラインおよび書面での申請が可能です。なお、登録番号や事業者情報は国税庁が公開している「適格請求書発行事業者公表サイト」で確認することができます。このサイトを通じて、取引先の事業者がインボイス発行可能かどうかを確認することができます。
インボイス制度は会社員に関係ある?
副業をしている会社員には関係あり!
昨今の副業解禁の動きにより、多くの会社員がライター、デザイナー、動画編集者、コンサルタントなどの業種で副業を行うようになっています。こうした副業の多くは、業務委託契約や請負契約に基づいて報酬が支払われるため、給与所得ではなく「事業所得」または「雑所得」として扱われます。
このような副業収入がある場合、会社員であっても個人事業主として消費税の課税事業者となる可能性があります。そして、2023年10月から始まったインボイス制度によって、消費税の仕入税額控除の要件が厳格化されたため、副業の発注者である企業側が「適格請求書発行事業者(インボイス登録済み)」のみに仕事を発注するようになるケースが増えています。
つまり、副業で取引先からの信頼を維持し、継続的に仕事を受注するためには、インボイス登録の有無が重要な判断材料になるのです。
会社員の本業にはインボイスは影響しない
通常、会社員として企業に雇用されている場合、給与所得者であり、消費税の課税対象ではありません。企業が従業員に支払う給与や賞与は消費税の課税対象外であり、インボイス制度とは直接関係しません。そのため、正社員・派遣社員・契約社員など形態を問わず、勤務先から受け取る給与に関して、インボイス制度の導入による影響はありません。
また、給与支払いにはインボイス(適格請求書)の交付義務や保存義務も発生しないため、会社員が労働の対価として受け取る収入について、インボイス制度上の手続きは一切不要です。
課税・免税の違いと影響範囲
消費税法では、基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下であれば、原則として「免税事業者」となり、消費税の申告・納税義務が免除されます。副業で年間売上が少ない会社員も多くの場合、これに該当します。しかし、インボイス制度の導入により、免税事業者のままだとインボイス(適格請求書)の発行ができず、取引先の仕入税額控除が認められなくなります。
結果として、以下のような影響が出る可能性があります。
|
区分 |
インボイス登録なし(免税事業者) |
インボイス登録あり(課税事業者) |
|
取引先の対応 |
仕入税額控除できず取引敬遠の可能性 |
問題なく仕入税額控除可能 |
|
仕事の継続性 |
発注打ち切りリスクあり |
継続的な取引が見込める |
|
消費税の納税 |
免除(ただし報酬に消費税を上乗せできないことも) |
納税義務あり(税務申告と納税が必要) |
|
事務的負担 |
少ない |
帳簿管理・インボイス発行・確定申告が必要 |
このように、インボイス制度における「課税事業者」と「免税事業者」では取引上の信頼性や経済的影響が大きく変わります。副業での収入がある会社員であっても、インボイス登録の必要性を正しく判断しないと、売上機会減少や取引打ち切りといったリスクに直面する場合があります。
なお、登録を選択した場合は「消費税課税事業者選択届出書」の提出が必要であり、一度選択すると原則2年間はその課税事業者としての義務が継続します。安易にインボイス登録するのではなく、自身の副業の内容や取引先の意向を踏まえ、慎重な判断が求められます。
インボイス制度による収入や税務への影響とは?
消費税の納税義務の発生について
インボイス制度の大きなポイントの一つが、免税事業者であっても実質的に消費税の納税が求められるケースが発生する可能性がある点です。これまで年間売上が1,000万円以下の副業を行う会社員は、消費税の納税義務が免除される「免税事業者」であることが多く、実際に消費税を納める必要がありませんでした。
しかし、インボイス制度が導入された2023年10月以降は、取引先が課税事業者(法人や大規模個人事業主)である場合、課税仕入控除を行うためには「適格請求書発行事業者」であることが求められます。これにより、免税事業者と取引するクライアントにとっては、消費税を控除できない不利益が生じるため、実質的に適格請求書発行事業者への登録を求められることが増えてきています。
結果として、副業で売上規模が小さくても、案件を継続するために自発的に課税事業者として登録し、消費税の納税義務を受け入れる必要が生じてきているのが現状です。
クライアントからの発注に与える影響
フリーランスのライター、デザイナー、エンジニアなどとして副業する会社員にとって、インボイス制度は顧客基盤に直接的な影響を与えることになります。とくに取引先が企業や課税事業者である場合、インボイスを発行できない非登録者との取り引きを避ける傾向が強まっています。
企業側は経費として計上する際に課税仕入控除が適用されるかどうかを重要視するため、非登録の副業会社員と契約継続を迷うケースも増えています。これは、「登録していない=取引コストが増す」という理由からです。
下記の表は、インボイスの登録有無によるクライアント側のメリット・デメリットの比較です。
|
登録状況 |
クライアント側の仕入控除 |
契約継続性 |
取引時の印象 |
|
適格請求書発行事業者(登録済) |
可能 |
高い |
信頼されやすい |
|
免税事業者(未登録) |
不可 |
低下の可能性あり |
消極的に見られる場合あり |
このように、取引先の視点に立ったとき、登録の有無が新規案件の獲得や既存契約の維持に大きく影響するため、収益の安定を考える副業会社員はインボイス対応を避けられない現実に直面しています。
収入減少のリスクとその回避方法
インボイス制度によって最も懸念されるのが、免税事業者が登録を行わないことで受ける収入減少リスクです。主に発注先からの契約打ち切り、価格交渉の不利、案件機会の減少といった形で影響が出ることがあります。
例えば、同業の登録事業者と比較され、クライアントから「取引コストが高くなる」という理由で選ばれにくくなるリスクもあります。副業収入を安定的に維持するためには、以下のような対策が重要です。
|
対策内容 |
具体例 |
|
価格提案の見直し |
消費税の分だけ単価を抑える工夫や、付加価値によって価格維持を図る |
|
業務効率化による利益確保 |
会計ソフトや請求書作成ツール(例:freee、マネーフォワード)を活用する |
|
クライアントの質を見直す |
適格請求書の必要性が低い個人相手の仕事を増やす |
|
登録後も損益分岐点を意識 |
売上と納税額のバランスを定期的に点検する |
さらに、青色申告の導入、副業用の専用口座・会計帳簿の整備、経費処理の見直しなど、収入の最適化と税負担軽減のための工夫も収入減少に対抗するうえでは欠かせません。
副業が小規模であればインボイス登録の是非は慎重に検討すべきですが、登録によって新たな契約機会が生まれる可能性もあるため、単純に「税負担が増える」とネガティブに捉えすぎることなく、データと実情に基づく判断が重要です。
副業会社員のインボイス登録のメリットとデメリット
登録による信用アップの可能性
副業としてフリーランスや個人事業主として活動している会社員にとって、「適格請求書発行事業者」としてインボイス制度に登録することには一定のメリットがあります。
インボイス制度に登録していることは、消費税の納税義務者であり、税務処理を適切に行っている証拠となるため、特に法人や企業との取引では「信用がある副業者」として評価されやすくなる傾向があります。
特に取引先が課税事業者である法人の場合、仕入税額控除を行うためにはインボイス(適格請求書)の受領が必須となるため、インボイス登録をしていない副業者に対する発注を見送る企業も出てきており、登録することで仕事の継続や拡大につながる可能性もあります。
納税義務と事務負担の増加
一方で、インボイス登録を行うと、これまで「免税事業者」として消費税の納税が免除されていた副業会社員であっても、登録後は「課税事業者」となり、消費税の納税義務が発生します。年間売上が1,000万円を超えなくても、登録により強制的に課税事業者になる点は大きな負担です。
実際に消費税の納税義務が発生することで、以下のような事務的負担が増加します。
- 消費税の申告書作成と提出(基本的に年1回、必要に応じて中間申告もあり)
- 月ごとの売上と支出に対する帳簿管理の厳格化
- 会計ソフトや税理士への委託費用が発生する可能性
これらの要因から、副業の収入が少ない会社員にとっては、インボイス登録によって得られる信用に対して事務・金銭的負担が大きくなるケースもあり、慎重な判断が求められます。
登録しない場合に直面する問題
インボイス制度への未登録、つまり免税事業者のままでいることにもリスクがあります。特に以下のような影響が考えられます。
|
未登録のままの場合の影響 |
具体的なリスク |
|
取引先が法人の場合 |
仕入税額控除ができないため、取引を敬遠される可能性が高い |
|
報酬の減額 |
相手先が消費税分を報酬から差し引いて支払ってくる場合がある |
|
契約の打ち切り |
インボイス対応を理由に取引先が今後の契約を見送る可能性もある |
特に、業務委託契約を結んでいる副業会社員の場合、クライアントが課税事業者であり、中小企業や法人である場合、「インボイスを発行できない業者」として除外される懸念が強まっています。
一方で、副業の取引先が個人(非課税事業者)やインボイスを必要としない事業者である場合は、無理に登録する必要がないケースもあります。その場合、課税事業者になることでかえって納税義務や帳簿管理などの負担が不利に働く可能性もあるため、登録の必要性は慎重に判断すべきです。
実際に登録が必要か判断するためのチェックポイント!
インボイスの登録が必要なケース
インボイス制度における「登録」とは、正式には「適格請求書発行事業者」として国税庁に登録することを意味します。この登録が必要になるのは、以下のようなケースです。
|
状況 |
登録が必要な理由 |
|
取引先が法人、または課税事業者 |
インボイス(適格請求書)がないと仕入税額控除ができないため、登録事業者との取引を希望されるケースが多い。 |
|
副業の売上高が高額 |
自分が消費税課税事業者となる可能性があり、その際インボイス発行事業者登録が前提となる。 |
|
定期的に請負・業務委託を受けている |
継続取引の場合、取引先がインボイス対応を求める可能性が高い。 |
とくにフリーランスとして請負契約をしている場合は、登録を強く求められる傾向にあります。
自分の副業の取引先の性質
インボイス制度で最も重要なのは、「誰と取引をしているか」です。副業収入のうち、以下のような取引先が多い場合には、登録の必要性が高まります。
- 広告代理店や制作会社などの法人企業
- 課税事業者の個人事業主
- インボイス未対応の事業者を排除しようとしている企業
逆に、以下のような取引先であれば、急いで登録する必要はないこともあります。
- 一般消費者を相手にしている副業(例:物販、ネットショップ)
- 同人活動など、非課税者の個人
要するに、仕入税額控除を行う事業者が取引相手かどうかが、判断の最重要ポイントとなります。
売上・経費・利益構造の確認
インボイスの登録を判断するうえで、自分の副業の収支構造を明確に把握しておくことが重要です。以下の3要素を確認しましょう。
|
項目 |
目安・観点 |
ポイント |
|
売上 |
年間1,000万円以下かどうか |
1,000万円未満は原則「免税事業者」だが、インボイス発行には登録必須 |
|
経費 |
どれほどの仕入・必要経費があるか |
仕入税額控除を利用する意味があるかを判断 |
|
利益 |
手元に残る利益額の想定 |
登録によって納税額が増えすぎないか確認 |
特に注意すべきは、「売上が1,000万円未満でもクライアント対応のために登録を迫られる場合」です。この場合、消費税の納税義務が新たに発生し、結果として利益が圧縮される可能性があります。
登録していないと契約打ち切りとなる可能性
副業先との契約において、今後の継続を左右する要素となるのが「インボイス登録の有無」です。以下のようなリスクが存在します。
- インボイス非対応であることを理由に新規の案件獲得が難しくなる
- 既存の契約や定期案件が終了する恐れがある
- 報酬を税込から税抜に変更され、実収入が減少する
たとえば、大手メディアや人材系企業などでは、すでにインボイス登録が必須条件になっているケースも多く、登録していないことで取引対象から外されてしまう危険もあります。
副業を持続的に行っていくためには、こうしたリスクを事前に把握し、自身のスタンスを明確に決めておくことが欠かせません。
副業をしている会社員がインボイス制度で注意すべきポイント!
副業の形態別影響(フリーランス・個人事業主など)
副業で収入を得ている会社員の場合、その副業の形態によってインボイス制度の影響度が大きく異なります。たとえば、「フリーランス」や「個人事業主」として活動している場合、取引先が法人や課税事業者であることが多く、インボイス(適格請求書)の発行が求められる可能性が高くなります。
一方で、メルカリのような個人間取引や、会社から給与として受け取るアルバイト・業務委託契約など、消費税が関係しない取引ならば、インボイス制度の影響は限定的です。
以下に副業形態ごとの影響度を整理します。
|
副業形態 |
インボイス制度の影響度 |
適格請求書発行の必要性 |
|
ライター・デザイナー(業務委託) |
高 |
必要な場合が多い |
|
物販(ハンドメイド・せどりなど) |
中 |
取引先による |
|
YouTube・アフィリエイト収入 |
低 |
基本的に不要 |
|
個人間取引(フリマアプリ等) |
低 |
不要 |
このように、副業のスタイルによって必要とされる対応は異なります。自身の副業形態を把握し、取引先の性質を見極めることが重要です。
年間売上1,000万円未満の場合の対応
会社員の多くは副業の年間売上が1,000万円未満であることが多く、この場合、消費税の免税事業者に該当します。免税事業者は原則としてインボイス(適格請求書)を発行できません。
しかし、インボイス制度施行後は、「適格請求書発行事業者」でなければ、取引先が仕入税額控除を受けられず、一部の法人クライアントからは契約継続の条件として、インボイス登録を求められる場合も増えています。
売上が少なくても、業務委託契約などではクライアント側が消費税を控除できるかどうかを重視するため、インボイス登録が求められることがあります。よって、「売上が少ない=関係ない」と考えるのではなく、取引相手のニーズに応じた対応が重要です。
なお、免税事業者が任意でインボイス発行事業者に登録することも可能ですが、その場合は消費税の納税義務が発生し、帳簿管理や確定申告の手間が増します。
免税事業者の継続と登録の比較
|
ステータス |
消費税の納税義務 |
クライアントへの影響 |
帳簿管理の手間 |
|
免税事業者(非登録) |
なし |
取引打ち切りの可能性 |
比較的軽い |
|
適格請求書発行事業者(登録) |
あり |
信頼性が高まる傾向 |
帳簿・請求書管理が必要 |
自分の副業の内容や将来の拡大予定を踏まえて、登録の有無を判断しましょう。特に継続的に業務委託を受けている場合には、登録しないことで新規契約を逃すリスクも出てきます。
まとめ
インボイス制度は会社員の本業には影響しませんが、副業でフリーランスや個人事業主として収入を得ている場合は関係してきます。特に取引先が企業の場合、適格請求書の発行が求められることが多く、登録しないと契約打ち切りや報酬減額のリスクも。副業の規模や内容に応じて、制度の影響や対策を正しく把握し、適切に対応することが重要です。