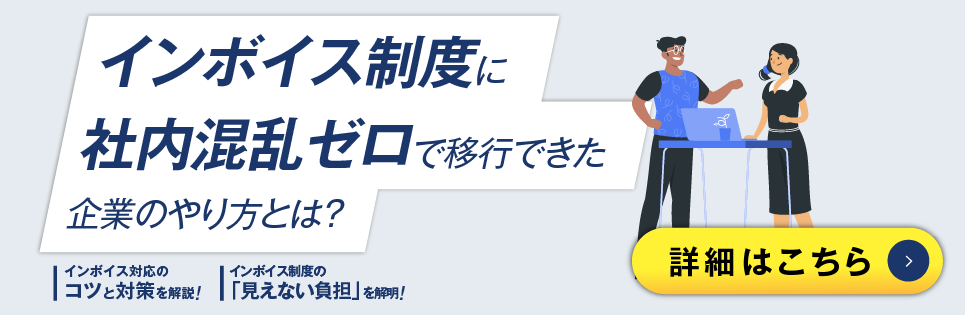インボイス登録はいつまで?申請の流れや期限をわかりやすく解説
更新日:2025.12.06
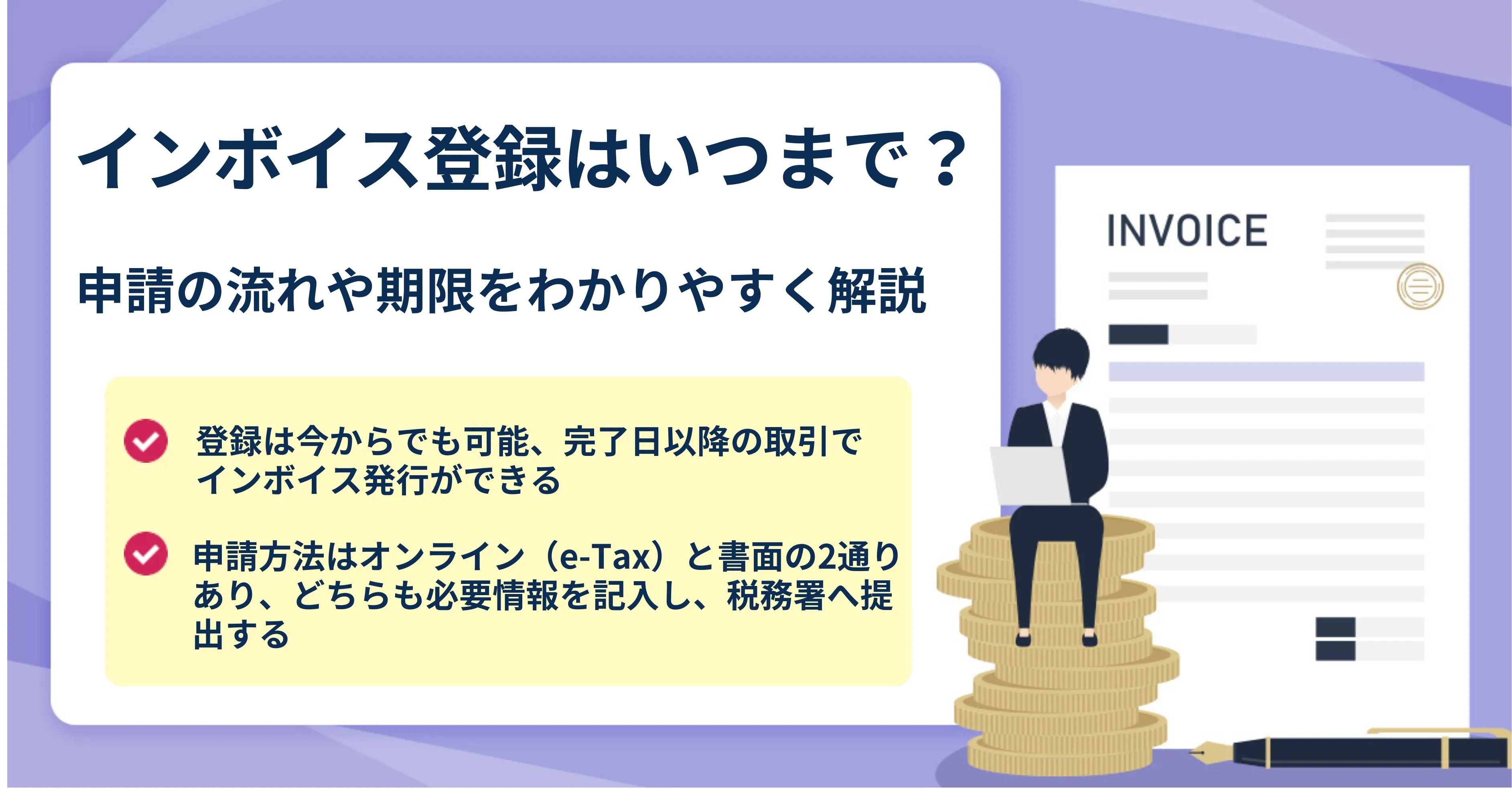
ー 目次 ー
2023年10月に開始されたインボイス制度に関する登録期限や申請方法について、この記事を読めばいつまでに何をすべきかが明確に分かります。課税事業者・免税事業者それぞれの対応や登録の流れ、間に合わなかった場合の対応策までを網羅的に解説。登録のタイミングによって消費税の仕入税額控除にどのような影響があるのかもわかります。
インボイス制度とは?
インボイス制度の基本的な仕組み
インボイス制度とは、正式には「適格請求書等保存方式」と呼ばれる、2023年10月1日から日本で導入された消費税の仕入税額控除に関する新しい制度です。インボイス制度では、仕入先等から交付される「適格請求書」(インボイス)を保存しておくことが、消費税の仕入税額控除を受けるための要件となります。
適格請求書(インボイス)とは、税率ごとに区分された消費税額など、一定の記載要件を満たした請求書や領収書のことです。この制度により、取引の透明化・適正化が強化され、不正防止や税収確保にもつながることが期待されています。
適格請求書に必要な記載事項
|
項目 |
内容 |
|
① 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号 |
国税庁に登録された事業者の情報が必要です。 |
|
② 取引年月日 |
仕入れやサービスの提供などが行われた日付。 |
|
③ 取引の内容(軽減税率の対象である場合はその旨) |
商品の個別内容や税率の種類も記載が必要です。 |
|
④ 取引金額(税込価格)および適用税率ごとに区分した消費税額等 |
10%や8%といった税率別に明細を記載。 |
|
⑤ 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称 |
受領側の事業者名も記載が必要なケースがあります。 |
導入の背景と目的
インボイス制度の導入背景には、消費税制度の適正化と仕入税額控除の厳格化があります。従来の「区分記載請求書等保存方式」では、不完全な請求書や実態のない仕入れに基づいて、仕入税額控除が行われるケースもあり、税務リスクが高まっていました。
その点、インボイス制度では、登録された「適格請求書発行事業者」のみがインボイスを発行できるため、不正な仕入税額控除の防止と、課税の適正化が期待されています。また、同制度は、軽減税率制度に対応する目的もあり、税率ごとの管理・記録をより正確に行うための基盤ともいえます。
登録しない場合のメリット・デメリット
インボイス制度に登録しないことは可能ですが、その選択には明確なメリットとデメリットが存在します。特に取引先が課税事業者である場合、登録しないことによる影響は大きくなります。
|
項目 |
メリット |
デメリット |
|
課税事業者に登録しない |
引き続き消費税の納税義務がない 会計処理や消費税申告の手間が少ない |
適格請求書の発行ができず、取引先が仕入税額控除を受けられない 取引の選択肢が減少(特にBtoB取引) |
|
課税事業者に登録する |
インボイスの発行が可能になり、取引の信頼性が向上 仕入税額控除の対象となる |
消費税の申告・納税義務が発生 帳簿と請求書の管理が厳格になる |
免税事業者がインボイス登録する場合の注意点
免税事業者がインボイスを発行するためには、まず「適格請求書発行事業者」として登録し、課税事業者となる必要があります。これにより、消費税の納税義務が発生しますが、その反面としてインボイスの発行が可能になり、取引先との関係において有利になることがあります。
注意点としては以下の項目があります。
- 一度登録すれば、基本的に2年間は免税事業者へ戻れない。
- 消費税の課税対象売上、仕入税額控除などの計算が必要になる。
- 記帳義務や請求書の発行義務が厳格になるため、税理士など専門家のサポートが必要となることも。
- 帳簿の保存期間や形式が厳格に求められ、税務調査への対応力が求められる。
特にフリーランス・個人事業主は、取引先の意向や売上見込みに応じて、登録の判断を慎重に行うことが重要です。
インボイス登録の期限はいつまで?
制度開始日と登録申請期限
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、2023年10月1日から正式に開始されました。事業者がこの制度に対応するためには、まず「適格請求書発行事業者」としての登録が必要です。登録を希望する場合は、開始日である2023年10月1日から逆算して、以下の登録期限を守らなければなりません。
2023年10月1日からインボイスを交付するためには、原則として同年3月31日までに登録申請書を税務署に提出する必要がありました。この期限を過ぎた場合でも登録は可能ですが、その場合は登録日以降でなければインボイスの発行ができません。
登録申請書は、電子申請(e-Tax)あるいは書面にて提出することが可能であり、申請の際には「適格請求書発行事業者公表サイト」上に事業者情報が公開される可能性があることにも留意が必要です。
登録のタイミングによる影響
インボイス制度において、登録のタイミングは取引先や売上に大きな影響を与える可能性があります。開始日(2023年10月1日)からすぐにインボイスを発行できる状態にしておかないと、以下のような実務的な不利益を被ることがあります。
|
登録タイミング |
影響 |
|
2023年3月31日までに登録申請 |
2023年10月1日からインボイス発行が可能。取引先に対して課税仕入れ控除を提供できるため、取引上の信頼性が維持されやすい。 |
|
2023年4月1日以降に申請 |
登録日からのインボイス発行しか認められず、制度開始日から登録日までの期間に交付した請求書は仕入税額控除の対象とならない。取引先から登録事業者との契約を優先される可能性がある。 |
特にフリーランスや個人事業主が法人と取引している場合、登録の遅れによって取引契約を見直されることがあるため、早めの申請が推奨されます。
既に課税事業者である場合の登録期限
基準期間の売上が1,000万円を超えるなどの要件を満たし、もともと「消費税課税事業者」である企業や個人事業主についても、インボイス発行のためには登録が必須です。課税事業者であっても、自動的にインボイス発行事業者になるわけではないため、別途登録申請をしなければなりません。
課税事業者がインボイス制度の施行日に登録を間に合わせるには、2023年3月31日までに申請を行う必要がありました。
もし課税事業者が登録期限を過ぎた場合、その申請日から登録日までの期間にはインボイスの発行ができず、仕入税額控除にも支障が出るおそれがあります。こうした期間の売上については、インボイスが発行できないため、取引先からの信頼性や選定理由において不利になる可能性もあります。
インボイス登録の申請方法と手続きの流れ
e-Taxを使ったオンライン申請手順
インボイス制度への登録申請は、国税庁の「e-Tax(イータックス)」を活用することで、オンラインからスムーズに行うことができます。特に、すでにe-Tax利用開始手続きをすませている場合は、お手元のパソコンまたはスマートフォンから簡単に申し込みが可能です。
以下は、e-Taxを用いたインボイス登録の申請手順です。
- 利用者識別番号の取得:まだ取得していない場合は、e-Taxの利用開始届出書を提出し、取得する必要があります。
- e-TaxソフトウェアまたはWeb版にログイン:国税庁のe-Taxサイトにアクセスし、ログインします。
- 「適格請求書発行事業者の登録申請書」の選択:メニューから必要な登録申請書を選択します。
- 必要事項の入力:氏名、所在地、事業の種類、消費税の課税状況などを正確に入力します。
- 添付書類の確認:個人事業主の場合は本人確認書類(運転免許証など)、法人なら登記事項証明書などが必要なケースもあります。
- 申請書類の提出:内容を確認後、提出ボタンをクリックし、電子署名が行われて申請完了。
- 受付完了通知の保存:申請完了後、受付完了通知(電子データ)が発行されるので、必ず保存しておきましょう。
e-Taxを利用すれば、24時間どこからでも申請が可能なため、繁忙期でも登録を逃すリスクを軽減できます。ただし、電子証明書の更新やログインエラーなど、技術的な問題が起こることもあるため、余裕を持って申請を行いましょう。
書面での申請方法
e-Taxを利用できない場合や、書面での申請を希望する場合には、所轄の税務署に書類を郵送または持参する方法もあります。
書面申請の流れは以下の通りです。
- 国税庁ホームページから「適格請求書発行事業者の登録申請書」(様式番号:令和5年様式)がダウンロード可能です。
- 印刷し、必要事項を手書きまたは入力して記載します。
- 必要に応じて、本人確認書類や登記事項証明書を添付します。
- 記入内容を確認のうえ、所轄の税務署に郵送または窓口に持参して提出します。
- 控えが必要な場合には、コピーと返信用封筒(切手貼付)を同封することで返送してもらえます。
書面申請は処理に時間がかかる場合があるため、提出後は審査に数週間を要することが一般的です。余裕を持って申請期限の前に提出を完了させておくことが重要です。
登録完了後に届く通知書と保存義務
インボイス登録申請が受理されると、税務署から「適格請求書発行事業者の登録通知書」が届きます。この通知書には以下の情報が記載されています。
|
項目名 |
内容 |
|
登録番号 |
インボイス制度上、取引先に提示するために必要な固有の番号 |
|
登録年月日 |
適格請求書発行事業者として登録された正式な日付 |
|
事業者名 |
登録された個人または法人の名称 |
|
登録の取消などの有無 |
免税事業者であったかどうかに関する詳細情報 |
この通知書は今後の請求書発行や税務調査時などに必要となるため、大切に保管してください。また、取引先にインボイス番号を提供する際にも活用します。
通知書が手元に届くまでには、申請方法や混雑状況によって異なりますが、おおよそ2〜4週間程度かかるとされています。特に制度開始直前は申し込みが集中するため、早めの申請が推奨されます。
さらに、通知を受けた後は、登録事業者としての義務が発生します。これには、適格請求書の発行、帳簿保存要件への対応、消費税の課税計算方式の変更対応などが含まれます。
申請が間に合わなかった場合の対処方法!
制度開始後の登録について
インボイス制度は、2023年10月1日から開始されました。この日時点で適格請求書発行事業者として登録されていない場合でも、その後に登録することは可能です。ただし、登録日以降でなければ適格請求書(インボイス)を発行することはできません。
つまり、制度開始前までに登録が完了していなかった場合、インボイスが発行できない期間に取引先が仕入税額控除を受けられなくなる可能性があります。仕入税額控除の恩恵を得られるのは、インボイス登録日以降の取引からとなるため、取引先からの信頼低下や取引停止といったリスクも生じます。
制度開始後に登録申請を行う場合には、原則として申請書の提出月の翌月初日から登録が有効となります。たとえば、2024年4月に申請をして受理された場合、2024年5月1日から適格請求書発行事業者としての登録が認められます。
|
申請月 |
適格請求書発行事業者の登録開始日 |
備考 |
|
2023年9月まで |
2023年10月1日 |
制度開始前申請で遡及認定 |
|
2023年10月以降 |
申請書の提出月の翌月初日 |
例:2024年4月申請→2024年5月1日登録 |
遅れて登録する際の注意事項
制度開始後に登録を行う場合には、以下の注意点を押さえておく必要があります。
1. 登録効力の遡及適用はできない
2023年10月1日以降に申請した場合には、基本的に登録効力を遡及させることはできません。そのため、制度開始日以降に初めてインボイス登録を行おうとする場合、登録日より前の期間は適格請求書を発行できず、取引先が仕入税額控除を受けられなくなります。
2. 課税事業者としての届出が必要
免税事業者がインボイス制度開始後に登録を検討する場合、税務署に対して「消費税課税事業者選択届出書」を提出しなければなりません。インボイス制度の登録申請とは別にこの届出が必要となるため、事前の手続き確認が重要です。
3. 見積書や契約書の表記内容に注意
制度の開始時点でインボイスが発行できない状態であっても、見積書や契約書に「適格請求書発行事業者」の登録番号を記載し続けてしまうと、誤認を与えるリスクがあるため注意が必要です。登録が完了した日から登録番号を使用するようにしましょう。
4. 取引先との関係構築がカギ
請求書を受け取る側である取引先にとって、仕入税額控除を行えるかどうかはコスト面で非常に重要です。制度開始前にインボイス登録をしなかった場合、事後的に「なぜ登録を行わなかったのか」「いつ登録するのか」といった説明責任が発生する可能性があります。取引先との信頼を維持するためにも、登録の計画やスケジュールを早めに説明・共有しておくことが大切です。
5. 制度開始直後は申請の混雑に注意
インボイス制度が始まってからしばらくの間は、国税庁や税務署への登録申請が急増した背景があります。そのため、登録完了までに通常より多くの時間がかかることがありました。特に年末や年度末などの繁忙期に申請すると、処理に時間を要する可能性があるため、早めの行動が求められます。
まとめると、インボイス制度に未登録のまま制度が開始されてしまっても、申請自体はいつでも可能です。しかし、登録日以降の取引にしかインボイスを発行できず、税務面および取引先対応におけるリスクが伴います。登録申請は早めに行い、必要な手続きも確認・準備しておきましょう。
登録後に変更や廃止する方法は?
登録後の内容変更手続き
インボイス制度(適格請求書等保存方式)において、適格請求書発行事業者として登録された後に、事業内容や住所、名称などの届出情報に変更が生じた場合は、速やかに「適格請求書発行事業者の登録事項変更届出書」を提出する必要があります。
変更届は、変更があった事実を知った日から原則として速やかに提出しなければなりません。税務署に提出する書面での届出のほか、e-Taxを利用すればオンラインでの申請も可能です。提出先は納税地を所轄する税務署となります。
変更が必要な主な事項には以下のようなものがあります。
|
変更項目 |
必要な手続き |
備考 |
|
氏名または名称 |
変更届の提出 |
法人の場合は登記簿謄本の添付が必要な場合あり |
|
主たる事務所または事業所の所在地 |
変更届の提出 |
所在地変更届と併せて提出する場合あり |
|
法人番号(法人のみ) |
税務署への相談が必要 |
法人格の変更を伴う場合は新規登録の必要あり |
|
課税期間の変更 |
別途届出書が必要 |
課税期間によってインボイスの取扱も変わる場合あり |
変更内容によっては、登録番号や登録の有効性に影響を及ぼす場合もあるため、誤った情報のまま放置せず、すみやかに適切な手続きを行うことが重要です。
登録の取りやめ(廃止届出書)の提出方法
インボイス制度の登録を行った事業者が、廃業や消費税課税事業者からの変更(免税事業者への転換)などの理由により、適格請求書発行事業者の登録を取りやめたい場合は、「適格請求書発行事業者の登録の取消しに関する届出書(廃止届出書)」を提出する必要があります。
主な登録取消しの理由には以下のようなケースが考えられます。
- 事業を廃止した場合
- 課税売上高が1,000万円以下となり、翌課税期間から免税事業者となることを選択した場合
- 適格請求書を発行する必要がなくなった場合
登録の取消し申請は以下の手順で行います。
- 「適格請求書発行事業者の登録の取消しに関する届出書(廃止届出書)」を記入する
- 納税地の所轄税務署に提出する(郵送・窓口・e-Taxで可能)
- 税務署が受理し、登録取消し日を判断・処理(基本的には提出日以降の日付が指定されます)
登録の取消しを行った場合、インボイス(適格請求書)の発行ができなくなるため、取引先との契約や取扱いに影響が出る可能性があります。免税事業者へ戻ることにより、仕入税額控除が受けられなくなる点に注意しましょう。
また、一度登録の取消しを行った後に再度インボイスの登録を希望する場合は、新たに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。その際、元の登録番号が引き継がれるとは限らないため、取引先への周知が再度必要となる点も考慮してください。
なお、登録の取消しは将来に向けて効力を持つ手続きとなるため、過去にさかのぼっての取消しは原則としてできません。取りやめを希望する事業者は、早期に税務署へ相談することが推奨されます。
【Q&A】インボイス制度に関するよくある質問
個人事業主でも登録は必要?
個人事業主であっても、課税事業者として取引先に消費税を請求し、仕入税額控除の適用を受ける場合には、インボイス発行事業者としての登録が必要です。特にフリーランスや一人親方などBtoB(事業者対事業者)取引を行う個人事業主は、取引先から適格請求書(インボイス)を求められることが多く、登録しなければ今後の取引に支障が出る可能性があります。
ただし、免税事業者として今後も仕入税額控除を受けずに済む形で事業を継続するつもりであれば、登録は必須ではありません。しかしその場合、取引先の課税事業者にとって仕入税額控除ができない分、取引条件の変更や単価調整などを求められるリスクがあるため注意が必要です。
消費税免税事業者でもインボイス登録したほうがいい?
消費税の免税事業者でも、将来的に取引先との関係維持や商機の拡大を目指す場合、インボイス登録を検討する価値があります。インボイス制度では、取引先が仕入税額控除を行うためには、適格請求書発行事業者からの請求書が必要となります。そのため、免税事業者のままでいると、取引先が税務上のメリットを失うことになり、結果的に取引を控えられたり、報酬単価を下げられたりする恐れがあります。
一方、登録を行うと消費税を納める義務が発生するため、納税負担が増えることになります。インボイス登録による収支への影響をシミュレーションした上で、今後の事業方針と照らして判断することが大切です。
報酬が少ない場合のインボイス登録の判断は?
年間の売上が1,000万円未満で、現在は免税事業者である場合、報酬が少ないとインボイス制度への登録によってかえって税負担が重くなることがあります。特に経費が少なく、仕入税額控除のメリットを十分に受けられない業種(たとえばライター、イラストレーター、コンサルタントなど)にとっては慎重な判断が必要です。
以下の表に、報酬が比較的少ない事業者にとってのインボイス登録のメリット・デメリットを整理しています。
|
項目 |
インボイス登録する場合 |
インボイス登録しない場合 |
|
消費税の扱い |
課税事業者として、仕入税額控除を適用できるが、納税義務が発生 |
免税事業者として消費税を納める必要なし |
|
取引先への影響 |
取引先が仕入税額控除できるため、継続取引や単価維持が期待できる |
取引先が仕入税額控除できず、単価調整や契約打ち切りのリスクがある |
|
会計処理の手間 |
増加する(税区分の管理、消費税申告など) |
現状のままでよい |
|
収支への影響 |
売上に対して消費税納付分が控除されるため利益が減る可能性あり |
収入に消費税を上乗せして実質的な利益増になる構造を継続できる |
報酬の規模によっては、免税事業者として継続したほうが利益率を確保しやすいケースもあります。ただし、将来の売上見込み、取引先のニーズ、税制変更の可能性などを踏まえて、中長期的な視点から検討することが重要です。
インボイス登録した場合、取り消しできる?
インボイス発行事業者の登録は、原則として自由に取り消すことができます。ただし、一度登録すると課税事業者としての義務が生じるため、安易に登録するのではなく制度や税負担をよく理解したうえで判断する必要があります。
取り消し(登録の廃止)を希望する場合は、「適格請求書発行事業者の登録の取消しに関する届出書(登録の取消届出書)」を税務署に提出します。届出を行うタイミングによって、登録の取り消しが有効となる日が異なるため、事前にスケジュール管理が必須です。
副業でも登録が必要?
副業でも、企業など他の事業者と取引をしていて、かつ報酬に消費税が含まれる場合、適格請求書を発行できるかどうかが問題になる場合があります。仮に免税事業者で適格請求書が発行できないと、その取引先は仕入税額控除を受けられなくなり、今後の取引に影響が出る可能性があります。
副業での年間売上が1,000万円未満であり、あくまでスポット的な業務で主たる収入源ではない場合は、登録を急ぐ必要はないケースもありますが、取引先の意向や業界慣習を事前に確認することが大切です。
登録番号は公開される?
インボイス制度では、インボイス発行事業者として登録されると、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」にて登録番号、氏名または名称、所在地などの情報が公開されます。この情報は、取引先が仕入税額控除の適用要件を満たしているか確認するために参照されます。
個人情報の公開に懸念がある個人事業主の場合、屋号付きで登録する、事務所用の住所で登録するなどの配慮が有効です。プライバシーを守りつつも、税制上の要件を満たすための工夫が求められます。
まとめ
インボイス制度の登録期限は原則として2023年10月1日からの適格請求書発行を希望する場合、2023年3月31日までに申請する必要がありました。申請が遅れた場合も制度開始後の登録は可能ですが、適格請求書を発行できるのは登録日以降になります。特に免税事業者には課税事業者への転換が必要なため慎重な判断が重要です。適切な時期に正しい手続きを行い、制度の影響を受けないよう早めの準備を心がけましょう。