リベートはインボイスが必要?支払側・受取側の対応と仕訳ルールを解説
更新日:2025.12.06
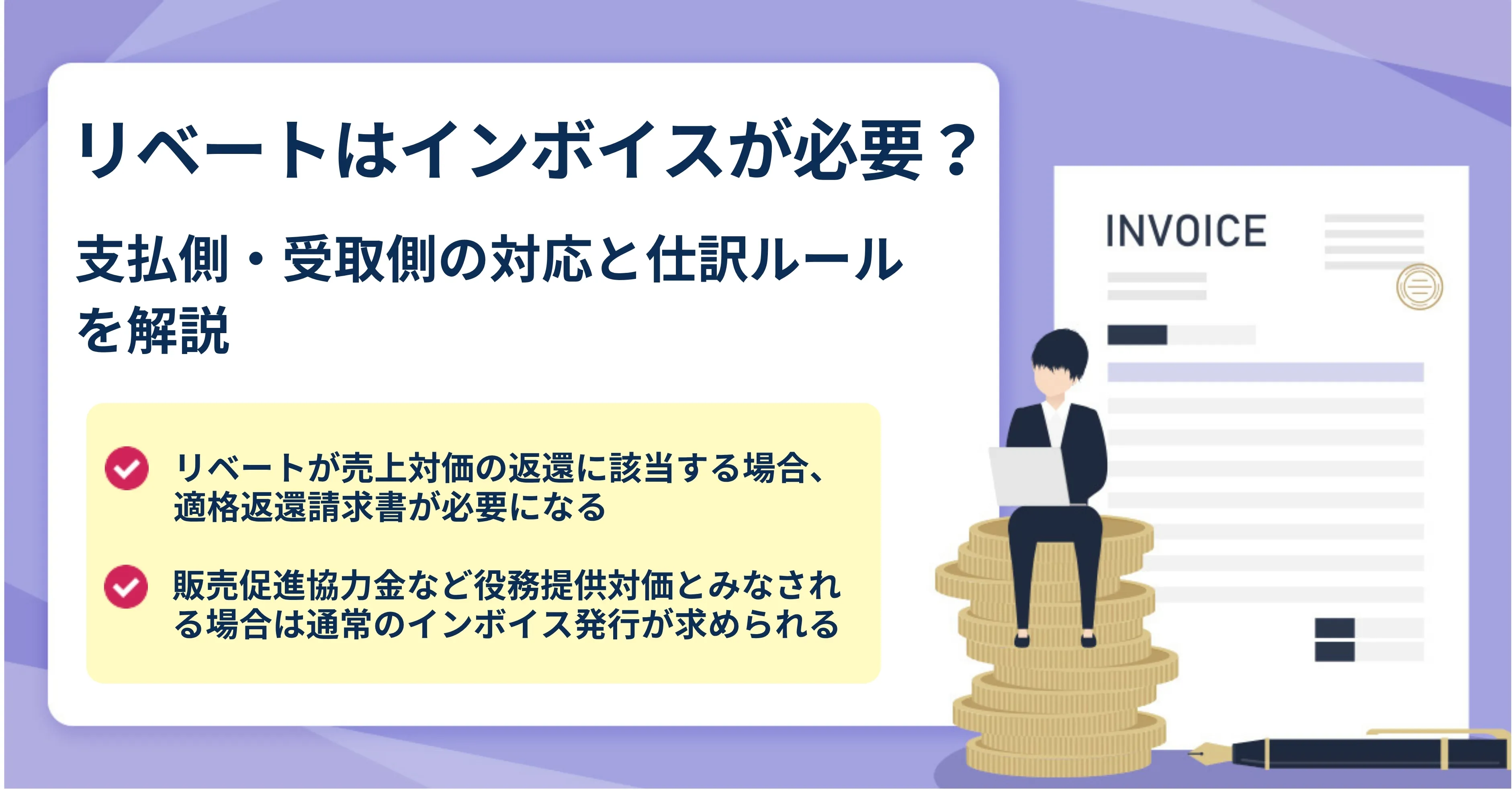
ー 目次 ー
インボイス制度が始まり、リベートの経理処理にお困りではありませんか?実は、リベートは原則として「売上対価の返還等」に該当するため、インボイス(正確には適格返還請求書)の対応が求められるケースがあります。本記事では、インボイスが必要になる・ならないリベートの違いや、支払側・受取側それぞれの対応方法、仕訳例まで丁寧に解説します。支払通知書で代替する方法もわかりますので、実務にすぐ活かせるようぜひご覧ください。
まずおさらい!リベートとインボイス制度の基本をやさしく解説
2023年10月1日から開始されたインボイス制度。リベートがインボイスの対象になるのか、どのような対応が必要になるのかを正しく理解するためには、まず「インボイス制度」と「リベート」それぞれの基本を把握しておくことが不可欠です。この章では、複雑に思える両者の基本をやさしく解説します。
そもそもインボイス制度とは?
インボイス制度とは、正式名称を「適格請求書等保存方式」といいます。消費税の仕入税額控除を受けるための新しいルールです。商品の販売やサービスの提供を行った事業者(売手)が、取引相手(買手)に対して、正確な適用税率や消費税額などを伝えるための書類「適格請求書(インボイス)」を交付し、双方がそれを保存することを定めています。
買手側は、原則としてこの適格請求書(インボイス)がなければ、支払った消費税分の仕入税額控除が受けられなくなり、結果として納税額が増える可能性があります。
リベートとは?販売奨励金や値引きとはなにがちがう?
リベートとは、一定期間内にあらかじめ決められた条件(取引数量や取引金額など)を達成した際に、売手が買手に対して売上代金の一部を返金(割戻し)する制度です。会計上は「売上割戻」として処理されるのが一般的です。リベートは取引後に支払われる金銭である、という点がポイントになります。
経理処理において混同しやすい「販売奨励金」や「値引き」との違いを理解しておきましょう。
|
種類 |
タイミング |
内容・目的 |
売手側の会計処理(例) |
|
リベート(売上割戻) |
取引後 |
一定の取引量や額に応じて、代金の一部を後から返金する。 |
売上高のマイナス(売上割戻) |
|
販売奨励金 |
取引後 |
販売促進を目的として、金銭や物品を提供する。リベートとほぼ同義で使われることも多い。 |
経費(販売促進費)または売上高のマイナス |
|
値引き |
取引時 |
商品のキズや納期遅延などを理由に、その場で代金から直接減額する。 |
売上高のマイナス(売上値引) |
このように、リベートは取引の対価そのものを減額する「値引き」とは異なり、「売上にかかる対価の返還等」に該当します。この性質の違いが、インボイス制度における取り扱いの重要なポイントとなります。
リベートはインボイスの対象?交付が必要になるケースを解説!
結論から言うと、リベートはインボイス(正しくは適格返還請求書)の交付対象になるケースとならないケースがあります。
ここでは、どのようなリベートがインボイスの対象となり、どのような場合に対象外となるのか、その判断基準を具体的に解説します。
インボイスの交付が必要になるリベートの特徴とは?
インボイスの交付が必要になるのは、そのリベートが消費税法上の「売上に係る対価の返還等」に該当する場合です。これは、一度確定した売上金額から、後日その一部を買い手(リベート受取側)に返金する性質を持つものを指します。
具体的には、以下のようなリベートが該当します。
- 一定期間の取引量や取引金額に応じて支払われるリベート(仕入割戻し)
- 販売数量の実績に応じて支払われる販売奨励金
- 決済期日より前に代金を支払った場合に受けられる支払奨励金(早期支払リベート)
- 取引先との契約であらかじめ定められた条件を達成した場合に支払われるリベート
これらのリベートを支払う側(売手)は、返金した金額にかかる消費税額を、自社の売上にかかる消費税額から差し引く(仕入税額控除)ことができます。その控除を受けるための証明書類として、リベートの受取側(買手)から交付される「適格返還請求書(返還インボイス)」が必要になるのです。
交付が不要なケースは?インボイス対象外となるリベートの例
一方で、すべてのリベートが「売上に係る対価の返還等」に該当するわけではありません。インボイス(適格返還請求書)の交付が不要なのは、リベートが売上代金の返金ではなく、別の取引の対価とみなされる場合です。
例えば、以下のようなケースは「売上に係る対価の返還等」には該当しません。
- 新商品の陳列棚確保やポップ設置などに対する「販売促進協力金」
- 自社製品をチラシやカタログに掲載してもらうための「広告宣伝費」
- 事業とは直接関係なく、贈答として渡される金品
これらの支払いは、商品の販売促進という「役務提供」に対する対価とみなされます。そのため、売上代金の返金ではなく、支払側(売手)にとっては課税仕入れとなります。この場合、リベートの受取側(買手)は「適格返還請求書」ではなく、役務提供の対価として通常の「適格請求書(インボイス)」を交付する必要があります。
両者の違いをまとめると、以下のようになります。
|
リベートの性質 |
インボイスの扱い |
根拠 |
|
売上高や販売数量に応じた返金 (例:仕入割戻し) |
適格返還請求書が必要 |
売上に係る対価の返還等に該当するため |
|
販売促進活動への協力対価 (例:陳列協力金、広告掲載料) |
適格請求書が必要 (適格返還請求書ではない) |
役務提供の対価であり、課税仕入れに該当するため |
自社が支払う、あるいは受け取るリベートがどちらの性質を持つのかを契約内容や実態に即して正しく判断することが、インボイス制度への適切な対応につながります。
販売奨励金のインボイス対応はどうなる?リベートとの違いに注意
販売奨励金とは、特定の販売実績や販売活動に応じて支払われる報奨金のことです。
インボイス制度上では、この販売奨励金が「対価性があるかどうか」によって、適格請求書(インボイス)の交付義務が発生するかが変わります。
たとえば、商品の販売実績に応じて金額が決まる販売奨励金は、役務提供に対する対価とみなされることが多く、その場合はインボイスの交付が必要 一方で、単なる協力金や寄付的な性質が強い場合は、インボイス不要のケースもあります。
リベートと混同されがちですが、リベートは売買契約に付随する割戻し的な性格を持つのに対し、販売奨励金は役務性(販売活動への対価)が問われやすいため、インボイスの判断基準が異なる点に注意が必要です。
歩引き(値引き)とリベートではインボイスの扱いが異なる?
インボイス制度においては、「歩引き(値引き)」と「リベート」では税務上の扱いが明確に区別されています。
その違いを理解しておかないと、適格請求書の交付漏れや消費税の取り扱いミスにつながるリスクがあります。
歩引き(値引き)は、商品の売上に直接反映される価格調整であるため、請求書や納品書で単価や金額から差し引く形式が一般的です。
この場合、インボイスにも正しい税込価格を記載すれば、追加でインボイスを発行する必要はありません。
一方、リベートは売上後に一定条件に基づいて支払われる金銭的還元であり、別途インボイスの交付が必要になることがあります。
とくに、金銭で支払う場合や対価性があると判断される場合は、適格請求書の発行義務が発生します。
このように、値引き=インボイス不要/リベート=要注意と覚えておくと判断の参考になります。
リベートの支払側(売手側)のインボイス対応まとめ
インボイス制度において、リベートを支払う側(売手)は「売上対価の返還等」として、売上にかかる消費税額からリベートに相当する消費税額を差し引くことができます。この適用を受けるためには、原則として「適格返還請求書(返還インボイス)」の保存が義務付けられています。ここでは、支払側が取るべき具体的な対応方法と仕訳例を解説します。
支払側が行うべき2つの対応パターン
リベートを支払う売手側が「売上対価の返還等」の適用を受けるための対応には、主に2つのパターンがあります。取引の実態や相手方との関係性に応じて、どちらかの方法を選択することになります。
パターン1 受取側から適格返還請求書を発行してもらう
最も原則的な方法が、リベートの受取側(買手)から「適格返還請求書(返還インボイス)」を発行してもらい、それを受領・保存する方法です。これは、通常の請求書とは逆に、お金を受け取る側(買手)がお金を支払う側(売手)に対して発行する書類となります。売手はこの返還インボイスを保存することで、仕入税額控除の要件を満たすことができます。
パターン2 支払側が支払通知書を作成し相手の確認を受ける
多数の取引先にリベートを支払う場合など、買手一社一社に返還インボイスの発行を依頼するのが難しいケースもあります。その場合、リベートを支払う売手側が「支払通知書」を作成し、相手方(買手)の確認を受けることで、返還インボイスの代わりとすることが認められています。
この支払通知書を返還インボイスとして扱うには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
- 通知書に、適格返還請求書の記載事項(※)がすべて記載されていること
- 通知書の内容について、相手方(買手)の確認を受けていること
※記載事項の詳細は、本記事の「リベートの受取側(買手側)のインボイス対応」の章で解説します。
相手方の確認は、書面へのサインや押印のほか、メールや電子データで「内容を確認し、了承しました」といった返信をもらう形でも問題ありません。
リベート支払側の仕訳例を解説!
リベートを支払った際の会計処理(仕訳)は、インボイス制度の開始前後で勘定科目に大きな変更はありません。ただし、消費税の扱いを正しく認識しておくことが重要です。ここでは、税込経理方式の仕訳例をご紹介します。
【前提条件】
- A社(売手)がB社(買手)に110,000円(うち消費税10,000円)の商品を掛けで販売した。
- 後日、販売実績に応じて、A社はB社にリベートとして現金で11,000円(うち消費税1,000円)を支払った。
- A社は適格返還請求書の交付を受け、保存している。
【仕訳例】
|
取引内容 |
借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
|
商品販売時 |
売掛金 |
110,000円 |
売上 |
110,000円 |
|
リベート支払時 |
売上割戻(または売上値引) |
11,000円 |
現金預金 |
11,000円 |
この仕訳により、リベート支払額(11,000円)が売上から控除されます。税抜経理方式の場合は、リベート支払時に借方を「売上割戻 10,000円」「仮受消費税 1,000円」として処理し、売上にかかる消費税額からリベート分の消費税額を直接減額します。
リベートの受取側(買手側)のインボイス対応
インボイス制度において、リベートを受け取る側(買手側)は、原則として「適格返還請求書(返還インボイス)」を発行する義務を負います。これは、リベートが消費税法上の「売上に係る対価の返還等」に該当する場合があるためです。ここでは、リベート受取側の具体的な対応方法と仕訳について詳しく解説します。
受取側が行うべきことは適格返還請求書の発行!
リベートの支払側(売手)が仕入税額控除を受けるためには、その取引がインボイス制度の要件を満たしている必要があります。リベートは、買手が仕入れた商品代金の一部が返還される性質を持つため、買手が売手に対して「対価を返還した」ことを証明する書類を発行する、という考え方になります。
この証明書類が「適格返還請求書(返還インボイス)」です。したがって、リベートを受け取る買手は、支払側である売手に対して適格返還請求書を交付する義務が生じます。これにより、売手側はリベート分の消費税について仕入税額控除を適用できるようになります。
適格返還請求書(返還インボイス)の書き方
適格返還請求書には、通常のインボイス(適格請求書)とは少し異なる記載事項が定められています。以下の項目を漏れなく記載する必要があります。
|
記載事項 |
記載内容のポイント |
|
発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 |
リベートの受取側(買手)の氏名または名称と、Tから始まる13桁の登録番号を記載します。 |
|
対価の返還等を行う年月日 |
リベートが支払われた日など、実際に返還処理が行われた年月日を記載します。 |
|
対価の返還等の基となった取引を行った年月日 |
リベートの対象となった元の取引(仕入)が行われた年月日を記載します。取引期間が長い場合は「〇年〇月分」のように記載することも可能です。 |
|
対価の返還等の取引内容 |
「販売奨励金として」「〇月分リベートとして」など、リベートの内容がわかるように記載します。軽減税率の対象取引に関するリベートの場合は、その旨も明記します。 |
|
税率ごとに区分して合計した対価の返還等の金額(税抜又は税込) |
リベートの金額を、適用税率(10%対象、8%対象)ごとに区分して合計した金額を記載します。 |
|
対価の返還等に係る消費税額等又は適用税率 |
税率ごとに区分した消費税額、または適用税率のいずれかを記載します。 |
支払通知書でインボイス対応する場合の注意点
取引の実務上、リベートの金額を計算するのは支払側(売手)であるケースがほとんどです。そのため、受取側(買手)が適格返還請求書を発行する代わりに、支払側(売手)が発行する「支払通知書」をもって適格返還請求書とすることも認められています。
この方法をとる場合、受取側(買手)は以下の点に注意が必要です。
- 送られてきた支払通知書が、適格返還請求書の記載事項をすべて満たしているかを確認する。
- 内容を確認したうえで、その支払通知書を相手方(売手)に返送するか、メール等で確認・承認した旨を伝える。
- 相手方の確認を受けた支払通知書の写しを、自社で保存する。
この手続きにより、支払通知書が正式な返還インボイスとして扱われ、売手は仕入税額控除を受けることができます。受取側としては、書類発行の手間が省けるというメリットがあります。
リベート受取側の仕訳例を解説!
リベートを受け取った際の会計処理は、そのリベートの性質によって勘定科目が異なります。一般的には「仕入割引」または「雑収入」として処理します。ここでは、110,000円(うち消費税10,000円)のリベートを現金で受け取った場合の仕訳例を解説します。
【雑収入として処理する場合】
リベートが仕入高とは直接関係ない営業外の収益とみなす場合の処理です。
|
借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
|
現金預金 |
110,000円 |
雑収入 |
100,000円 |
|
仮受消費税等 |
10,000円 |
【仕入割引として処理する場合】
リベートが仕入代金の実質的な減額であるとみなす場合の処理です。
|
借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
|
現金預金 |
110,000円 |
仕入割引 |
100,000円 |
|
仮受消費税等 |
10,000円 |
インボイス制度においては、いずれの勘定科目で処理する場合でも、消費税額を明確に区分して記帳することが重要です。これにより、正確な消費税の申告・納税が可能となります。
Q&A|リベートとインボイスに関するよくある質問
リベートとインボイス制度に関して、特に判断に迷いやすいケースをQ&A形式で解説します。自社の状況と照らし合わせ、適切な対応を確認しましょう。
インボイス制度開始前に発生したリベートでも、交付義務はある?
リベートの支払いがインボイス制度開始後(2023年10月1日以降)であっても、その算定の基礎となる取引がすべて制度開始前(2023年9月30日以前)に行われたものであれば、適格返還請求書(返還インボイス)の交付義務はありません。
これは、売上にかかる対価の返還等に係る消費税額は、その基となる取引が行われた時点の消費税率・税制に基づいて計算されるためです。したがって、制度開始前の取引に基づくリベートについては、旧来の区分記載請求書等保存方式に則った対応となります。
ただし、リベートの算定期間が2023年9月30日と10月1日をまたぐ場合は注意が必要です。この場合、制度開始後の取引期間に対応するリベート額については、適格返還請求書の交付義務が発生します。算定期間を明確に区分し、適切に対応することが求められます。
1万円未満のリベートでもインボイスは必要?
結論から言うと、原則としてリベートの金額が1万円未満であっても、相手方(買手)が課税事業者である場合、適格返還請求書の交付義務は免除されません。
インボイス制度には、税込1万円未満の課税仕入れについてインボイスの保存がなくても帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる「少額特例」という制度があります。しかし、これはあくまで仕入れ側(リベートの受取側)の特例であり、売上側(リベートの支払側)のインボイス交付義務を免除するものではありません。
支払側と受取側の対応を整理すると、以下のようになります。
|
立場 |
対応のポイント |
|
リベート支払側(売手) |
金額にかかわらず、相手方から求められた場合は適格返還請求書(または支払通知書)を交付する義務がある。 |
|
リベート受取側(買手) |
少額特例の対象事業者(※)であれば、税込1万円未満のリベートについてインボイスがなくても帳簿への記載のみで仕入税額控除の適用が可能。ただし、相手方にインボイスの発行を求めることもできる。 |
※少額特例の対象事業者:基準期間(前々年・前々事業年度)の課税売上高が1億円以下、または特定期間(前年・前事業年度開始から6ヶ月)の課税売上高が5,000万円以下の事業者。
なお、例外として「売上値引、返品、割戻し等に係る対価の返還等」について、振込手数料相当額を値引きとして処理し、その金額が税込1万円未満である場合には、適格返還請求書の交付義務が免除される特例があります。リベートの支払いを銀行振込で行い、その手数料を受取側が負担するようなケースでは、この特例が適用できる可能性があります。
まとめ
リベートの経理処理は、インボイス制度の導入により注意点が大きく変わりました。原則として「売上対価の返還等」に該当するリベートには、適格返還請求書(返還インボイス)の交付・保存が求められます。支払側は受取側に発行を依頼するか、支払通知書で代替し、受取側はその確認・保存などの対応が必要です。今回ご紹介した判断基準や仕訳ルールを参考に、自社の実務に合わせた正確な対応を進めていただければ幸いです。










