ネットショップ事業者はインボイス制度に登録するべき?仕入れにおける影響とあわせて解説
更新日:2025.07.28
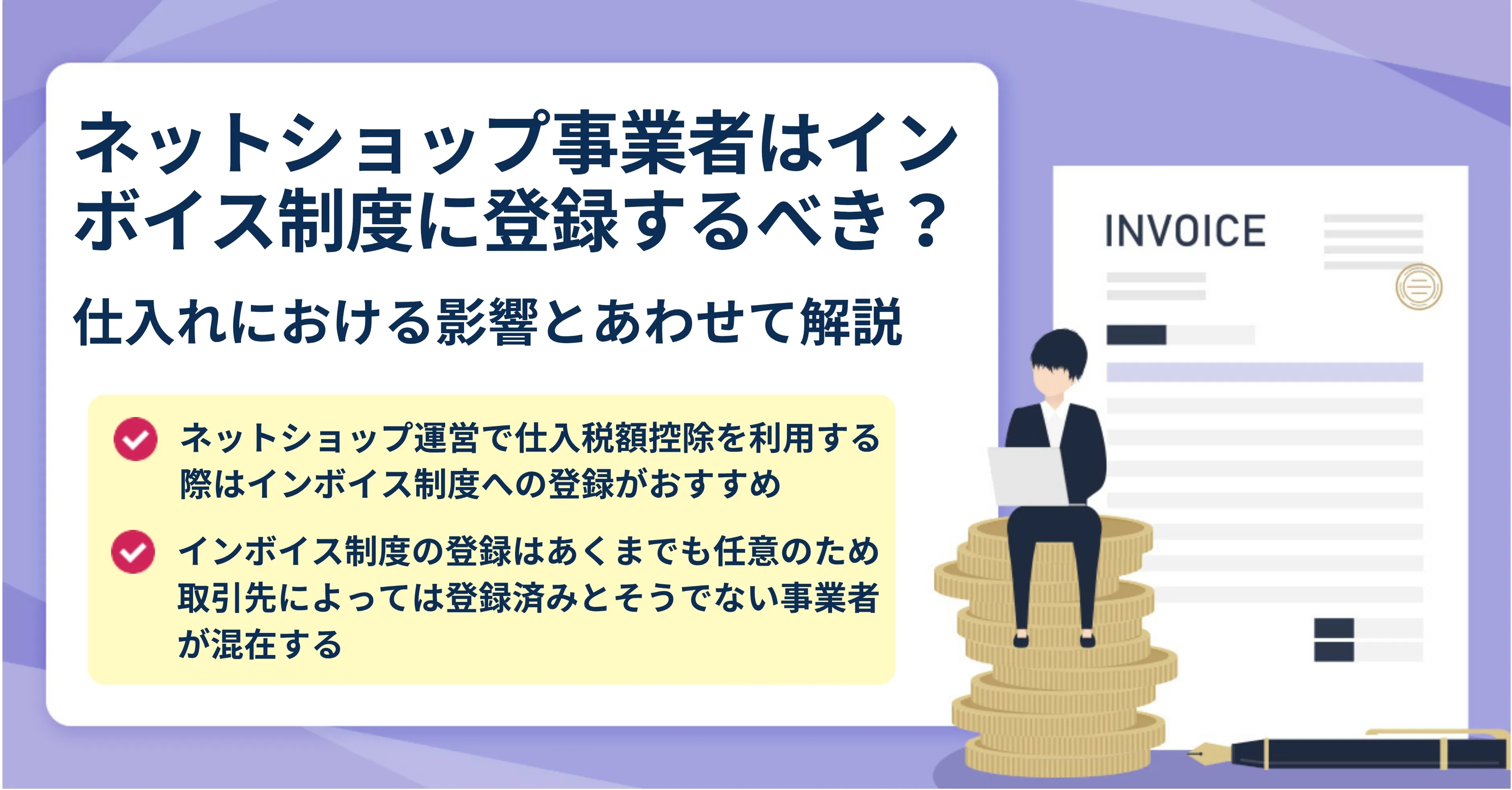
ー 目次 ー
ネットショップ運営では、領収書の受け取りや発行を日常的におこなうため、消費税の処理について意識する機会が多い業態といえます。そのため、インボイス制度への登録に必要性を感じることも少なくありません。
ただし、インボイス制度への登録はあくまでも任意であり、登録をするかは事業規模や取引先との関係性など、個々の状況によって判断する必要があります。
登録のタイミングを見誤ると、売上や機会損失につながる可能性もあるため、慎重に検討することが重要です。
本記事では、ネットショップ事業者がインボイス制度に登録するべきかについて、仕入時の影響や取引先との兼ね合いも交えつつ解説します。
【結論】ネットショップ運営で仕入税額控除を利用する際はインボイス制度への登録がおすすめ
インボイス制度への登録は任意であり、手続きの手間などを理由に、免税事業者のままにしている事業者も少なくありません。
しかし、インボイス制度に登録していないと「仕入税額控除」が適用されず、本来控除できる消費税をすべて負担する必要があります。これは、実質的な仕入コストの増加であり、利益を圧迫する原因になりかねません。
また、仕入税額控除はインボイス発行事業者からの仕入れが前提のため、自社がインボイス制度に未登録の場合、取引先に敬遠されるリスクもあります。
これらの点から、ネットショップを運営する際は、適格請求書を発行できるように準備することが推奨されています。
【注意!】取引先のインボイス制度の登録状況も加味して検討する必要がある
ネットショップを運営するうえで、インボイス制度への登録が推奨されているものの、取引先の状況次第では登録しないという選択肢も考えられます。
一般的には、仕入税額控除の観点ではインボイス制度への登録を済ませ、インボイス事業者同士で取引をおこなうのが理想です。しかし、登録が任意である以上、未登録の事業者と取引することは避けては通れません。
さらに、下請法によりインボイス制度を理由に契約を一方的に変更したり解除したりできないため、自社が損をする可能性もあります。
インボイス事業者になると、帳簿管理や請求書発行の体制を見直す必要もあるため、取引先の登録状況を踏まえたうえで判断することが大切です。
ネットショップ事業者がインボイス制度の登録で受けられる特例・制度とは?
インボイス制度への登録は任意であり、手続きの手間や制度の複雑さが原因で、登録を先送りにしている事業者も少なくありません。
しかし、インボイス制度に登録すると「仕入税額控除」が受けられるのはもちろん、事業者にとって有利な特例や制度を利用できるといった利点があります。
ここでは、ネットショップ事業者がインボイス制度に登録することで受けられる特例や制度を4つ解説します。
- 少額特例
- 2割特例
- IT導入補助金
- 小規模事業者持続化補助金
①少額特例
少額特例とは、税込1万円未満の課税仕入れに対して、インボイスの保存が不要となる制度のことです。これにより、仕入先がインボイス制度未登録であっても、一定条件のもとで仕入税額控除が適用されます。
ただし、事業者自身が基準期間の課税売上高が1億円以下、または特定期間で5,000万円以下という条件を満たしていなければ、少額特例は適用されません。
また、特例の期間が2029年9月30日までのため、それ以降の対応についても同時に検討しておくことが大切です。
②2割特例
2割特例は、免税事業者から課税事業者になった際に、消費税の納税額を軽減する制度のことです。具体的には、売上にかかる消費税額の2割の納付で済むことから、課税事業者になった直後の負担軽減に大きく役立ちます。
また、帳簿や仕入れの内容にかかわらず適用できるため、納税額の計算もシンプルで手間がかかりません。
ただし、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であることや、適用期間が2026年9月30日までなど要件もあります。そのため、対象者や適用期間を確認しておくことが重要です。
③IT導入補助金
IT導入補助金は、中小企業や小規模事業者を対象に、インボイス制度に対応するための備品やシステムの導入費用を補助する制度です。
インボイス制度に対応するためには、レジや業務ソフトなどの環境整備が必要であり、資金不足になるケースもめずらしくありません。IT導入補助金では導入する備品によって、最大350万円まで補助を受けられる場合があります。
パソコンやタブレット、レジ、券売機なども対象となるため、コストが原因で導入が難しい場合は補助金の利用を検討しましょう。
④小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が制度変更に対応する際に、設備投資や販路開拓を支援するための制度です。制度変更の内容は多岐にわたり、その1つとしてインボイス制度への対応も含まれています。
補助額については一般型と創業型に分かれており、一般型が最大100万円、創業型が最大250万円となっています(※)。
また、税理士のような専門家への相談費用も含まれるため、補助金を検討している事業者は商工会や創業型補助金事務局に相談しましょう。
(※)インボイス特例が上乗せされた額
ネットショップ事業者がインボイス制度に対応する際にするべき事前準備
ネットショップ運営をはじめ、事業者がインボイス制度に対応するためには、登録手続きや取引先への周知など、事前準備が不可欠です。
この点を理解していないと、必要なタイミングでインボイスを発行できず、取引や経理処理に支障が出るおそれがあります。そのため、事前に何を準備するべきか把握し、計画的に対応することが大切です。
ここでは、ネットショップ事業者がインボイス制度に対応する際に必要な事前準備を2つ解説します。
- インボイス制度の登録手続きをする
- 取引先へ登録番号を通知する
①インボイス制度の登録手続きをする
ネットショップ運営者がインボイス制度に対応するためには、最初に登録手続きを済ませる必要があります。事業開始直後は免税事業者であるため、課税事業者になるためには申請が必要です。
登録方法は2つあり、国税庁の公式サイトから書類をダウンロードして郵送で提出する方法と、e-Taxを利用してオンライン申請する方法から選択できます。
どちらにするか迷っている場合は、e-Taxのほうが自宅で完結し、登録通知の受け取りも早いためおすすめです。
関連記事:インボイス制度の登録方法とは?申請のやり方や注意点を解説
②取引先へ登録番号を通知する
インボイス制度への登録手続きが完了し、登録通知を受け取ったら、取引先にインボイス事業者に登録されたことを報告しましょう。
とくに、すでにインボイス事業者である取引先にとっては、仕入税額控除の可否にも関わる重要な情報です。速やかに報告することで信頼性の確保や、取引停止のリスク回避にも繋がります。
また、請求書の形式や送付手段も報告しておくと、取引先も経理処理がスムーズにでき、より良好な関係構築のきっかけになるでしょう。
ネット仕入れに影響?大手ECサイトのインボイス制度への対応状況
ネットショップを運営する際は仕入作業が必須であり、ECサイト(ネット通販)を利用する際は、インボイス対応の領収書が発行できるか確認しなければいけません。
仕入税額控除を活用して、消費税の負担を軽減させるためにも、購入前に対応できるか確認することが重要です。
ここでは、大手ECサイト4つのインボイス制度への対応状況について解説します。
- Amazon:注文履歴からインボイスの発行が可能
- 楽天市場:購入履歴からインボイスの発行が可能
- Yahooショッピング:注文履歴からインボイスの発行が可能
- メルカリ:インボイスの発行機能なし
①Amazon:注文履歴からインボイスの発行が可能
Amazonはインボイス制度に対応しており、必要に応じて適格請求書(インボイス)を発行することが可能です。
発行やダウンロードについては、注文履歴にアクセスし、該当する商品の「領収書等」から適格請求書を選択します。なお、Amazonのアプリから適格請求書の発行、およびダウンロードはできないため、必要な場合はWebサイトから対応しましょう。
②楽天市場:購入履歴からインボイスの発行が可能
楽天市場では、購入履歴からインボイス制度に対応した領収書をダウンロードすることが可能です。
利用するショップがインボイス事業者である場合、会社概要のページに「対応可能」と表示されます。仕入税額控除を受ける場合は、購入前に対応状況を確認しておくと安心です。
③Yahooショッピング:注文履歴からインボイスの発行が可能
Yahooショッピングは、出店者によってはインボイス制度に対応した領収書を発行することが可能です。インボイス制度の対応状況については、出店者の会社概要ページから確認できます。
ただし、出店者がインボイス事業者であっても注文履歴から領収書発行ができない場合もあるため注意が必要です。もし、領収書が必要な場合は各ストアに問い合わせしましょう。
④メルカリ:インボイスの発行機能なし
メルカリは、ほかの大手ECサイトとは異なり適格請求書の発行機能はありません。そのため、適格請求書の発行が必要な場合は直接ショップに連絡する必要があります。
ただし、問い合わせをしても必ず適格請求書を発行してもらえるわけではありません。確実にインボイス制度に対応したい場合は、はじめから対応可能なECサイトを利用するのがおすすめです。
まとめ|仕入れや取引先の対応状況を考慮して登録を検討しよう!
本記事では、ネットショップ事業者がインボイス制度に登録するべきかについて、仕入時の影響や取引先との兼ね合いも交えつつ解説しました。
仕入れをする機会が多いネットショップ運営では、仕入税額控除を活用して消費税の負担を軽減するためにも、インボイス制度への登録が推奨されています。
また、仕入税額控除はインボイス発行事業者同士でしか適用できないことから、自社が未登録のままだと、新規取引先に影響が出る可能性があります。
インボイス制度への登録は任意ではあるものの、仕入規模や取引先の登録状況を踏まえて、自社にとって適切な判断をすることが重要です。










